マザードール -more smile-
昔から、僕はよく笑う明るい子だったらしい。
笑うこと、泣かないことを…覚えて無いけど誰かに約束した気がして、泣かない様に明るく振舞ってきた
ただ、両親が事故で他界したあの日だけは…僕はその約束を守れなかった。
大好きな両親だった、いつも優しくて…愛情いっぱいに僕を愛してくれていた。
笑いが絶えない家庭で、これがずっと続くものだと思い込んでいた…しかしそんな幸せが壊れるのは一瞬だった。
突然の交通事故、それもかなり大きな規模で発生して僕の両親は巻き込まれて亡くなった。
きっと、今まで生きてきた中で一番泣いた。
涙が出なくなっても、嗚咽を漏らし続け…そして、両親の後を追うことも考えた。
"もう、泣かないで…って、約束したのに"
そこに立っていたのは僕が生まれた時から居間に飾られている、芸術品の様な気品がある古いアンティークドールだった。
普段は感情のない、無の顔をしていてそこに生気は感じられないが、今はまるで生きているかの様に表情を変え、動いている
人形が勝手に動き出す…ありえない光景だが、何故か僕は、まるで生きている様な今の彼女を知っている様な気がした。
「君は…人形の…」
「アロマ」
アロマ、彼女はそう名乗った。
アロマ、あろま…初めて聞く名前のはずなのに、とても呼び慣れた名前だった。
「また泣き虫さんなのね…泣かないって、約束したじゃない。」
「…無理だよ、そんなの…悲しくて、苦しくてたまらないんだ…」
「…そう、だったら仕方ないわね。」
となりに座った小さな身体の彼女は、そのまま僕のことを抱きしめた。
あぁ、なんだかずっと前にもこんなことがあった気がする…懐かしい、母さんがこうしてくれたのかな
人形が動いているなんて、きっと夢だろうけど…夢でもいい、少しでも長く…この温もりを感じていたい
「また、貴方が泣かないで笑えるときまで…側にいてあげるから。」
「…」
「貴方が泣いていると、私は落ち着かないの。」
…
両親が他界して、何故か家に飾られていた人形のアロマが動き出して僕の世話をし始めたのが数年前の出来事だ。
一時の夢かと思っていたが、今まで暮らしてきてアロマは生きている人形という超常的な存在で、そのそんざいはどうやら夢ではないらしい。
アロマは昔両親に拾われてからずっと家にいて、両親はもちろんのこと僕のこともよく見てきたのだとか。
ただし本来であれば知られざる存在として人前に姿を現わすことは無いはずだった、とアロマから聞いた
あの日、僕が泣いたから放っておけなかったと、アロマは言った。
あの日、僕…松風カオルが泣かなかったら…アロマには出会えてなかった。
あの日、僕は彼女に救われた。
…あの日以来、僕は笑うことができない。
「カオル〜〜〜!朝よ、起きなさい〜!」
ドタバタと騒がしく部屋に入ってくる小さな身体の女の子、フリルのついた可愛らしい服に煌びやかな金髪。
宝石の様な碧い瞳で、芸術品のような作り込まれた美しい顔立ちの彼女…生きた人形のアロマだ。
「…あぁ、起きてるよ。アロマ。」
「あら、いい子いい子〜♪ちゃんと起きていてえらいですわね〜♪」
「朝起きるだけで褒められる世界、チョロいね」
「さぁ、朝ごはん出来てるから降りていらっしゃい」
「はいはい、分かってるよ…っと」
「きゃっ、急に抱っこして…レディを気軽に抱えるものじゃありませんことよ?一言かけて下さいまし。」
「いいじゃん、この方が楽でしょ?それに、ちょっと昔のこと思い出してさ…アロマのこと、もっと感じてたいんだ。」
「あらあら…もう、しょうがない子ね。ほらほら、早く行きましてよ。」
ちょっと文句を言うアロマだが、甘んじて抱っこさせてもらう…この程よい重さと暖かさが、アロマの存在を実感させてくれる。
「今日は学校もお休みねぇ、こんなにいい天気だしどこか出かけるかしら?」
「…いや、家にいるよ。外出ても楽しくないし、アロマといた方が楽しいよ」
「あらぁ、嬉しいこと言ってくれるのね♪それじゃあ一緒にテレビでも見ましょうか」
朝食後、今日は学校も休みなので家でアロマとのんびりすることにした
リビングのソファに座り、膝の上でアロマを抱えてテレビのチャンネルを変えていく
「面白いテレビやってないなー」
「この前録画したお笑いの番組はどうかしら?なかなか面白かったからオススメでしてよ」
「…アロマって、その見た目でお笑いとか好きだよね」
「いいじゃありませんの。人を笑顔にする番組、素晴らしいですわ♪」
「そう…」
僕は感情の中で、笑うということが上手く出来ない。
感情が無い、わけではない。
楽しいと思うし、嬉しい感じる…と思う。
ただ、あの日以来、感情を表に出すことがうまくできなくなったようだった。
アロマがこうしてお笑いの番組を見せるのは、笑わなくなった僕のことを思ってのことだったりするのかもしれない
「ふふ、ふふっ…くくっ、バナナ…バナナですって!あー、お腹痛いですわ…」
「…」
きっと、僕のため…どうにか笑わせようと、してくれているんだろう、多分。
覚えてはないけど、たしかに約束したんだ。
昔、笑うことを…泣かないことを…きっとアロマに
「…ねぇ」
「ひぃ〜…くくくっ、ん?何かしらカオル?」
「…僕ってさ、ずっと前にアロマに会ったことあるのかな」
「…あるわよ、ご両親が無くなった日。あの時泣いてるカオルが見てられなくて〜」
「いや、それより前…うんと小さい頃とか、アロマはその時からうちにいたんだよね?」
「ええ、拾われてきた人形として…ね。でも、ちゃんと喋ったのはあの時が初めてのはずよ?そうでしょう?」
「いや、うん…そうだと、思うけど…」
「何か小さい頃のことでも思い出した?」
「いや、そうじゃないんだ…ゴメン、何でもないよ」
「そう、ならいいのだわ♪」
アロマは、昔に出会っていることを聞くと何故か否定する。
たしかに確固たる証拠があるわけじゃないけど、それでも小さな頃の僕とアロマが出会っていることは何も不思議ではない。
ただでさえ長い間生きている人形である正体を隠していたアロマだ、当時のことを隠すのであればアロマにも事情があるのだろう。
(…当時のこと、もし会っているなら興味あるけど。無理に聞くものでもないしね…)
「…じ〜」
「な、なに?アロマ…」
僕の考えていることをよそにアロマは僕の顔をじっと覗き込む
「えいっ♪」
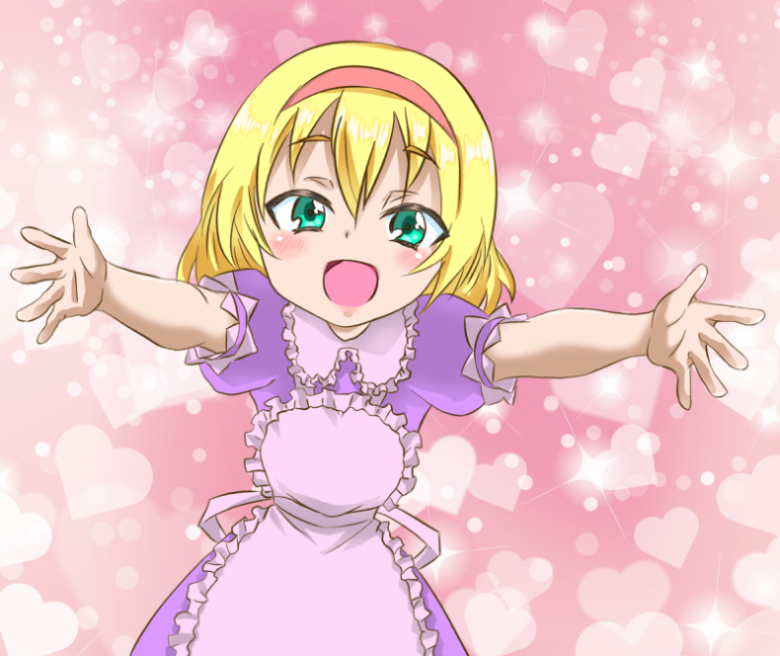
「…あにふるの(なにするの)」
アロマが僕の両頬を掌でぶにっと無理やり上げさせる
たまにやる、アロマが僕の顔に無理やり笑顔を作ろうとさせるやつだった
「そう…まだ、なのね」
「…だから無理だって」
「ふふ、私はそう遠くないと思ってるのだわ」
…
今からもう十何年も前になるかしらね、その頃から私は生きている状態の魔物であり、人形としてあらゆる人間をその美貌で虜にするつもりだった
そして、私はとある家庭に拾われた。
"なんだ?こんなところにこんな綺麗な人形が…せっかくだ、うちの子のおもちゃにプレゼントしてあげよう"
(ふふっ、愚かな人ね…これから私のことしか考えられなくしてあげるから…♪)
"あら貴方、この人形は?"
"あぁ、拾ったんだ。綺麗だろう?うちの子のおもちゃにと思って"
"あらあら、うちの子は男の子よ?"
"いいじゃないか、こんなに綺麗な人形なんだ。うちの子には美的感覚も養ってもらいたいからね"
"いいわねぇ、将来は芸術家かしら?"
(ふふ、呑気な人達ね…夫婦かしら?子供を含めて私のことしか愛せなくしてあげるから覚悟しなさい…)
私はリビングドールとしての所有者の愛情を全て頂くことが使命だったから、そんな風に考えていた
あの子に出会うまでは…
「おぎゃあ!おぎゃあ!」
「へぇ…この家には赤ちゃんがいるのね」
夜の時間、人が寝静まる静寂な時間こそ魔物である私の活動時間。
いきなり動いているのがバレてしまっては家を追い出されてしまう可能性があるから、時間をかけてゆっくりと私という存在を認識させる必要があった
そのため今は人目のない夜だけが活動時間になるのだわ
「ふーん、赤ちゃんねぇ…そんなに可愛いものかしら?私の方が圧倒的に…」
「おぎゃあ!おぎゃあ!」
「クスクス、ぶちゃいくなおサルさんみたいなのだわ。私の方が美しいわね…」
あの子との出会いはこれが初めてだった、向こうはまだ小さな赤ん坊で…この子も将来、私の虜にする予定だった。
「人間の赤ちゃんだなんて初めて見るわね…珍しいしちょっと観察しようかしら」
…
「おぎゃあ!おぎゃあ!」
「…い、いつまで泣くのかしら…?だ、大丈夫なの?声枯れてきてるわよ?」
かれこれ観察を始めてから数時間、この赤ん坊はずっと泣いていた。
お腹が空いているか、おしめを取り替えなくちゃいけない時間なのかしら
「おぎゃあ!おぎゃあ!」
「ちょいとこの子のママ!もう何時間も泣いてるわよ!おしめとミルク!」
流石に見過ごせなくなった私は、呑気に眠りこけている母親を起こしてあげることにしました。
万が一私を見られても、今なら夢だと思ってくれるだろうし…何より私はこの子の泣いている姿を見ているとどうしても落ち着かなかったから。
「ぐぅ…ぐぅ…あらいやだわ、私これでも人妻でぇ…zzz」
「起きない!ああもう…!仕方ないんだから…!」
母親の方は完全に起きる気配は無かった、まぁ普段からのお世話で疲れてるのかもしれないし…仕方ないからここは私が一肌脱いであげましょう
この家族は私が虜にするのだから、この赤ちゃんに何かあってはいけないのだわ
「さ、今おしめを…」
「おぎゃあ!おぎゃあ!」
「ああ暴れないでぇ!えっと、確かママの人はこうして抱っこしてあげて…」
「ふぎゃ…」
人形の私と比較してもまだ小さい赤ん坊のこの子を抱きかかえてあげる、柔らかくて熱くて…力を入れると壊れてしまいそうなほど…
「な、泣き止んだ…よしよし、効果絶大なのだわ。今のうちにミルクをあげて…」
「んまっ…」
「ミルクを飲んでるうちにおしめね、確かこうして…」
「きゃっきゃっ」
「…ふぅ、完了だわ!うふふ、私の顔見て笑うなんて失礼な赤ちゃんなのだわ。この名だたる人形職人に仕立てられた芸術的な顔の虜になるといいのだわ、ほらニコニコ〜♪」
「きゃっきゃっ♪」
この日以来…私は夜、眠っている母親の代わりにこの子のお世話をすることになった。
「ふむ、このたまごク○ブって本は中々学べることが多いのだわ。」
「おぎゃあ!おぎゃあ!」
「!…よしよし、ここにいるわよぉ〜」
「あぅ〜…あうあう〜♪」
「はい、ニコニコ〜♪…はぁ、なんであなたは15分毎に泣くのかしら?毎晩ずっと…」
「あぅ?」
「母親が寝てしまう夜中、貴方の面倒をずっと見て…知ってるかしら?貴方のママなんて"ウチの子、夜はぐっすりで良い子なのよ"なんて言うのよ、貴方はむしろ夜型なのにね?」
貴方が泣くと、私はどうしても落ち着かないの
…だから、早く大きくなって泣かないようになってね。
…
「昔昔、とある芸術家に作られたアロマと呼ばれる人形がおりました。」
あれから時折、私は自分の昔話をこの子に聞かせてあげる
「彼女は美を追求された大変美しい人形で、世に出てたくさんの人々を魅了し愛されるはずでした。」
まだ喋れないこの子が話を理解しているか分からないけど、それでも私のことを少しでも愛してくれたら…
「しかし彼女が世に出ることはありませんでした、彼女を創り出した芸術家が、完成間近で病に伏し…亡くなってしまったから。」
そう、愛してもらえたら…どんなに嬉しいか…
「芸術家が亡くなり、世に出ることが出来なかった彼女は…自ら世界に飛び出しました、世界の人々をこの美貌で魅了する使命のため、生まれた理由のため、魔物と呼ばれる存在になって。」
「あ、りょ…ま」
「ん?」
「ありょ、ま」
「貴方、今…しゃべった…?」
「あぅ…」
「わ、立っ…!」
今までハイハイしか出来なくて、言葉も喋れなかったあの子が…立ち上がって、私の名前をたしかに喋った。
「ありょま」
にこぉ、と微笑んだ顔が、とても愛おしくて…堪らなく胸が熱くなって…
「 」
きっとこの時から私は、いいえ…それよりもずっと前から、自分の使命なんてどうでもよくなっていて
人々を魅了するという生き方を放棄して、この子をあらゆる障害から守って、この笑顔を絶やさないようにしようと…そう決めました。
…
それから3年も過ぎて…私とあの子の、夜だけの逢瀬に変化が訪れます。
「さぁ!今日は何をして遊ぼうかしら!お絵かき?積み木かしら?それともおままごと…」
「うん…」
「あら、貴方…」
今まで夜に眠ることのなかったあの子は…こっくりこっくりと船を漕ぎ、とうとう眠ってしまって…
「3歳になって…やっと朝まで起きずに寝られるようになったのね…」
あの子がちゃんと、夜に眠ることができるようになった…それが意味をすることは
「夜にお世話する私の役目はおしまいかしら。」
夜だけ、眠れないこの子のお世話する関係の終わり。
「…でも、ずっとそばにいるからね。貴方の幸せを願って、見守っててあげるから…だから、もう泣いちゃダメよ。ずっと、笑っていてね。」
本当は、この子の幸せを考えるなら…私はここで消えるべきでした
人ならざる魔物、リビングドールの私は…この子に普通の人間と同じ幸せをあげることができないから。
本来いるはずのない存在として、この子の前から消えるべきだったのに…もうあの子を見守っているだけで、よかったのに…
「うあぁ…お母さん、お父さん…!」
"ただ、あの時…あの子が泣いたから"
あの子が泣くと、私はどうにも落ち着かないの。
「もう、泣かないで…って、約束したのに」
だから、あの時…再びあの子に声をかけてしまった。
両親を亡くすという理不尽な障害も、あの子が自力で乗り越えるべき試練だったのかもしれないけど…
それでもあの時、泣いたあの子を放ってはおけなかった。
あの時以来…私とカオルの関係は昔と同じように戻った。
けれど、ひとつだけ戻らないものがありました。
「ねぇ、笑って?ほら、ニコニコ〜♪」
「…」
カオルの笑顔が消えてしまった、感情そのものが希薄になってしまったようでした。
あの出来事の直後に比べたら、今は大分感情を出してくれるようになったけれど…あの子が笑うことはありません。
いつか、またカオルが笑ってくれるまで…その時まで私は、側にいましょう
そしてカオルがまた笑って幸せになった時、私は…再びただのお人形に戻る。
生まれたばかりの貴方が、その小さな身体で立ち上がって…名前を呼んで、笑いかけてくれたあの日から…私は貴方の為だけに生きると決めたから
…
「アロマ、お笑い番組終わったよ」
「…え、あら本当なのだわ」
「次の録画した番組も見る?」
「んー、次何かしら…あ!短編恋愛シリーズドラマ『恋する魔物は切なくて』のベスト集じゃない、見ましょう!」
「ん…」
世界的に有名な恋愛ドラマ、僕はそんなに興味ないけど…まぁ、アロマが見たいならいいか
「…いつかはカオルも恋愛とかするのかしらね」
「どうだろうね…」
「いつか、人を好きになったら…貴方にも笑顔が戻るかもしれないですわ」
「僕は、アロマのこと好きだよ?」
「なぅっ!?お、おバカ…恋愛感情のことですわ」
恋愛感情…人を好きになるってどういうことなのかな
僕はアロマが好き、だと思う…ずっと一緒に居たいと思っているし、離れたくないとも思っている
これは恋愛の好き、とは違うのだろうか
「恋をした時の好き、って気持ちはね?胸がキューってして、苦しくなるの。胸がドキドキしてたまらなくじっとしていられなくなるの」
「…不整脈?」
「難しい言葉知ってるわね、って違いますわよ!」
「冗談、冗談」
「真顔で言われても困るのだわ…仮に、カオルが私のこと好きでもダメよ。私ね、実は貴方より好きな人がいるの。」
「えっ」
初耳だった、アロマは外に出ることはあまり無いし僕以外の人間と関わりがあるなんて…なんだろう、今の言葉を聞いた瞬間、胸が何かに刺されたような痛みを感じる
母さんや父さんを亡くしたあの日に似た、苦しい痛みが僕の胸を締め付けた
「ね、ねぇ…それって、誰?」
「知りたい?」
「…」
「あら、あなたのそんな顔を見るのは久しぶりね。…私の好きな人、それはね、笑顔の貴方よ」
「笑顔の、僕?」
「世界一素敵な殿方なのよ、私の生き方を変えてしまうくらい…あなたにも、会わせてあげたいくらいだわ」
「なんだよ、なんだよ…それ、可笑しいよ。僕はもう笑えないかもしれないのに、それなのにアロマは笑顔の僕が一番だっていうの…?」
「あの日以来ね、貴方の涙を見るのは」
「泣いてる…?僕は今、泣いているの…?」
「…泣くことが出来るなら…感情はもう、取り戻しているのでしょう?」
「胸が熱いよ、熱い何かが…込み上げてくるんだ…それが、目から溢れてきて…苦しくて、胸がキューってするんだ…!」
「ふふ、嬉しい…カオルは私にちゃんと恋愛感情を持ってくれているのね?ねぇ、だから、もう観念して…私の大好きな人に会わせて?」
「アロマ、アロマぁ…っ!」
私の大好きな笑顔が、目の前で弾ける。
あぁ…ようやく、帰ってきてくれたのね。
「ねぇ、今…僕は笑えてる?」
「えぇ、えぇ…っ」
長かったわ、あの日から1秒が一生に感じるくらい。
「おかえりなさい、私の大好きな人。」
おしまい。
笑うこと、泣かないことを…覚えて無いけど誰かに約束した気がして、泣かない様に明るく振舞ってきた
ただ、両親が事故で他界したあの日だけは…僕はその約束を守れなかった。
大好きな両親だった、いつも優しくて…愛情いっぱいに僕を愛してくれていた。
笑いが絶えない家庭で、これがずっと続くものだと思い込んでいた…しかしそんな幸せが壊れるのは一瞬だった。
突然の交通事故、それもかなり大きな規模で発生して僕の両親は巻き込まれて亡くなった。
きっと、今まで生きてきた中で一番泣いた。
涙が出なくなっても、嗚咽を漏らし続け…そして、両親の後を追うことも考えた。
"もう、泣かないで…って、約束したのに"
そこに立っていたのは僕が生まれた時から居間に飾られている、芸術品の様な気品がある古いアンティークドールだった。
普段は感情のない、無の顔をしていてそこに生気は感じられないが、今はまるで生きているかの様に表情を変え、動いている
人形が勝手に動き出す…ありえない光景だが、何故か僕は、まるで生きている様な今の彼女を知っている様な気がした。
「君は…人形の…」
「アロマ」
アロマ、彼女はそう名乗った。
アロマ、あろま…初めて聞く名前のはずなのに、とても呼び慣れた名前だった。
「また泣き虫さんなのね…泣かないって、約束したじゃない。」
「…無理だよ、そんなの…悲しくて、苦しくてたまらないんだ…」
「…そう、だったら仕方ないわね。」
となりに座った小さな身体の彼女は、そのまま僕のことを抱きしめた。
あぁ、なんだかずっと前にもこんなことがあった気がする…懐かしい、母さんがこうしてくれたのかな
人形が動いているなんて、きっと夢だろうけど…夢でもいい、少しでも長く…この温もりを感じていたい
「また、貴方が泣かないで笑えるときまで…側にいてあげるから。」
「…」
「貴方が泣いていると、私は落ち着かないの。」
…
両親が他界して、何故か家に飾られていた人形のアロマが動き出して僕の世話をし始めたのが数年前の出来事だ。
一時の夢かと思っていたが、今まで暮らしてきてアロマは生きている人形という超常的な存在で、そのそんざいはどうやら夢ではないらしい。
アロマは昔両親に拾われてからずっと家にいて、両親はもちろんのこと僕のこともよく見てきたのだとか。
ただし本来であれば知られざる存在として人前に姿を現わすことは無いはずだった、とアロマから聞いた
あの日、僕が泣いたから放っておけなかったと、アロマは言った。
あの日、僕…松風カオルが泣かなかったら…アロマには出会えてなかった。
あの日、僕は彼女に救われた。
…あの日以来、僕は笑うことができない。
「カオル〜〜〜!朝よ、起きなさい〜!」
ドタバタと騒がしく部屋に入ってくる小さな身体の女の子、フリルのついた可愛らしい服に煌びやかな金髪。
宝石の様な碧い瞳で、芸術品のような作り込まれた美しい顔立ちの彼女…生きた人形のアロマだ。
「…あぁ、起きてるよ。アロマ。」
「あら、いい子いい子〜♪ちゃんと起きていてえらいですわね〜♪」
「朝起きるだけで褒められる世界、チョロいね」
「さぁ、朝ごはん出来てるから降りていらっしゃい」
「はいはい、分かってるよ…っと」
「きゃっ、急に抱っこして…レディを気軽に抱えるものじゃありませんことよ?一言かけて下さいまし。」
「いいじゃん、この方が楽でしょ?それに、ちょっと昔のこと思い出してさ…アロマのこと、もっと感じてたいんだ。」
「あらあら…もう、しょうがない子ね。ほらほら、早く行きましてよ。」
ちょっと文句を言うアロマだが、甘んじて抱っこさせてもらう…この程よい重さと暖かさが、アロマの存在を実感させてくれる。
「今日は学校もお休みねぇ、こんなにいい天気だしどこか出かけるかしら?」
「…いや、家にいるよ。外出ても楽しくないし、アロマといた方が楽しいよ」
「あらぁ、嬉しいこと言ってくれるのね♪それじゃあ一緒にテレビでも見ましょうか」
朝食後、今日は学校も休みなので家でアロマとのんびりすることにした
リビングのソファに座り、膝の上でアロマを抱えてテレビのチャンネルを変えていく
「面白いテレビやってないなー」
「この前録画したお笑いの番組はどうかしら?なかなか面白かったからオススメでしてよ」
「…アロマって、その見た目でお笑いとか好きだよね」
「いいじゃありませんの。人を笑顔にする番組、素晴らしいですわ♪」
「そう…」
僕は感情の中で、笑うということが上手く出来ない。
感情が無い、わけではない。
楽しいと思うし、嬉しい感じる…と思う。
ただ、あの日以来、感情を表に出すことがうまくできなくなったようだった。
アロマがこうしてお笑いの番組を見せるのは、笑わなくなった僕のことを思ってのことだったりするのかもしれない
「ふふ、ふふっ…くくっ、バナナ…バナナですって!あー、お腹痛いですわ…」
「…」
きっと、僕のため…どうにか笑わせようと、してくれているんだろう、多分。
覚えてはないけど、たしかに約束したんだ。
昔、笑うことを…泣かないことを…きっとアロマに
「…ねぇ」
「ひぃ〜…くくくっ、ん?何かしらカオル?」
「…僕ってさ、ずっと前にアロマに会ったことあるのかな」
「…あるわよ、ご両親が無くなった日。あの時泣いてるカオルが見てられなくて〜」
「いや、それより前…うんと小さい頃とか、アロマはその時からうちにいたんだよね?」
「ええ、拾われてきた人形として…ね。でも、ちゃんと喋ったのはあの時が初めてのはずよ?そうでしょう?」
「いや、うん…そうだと、思うけど…」
「何か小さい頃のことでも思い出した?」
「いや、そうじゃないんだ…ゴメン、何でもないよ」
「そう、ならいいのだわ♪」
アロマは、昔に出会っていることを聞くと何故か否定する。
たしかに確固たる証拠があるわけじゃないけど、それでも小さな頃の僕とアロマが出会っていることは何も不思議ではない。
ただでさえ長い間生きている人形である正体を隠していたアロマだ、当時のことを隠すのであればアロマにも事情があるのだろう。
(…当時のこと、もし会っているなら興味あるけど。無理に聞くものでもないしね…)
「…じ〜」
「な、なに?アロマ…」
僕の考えていることをよそにアロマは僕の顔をじっと覗き込む
「えいっ♪」
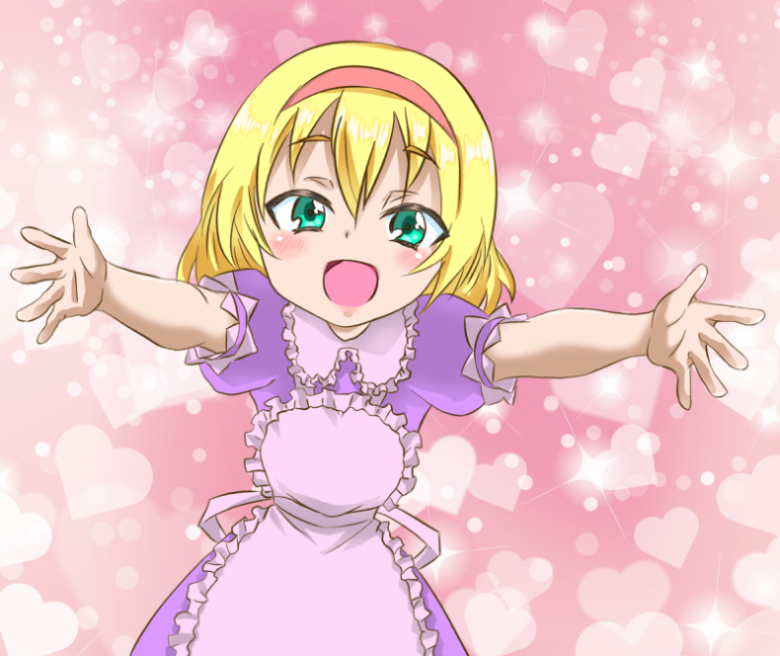
「…あにふるの(なにするの)」
アロマが僕の両頬を掌でぶにっと無理やり上げさせる
たまにやる、アロマが僕の顔に無理やり笑顔を作ろうとさせるやつだった
「そう…まだ、なのね」
「…だから無理だって」
「ふふ、私はそう遠くないと思ってるのだわ」
…
今からもう十何年も前になるかしらね、その頃から私は生きている状態の魔物であり、人形としてあらゆる人間をその美貌で虜にするつもりだった
そして、私はとある家庭に拾われた。
"なんだ?こんなところにこんな綺麗な人形が…せっかくだ、うちの子のおもちゃにプレゼントしてあげよう"
(ふふっ、愚かな人ね…これから私のことしか考えられなくしてあげるから…♪)
"あら貴方、この人形は?"
"あぁ、拾ったんだ。綺麗だろう?うちの子のおもちゃにと思って"
"あらあら、うちの子は男の子よ?"
"いいじゃないか、こんなに綺麗な人形なんだ。うちの子には美的感覚も養ってもらいたいからね"
"いいわねぇ、将来は芸術家かしら?"
(ふふ、呑気な人達ね…夫婦かしら?子供を含めて私のことしか愛せなくしてあげるから覚悟しなさい…)
私はリビングドールとしての所有者の愛情を全て頂くことが使命だったから、そんな風に考えていた
あの子に出会うまでは…
「おぎゃあ!おぎゃあ!」
「へぇ…この家には赤ちゃんがいるのね」
夜の時間、人が寝静まる静寂な時間こそ魔物である私の活動時間。
いきなり動いているのがバレてしまっては家を追い出されてしまう可能性があるから、時間をかけてゆっくりと私という存在を認識させる必要があった
そのため今は人目のない夜だけが活動時間になるのだわ
「ふーん、赤ちゃんねぇ…そんなに可愛いものかしら?私の方が圧倒的に…」
「おぎゃあ!おぎゃあ!」
「クスクス、ぶちゃいくなおサルさんみたいなのだわ。私の方が美しいわね…」
あの子との出会いはこれが初めてだった、向こうはまだ小さな赤ん坊で…この子も将来、私の虜にする予定だった。
「人間の赤ちゃんだなんて初めて見るわね…珍しいしちょっと観察しようかしら」
…
「おぎゃあ!おぎゃあ!」
「…い、いつまで泣くのかしら…?だ、大丈夫なの?声枯れてきてるわよ?」
かれこれ観察を始めてから数時間、この赤ん坊はずっと泣いていた。
お腹が空いているか、おしめを取り替えなくちゃいけない時間なのかしら
「おぎゃあ!おぎゃあ!」
「ちょいとこの子のママ!もう何時間も泣いてるわよ!おしめとミルク!」
流石に見過ごせなくなった私は、呑気に眠りこけている母親を起こしてあげることにしました。
万が一私を見られても、今なら夢だと思ってくれるだろうし…何より私はこの子の泣いている姿を見ているとどうしても落ち着かなかったから。
「ぐぅ…ぐぅ…あらいやだわ、私これでも人妻でぇ…zzz」
「起きない!ああもう…!仕方ないんだから…!」
母親の方は完全に起きる気配は無かった、まぁ普段からのお世話で疲れてるのかもしれないし…仕方ないからここは私が一肌脱いであげましょう
この家族は私が虜にするのだから、この赤ちゃんに何かあってはいけないのだわ
「さ、今おしめを…」
「おぎゃあ!おぎゃあ!」
「ああ暴れないでぇ!えっと、確かママの人はこうして抱っこしてあげて…」
「ふぎゃ…」
人形の私と比較してもまだ小さい赤ん坊のこの子を抱きかかえてあげる、柔らかくて熱くて…力を入れると壊れてしまいそうなほど…
「な、泣き止んだ…よしよし、効果絶大なのだわ。今のうちにミルクをあげて…」
「んまっ…」
「ミルクを飲んでるうちにおしめね、確かこうして…」
「きゃっきゃっ」
「…ふぅ、完了だわ!うふふ、私の顔見て笑うなんて失礼な赤ちゃんなのだわ。この名だたる人形職人に仕立てられた芸術的な顔の虜になるといいのだわ、ほらニコニコ〜♪」
「きゃっきゃっ♪」
この日以来…私は夜、眠っている母親の代わりにこの子のお世話をすることになった。
「ふむ、このたまごク○ブって本は中々学べることが多いのだわ。」
「おぎゃあ!おぎゃあ!」
「!…よしよし、ここにいるわよぉ〜」
「あぅ〜…あうあう〜♪」
「はい、ニコニコ〜♪…はぁ、なんであなたは15分毎に泣くのかしら?毎晩ずっと…」
「あぅ?」
「母親が寝てしまう夜中、貴方の面倒をずっと見て…知ってるかしら?貴方のママなんて"ウチの子、夜はぐっすりで良い子なのよ"なんて言うのよ、貴方はむしろ夜型なのにね?」
貴方が泣くと、私はどうしても落ち着かないの
…だから、早く大きくなって泣かないようになってね。
…
「昔昔、とある芸術家に作られたアロマと呼ばれる人形がおりました。」
あれから時折、私は自分の昔話をこの子に聞かせてあげる
「彼女は美を追求された大変美しい人形で、世に出てたくさんの人々を魅了し愛されるはずでした。」
まだ喋れないこの子が話を理解しているか分からないけど、それでも私のことを少しでも愛してくれたら…
「しかし彼女が世に出ることはありませんでした、彼女を創り出した芸術家が、完成間近で病に伏し…亡くなってしまったから。」
そう、愛してもらえたら…どんなに嬉しいか…
「芸術家が亡くなり、世に出ることが出来なかった彼女は…自ら世界に飛び出しました、世界の人々をこの美貌で魅了する使命のため、生まれた理由のため、魔物と呼ばれる存在になって。」
「あ、りょ…ま」
「ん?」
「ありょ、ま」
「貴方、今…しゃべった…?」
「あぅ…」
「わ、立っ…!」
今までハイハイしか出来なくて、言葉も喋れなかったあの子が…立ち上がって、私の名前をたしかに喋った。
「ありょま」
にこぉ、と微笑んだ顔が、とても愛おしくて…堪らなく胸が熱くなって…
「 」
きっとこの時から私は、いいえ…それよりもずっと前から、自分の使命なんてどうでもよくなっていて
人々を魅了するという生き方を放棄して、この子をあらゆる障害から守って、この笑顔を絶やさないようにしようと…そう決めました。
…
それから3年も過ぎて…私とあの子の、夜だけの逢瀬に変化が訪れます。
「さぁ!今日は何をして遊ぼうかしら!お絵かき?積み木かしら?それともおままごと…」
「うん…」
「あら、貴方…」
今まで夜に眠ることのなかったあの子は…こっくりこっくりと船を漕ぎ、とうとう眠ってしまって…
「3歳になって…やっと朝まで起きずに寝られるようになったのね…」
あの子がちゃんと、夜に眠ることができるようになった…それが意味をすることは
「夜にお世話する私の役目はおしまいかしら。」
夜だけ、眠れないこの子のお世話する関係の終わり。
「…でも、ずっとそばにいるからね。貴方の幸せを願って、見守っててあげるから…だから、もう泣いちゃダメよ。ずっと、笑っていてね。」
本当は、この子の幸せを考えるなら…私はここで消えるべきでした
人ならざる魔物、リビングドールの私は…この子に普通の人間と同じ幸せをあげることができないから。
本来いるはずのない存在として、この子の前から消えるべきだったのに…もうあの子を見守っているだけで、よかったのに…
「うあぁ…お母さん、お父さん…!」
"ただ、あの時…あの子が泣いたから"
あの子が泣くと、私はどうにも落ち着かないの。
「もう、泣かないで…って、約束したのに」
だから、あの時…再びあの子に声をかけてしまった。
両親を亡くすという理不尽な障害も、あの子が自力で乗り越えるべき試練だったのかもしれないけど…
それでもあの時、泣いたあの子を放ってはおけなかった。
あの時以来…私とカオルの関係は昔と同じように戻った。
けれど、ひとつだけ戻らないものがありました。
「ねぇ、笑って?ほら、ニコニコ〜♪」
「…」
カオルの笑顔が消えてしまった、感情そのものが希薄になってしまったようでした。
あの出来事の直後に比べたら、今は大分感情を出してくれるようになったけれど…あの子が笑うことはありません。
いつか、またカオルが笑ってくれるまで…その時まで私は、側にいましょう
そしてカオルがまた笑って幸せになった時、私は…再びただのお人形に戻る。
生まれたばかりの貴方が、その小さな身体で立ち上がって…名前を呼んで、笑いかけてくれたあの日から…私は貴方の為だけに生きると決めたから
…
「アロマ、お笑い番組終わったよ」
「…え、あら本当なのだわ」
「次の録画した番組も見る?」
「んー、次何かしら…あ!短編恋愛シリーズドラマ『恋する魔物は切なくて』のベスト集じゃない、見ましょう!」
「ん…」
世界的に有名な恋愛ドラマ、僕はそんなに興味ないけど…まぁ、アロマが見たいならいいか
「…いつかはカオルも恋愛とかするのかしらね」
「どうだろうね…」
「いつか、人を好きになったら…貴方にも笑顔が戻るかもしれないですわ」
「僕は、アロマのこと好きだよ?」
「なぅっ!?お、おバカ…恋愛感情のことですわ」
恋愛感情…人を好きになるってどういうことなのかな
僕はアロマが好き、だと思う…ずっと一緒に居たいと思っているし、離れたくないとも思っている
これは恋愛の好き、とは違うのだろうか
「恋をした時の好き、って気持ちはね?胸がキューってして、苦しくなるの。胸がドキドキしてたまらなくじっとしていられなくなるの」
「…不整脈?」
「難しい言葉知ってるわね、って違いますわよ!」
「冗談、冗談」
「真顔で言われても困るのだわ…仮に、カオルが私のこと好きでもダメよ。私ね、実は貴方より好きな人がいるの。」
「えっ」
初耳だった、アロマは外に出ることはあまり無いし僕以外の人間と関わりがあるなんて…なんだろう、今の言葉を聞いた瞬間、胸が何かに刺されたような痛みを感じる
母さんや父さんを亡くしたあの日に似た、苦しい痛みが僕の胸を締め付けた
「ね、ねぇ…それって、誰?」
「知りたい?」
「…」
「あら、あなたのそんな顔を見るのは久しぶりね。…私の好きな人、それはね、笑顔の貴方よ」
「笑顔の、僕?」
「世界一素敵な殿方なのよ、私の生き方を変えてしまうくらい…あなたにも、会わせてあげたいくらいだわ」
「なんだよ、なんだよ…それ、可笑しいよ。僕はもう笑えないかもしれないのに、それなのにアロマは笑顔の僕が一番だっていうの…?」
「あの日以来ね、貴方の涙を見るのは」
「泣いてる…?僕は今、泣いているの…?」
「…泣くことが出来るなら…感情はもう、取り戻しているのでしょう?」
「胸が熱いよ、熱い何かが…込み上げてくるんだ…それが、目から溢れてきて…苦しくて、胸がキューってするんだ…!」
「ふふ、嬉しい…カオルは私にちゃんと恋愛感情を持ってくれているのね?ねぇ、だから、もう観念して…私の大好きな人に会わせて?」
「アロマ、アロマぁ…っ!」
私の大好きな笑顔が、目の前で弾ける。
あぁ…ようやく、帰ってきてくれたのね。
「ねぇ、今…僕は笑えてる?」
「えぇ、えぇ…っ」
長かったわ、あの日から1秒が一生に感じるくらい。
「おかえりなさい、私の大好きな人。」
おしまい。
22/06/11 20:55更新 / ミドリマメ