04乽僒僀僋儘僾僗偲憖傝恖宍乮屻曇乯乿
乽僐乕僗働偔傫偭両丂夡傟偨傜壗搙偱傕巹偑廋棟偡傞偭両丂偩偐傜乧乧慜偵弌偰偭両両乿
丂偁傫側偵戝惡傪忋偘偨偺偼丄偄偮埲棃偩傠偆丠丂偦傟傕丄戝惃偺恖偑尒偰偄傞慜偱丅
丂偱傕丄偁偺帪偼抪偢偐偟偄偲偐丄僸僩僣栚偺帺暘偑栚棫偮偲婥枴埆偑傜傟傞偲偐側傫偰丄偙傟偭傐偭偪傕巚偭偰側偐偭偨丅斵偺攚拞傪墴偟偰偁偘偨偄偲偄偆婥帩偪偱摢偺拞偑堦攖偵側傝丄敿偽柍変柌拞偩偭偨丅
丂偩偐傜丄帺暘偑慻傒捈偟偨儊僈僷儁僢僩偲偄偆嫄戝側僇儔僋儕恖宍偑帋崌偵彑偭偨偙偲埲忋偵丄斵偲堦弿偵擇夞愴傊偲恑傔偨偙偲偑婐偟偐偭偨丅
丂偦偟偰乽儂僲僇偪傖傫乿偲屇傃偐偗傜傟偨偲偒乧乧偳偆偟偰帺暘偑偙偙傑偱偐偐傢偭偰偒偨偺偐丄偦偺棟桼偵婥偯偔偙偲偑偱偒偨丅
丂偦偭偐乧乧僐乕僗働偔傫丄偁偺恖偵帡偰傞傫偩劅劅
丂偢偭偲怱偺墱偵巇晳偄崬傫偱偄偨丄巚偄偲崌傢偣偰丅
亙仠亜
丂戞敧夞慡擔杮儘儃俿俼倄慖庤尃丄抧嬫梊慖夛擇夞愴丅
丂傾僫僂儞僗偲偲傕偵丄擇懱偺恖宆廳婡劅劅儊僈僷儁僢僩偑僶僩儖僗僥乕僕偵忋偑傝丄奺乆偺懸婡慄傊偲曕傪恑傔傞丅
乽憡庤偼婂儢庱戝妛偺儘儃僢僩尋媶夛乧乧戝夛偺忢楢偝傫偩傛乿
乽乧乧彑偰傞丠乿
乽彑偮傛丅儂僲僇偪傖傫偑惍旛偟偰偔傟偨僐僀僣偱乿
丂椬偵偄傞僒僀僋儘僾僗柡偵偦偆摎偊傞偲丄峛夘偼慜傪曕偔帺暘偺婡懱偵帇慄傪岦偗偨丅
乽偄偭偗偉僐乕僗働両丂偦偙偺僾儗僀儎乕偛偲傇偭偲偽偣乣偭両両乿
乽乧乧偦傟傗偭偨傜堦敪偱斀懃晧偗偵側傞偱丄僫僊乿
乽側傫偩偲両丠丂偊偊偄偭丄偙偺巹偑偄傞尷傝偦傫側恀帡偼愨懳偵偝偣傫偧偭両乿
丂杊岇僼僃儞僗偺奜懁偵偼丄崱擔傕戝惃偺僊儍儔儕乕偑墳墖偵廤傑偭偰偄傞丅
丂擇恖偑墶栚偱偆偐偑偆偲丄婂儢庱戝儘儃尋偺彈惈僾儗僀儎乕乮偺嫻乯傪恊偺僇僞僉偲偽偐傝偵僸僩僣栚偱嵘傒偮偗側偑傜惡傪忋偘傞僎僀僓乕柡僫僊偵丄斵曽偑嬯徫傪晜偐傋偰僣僢僐傫偱丄償傽儖僉儕乕偺儖儈僫偑旣傪捿傝忋偘傑偔偟棫偰偰偄偨丅偦偺墶偱丄暥梩偑僗儅儂曅庤偵庤傪怳偭偰偔傞丅
乽乧乧乧乧乿
乽乧乧偔偡偭乿
丂桭恖偨偪偺暯忢塣揮側巔偵丄尐偺椡偑偄偄嬶崌偵敳偗偨丅
丂峛夘偨偪偺婡懱乹俿倃亅係係夵乺偵憡懳偡傞偺偼丄棏宆偺摢晹偑摿挜揑側墿怓偺儊僈僷儁僢僩丅搊榐婡懱柤偼乹僉僋儌儞侽俁乺丅嫻偲椉尐偺僟儊乕僕儅乕僇乕偺怓偼巼丅
丂帋崌奐巒偺僐乕儖偑嬁偒丄僗僞乕僩僔僌僫儖偺怓偑曄傢傞丅擇懱偼摨帪偵懸婡慄傪廟傝丄恀偭惓柺偐傜傇偮偐傝崌偭偨乧乧
丂乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧
乽Winner両丂僠乕儉丒儌僲傾僀僈乕儖僘両両乿
乽側傫偱乧乧偁傫側億儞僐僣偵劅劅偭乿
丂嫻偲塃尐偺僟儊乕僕儅乕僇乕偺怓偑曄傢偭偨傑傑揚廂偝傟偰偄偔乹僉僋儌儞侽俁乺傪堦曀偟丄婂儢庱戝儘儃尋偺彈惈僾儗僀儎乕偼壵棫偨偟偘偵偮傇傗偄偨丅
丂岥乆偵側偩傔傛偆偲偡傞庢傝姫偒偨偪偺惡傪柍帇偟偰丄憡庤僠乕儉偺婡懱傪嵘傒晅偗傞丅
乽乧乧乧乧乿
丂嬐嵎偩偭偨丅岦偙偆傕嵍尐偺儅乕僇乕偺怓偑曄傢傝丄偦偙偐傜旾傪媡懁偵嬋偘傜傟偨嵍榬偑傇傜傇傜偲椡側偔悅傟壓偑偭偰偄傞丅僣僊僴僊側尒偨栚傕偁偭偰丄憡庤偺榬傪捵偟偨偦偺弖娫偵乽彑偭偨両乿偲桘抐丄枬怱偟偰偟傑偭偨偺偑帺暘偨偪偺攕場偩偭偨偺偩傠偆丅
丂傑偝偐僇僂儞僞乕偱丄嫻尦偵摢撍偒偟偰偔傞偲偼巚偄傕偟側偐偭偨丅
丂傆偲丄岦偙偆偺僙僐儞僪偲栚偑崌偭偨丅悈怓偺敡丄妟偵惗偊偨僣僲丄儅儞僈傒偨偄側戝偒側僸僩僣栚偺恖奜彮彈劅劅杺暔柡丅
丂徟偭偨傛偆偵偍帿媀偝傟丄栚傪堩傜偝傟偨丅
乽乧乧偭両乿
丂壔偗暔彈偑偭乧乧偲埆懺傪偮偒偐偗丄偡傫偱偺偲偙傠偱偦傟傪堸傒崬傓丅
丂儅乕僔儍儖傗戝惃偺僊儍儔儕乕偑尒偰偄傞慜偱偦傫側偙偲傪岥憱偭偨傜丄晧偗偨偔偣偵傒偭偲傕側偄丄尒嬯偟偄丄戝恖偘側偄丄噣偁偺噥楢拞偲摨椶偐傛劅劅偲媡偵僨傿僗傜傟丄偙偪傜偑偄傜偸抪傪偐偔偩偗偱偁傞丅
丂斵彈偼彮偟夨偟婥偵棴傔懅傪揻偒丄纟傪曉偟偨丅
亙仠亜
丂師偺帋崌偼堦廡娫屻丅偦傟傑偱偵婡懱傪廋棟偟丄摦偐偣傞傛偆惍旛偟側偗傟偽側傜側偄丅
丂偄偮傕偺晹幒搹偺墶偱丄峛夘偲儂僲僇偼儊僈僷儁僢僩乹俿倃亅係係夵乺偺廋棟傪巒傔偰偄偨丅
丂僫僊偨偪偼晹妶摍偱晄嵼丅戙傢傝偵庤揱偭偰偔傟偰偄傞偺偼劅劅
乽傛偭丄偍偭偲偲偭乧乧偍乕偄儂僲僇偀丄偙傟偳偙偵抲偔傫偩丠乿
乽偙偭偪丅偙偺恀傫拞偵備偭偔傝抲偄偰乿
乽偁偄傛偭乿
丂摢傂偲偮崅偄恎挿丄墿椢怓偺敡丄愒偄敮丄僶儞僟僫傪姫偄偨妟偐傜惗偊偨擇杮偺僣僲丅
丂婡懱偐傜庢傝奜偝傟偨嵍尐偺僇僂儕儞僌傪曅庤偵帩偭偨懱憖暈巔偺僆乕僈柡僒僉偑丄儂僲僇偑巜嵎偡僽儖乕僔乕僩偺忋偵偦傟傪偦偭偲壓傠偟偨丅乽乧乧堄奜偲寉偄傫偩側丅嫄恖偺奪偩偐傜傕偆偪傚偭偲廳偄傕傫偩偲巚偭偰偨偤乿
乽偁傫傑傝廳偄偲娭愡晹偵晧扴偑偐偐傞偐傜偹丅僶僢僥儕乕偺徚栒傕憗偔側傞偟丄杊屼椡傪懝側傢側偄僊儕僊儕傑偱寉検壔偟偰傞傫偩乿
丂婡懱偺庱偺偲偙傠偵屪偑偭偰摢晹偺僙儞僒乕傪嵞挷惍偟偰偄偨峛夘偑丄惛枾僪儔僀僶乕曅庤偵偦偆愢柧偡傞丅傕偭偲傕僆乕僈婎弨偱偺乽寉偄乿偱偁偭偰丄尐晹偺奜憰偼偦偙偦偙廳偝偑偁傞丅埲慜僆乕僶乕儂乕儖偟偨偲偒偼丄峛夘偲斵曽偑擇恖偑偐傝偱庢傝奜偟偰偄偨丅
乽傆偆傫乧乧傑丄梫偼彑偮偨傔偵偄傠偄傠岺晇偝傟偰傞偭偰偙偲偩傛側乿
乽傑丄傑偁偹乧乧乿
丂榬傪慻傒丄暘偐偭偰偄傞偐偺傛偆偵僂儞僂儞偆側偢偔丅偦傫側僒僉偵嬯徫傪晜偐傋傞峛夘偩偑丄撪怱偱偼偙偺婼柡偑偄偮乽堦搙僐僀僣乮儊僈僷儁僢僩乯偲愴傢偣傠傛乿偲偐尵偄偩偝側偄偐丄價僋價僋偟偰偄偨傝偡傞丅
乽傎偐偺奪偼偳乕偡傫偩丠丂儂僲僇乿
乽崱擔偼嵍榬偺廋棟偩偗偩偐傜乧乧偙傟偱偄偄乿
丂偄偒側傝傆傜偭偲尰傟偰丄傾僞僔偵傕庤揱傢偣傠偲惡傪偐偗偰偒偨僒僉丅暦偗偽暥梩偑僗儅儂偱嶣偭偰偄偨帋崌偺摦夋傪尒偰丄嫽枴傪偍傏偊偨偺偩偲偐丅
丂偪側傒偵斵彈偨偪杺暔柡偼丄恎懱峔憿偑僸僩偲偼堘偆偲偄偆棟桼偱僗億乕僣嫞媄夛傊偺弌応傪惂尷偝傟偰偄傞乮嬻傪旘傫偩傜儂乕儉儔儞儃乕儖傕傾僂僩偵偝傟傞乧乧偲偄偆椺偊曽傪恀婄偱偡傞楢拞偼僶僇偭傐偄偲巚偆偑乯丅偦傫側拞偱摨偠杺暔柡偺拠娫偑儌乕僞乕僗億乕僣偺儊僇僯僢僋偲偟偰偱偼偁傞偑丄岞幃偺戝夛偵嶲壛偟彑偪恑傫偱偄傞偺偩丅奆丄戝側傝彫側傝婥偵側偭偰偄傞偺偩傠偆丅
丂乧乧婥偵側偭偰偄傞偺偼丄傕偪傠傫偦傟偩偗偱偼側偄偺偩偑丅
乽傆乣傫丄拞恎偼愴摤梡偺杺摫媊巿傒偨偄側傫偩側乿
丂僼儗乕儉偲僔儕儞僟乕偑攳偒弌偟偵側偭偨乹俿倃亅係係夵乺偺嵍榬傪偟偘偟偘偲挱傔丄僒僉偑傐偮傝偲偮傇傗偔丅偝偡偑偵廋棟拞偺儊僈僷儁僢僩偵彑晧傪傆偭偐偗傞側傫偰偙偲偼偟側偐偭偨偑丄帺暘偺榬偲尒斾傋偰偄傞偁偨傝丄偦偺婥偑側偄偲偼尵偊側偄傛偆偩丅
乽杺摫媊巿丠乿
乽憰拝幰偺帩偮杺椡偱摦偔媊庤傗媊懌偺偙偲劅劅乿
丂庱傪孹偘傞峛夘偵丄儂僲僇偑婄傪忋偘偰摎偊偨丅偙偭偪偺悽奅偱尵偆偲偙傠偺僒僀僶乕媊巿偺傛偆側傕偺傜偟偄丅
乽偦偆偦偆儂僲僇偺恊晝偝傫側丄偪傚偭偲柤偺抦傟偨杺摫媊巿惢嶌偺儅僀僗僞乕乮柤恖乯側傫偩偤乿
乽傊偊乧乧偦偆側傫偩乿
乽偆傫乿
丂彮偟徠傟偔偝偦偆偵偟側偑傜傕丄僒僀僋儘僾僗柡偼屩傜偟偘偵偆側偢偔丅
丂斵彈偑堎悽奅偺僇儔僋儕巇妡偗劅劅儊僈僷儁僢僩傪惍旛偡傞偙偲偑偱偒偨偺偼丄庬懓摿惈偱庴偗宲偄偱偒偨抌栬乮嬥懏壛岺乯媄擻偵壛偊偰丄偦傫側壠掚娐嫬偱堢偭偰偒偨偐傜偐乧乧媟棫偵嵗偭偰婡懱偺嵍旾傪廋棟偡傞偦偺巔傪尒偮傔丄峛夘偼彫偝偔徫傒傪晜偐傋偨丅
丂栙乆偲嶌嬈傪懕偗傞峛夘偲儂僲僇丅庤帩偪柍嵐懣偵側偭偨僒僉偼丄儂僲僇偵偦偭偲嬤婑傝丄偪傚偄偪傚偄偲庤彽偒偟偨丅
乽壗丠乿
丂儂僲僇偼庤傪巭傔偰丄媟棫偺忋偐傜恎傪忔傝弌偡丅
乽傗偭傁帡偰傞傛側丄傾僀僣乧乧乿
乽乧乧両乿
丂帹尦偵彫惡偱殤偐傟丄僒僀僋儘僾僗柡偺摦偒偑屌傑偭偨丅
乽偩劅劅扤丄偵丠乿
乽扤偭偰乧乧儀僀儕偝傫偵偩傛丅恊晝偝傫偺掜巕偱丄儂僲僇偺弶楒偺憡庤劅劅乿
乽偪丄偪傚偭偲懸偭偰偭両丂偼偼偼弶楒偭偰丄乧乧偪丄堘偆偐傜偭両丂堘偆偐傜偭両乿
丂撪怱傪尒摟偐偝傟偨傛偆偵巜揈偝傟丄偁傢偰偰惡傪忋偘傞丅
丂摢晹僙儞僒乕偺挷惍傪懕偗偰偄偨峛夘偑丄乽偳偆偟偨偺丠乿偲岦偒捈偭偰偒偨丅
乽偪丄偪偭偪傖偄崰偺榖偩偟乧乧偦傟偵丄傋丄儀僀儕偝傫偵偼丄傟乧乧儗僀僔儍丄偝傫偑乧乧偄偨丄偟劅劅乿
丂偝偭偒埲忋偵婄傪愒傜傔丄偆偮傓偔儂僲僇丅
丂偦傟偼斵彈偑傑偩梒偐偭偨崰丄晝恊偺僼傽僋僩儕乕偱摥偒偩偟偨尦婻巑尒廗偄偺彮擭偲丄
乽僒僉偝傫丄儗僀僔儍偝傫偭偰丠乿
乽儀僀儕偝傫偺楒恖乧乧儂僲僇偺恊晝偝傫偺岺朳偱丄媊巿偺儌僯僞乕傗偭偰傞僆乕僩儅僩儞偺偍巓偝傫偩偤乿
乽偍丄僆乕僩儅僩儞丠乿
丂偙偪傜偺悽奅偱偼丄庡偵侾俀乣侾俋悽婭偵偐偗偰儓乕儘僢僷摍偱嶌傜傟偨帺摦恖宍傗丄僨僕僞儖夞楬偺僾儘僌儔儉愝寁偱巊傢傟傞寁嶼儌僨儖傪巜偡扨岅側偺偩偑丄
丂劅劅偊乕偭偲妋偐丄杺暔柡斉僈僀僲僀僪乮彈惈宆傾儞僪儘僀僪乯偩偭偨偭偗乧乧
丂岦偙偆偺悽奅偱偼僑乕儗儉傗噣庺偄偺恖宍噥傑偱杺暔柡壔偟偰恖娫偺抝惈偲楒垽偡傞偲偄偆偺偩偐傜丄傾儞僪儘僀僪偲恖娫偺僇僢僾儖側傫偰捒偟偔傕側傫偲傕側偄偺偐傕偟傟側偄丅側偍乽僆乕僩儅僩儞乿偲暦偄偰丄朸侽侽偵弌偰偒偨敔宆偺帺摦懳恖峌寕儘儃僢僩偑偪傜偭偲摢傪棭傔偨偺偼撪弿偩丅
丂峛夘偑撪怱偱傂偲傝僣僢僐儈偟偰偄傞偲丄栙偭偰壓傪岦偄偰偄偨儂僲僇偑丄傐偮傝偲偮傇傗偄偨丅
乽帡偰側偄傛乧乧乿
乽乧乧偊丠乿
丂峛夘偲僒僉偑尒偮傔傞拞丄斵彈偼庤偵偟偨岺嬶傪帩偪捈偟丄婄傪愒偔偟偨傑傑嵘傒偮偗傞傛偆側栚偮偒偱儊僈僷儁僢僩偺廋棟傪嵞奐偟偨丅乽帡偰側偄乧乧丄帡偰側偄乧乧乧乧帡偰側偄偐傜劅劅乿
乽乽乧乧乧乧乿乿
丂帺暘偵尵偄暦偐偣傞傛偆偵偦偆孞傝曉偟側偑傜丄堦怱晄棎偵庤傪摦偐偡丅
丂棴傔懅傪揻偄偨僒僉偑傆偲尒忋偘傞偲丄婡懱偺尐偵屪偭偨峛夘偑壗偐尵偄偨偘側婄偲娽嵎偟傪儂僲僇偵岦偗偰偄偨乧乧
乽儂僲僇偪傖傫丄偦偙丄庢傝晅偗偑媡劅劅乿
乽乧乧偁乿
亙仠亜
丂峏幯巗拞墰岞墍惵嬻峀応丄抧嬫梊慖夛嶰夞愴丅
丂偙傟偵彑偰偽儀僗僩係劅劅弨寛彑偵恑傔傞偲偁偭偰丄奺僠乕儉偲傕枩慡偺僐儞僨傿僔儑儞偱婡懱傪帩偪崬傒丄墳墖偵傕偙傟傑偱埲忋偵恖偑廤傑偭偰偄傞丅
丂柧椢娰妛墍偐傜偼偄偮傕偺柺乆偵壛偊偰丄惍旛傪庤揱偭偨僆乕僈柡偺僒僉偲傾儔僋僱柡偺儎儓僀偺巔傕偁偭偨丅僼僃儞僗偺奜懁偐傜棫偪尒偱娤愴偡傞偺偱丄壓敿恎偑嫄戝僌儌偱傕戝忎晇乧乧傕偭偲傕偁偐傜偝傑偵恖奜側尒偨栚偵丄墦姫偒偵偟偰寵埆姶傪業傢偵偟偰偄傞幰傕彮側偔側偄丅
丂偦傫側拞丄峛夘偲堦弿偵弌斣傪懸偭偰偄偨儂僲僇偼丄僫僊偵僷僪僢僋偺棤傊偲楢傟偰偙傜傟偨丅
乽乧乧僫僊偪傖傫丄媫偵偳偆偟偨偺丠乿
丂傕偆偡偖帋崌側傫偩偗偳乧乧偲屗榝偆儂僲僇偺尵梩偵丄僫僊偼偮偐傫偱偄偨斵彈偺庤傪曻偡偲丄備偭偔傝怳傝曉偭偨丅
乽乧乧側偁儂僲僇丄僐乕僗働偲壗偐偁偭偨丠乿
乽両乿
丂僺僋儞丄偲尐偑挼偹忋偑傞丅乽傋丄暿偵壗傕乧乧側偄丄傛乿
乽乧乧乧乧乿
丂偁偐傜偝傑偵栚傪塲偑偣堩傜偡恊桭偵丄僫僊偼攚拞偺怗庤傪偔偹傜偣棴傔懅傪揻偄偨丅
丂帺暘傕偦偆側偺偩偑丄側傑偠扨娽偑戝偒偄暘丄梋寁偵偦傟偑傛偔傢偐傞乧乧
乽偙側偄偩偐傜傆偨傝偲傕丄側乣傫偐僊僋僔儍僋偟偰傞偭偰偄偆偐丄堄幆偟側偄傛偆偵偟傛偆偲偟偰丄偐偊偭偰堄幆偟夁偓偰傞偭偰偄偆偐劅劅乿
乽偦丄偦傫側偙偲乧乧側偄丄偗偳乧乧乿
丂婄傪愒傜傔尵偄揵傓儂僲僇丅偦傫側斵彈偵丄僫僊偼婄偺恀傫拞偵偁傞扨娽傪僊儑儘儕偲摦偐偡丅
乽乧乧乧乧乿
丂儂僲僇偼偦偺帇慄偐傜摝偘傞傛偆偵偆偮傓偄偨丅
丂峛夘偑帺暘偺弶楒偩偭偨恖偵帡偰偄傞乧乧偲丄悽榖從偒僆乕僈柡偺僒僉偵巜揈偝傟偰偐傜偢偭偲丄斵彈偺怱偺掙偵偖偠偖偠偟偨婥帩偪偑揵偺傛偆偵傢偩偐傑偭偰偄傞丅
丂斵劅劅峛夘傪丄偐偺恖偺噣戙傢傝噥偲偟偰尒偰偄傞傫偠傖側偄偐偲偄偆丄帺屓寵埆偵帡偨婥帩偪偑丅
丂楒垽偵僱僈僥傿償婥枴側偺傕偁偭偰丄堦搙偦偆巚偭偰偟傑偆偲側偐側偐偦偙偐傜敳偗弌偣側偄丅偩偗偳峛夘偺偦偽傪棧傟偨偔側偄乧乧儊僈僷儁僢僩偺廋棟傗惍旛丄帋崌拞偺僶僢僋傾僢僾傪棟桼乮僟僔乯偵丄帺暘偱帺暘偵尵偄栿偟偰偄傞偺傕寵偩偲巚偆劅劅
丂偦傫側恊桭偺婥帩偪偵婥偯偄偰偄傞偺偐丄偼側偐傜偍尒捠偟側偺偐丄僫僊偼戝偒偔懅傪媧偆偲丄
乽儂僲僇両乿
丂嫮偄岥挷偱屇偽傟丄儂僲僇偼斀幩揑偵婄傪忋偘偨丅
丂師偺弖娫僫僊偺愒偔岝傞扨娽偲栚偑崌偭偰丄恎懱偑摦偐側偔側傞丅
乽側丄僫僊丄偪傖傫乧乧壗丄傪劅劅乿
丂幾娽偵尒偮傔傜傟丄儂僲僇偺栚偺徟揰偑掕傑傜側偔側偭偰偄偔丅
乽僎僀僓乕偺僫僊偑柦偢傞両丂乧乧儂僲僇丄偪傚偭偲慺捈偵側傟偭乿
乽偁劅劅乿
丂倁僒僀儞偟偨塃庤傪墶偵搢偟偰栚偺抂偵摉偰丄偳偙偧偺傾僯儊傒偨偄側億乕僘傪偒傔偰埫帵傪堦敪丅偦偟偰崨偗偨忬懺偱屌傑偭偨儂僲僇偺攚屻偵夞偭偰丄偦偺椉尐偵億儞偲庤傪抲偔丅
乽傎傜儂僲僇丄僐乕僗働偑懸偭偰傞偧乿
乽偊丠丂偁丄偆劅劅偆傫乧乧乿
丂壗傕峫偊偢偵傏傫傗傝偟偰偄偰丄媫偵偼偭偲変偵曉偭偨傛偆側姶妎傪偍傏偊丄僫僊偵攚拞傪墴偝傟偨儂僲僇偼摢傪怳偭偰偦偆墳偊傞偲丄尵傢傟偨傑傑僷僪僢僋偵岦偐偭偰纟傪曉偟偨丅
乽乧乧偁傟丠乿
丂側傫偩偐傛偔傢偐傜側偄偗偳丄偄偮偺娫偵偐偪傚偭偲偩偗婥帩偪偑寉偔側偭偨傛偆側婥偑偡傞乧乧斵彈偼懌傪巭傔偰怳傝岦偒丄偵傑偭偲旝徫傓恊桭偺婄傪尒偨丅
乽偁傝偑偲丄僫僊偪傖傫乿
乽偑傫偽傟傛丄儂僲僇乿
丂偦偺屻傠巔傪尒憲傝丄僎僀僓乕柡偼敮偺拞偐傜怢傃偨怗庤傪婡寵傛偝偘偵備傜備傜偲摦偐偡丅
丂劅劅傾僞僔傕僐乕僗働偼儀僀儕偝傫偵帡偰傞偲巚偆偧丅婡夿偄偠傝偑岲偒側偲偙偲偐丄摱婄側偲偙偲偐乧乧
乽儂僲僇偪傖傫丄偰屇傇偲偙偲偐側偭侓乿
丂偒偟偟偭丄偲僀僞僘儔偭傐偄徫傒傪晜偐傋傞僫僊丅
丂偦偺婥偵側傟偽儂僲僇偵乽崱偡偖僐乕僗働偵僐僋傟乿偲丄幾娽偺椡偱柦椷偡傞偙偲傕偱偒傞偺偩偑丄偦偙偼壋彈側杺暔柡丅垽偺崘敀偼憖傜傟偰偱偼側偔帺暘偺堄巚偱劅劅偲巚偭偰偟傑偆偺偼丄斵彈傕傑偨偦偆偄偆偺偵摬傟偰偄傞偐傜側偺偐傕偟傟側偄乧乧巜揈偝傟偨傜愨懳斲掕偡傞偩傠偆偗偳丅
亙仠亜
乽戞巐帋崌丄柧椢娰妛墍亀僠乕儉丒儌僲傾僀僈乕儖僘亁懳丄棫壴旽戝晅懏崅峑亀僠乕儉丒僀儞僼傿僯僢僩儕僶乕僒乕亁傪奐巒偟傑偡劅劅乿
丂僫僊偨偪柧椢娰妛墍偺柺乆偑尒庣傞拞丄塃榬晹偲嵍媟晹傪惵偔揾傝暘偗偨奃敀怓偺恖宆廳婡偑丄傾僫僂儞僗偲偲傕偵懸婡慄傊偲曕傪恑傔傞丅僇儔乕儕儞僌偩偗偱側偔丄搊榐婡懱柤傕乹俿倃亅係係夵乺偐傜乹僽儔僂儂儖儞乺傊偲夵傔傜傟丄偦偺柤偺捠傝丄妟偵摉偨傞晹暘偵僽儗乕僪僞僀僾偺忺傝僣僲偑怴偨偵庢傝晅偗傜傟偨丅塃泺晹偺僇僂儕儞僌偵偼俵俤俬俼倄俷俲倀俲俙俶偲幬傔偵報帤偝傟偰偄傞丅
丂偦傫側峛夘偨偪偺婡懱偵憡懳偡傞偺偼丄弮敀偺僇僂儕儞僌偱慡恎傪寗側偔暍傢傟丄偦偙偐偟偙偵愒偄儔僀儞偺揾憰偑巤偝傟偨丄偄傢備傞僨儌儞僗僩儗乕僞乕僇儔乕偺儊僈僷儁僢僩丅僟儊乕僕儅乕僇乕偺怓偼僀僄儘乕丅偍偦傜偔偙傟傕屻晅偗偝傟偨偺偱偁傠偆丄僑乕儖僪偵揾傜傟偨妟偺倁帤僣僲偑栚傪堷偔丅
丂側傫偱傕戝庤廳婡儊乕僇乕偑奐敪偟偨丄師婜庡椡儌僨儖偺帋嶌婡劅劅僾儘僩僞僀僾側偺偩偲偐丅
乽偦傟偵偟偰傕偁偺恖傜丄偳側偄尒偰傕崅峑惗偵偼尒偊偟傑傊傫乧乧乿
乽偄傗偳偆尒偰傕偍偭偝傫偱偟傚傾儗乿
丂庤傪杍偵摉偰偰庱傪孹偘傞儎儓僀偺揤慠儃働婥枴側敪尵偵丄暥梩偼懄嵗偵僣僢僐傒曉偟偨丅
丂憡庤僠乕儉偺婡懱偺椬偵棫偮僾儗僀儎乕偼斵彈偨偪偲摨擭戙偺抝巕偩偑丄屻傠偱峊偊偰偄傞僙僐儞僪擇恖偼斾歡偩偲偐榁偗婄偩偲偐偱偼側偔丄惓恀惓柫偺傾儔僒乕抝惈偩偭偨丅
丂暥梩偼庤偵偟偨僗儅儂偺俥俿僨傿僗僾儗僀偵丄梊慖夛偺嶲壛僠乕儉儕僗僩傪昞帵偝偣傞丅
乽僠乕儉丒俬俶俥儕僶乕僒乕丄僾儗僀儎乕恄尨僕儞乮偠傫偽傜丒偠傫乯丄搊榐婡懱柤乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺丅乧乧偝偭偒偺傾僫僂儞僗偱妛峑戙昞傒偨偄偵徯夘偝傟偰偨偗偳丄幚幙偼屄恖嶲壛側偺偹乿
乽庤揱偳偆偰偔傟傞偍桭偩偪丄妛峑偵偄偨偼傟傊傫偺偱偭偟傖傠偐乧乧丠乿
丂偦傟傪墶偐傜擿偒崬傒丄壗婥偵僸僪僀偙偲傪尵偆儎儓僀丅偳偆偱傕偄偄偑丄僆僲儅僩儁傒偨偄側柤慜偩側偲巚偆丅
丂儌乕僞乕僗億乕僣偲偟偰偼傑偩傑偩楌巎偺愺偄儘儃俿俼倄偩偐丄儊乕僇乕偑幚愌偺偁傞僾儗僀儎乕傗僠乕儉偵婡懱傗僷乕僣傪採嫙偟偨傝偡傞偙偲傕偁傞丅儊僇僯僢僋偑攈尛偝傟偰偄偰傕偍偐偟偔偼側偄丅
乽偗偳偁偺僠乕儉偭偰偝丄妋偐堦搙傕愴傢偢偵彑偪忋偑偭偰偒偨傫偩傛側乿
乽儅僕偐丠丂側傫偱傑偨偦傫側偙偲偵側偭偰傫偩丠丂僫僊乿
丂偮偄偝偭偒傑偱乽偁偺敀偄偺偐偭偗乕乿偲偐尵偭偰偄偨僒僉偩偭偨偑丄堦揮乽偊乣偭乿偲偄偭偨姶偠偱廰柺傪晜偐傋偰怳傝曉傞丅
丂対傪岎偊偢彑棙傪摼傞劅劅彑幰傪柤忔傞側偳丄愴摤庬偱偁傞僆乕僈偺斵彈偵偼棟夝偟偑偨偄偙偲偱偁偭偨丅
乽偊偭偲乧乧僇僫僞丄僷僗乿
乽側傫偱偙偭偪偵怳傫偹傫丅乧乧傑偁丄堦夞愴偼弨旛偑娫偵崌傢傊傫偐偭偨憡庤僠乕儉偑婞尃偟偰丄擇夞愴偼帋崌奐巒捈屻偵婡懱偑媫偵摦偐傫傛偆偵側偭偨憡庤偑幐奿偵側偭偰劅劅偱丄嶰夞愴傑偱棃偨偭偪傘偆傢偗傗乿
丂弿愴偱偼偙偆偄偭偨儅僔儞僩儔僽儖偵傛傞幐奿偑偨傑偵偁偭偨傝偡傞偺偩偑丄擇夞楢懕晄愴彑偲偄偆偺偼偝偡偑偵捒偟偄丅側偍丄帋崌奐巒捈屻偵婡懱偑摦偐側偐偭偨応崌偵尷傝丄嶰暘娫偺惂尷帪娫撪偵嵞巒摦偱偒傟偽僟儊乕僕儅乕僇乕侾億僀儞僩暘偺噣尭揰噥傪庴偗偰帋崌偵暅婣偱偒傞偺偩偑丄擇夞愴偱偐偺僠乕儉偲摉偨偭偨憡庤偼偦傟偑偱偒側偐偭偨傢偗偩丅
乽側傫偩丄梫偡傞偵塣偩偗偺儎僣偭偰傢偗偐乧乧側傜儂僲僇偨偪偺妝彑偩側侓乿
丂偦偆尵偭偰嫻偺慜偱対偲暯庤傪扏偒崌傢偣丄僯儎儕偲晄揋側徫傒傪晜偐傋傞僒僉丅
乽偣傗偗偳媡偵尵偆偨傜丄婡懱偵偄偭傌傫傕僟儊乕僕庴偗偰傊傫偭偪傘偆偙偲傗偐傜側丅桘抐偼嬛暔傗偱乿
丂偐偨傗儊乕僇乕嬣惢丄偙偪傜偼巊偊傞拞屆僷乕僣傪偐偒廤傔偰儗僗僩傾偟偨婡懱丅儂僲僇偺挌擩側惍旛偱丄慜擇愴偺僟儊乕僕偼壜擻側尷傝儕儁傾偝傟偰偄傞偲偼偄偊丄晄埨偑慡偔側偄偲偄偆傢偗偱偼側偄丅
丂傑偁丄偦偙傜偁偨傝偼峛夘傕儂僲僇傕廳乆彸抦偟偰偄傞偲巚偆偑丅
乽偦傟偵偟偰傕丄偦偺僕儞僶儔僕儞偲偐偄偆憡庤偺嫄恖婡尛偄乧乧偳偆傕婥偵側傞乿
乽捒偟偄傢偹丅儖儈僫偑偦傫側偙偲尵偆側傫偰乿
乽偍丠丂偝偰偼偁傫側丄偍傏偭偪傖傑偭傐偄偺偑僞僀僾側偺偐丠丂偍慜乿
乽擭偐傜擭拞敪忣偟偰偄傞婱條傜杺暔柡偲堦弿偵偡傞側偭乿
丂僫僊偵拑壔偝傟丄娫敮擖傟偢偵搟柭傝曉偡儖儈僫丅偦偟偰傑偨丄憡庤僠乕儉偺僾儗僀儎乕傊偲帇慄傪栠偡丅
丂帹偵僀儞僇儉傪晅偗僾儘億傪庤偵偟偨丄傁偭偲尒偼攚偺崅偄惔寜姶偺偁傞僀働儊儞丅墶偵棫偮弮敀偺儊僈僷儁僢僩偲憡傑偭偰丄傑傞偱偙偺応偺庡栶偺傛偆偵傕尒偊傞乧乧偑丄
丂劅劅僄價僴儔偲僒僀僋儘僾僗傪尒傞偁偺栚偮偒丄傑傞偱僾儔僀僪偩偗偑旍戝壔偟偨斀杺攈偺恄姱暫偺傛偆偩乧乧
丂岥拞偱偦偆偮傇傗偒丄彈巕崅惗償傽儖僉儕乕偼恎傪嫮挘傜偣偨丅
丂帋崌奐巒偺僐乕儖偑嬁偒丄僔僌僫儖偑愒偐傜惵偵愗傝懼傢傞丅
乽尒偊偨偧僢両丂栺懇偝傟偨彑棙傊偺僂傿僯儞僌儘乕僪両両乿
丂僠乕儉丒俬俶俥儕僶乕僒乕偺僾儗僀儎乕恄尨僕儞偼偦偆惡傪忋偘側偑傜丄垽婡乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺傪僟僢僔儏偝偣偨丅
丂堦夞愴丄擇夞愴偲傕晄愴彑偱丄偦傠偦傠偪傖傫偲愴偭偰彑偨偹偽奿岲偑偮偐側偄側偲巚偭偰偄偨偲偙傠偵丄懳愴憡庤偲偟偰弌偰偒偨偺偼拞屆偺僣僊僴僊婡懱乧乧斵偑撪怱偱僈僢僣億乕僘傪庢偭偨偺偼尵偆傑偱傕側偄丅
丂偦偆丄偙偪傜偑晧偗傞梫慺側偳堦愗側偄丅偙偺戝夛偵弌応偡傞偨傔偵丄恊偺僐僱偲嬥傪巊偭偰丄儊乕僇乕偐傜僾儘僩僞僀僾偺婡懱劅劅嵟怴媄弍傪偮偓崬傫偱嶌傜傟偨儚儞僆僼婡傪庢傝婑偣偨偺偩偐傜丅
丂僕儞偼偦偺婄偵彑棙傪妋怣偟偨徫傒傪晜偐傋丄庤庱傪擯偭偰俥俿僨傿僗僾儗僀忋偺傾僀僐儞傪慖戰丅弮敀偺婡懱偼慜偵偲傃崬傓傛偆偵塃榬傪孞傝弌偡乧乧偑丄憡庤偺婡懱偼敿恎傪偢傜偟偰偦傟傪偐傢偟丄僇僂儞僞乕偱嵍偺堦寕傪曻偭偰偒偨丅
乽偔乧乧両乿
丂婡懱偺岦偒傪嫮堷偵曄偊偰偦偺峌寕傪旔偗傛偆偲偟偨偑丄偑傜嬻偒偺塃尐偵僋儕僥傿僇儖僸僢僩傪傕傜偄丄偄偒側傝僟儊乕僕儅乕僇乕偺怓偑僀僄儘乕偐傜僆儗儞僕傊偲曄傢傞丅
丂僗儔僀僨傿儞僌婥枴偵媟傪塣偽偣丄摜傫挘傜偣傞傛偆偵婡懱傪棫偰捈偡偲丄
乽乧乧傗傞側僢両丂偝偡偑偼弨乆寛彑傑偱彑偪忋偑偭偰偒偨偩偗偺偙偲偼偁傞僢両乿
丂僾儘億偐傜怢傃偨働乕僽儖傪傂偲怳傝偟丄斵偼幣嫃偑偐偭偨岥挷偱懳愴憡庤偵岅傝偐偗偨丅
丂傓傠傫撪怱偱偼偦傫側偙偲栄傎偳傕巚偭偰偼偄側偄丅崱偺偼扨側傞傑偖傟丅傛偗偨偲偒偵怳傝夞偟偨庤偑丄偨傑偨傑忋庤偄嬶崌偵摉偨偭偨偩偗乧乧偁傫側宆棊偪偺儊僈僷儁僢僩偑丄偙偺乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺偺婡摦椡偵偮偄偰偙傟傞偼偢偑側偄偺偩劅劅
乽偩偑僶僩儖偼巒傑偭偨偽偐傝僢両丂彑晧偼偙傟偐傜乧乧乧乧暦偗傛両乿
丂僣僊僴僊婡懱偺僾儗僀儎乕劅劅峛夘偼僕儞偺乽岅傝乿傪僈儞柍帇偟偰僾儘億傪憖嶌丅乹僽儔僂儂儖儞乺偼攚拞偺働乕僽儖傪東偟偰慜偵摜傒崬傫偩丅偁傢偰偨傛偆偵孞傝弌偝傟偨戝怳傝側僷儞僠傪奜傊抏偒丄偑傜嬻偒偵側偭偨嫻尦偵塃偺対傪孞傝弌偡丅
乽乧乧両丂偝偣傞偐僢両乿
丂僾儘億偐傜擖椡偝傟偨摦嶌傪娫敮擖傟偢偵僉儍儞僙儖偝傟丄偄偒側傝偺惂摦偵斶柭偠傒偨壒傪忋偘傞旼偲懌庱偺娭愡晹乧乧忋敿恎傪擯偭偰僟儊乕僕儅乕僇乕傊偺捈寕傪恏偆偠偰旔偗丄乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺偼嬄偗斀傝塲偖傛偆側懱惃偵側傝側偑傜傕娫崌偄傪庢傝丄椉榬傪戝偒偔怳偭偰峔偊捈偡丅
乽偙偺婡摦椡偵偮偄偰偙傟傞偺偼僢丄摨偠僾儘僩僞僀僾劅劅暦偗偭偰偽両乿
乽乧乧乧乧乿
丂愴偭偰偄傞嵟拞偵傾僯儊偭傐偔僙儕僼傪寛傔偨偄傜偟偄偑丄偦傫側偙偲偵晅偒崌偆婥側傫偐偝傜偝傜側偄丅
丂峛夘偼偝傜偵帺婡傪墴偟崬傒丄堦杮僤僲偺儊僈僷儁僢僩偼憡庤偺嵍尐栚偑偗偰捛寕傪曻偭偨丅敿恎傪欜歭偵堷偄偨偨傔儅乕僇乕偺怓偙偦曄傢傜側偐偭偨偑丄弮敀偺儊僈僷儁僢僩偼曅懌棫偪偵側傝偐偗丄僶儔儞僗傪曵偟偰屻傠偵傛傠傔偔丅
丂僺僢劅劅両乽乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺僗僥乕僕傾僂僩丅僽儗僀僋両乿
丂偄偮偺娫偵偐僗僥乕僕偺抂傑偱捛偄媗傔傜傟偰偄偨丅柍棟栴棟廳怱傪堏偟偨塃懌偑応奜偵偼傒弌偟丄寈崘壒偲摨帪偵摜傒墇偊偨儔僀儞偑愒偔岝傞丅
丂擇懱偺儊僈僷儁僢僩偼偦偺摦偒傪巭傔丄僾儗僀儎乕偲偲傕偵嵞傃懸婡慄傊偲栠偭偨丅
乽儁僫儖僥傿偼捝偄偑丄巇愗傝捈偣偨偺偼傓偟傠岲搒崌丅偄偔偧両丂杮摉偺愴偄偼偙傟偐傜偩偭両乿
乽乧乧乧乧乿
乽乧乧側偁僇僫僞丄傾僀僣側傫偱偄偪偄偪壗偐尵偄側偑傜丄帺暘偺儘儃僢僩偵億乕僘庢傜偣偰傫偩丠乿
丂媟晹傪戝偒偔奐偒丄巜傪僺儞偲怢偽偟偨椉榬傪戝偒偔夞偟偰崢傪擯傞劅劅
丂儌乕僞乕壒傪柭傜偟偰戝偘偝側峔偊傪偲傞乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺傪嬥栐偺奜偐傜層嶶廘偘偵尒傗傝丄僫僊偼椬偵栤偄偐偗傞丅
乽僸儘僀僢僋儉乕僽偱亀帺暘偑庡栶偩亁偭偰傾僺偭偰傞傫傗側劅劅乿
乽偆傢偦傟晧偗偨傜傔偭偪傖僀僞偄傗偮偠傖傫乧乧乿
乽傑偁偣傗偗偳乧乧枹偩偵偁傫側偙偲偡傫偺偍傞傫偐乿
丂僟儊乕僕僇僂儞僩侾乕侽偱帋崌嵞奐丅僔僌僫儖偑曄傢傞偲摨帪偵丄惵偄婡懱偲敀偄婡懱偼恀偭惓柺偐傜夛揋偡傞丅
丂対傪孞傝弌偡偙偲悢崌丅屳偄偺峌寕傪椊偓崌偆偑乧乧
乽偽偭乧乧僶僇側僢両丠丂墴偝傟偰偄傞僢丠乿
丂愭傎偳偐傜偺柍棟側婡摦偱媟晹偺摜傫挘傝偑岠偐側偔側傝偩偟偨弮敀偺儊僈僷儁僢僩偑丄彊乆偵屻戅偟巒傔傞丅
乽傑偩偩乧乧傑偩偄偗傞僢丅僾儘僩僞僀僾偼埳払偠傖側偄僢両乿
丂側偍傕偳偙偐偱暦偄偨傛偆側僙儕僼傪揻偒側偑傜丄僕儞偼僾儘億偺廃埻偵晜偐傇俥俿僨傿僗僾儗僀偐傜僐儅儞僪傪慺憗偔擖椡丄僄儞僞乕僉乕偱偁傞僩儕僈乕傪抏偄偨丅
丂偡偱偵儅乕僇乕偺怓偑曄傢偭偰偄傞塃尐傪惓柺偵岦偗丄乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺偼幬傔慜傊堦曕摜傒弌偡乧乧
亀僐乕僗働偔傫偭両丂嵍偭両亁
乽乧乧両両乿
丂僀儞僇儉偐傜暦偙偊偰偒偨儂僲僇偺惡偵丄峛夘偼偡偐偝偢斀墳偟偨丅
丂僼僃僀儞僩傪偐偗偰媡懁傊偲墶偭挼傃偟偨弮敀偺婡懱偵崌傢偣偰乹僽儔僂儂儖儞乺傕嵍傊偲摜傒崬傒丄偦偺摦偒偵楢摦偝偣偨崢偺擯傝偐傜撱偖傛偆偵曻偭偨塃榬偱憡庤偺庱傪姞傞丅
丂壓榬晹偺僇僂儕儞僌偑妱傟偰丄惵偄攋曅偑廃埻偵旘傃嶶傞丅
丂墶堏摦偺儀僋僩儖偵儔儕傾僢僩偺堦寕傪崌傢偝傟偰丄愒偄椉懌偑抧柺偐傜棧傟傞劅劅
丂乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺偼丄偦偺傑傑壒傪棫偰偰墶搢偟偵側偭偨丅
乽乧乧偳偆偩偭両乿
丂僐儞僩儘乕儖働乕僽儖傪偟側傜偣丄峛夘偑嫨傫偩丅
丂弮敀偺婡懱偼僗僥乕僕偵扏偒偮偗傜傟偨傑傑丄僾儗僀儎乕偺憖嶌偵傕斀墳偣偢丄僺僋儕偲傕摦偐側偄丅
乽乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺帋崌懕峴晄擻丅劅劅戞巐帋崌Winner両丂僠乕儉丒儌僲傾僀僈乕儖僘両両乿
丂帋崌廔椆偺儂乕儞偲崑夣側俲俷彑偪偵暒偔娊惡偺拞丄乹僽儔僂儂儖儞乺偼徴寕偱摦偐側偔側偭偨塃榬偺戙傢傝偵丄嵍榬傪崅乆偲宖偘偨丅
丂惍旛偟偨僷乕僩僫乕傪怣棅偟丄婡懱傪尷奅傑偱巊偄愗偭偨僾儗僀儎乕偲丄僇僞儘僌僗儁僢僋偩偗偵棅偭偨幰偲偺嵎偑擛幚偵尰傟偨帋崌偩偭偨丅
乽乧乧僐乕僗働偔傫両乿乽儂僲僇偪傖傫両乿
丂嬱偗婑偭偰偒偨僒僀僋儘僾僗柡偲栚傪崌傢偣丄僴僀僞僢僠偟偰彑棙傪婌傃崌偆丅傆偨傝偑娤媞惾偺曽傪尒傞偲丄僼僃儞僗偺岦偙偆偐傜僫僊傗斵曽偨偪偑庤傪怳偭偰偄傞丅
丂偩偑丄儖儈僫偩偗偼堦恖丄尟偟偄昞忣偱僗僥乕僕傪尒偮傔偰偄偨丅偦偺帇慄偺愭偱丄墶搢偟偵側偭偨帺婡偺偦偽偵棫偮攕幰劅劅僕儞偑偆偮傓偄偨傑傑丄堦弖僯儎僢偲岥偺抂傪榗傔傞丅
丂偦偟偰斵偼丄偍傕傓傠偵婄傪慜偵岦偗傞偲丄
乽墭偄乧乧墭偄偧両丂偦偆傑偱偟偰彑偪偨偄偺偐偍慜僢両乿
丂傑傢傝偵暦偙偊傞傛偆儚僓偲戝惡傪忋偘丄峛夘偺婄傪巜嵎偟偨丅
亙仠亜
乽乧乧乧乧乿
乽乧乧乧乧乿
乽側丄側傫偩乧乧丠乿
丂儗僊儏儗乕僔儑儞傕堘斀偟偰偄側偄偟丄斀懃傕偟偰偄側偄丅儅乕僔儍儖偐傜偺寈崘傕栣偭偰側偄丅
丂鎎傞峛夘丄偞傢偮偔娤媞惾丅
丂傑傢傝偺帇慄偑帺暘偵廤傑偭偰偄傞偺傪妋擣偟丄僕儞偼偝傜偵惡傪挘傝忋偘偨丅
乽偦傕偦傕偦傫側僗僋儔僢僾偺婑偣廤傔偱偱偒偨儊僈僷儁僢僩偑丄崅惈擻僾儘僩僞僀僾婡偲屳妏偵愴偄彑棙偡傞側傫偰枩偵傂偲偮傕偁傝偊側偄両丂偮傑傝乧乧僢両乿
丂偦偟偰丄峛夘偺攚拞偵塀傟側偑傜嫰偊偨傛偆側帇慄偱偙偪傜傪偆偐偑偆僸僩僣栚偺恖奜彮彈傪嵘傔偮偗傞偲劅劅
乽偦偙偵偄傞壔偗暔彈偵杺朄傪巊傢偣偰僢丄僘儖傪偟偨偲偄偆偙偲偩僢両乿
乽側偭丠乿
丂埇偭偨塃庤傪嫻偵摉偰丄嵍庤傪墶偵戝偒偔奐偒丄噣僊儍儔儕乕偵岦偐偭偰噥壈柺傕側偔偦偆庡挘偟偨丅
乽帺暘偺婡懱傪杺朄偱嫮壔偟偨偐僢丄偁傞偄偼偙偭偪偺婡懱傪杺朄偱庛懱壔偝偣偨偐僢両丂偙偄偮傜偼堦夞愴偐傜偦偆傗偭偰晄惓傪偟懕偗丄彑偪忋偑偭偰偒偨傫偩僢両乿
乽傆偞偗傞側偭両丂扤偑偦傫側偙偲偡傞偐両乿
丂帠幚偱偁傞偐偺傛偆偵寛傔偮偗傞偦偺岥挷偵丄偄偮傕偼梋寁側潌傔帠傪寵偆峛夘傕偝偡偑偵惡傪峳偘偰搟柭傝曉偡丅
乽拞悽暥柧儗儀儖偺僼傽儞僞僕乕悽奅偐傜棃偨壔偗暔彈偵丄儊僈僷儁僢僩偺惍旛側偳偱偒傞傢偗偑側偄僢両丂偩偐傜杺朄偲偄偆僠乕僩偵棅偭偨僢両丂偪傚偭偲峫偊傟偽扤偱傕暘偐傞偙偲偩僢両乿
乽儂僲僇偪傖傫偨偪偺偙偲抦傝傕偟側偄偱丄彑庤側偙偲尵偆側偭両乿
丂傇偭偪傖偗丄尵偄偑偐傝埲奜偺壗暔偱傕側偄丅
丂僼傽儞僞僕乕悽奅偼拞悽儓乕儘僢僷晽劅劅側偳偲偄偆屌掕娤擮偟偐側偄僕儞偵丄杺暔柡傗斵彈偨偪偺杺朄偵偮偄偰偺棟夝側偳偁傝偼偟側偄丅偲偄偆偐丄杺朄杺朄偲尵偭偰傞妱偵丄杮婥偱偦傟偑巊傢傟偨偲峫偊偰偄傞偐偳偆偐傕媈傢偟偄丅
丂梫偼敾掕傪暍偡偨傔偵丄峛夘偨偪偑晄惓傪偼偨傜偄偨偲娤媞偨偪傗儅乕僔儍儖偵巚傢偣傟偽偄偄偺偩偐傜丅
乽偍偄僆儅僄偭丄尵偆偵偙偲寚偄偰側傫偰偙偲偸偐偟傗偑傞両乿
乽壗僀僠儍儌儞偮偗偰傫偹傫偭両丂偍慜偦傟儗僀僴儔乮儗僀僔儍儖僴儔僗儊儞僩亖恖庬揑曃尒偵婎偯偔寵偑傜偣乯傗偧偭両乿
乽偒偭偪傝晧偗偨偔偣偵傒偭偲傕偹偊偧偭両丂愴偄僫儊偰傫偺偐僥儊僄偭両乿
丂僼僃儞僗偺奜懁偐傜丄僫僊偨偪傕搟傝偺惡傪忋偘傞丅
丂偩偑丄懠偺娤媞偨偪偼椬摨巑偱婄傪尒崌傢偣偨傝丄僶僩儖僗僥乕僕偵崲榝偺帇慄傪搳偘偐偗偨傝丄偁偐傜偝傑偵晭曁偺昞忣傪晜偐傋偨傝劅劅
丂僈僢劅劅両乽乧乧両丂僐乕僗働偔傫偭両両乿
丂偄偒側傝儂僲僇偵岦偐偭偰搳偘偮偗傜傟偨愇偑丄斵彈傪偐偽偭偨峛夘偺偙傔偐傒偵捈寕偟偨丅
乽偩丄戝忎晇乧乧乿
乽乧乧乧乧乿
丂妟傪墴偝偊偰婄傪偟偐傔側偑傜傕丄斵偼怱攝偐偗傑偄偲徫傒傪晜偐傋傛偆偲偡傞丅
丂儂僲僇偼桬婥傪怳傝峣偭偰丄愇偑旘傫偱偒偨曽傪嵘傒偮偗偨丅
乽傑乧乧杺朄側傫偰丄巊偭偰丄側偄乧乧乧乧偪傖傫偲丄惍旛乧乧偟偨乧乧乿
丂偨偳偨偳偟偔丄偲傕偡傟偽岥偛傕傝偦偆偵側傝側偑傜傕丄娤媞惾偵岦偐偭偰斀榑偡傞丅
丂偩偑埆堄偼梕堈偵揱攄偟丄憹暆偟偰偄偔乧乧
丂岥偱偼側傫偲偱傕尵偊傞傛側偀劅劅
丂杺朄巊偭偰側偄偙偲徹柧偟偰傒偣傠傛劅劅
丂偦偺懠戝惃偵噣婄噥偼側偄丅愒怣崋丄傒傫側偱搉傟偽晐偔側偄丅
丂堸傒偝偟偺儁僢僩儃僩儖傗價儞丄嬻偒娛丄僑儈側偳偑丄傆偨傝偵師乆偲搳偘偮偗傜傟傞丅
丂峛夘偼傑傞偱僸僩偺廥偄柺傪尒偣傑偄偲偡傞偐偺傛偆偵丄儂僲僇偺摢傪書偒婑偣丄弬偵側偭偨丅
乽儂僲僇偭両乿乽峛夘偉偭両乿
丂僫僊偲斵曽偺嫨傃惡偑丄娤媞惾偐傜偺攍惡偵偐偒徚偝傟傞丅
丂墭偄側偝偡偑壔偗暔彈墭偄劅劅
丂恖娫條偺戝夛偵弌偰偔傫偠傖偹乕傛偭劅劅
丂偲偭偲偲尦偄偨悽奅偵婣傝傗偑傟偭劅劅
丂偐乕偊傟偭丄偐乕偊傟偭劅劅
丂偐乕偊傟偭丄偐乕偊傟偭劅劅
丂偐乕偊傟偭丄偐乕偊傟偭劅劅
丂偐乕偊傟偭丄偐乕偊傟偭劅劅
丂乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧
丂偩偑丄帺暘偨偪偑崱偙偺応偐傜摝偘偨傜丄憡庤偺尵偭偨偙偲傪擣傔偨偙偲偵側傞丅
丂偦傟偩偗偼愨懳偱偒側偄丅僒僀僋儘僾僗柡傪偐偒書偔榬偵丄峛夘偼椡傪崬傔偨丅
乽偔偭偦偋僥儊僄傜偦偙摦偔側偭両丂慡堳僽僢偲偽偟偰傗傞偭両両乿
乽偩傔傛僒僉偭両丂庤傪弌偟偨傜偙偭偪偑埆幰偵偝傟傞両乿
乽僒僉偼傫偙傜偊偰乧乧偙傜偊偰偍偔傟傗偡偭両乿
丂僼僃儞僗傪堷偒偪偓偭偰斀懳懁傊墸傝崬傕偆偲偡傞僆乕僈柡傪丄昁巰偵巭傔傞暥梩偲儎儓僀丅杺暔柡偑恖娫偵婋奞傪壛偊偨傜嵟屻丄棟桼側偳娭學側偟偵丄僕儍乕僫儕僗僩傪柤忔傞儗億壆傗抦幆恖偲徧偡傞惡偲婄偩偗偑僨僇偄楢拞偑婐乆偲偟偰斵彈偨偪偺攔愃偵摦偔偩傠偆丅
丂僕儞偼憶偓懕偗傞僊儍儔儕乕偵攚傪岦偗丄僯儎儕乧乧偲岥偺抂傪榗傔傞丅
丂偦偺帪丄偁偨傝偵敀偄塇崻偑晳偄嶶偭偨乧乧
乽乧乧両丠乿
丂師偺弖娫丄娤媞惾偵偄偨幰偨偪偼僴僢偲変偵曉傝丄搳偘偮偗傛偆偲偟偰偄偨傕偺傪庤偐傜庢傝棊偲偟偨丅
丂偦偟偰殥偟棫偰傞傛偆偵婣傟僐乕儖傪孞傝曉偟偰偄偨抝偨偪偼丄椻悈傪梺傃偣傜傟偨傛偆側姶妎偲偲傕偵丄帺暘偨偪偺曽偑廃埻偐傜敀偄栚偱尒傜傟偰偄傞偙偲偵婥偯偔丅
乽偁乧乧乿
乽偄丄偄傗偦偺乧乧偭乿乽偙丄偙傟偼劅劅乿
丂斵傜偼杍傪堷偒偮傜偣側偑傜丄岆杺壔偡傛偆偵敿徫偄傪晜偐傋傞乧乧偑丄帇慄偵懴偊偒傟側偔側偭偨堦恖偑墎傪愗偭偨傛偆偵惡傪忋偘丄慡堳偑偦傟偵屇墳偟偰岥乆偵憶偓弌偟偨丅
乽乧乧偪丄堘偭丄偍劅劅壌偼偍慜傜偵丄偮丄偮傜傟偨偩偗偩偐傜側偭両乿
乽側偭壗尵偭偰傗偑傞偭両丂偍慜偑嵟弶偵愇搳偘偮偗偨傫偩傠偑偭両乿
乽偍慜偙偦偭両丂媰偄偰摝偘弌偡傑偱偰偭偰乕揑偵傗傠偆偤偭偰僎儔僎儔徫偭偰偨傠偑偭両乿
乽傏丄儃僋偼偭丄傗丄巭傔偨曽偑偄偄偭偰偄偄偄尵偭偨傫偩丄側偭乿
乽塕偮偗偭両丂堦斣婐偟偦乕偵婣傟婣傟偭偰姭偄偰偨偔偣偵偭両乿
丂偦偟偰丄屳偄偵愑擟傪側偡傝偮偗崌偆丅偙傟傕傑偨丄尒偨偔乮尒偣偨偔乯側偄僸僩偺廥偝丅
丂偩偑峛夘偼榬偺拞偱儂僲僇偵恎偠傠偓偝傟丄偁傢偰偰恎懱傪棧偟偨丅
乽偛劅劅偛傔傫丄儂僲僇偪傖傫乿
乽偆偆傫丅乧乧僐乕僗働偔傫偙偦戝忎晇丠乿
丂儂僲僇偼庱傪怳傞偲丄峛夘偺愒偔庮傟偨妟傊偲庤傪怢偽偟偨丅
丂偦偺巜偑乧乧偄傗偦偺恎懱偑傑偩偐偡偐偵恔偊偰偄傞偙偲偵婥偯偒丄峛夘偼寛堄傪屌傔偰斵彈偺庤傪庢偭偨丅
乽乧乧僐乕僗働丄偔傫丠乿
乽寛彑傑偱峴偭偨傜偪傖傫偲尵偆偮傕傝偩偭偨偗偳乧乧崱尵偆偹乿
丂偦偆慜抲偒偟偰丄屗榝偆儂僲僇偺僸僩僣栚偵帇慄傪崌傢偣傞偲丄
乽杔偼孨偑岲偒偩丅乧乧儂僲僇偪傖傫丄杔偺楒恖偵側偭偰乿
乽偊乧乧丠乿
丂師偺弖娫丄儂僲僇偺廃埻偐傜壒偑徚偊偨丅
丂恊桭傗拠娫偨偪偺嬃偔惡傕丄懠偺娤媞偨偪偺偞傢傔偒傕丄嬱偗偮偗偨儅乕僔儍儖偵擄暼傪偮偗傞懳愴憡庤偺暔尵偄傕丄寈旛僗僞僢僼偵媗傔婑傜傟偰側偍傕尵偄摝傟傛偆偲偡傞抝偨偪偺曎夝傕丄暦偙偊偰偄傞偗偳暦偙偊側偄丅
乽杮婥乧乧側偺丠乿
乽傕偪傠傫乿
乽偱傕巹丄杺暔柡乧乧僒僀僋儘僾僗丄偩傛丅栚偑堦偮偩偟丄僣僲傕偁傞偟丄敡傕惵偄偟劅劅乿
乽偦傟偑儂僲僇偪傖傫側傫偩偐傜丄偦傟偱偄偄傫偩乿
乽乧乧乧乧乿
丂峛夘偼斵彈偺戝偒側摰傪恀偭捈偖尒偮傔偰丄椡嫮偔偆側偢偔丅
丂偦偺帇慄偵婥埑偝傟偰儂僲僇偑栚傪堩傜偡偲丄杊岇僼僃儞僗偺岦偙偆偵僫僊偨偪偺巔偑尒偊偨丅
丂儂僲僇丄慺捈偵側傟偭劅劅
丂恊桭偺惡偑丄傑傞偱攚拞傪墴偟偰偔傟傞偐偺傛偆偵丄摢偺拞偱偙偩傑偡傞丅
丂儂僲僇偼岦偒捈傝丄堦曕慜偵恑傒弌傞偲丄
乽巹傕乧乧巹傕僐乕僗働偔傫偺偙偲偑丄乧乧戝岲偒偭両乿
丂椉榬傪峀偘偰偲傃偮偔傛偆偵書偒偮偒丄偦偺庤傪峛夘偺庱尦偵夞偟偰恎懱傪偔偭偮偗偨丅
丂傓偵傘傫劅劅偲丄嫻偺朿傜傒偑墴偟晅偗傜傟傞丅
丂偦偟偰嵍榬傪撍偒忋偘偨傑傑棫偮惵偄恖宆廳婡傪僶僢僋偵丄傆偨傝偼怬傪廳偹偨劅劅
乽乧乧乧乧乿乽乧乧乧乧乿乽乧乧乧乧乿乽乧乧乧乧乧乧乧乧乿
乽偽偭丄壔偗暔彈偲僉僗偩偲僢両丠丂乧乧傒傒傒尒偨偐傾儗傪僢両丂恖慜偱偁傫側恀帡傪傪偡傞傛偆側搝傜偩僢両両丂偁偄偮傜偑杺朄偱僘儖偟偨偺偼柧敀劅劅乿
乽偄偄偐傜偝偭偝偲揚廂偟側偝偄丅師偺帋崌偑巒傔傜傟側偄乿乽乧乧偊丠乿
丂懥傪旘偽偟偰巟棧柵楐側僐僩傪傑偔偟棫偰傞僕儞偵丄儅乕僔儍儖偺抝惈偼椻偨偔尵偄曻偭偨丅
丂傓傠傫丄敾掕峈媍側偳堦愗偲傝崌傢側偄丅偼側偐傜偲傝崌偆偮傕傝傕側偄丅
乽偩乧乧偩偐傜偝偭偒偐傜偢偭偲尵偭偰傞偩傠偑僢両丂偁偺僣僊僴僊偑僾儘僩僞僀僾婡偺乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺偵彑偮側偳丄枩偵傂偲偮傕偁傝偊側偄偲劅劅乿
乽偁丄偁偺丄偡偄傑偣傫乧乧乿
丂側偍傕儅乕僔儍儖偵尵偄曞傠偆偲偡傞斵偺屻傠偐傜丄崱傑偱偢偭偲栙偭偰尒偰偄偨丄偲偄偆偐僪儞堷偒偟偰偄偨傾儔僒乕抝惈劅劅僠乕儉丒俬俶俥儕僶乕僒乕偺僙僐儞僪偺傂偲傝偑丄偍偢偍偢偲岥傪嫴傫偱偒偨丅
乽偠乧乧幚偼偦偺婡懱丄帋嶌儌僨儖偺傑傑偩偲儗僊儏儗乕僔儑儞捠傜側偄偐傜丄嬱摦宯傪巗斕偺傕偺偲懼偊偰傞傫偱偡偗偳乿
乽側傫乧乧偩偲僢両丠乿
丂梫偡傞偵丄僈儚偩偗偩偭偨丅
乽閤偟偨傢偗偠傖側偄傫偱偡偗偳偹乣丅晛捠丄帋嶌婡偺栤戣揰傪夵椙偟偨巗斕儌僨儖偺曽偑丄憤崌惈擻偼岦忋偟偰傑偡偟乿
乽偆丄偆偆偆塕偩僢両丂傉丄僾儘僩僞僀僾偼検嶻宆傛傝傕丄嫮偄乧乧偼偢乧乧乧乧乿
丂傕偆堦恖偵偦偆尵傢傟丄崨偗偨婄偱僗僥乕僕偵傊偨傝崬傓僕儞丅僙僐儞僪傆偨傝偼婄傪尒崌傢偣丄偦偦偔偝偲揚廂弨旛傪巒傔傞乧乧弌岦埖偄偲偼偄偊丄偙傟埲忋晅偒廬偆媊棟偼側偄丅
丂偦傫側懳愴憡庤傪怟栚偵丄峛夘偼儂僲僇偲廳偹偰偄偨怬傪偦偭偲棧偟偨丅
乽偁丄偁偺乧乧儂僲僇偪傖劅劅傓偖偅両丠乿
乽傫乧乧偪傘偭丄偪傘傁劅劅偵傘傓偭丄傓偪傘乧乧傟傠偭丄傫偭丄乧乧傫偪傘丄乧乧乧乧乿
丂奆傑偱尵傢偝偢丄儂僲僇偼椉庤偱峛夘偺摢傪偮偐傓偲丄擇搙栚偺僉僗偱偦偺岥傪嵡偓丄墴偟擖傟偨愩偱岥撪傪骧鏦偡傞丅
乽傫丄傓偖偭丄乧乧傉偼偭両丂傎丄儂僲僇丄偪傖傫劅劅丠乿
乽偊傊傊偭丅傕偭偲乧乧傕偭偲尒偣偮偗傛偆丅僐乕僗働偔傫偲巹偺儔僽儔僽側偲丒偙丒傠侓乿
丂廜恖娐帇偺拞偱戝抇側偙偲傗偭偰偟傑偭偨斀摦側偺偐丄杺暔柡偲偟偰偺杮擻偑昞偵弌偰偒偨偺偐丄儂僲僇偼峛夘偺懥塼偑偮偄偨帺暘偺怬傪側偧傞傛偆偵鋜傔傞偲丄懅傪宲偓側偑傜帺暘偺柤慜傪屇傇垽偟偄噣僆僗噥偵岥妏傪偮傝忋偘偰旝徫傫偩丅
丂墣偭傐偔弫傫偩偦偺扨娽偵尒偮傔傜傟偰丄妎屽偟偰偄偨偲偼偄偊丄偁偁傕偆摝偘傜傟側偄側乧乧偲巚偄側偑傜傕徫傒傪曉偡峛夘丅崱夞偺審偱杺暔柡偑偙偺悽奅偺恖娫偵傑偩傑偩庴偗擖傟傜傟偰偄側偄偙偲傪捝姶偟偨偑丄偦傟偱傕屻夨傗晄埨偼慡偔側偄丅
乽偒偟偟偭丄傗偭偨偹儂僲僇偭侓乿
乽偍傔偱偲偆偳偡偊丄儂僲僇偼傫乿
乽慉傑偟偄偤偭乧乧偙偺偙偺偭両乿
丂僷僪僢僋傪捠偭偰嬱偗婑偭偰偒偨僫僊偨偪杺暔柡偺拠娫偵潌傒偔偪傖偵偝傟傞儂僲僇傪尒偰丄峛夘偼巚偆丅偙傫側傒傫側偑偄傞傫偩偐傜丄壗偑偁偭偰傕偒偭偲戝忎晇乧乧偲丅
丂偦偟偰恊桭偨偪偺僴僌偐傜夝曻偝傟偨僒僀僋儘僾僗柡偑丄傂偲偮偟偐側偄戝偒側摰偱恀偭捈偖尒偮傔偰偔傞丅
丂椬偵棃偨斵曽偵攚拞傪扏偐傟丄峛夘偼丄崱搙偼帺暘偐傜斵彈傪書偒偟傔偨丅
乽偁乕丄偄偮傑偱傕僀僠儍偮偄偰側偄偱丄孨偨偪傕偝偭偝偲揚廂偟偰偔傟側偄偐乧乧乿
乽乧乧傂偀偭両丠乿
丂墶偐傜奝暐偄偲偲傕偵暦偙偊偰偒偨儅乕僔儍儖偺惡偵丄儂僲僇偼婄傪恀偭愒偵偟偰丄偁傢偰偰峛夘偺攚拞偵塀傟傞丅
乽乽乧乧乧乧乿乿
乽戝惃偺帇慄偼崕暈偱偒偨傒偨偄傗偗偳丄恖尒抦傝偼傑偩捈傜傊傫偺傗側乧乧乿
丂崱偵側偭偰巚偄弌偟偨傛偆偵徠傟傞儂僲僇偲峛夘丅偦傫側傆偨傝偵斵曽偼偳偙偐慉傑偟偦偆側昞忣偱丄娽嬀偺墱偺栚傪嵶傔偨丅
丂to be continued...
劅 appendix 劅
乽戝忎晇側偺丠丂杺朄傪恖偵岦偗偰巊偭偪傖偄偗側偄傫偠傖乧乧乿
乽忬嫷傪尒掕傔傞偨傔旘傃忋偑偭偨嵺偵丄偨傑偨傑偄偮傕傛傝懡偔塇崻偑嶶偭偰偟傑偭偨偩偗偩丅偦傟偵巹偑巊偆偺偼杺朄偱偼側偔恄椡丅栤戣側偄乿
丂怱攝偡傞僋儔僗儊僀僩偵偦偆尵偄曉偡偲丄嬻偐傜晳偄崀傝偨儖儈僫偼攚拞偺梼傪柖嶶偝偣偨丅岝偺塇崻偵帺暘偺椡傪偺偣偰旘傃嶶傜偣丄帠懺傪捑惷壔偝偣偨偙偲偵婥偯偄偰偄傞偺偼斵彈劅劅暥梩偩偗偺傛偆偩丅
乽偱傕乧乧偁傝偑偲偆丄儖儈僫乿
乽姩堘偄偡傞側丅杺暔柡偺偁偄偮傜傪彆偗偨傢偗偠傖側偄乧乧傑傢傝偺恖娫偵婋奞偑媦偽側偄傛偆偵偡傞偵偼丄偁偁偡傞偺偑堦斣庤偭庢傝憗偐偭偨偩偗偩偐傜側乿
丂偦偆晅偗壛偊丄儖儈僫偼僶僩儖僗僥乕僕偵栚傪岦偗傞丅乽乧乧傓偟傠僄價僴儔偑僒僀僋儘僾僗偵懧偪偰偟傑偭偨偙偲偺曽偑丄巹偵偲偭偰偼桼乆偟偒偙偲偩乿
乽乧乧乧乧乿
丂廳乆偟偄岥挷偱榬傪慻傓償傽儖僉儕乕偵丄暥梩偼曫傟偨傛偆側棴傔懅傪揻偄偨丅
乽傑偝偐偲偼巚偆偗偳丄儂僲僇偲奀榁尨偵彫屍傒偨偄側恀帡偟側偄偱傛乿
乽偩偭乧乧扤偑偡傞偐偭丅偦傫側媥傒偺偨傃偵幚壠偵栠偭偰偒偰庤揱偄傕偟側偄偔偣偵弌偝傟偨椏棟偵働僠偮偗偨傝晹壆偺嬿偺儂僐儕偵寵枴尵偭偨傝帺暘偺巕偳傕偺柺搢墴偟晅偗偰梀傃偵峴偭偨傝慜偲摨偠嬸抯傗帺枬榖傪墑乆暦偐偣偨傝偡傞傛偆側偙偲偭両乿
乽乧乧側傫偱偦傫側偵嬶懱揑側偺傛乿
丂婄傪愒傜傔偦偭傐傪岦偔儖儈僫偩偭偨偑丄偦偺摰偼偪傜偪傜偲丄僗僥乕僕偱弨寛彑恑弌傪婌傇僫僊傗儂僲僇偨偪傪尒偰偄傞傛偆偩偭偨丅
乽儂儞僩丄慺捈偠傖側偄傫偩偐傜乧乧乿
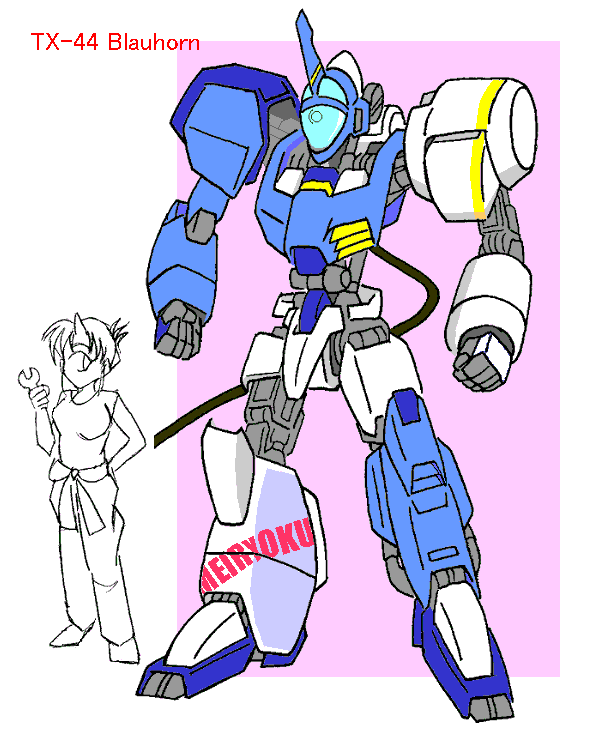
丂傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽丄傢傫偩偽偩偽偩偽偩偭丄僴僢両
丂傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽丄傢傫偩偽偩偽偩偽偩偭丄僴僢両
乽僐儅儞僢丄僪乕僢両両丂抧媴杊塹戉俶俿俼偱偁傞偭両乿
乽乽乽僐儅儞僢丄僪乕僢丄乧乧僥傿僢両両乿乿乿
乽側偭乧乧側傫側傫偩偍慜傜偭両丠乿
丂堄幆傪庢傝栠偟偨斵傜劅劅偁偺偲偒儂僲僇偵愇傪搳偘偮偗偨抝偨偪偼丄栚偺慜偵墶堦楍偱暲傫偱朸摿愴戉晽億乕僘傪僉儊傞楢拞偵丄嵗傝崬傫偩傑傑屻戅傝側偑傜搟柭傝曉偟偨丅
丂暻偵戝彫偝傑偞傑側儌僯僞乕偑愝抲偝傟偨丄憢偺側偄晹壆丅偦偙偵偄傞慡堳丄僈僞僀偺偄偄恎懱偵僌儗乕抧偵愒偲惵偺儔僀儞偑擖偭偨丄僂侟僩儔杊塹戉傒偨偄側傁偭偮傫傁偭偮傫偺儗僓乕僗乕僣傪拝偰丄帹摉偰偺偲偙傠偵揹忺偲傾儞僥僫偺偮偄偨僷僀儘僢僩梡僿儖儊僢僩傪彫榚偵書偊偰偄傞丅崢偵傇傜壓偘偰偄傞偺偼僾儘僢僾僈儞乧乧僆儌僠儍偩傠偆丄偨傇傫丅
乽僐儅儞僢丄僪乕僢両両 丂変乆偼孨偺傛偆側恖娫傪懸偭偰偄偨偭両丂搝傜偲愴偆巊柦偵栚妎傔偨愴巑傪偭両両乿
乽乽乽僐儅儞僢丄僪乕僢両両 乿乿乿
乽偩偐傜偄偭偨偄側傫側傫偩偭両丠乿
乽偰偄偆偐側傫偱偙傫側偲偙傠偵乧乧偘偭両乿
乽側乧乧側傫偱偙傫側偺拝偣傜傟偰傫偩側偭両丠乿
丂偼偭偲婥偯偔偲丄楢拞偲摨偠奿岲劅劅杊塹戉晽儗僓乕僗乕僣巔偵偝傟偰偄偨丅
丂偁傫側恀帡傪偟偨偣偄偱丄偳偆傗傜偙偄偮傜偵噣偍拠娫噥擣掕偝傟偰偟傑偭偨傛偆偩丅
丂杺暔柡傪乽恖椶偺揋乿乽暯榓傪嫼偐偡埆乿偲悂挳偟揋帇偡傞偙偲偱丄僸乕儘乕偵側偭偨婥偱偄傞偍傔偱偨偄楢拞偵丅
丂偟偐偟崱偝傜屻夨偟偰傕丄傕偆抶偄丅
丂傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽丄傢傫偩偽偩偽偩偽偩偭丄僴僢両
丂傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽丄傢傫偩偽偩偽偩偽偩偭丄僴僢両
乽偝偁偭両丂変傜抧媴杊塹戉俶俿俼戉堳偲偟偰僢丄偲傕偵抧媴怤棯傪偨偔傜傓埆偺杺暔偨偪偲愴偆偺偩偭両両乿
乽乽乽僐儅儞僢丄僪乕僢両両乿乿乿
乽僐儅儞僢両乿乽僐儅儞僢両乿乽僐儅儞僢両乿乽僐儅儞僢両乿
乽僐儅儞僢両乿乽僐儅儞僢両乿乽僐儅儞僢両乿乽僐儅儞僢両乿
乽乽乽僐儅儞僢丄僪乕僢丄乧乧僥傿僢両両乿乿乿
乽偆傢偁偁傛偭婑傞側婄嬤偯偗傞側旲懅悂偒偐偗傞側偁偁偁偭両乿乽傂偭丄恖偺榖傪劅劅乿
丂傾僢劅劅劅劅劅劅劅劅両両
丂堦廡娫屻劅劅
乽僐儅儞僢丄僪乕僢両両丂抧媴杊塹戉俶俿俼偱偁傝傑偡偭両丂擟柋悑峴拞側偺偱幾杺偟側偄偱偄偨偩偒偨偄偭両乿
乽偄偄偐傜偝偭偝偲柶嫋徹弌偟偰乿
丂偡偭偐傝噣愼傑偭偰噥偟傑偭偨斵傜偼愴摤婡偺傛偆側僂僀儞僌傗傜僲乕僘傗傜悅捈旜梼傗傜偱忺傝晅偗傜傟偨帺摦幵偵忔傝丄僒僀儗儞傪崅傜偐偵柭傜偟側偑傜揋偺怤棯嫆揰乮徫乯偱偁傞柧椢娰妛墍偺晘抧傊偲撍擖乧乧乧乧偡傞捈慜偵幵椉朄堘斀乮晄惓夵憿乯偱僷僩僇乕偵巭傔傜傟丄掞峈偟偨偨傔偦偺応偱慡堳戇曔偝傟偨劅劅
丂偁傫側偵戝惡傪忋偘偨偺偼丄偄偮埲棃偩傠偆丠丂偦傟傕丄戝惃偺恖偑尒偰偄傞慜偱丅
丂偱傕丄偁偺帪偼抪偢偐偟偄偲偐丄僸僩僣栚偺帺暘偑栚棫偮偲婥枴埆偑傜傟傞偲偐側傫偰丄偙傟偭傐偭偪傕巚偭偰側偐偭偨丅斵偺攚拞傪墴偟偰偁偘偨偄偲偄偆婥帩偪偱摢偺拞偑堦攖偵側傝丄敿偽柍変柌拞偩偭偨丅
丂偩偐傜丄帺暘偑慻傒捈偟偨儊僈僷儁僢僩偲偄偆嫄戝側僇儔僋儕恖宍偑帋崌偵彑偭偨偙偲埲忋偵丄斵偲堦弿偵擇夞愴傊偲恑傔偨偙偲偑婐偟偐偭偨丅
丂偦偟偰乽儂僲僇偪傖傫乿偲屇傃偐偗傜傟偨偲偒乧乧偳偆偟偰帺暘偑偙偙傑偱偐偐傢偭偰偒偨偺偐丄偦偺棟桼偵婥偯偔偙偲偑偱偒偨丅
丂偦偭偐乧乧僐乕僗働偔傫丄偁偺恖偵帡偰傞傫偩劅劅
丂偢偭偲怱偺墱偵巇晳偄崬傫偱偄偨丄巚偄偲崌傢偣偰丅
亙仠亜
丂戞敧夞慡擔杮儘儃俿俼倄慖庤尃丄抧嬫梊慖夛擇夞愴丅
丂傾僫僂儞僗偲偲傕偵丄擇懱偺恖宆廳婡劅劅儊僈僷儁僢僩偑僶僩儖僗僥乕僕偵忋偑傝丄奺乆偺懸婡慄傊偲曕傪恑傔傞丅
乽憡庤偼婂儢庱戝妛偺儘儃僢僩尋媶夛乧乧戝夛偺忢楢偝傫偩傛乿
乽乧乧彑偰傞丠乿
乽彑偮傛丅儂僲僇偪傖傫偑惍旛偟偰偔傟偨僐僀僣偱乿
丂椬偵偄傞僒僀僋儘僾僗柡偵偦偆摎偊傞偲丄峛夘偼慜傪曕偔帺暘偺婡懱偵帇慄傪岦偗偨丅
乽偄偭偗偉僐乕僗働両丂偦偙偺僾儗僀儎乕偛偲傇偭偲偽偣乣偭両両乿
乽乧乧偦傟傗偭偨傜堦敪偱斀懃晧偗偵側傞偱丄僫僊乿
乽側傫偩偲両丠丂偊偊偄偭丄偙偺巹偑偄傞尷傝偦傫側恀帡偼愨懳偵偝偣傫偧偭両乿
丂杊岇僼僃儞僗偺奜懁偵偼丄崱擔傕戝惃偺僊儍儔儕乕偑墳墖偵廤傑偭偰偄傞丅
丂擇恖偑墶栚偱偆偐偑偆偲丄婂儢庱戝儘儃尋偺彈惈僾儗僀儎乕乮偺嫻乯傪恊偺僇僞僉偲偽偐傝偵僸僩僣栚偱嵘傒偮偗側偑傜惡傪忋偘傞僎僀僓乕柡僫僊偵丄斵曽偑嬯徫傪晜偐傋偰僣僢僐傫偱丄償傽儖僉儕乕偺儖儈僫偑旣傪捿傝忋偘傑偔偟棫偰偰偄偨丅偦偺墶偱丄暥梩偑僗儅儂曅庤偵庤傪怳偭偰偔傞丅
乽乧乧乧乧乿
乽乧乧偔偡偭乿
丂桭恖偨偪偺暯忢塣揮側巔偵丄尐偺椡偑偄偄嬶崌偵敳偗偨丅
丂峛夘偨偪偺婡懱乹俿倃亅係係夵乺偵憡懳偡傞偺偼丄棏宆偺摢晹偑摿挜揑側墿怓偺儊僈僷儁僢僩丅搊榐婡懱柤偼乹僉僋儌儞侽俁乺丅嫻偲椉尐偺僟儊乕僕儅乕僇乕偺怓偼巼丅
丂帋崌奐巒偺僐乕儖偑嬁偒丄僗僞乕僩僔僌僫儖偺怓偑曄傢傞丅擇懱偼摨帪偵懸婡慄傪廟傝丄恀偭惓柺偐傜傇偮偐傝崌偭偨乧乧
丂乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧
乽Winner両丂僠乕儉丒儌僲傾僀僈乕儖僘両両乿
乽側傫偱乧乧偁傫側億儞僐僣偵劅劅偭乿
丂嫻偲塃尐偺僟儊乕僕儅乕僇乕偺怓偑曄傢偭偨傑傑揚廂偝傟偰偄偔乹僉僋儌儞侽俁乺傪堦曀偟丄婂儢庱戝儘儃尋偺彈惈僾儗僀儎乕偼壵棫偨偟偘偵偮傇傗偄偨丅
丂岥乆偵側偩傔傛偆偲偡傞庢傝姫偒偨偪偺惡傪柍帇偟偰丄憡庤僠乕儉偺婡懱傪嵘傒晅偗傞丅
乽乧乧乧乧乿
丂嬐嵎偩偭偨丅岦偙偆傕嵍尐偺儅乕僇乕偺怓偑曄傢傝丄偦偙偐傜旾傪媡懁偵嬋偘傜傟偨嵍榬偑傇傜傇傜偲椡側偔悅傟壓偑偭偰偄傞丅僣僊僴僊側尒偨栚傕偁偭偰丄憡庤偺榬傪捵偟偨偦偺弖娫偵乽彑偭偨両乿偲桘抐丄枬怱偟偰偟傑偭偨偺偑帺暘偨偪偺攕場偩偭偨偺偩傠偆丅
丂傑偝偐僇僂儞僞乕偱丄嫻尦偵摢撍偒偟偰偔傞偲偼巚偄傕偟側偐偭偨丅
丂傆偲丄岦偙偆偺僙僐儞僪偲栚偑崌偭偨丅悈怓偺敡丄妟偵惗偊偨僣僲丄儅儞僈傒偨偄側戝偒側僸僩僣栚偺恖奜彮彈劅劅杺暔柡丅
丂徟偭偨傛偆偵偍帿媀偝傟丄栚傪堩傜偝傟偨丅
乽乧乧偭両乿
丂壔偗暔彈偑偭乧乧偲埆懺傪偮偒偐偗丄偡傫偱偺偲偙傠偱偦傟傪堸傒崬傓丅
丂儅乕僔儍儖傗戝惃偺僊儍儔儕乕偑尒偰偄傞慜偱偦傫側偙偲傪岥憱偭偨傜丄晧偗偨偔偣偵傒偭偲傕側偄丄尒嬯偟偄丄戝恖偘側偄丄噣偁偺噥楢拞偲摨椶偐傛劅劅偲媡偵僨傿僗傜傟丄偙偪傜偑偄傜偸抪傪偐偔偩偗偱偁傞丅
丂斵彈偼彮偟夨偟婥偵棴傔懅傪揻偒丄纟傪曉偟偨丅
亙仠亜
丂師偺帋崌偼堦廡娫屻丅偦傟傑偱偵婡懱傪廋棟偟丄摦偐偣傞傛偆惍旛偟側偗傟偽側傜側偄丅
丂偄偮傕偺晹幒搹偺墶偱丄峛夘偲儂僲僇偼儊僈僷儁僢僩乹俿倃亅係係夵乺偺廋棟傪巒傔偰偄偨丅
丂僫僊偨偪偼晹妶摍偱晄嵼丅戙傢傝偵庤揱偭偰偔傟偰偄傞偺偼劅劅
乽傛偭丄偍偭偲偲偭乧乧偍乕偄儂僲僇偀丄偙傟偳偙偵抲偔傫偩丠乿
乽偙偭偪丅偙偺恀傫拞偵備偭偔傝抲偄偰乿
乽偁偄傛偭乿
丂摢傂偲偮崅偄恎挿丄墿椢怓偺敡丄愒偄敮丄僶儞僟僫傪姫偄偨妟偐傜惗偊偨擇杮偺僣僲丅
丂婡懱偐傜庢傝奜偝傟偨嵍尐偺僇僂儕儞僌傪曅庤偵帩偭偨懱憖暈巔偺僆乕僈柡僒僉偑丄儂僲僇偑巜嵎偡僽儖乕僔乕僩偺忋偵偦傟傪偦偭偲壓傠偟偨丅乽乧乧堄奜偲寉偄傫偩側丅嫄恖偺奪偩偐傜傕偆偪傚偭偲廳偄傕傫偩偲巚偭偰偨偤乿
乽偁傫傑傝廳偄偲娭愡晹偵晧扴偑偐偐傞偐傜偹丅僶僢僥儕乕偺徚栒傕憗偔側傞偟丄杊屼椡傪懝側傢側偄僊儕僊儕傑偱寉検壔偟偰傞傫偩乿
丂婡懱偺庱偺偲偙傠偵屪偑偭偰摢晹偺僙儞僒乕傪嵞挷惍偟偰偄偨峛夘偑丄惛枾僪儔僀僶乕曅庤偵偦偆愢柧偡傞丅傕偭偲傕僆乕僈婎弨偱偺乽寉偄乿偱偁偭偰丄尐晹偺奜憰偼偦偙偦偙廳偝偑偁傞丅埲慜僆乕僶乕儂乕儖偟偨偲偒偼丄峛夘偲斵曽偑擇恖偑偐傝偱庢傝奜偟偰偄偨丅
乽傆偆傫乧乧傑丄梫偼彑偮偨傔偵偄傠偄傠岺晇偝傟偰傞偭偰偙偲偩傛側乿
乽傑丄傑偁偹乧乧乿
丂榬傪慻傒丄暘偐偭偰偄傞偐偺傛偆偵僂儞僂儞偆側偢偔丅偦傫側僒僉偵嬯徫傪晜偐傋傞峛夘偩偑丄撪怱偱偼偙偺婼柡偑偄偮乽堦搙僐僀僣乮儊僈僷儁僢僩乯偲愴傢偣傠傛乿偲偐尵偄偩偝側偄偐丄價僋價僋偟偰偄偨傝偡傞丅
乽傎偐偺奪偼偳乕偡傫偩丠丂儂僲僇乿
乽崱擔偼嵍榬偺廋棟偩偗偩偐傜乧乧偙傟偱偄偄乿
丂偄偒側傝傆傜偭偲尰傟偰丄傾僞僔偵傕庤揱傢偣傠偲惡傪偐偗偰偒偨僒僉丅暦偗偽暥梩偑僗儅儂偱嶣偭偰偄偨帋崌偺摦夋傪尒偰丄嫽枴傪偍傏偊偨偺偩偲偐丅
丂偪側傒偵斵彈偨偪杺暔柡偼丄恎懱峔憿偑僸僩偲偼堘偆偲偄偆棟桼偱僗億乕僣嫞媄夛傊偺弌応傪惂尷偝傟偰偄傞乮嬻傪旘傫偩傜儂乕儉儔儞儃乕儖傕傾僂僩偵偝傟傞乧乧偲偄偆椺偊曽傪恀婄偱偡傞楢拞偼僶僇偭傐偄偲巚偆偑乯丅偦傫側拞偱摨偠杺暔柡偺拠娫偑儌乕僞乕僗億乕僣偺儊僇僯僢僋偲偟偰偱偼偁傞偑丄岞幃偺戝夛偵嶲壛偟彑偪恑傫偱偄傞偺偩丅奆丄戝側傝彫側傝婥偵側偭偰偄傞偺偩傠偆丅
丂乧乧婥偵側偭偰偄傞偺偼丄傕偪傠傫偦傟偩偗偱偼側偄偺偩偑丅
乽傆乣傫丄拞恎偼愴摤梡偺杺摫媊巿傒偨偄側傫偩側乿
丂僼儗乕儉偲僔儕儞僟乕偑攳偒弌偟偵側偭偨乹俿倃亅係係夵乺偺嵍榬傪偟偘偟偘偲挱傔丄僒僉偑傐偮傝偲偮傇傗偔丅偝偡偑偵廋棟拞偺儊僈僷儁僢僩偵彑晧傪傆偭偐偗傞側傫偰偙偲偼偟側偐偭偨偑丄帺暘偺榬偲尒斾傋偰偄傞偁偨傝丄偦偺婥偑側偄偲偼尵偊側偄傛偆偩丅
乽杺摫媊巿丠乿
乽憰拝幰偺帩偮杺椡偱摦偔媊庤傗媊懌偺偙偲劅劅乿
丂庱傪孹偘傞峛夘偵丄儂僲僇偑婄傪忋偘偰摎偊偨丅偙偭偪偺悽奅偱尵偆偲偙傠偺僒僀僶乕媊巿偺傛偆側傕偺傜偟偄丅
乽偦偆偦偆儂僲僇偺恊晝偝傫側丄偪傚偭偲柤偺抦傟偨杺摫媊巿惢嶌偺儅僀僗僞乕乮柤恖乯側傫偩偤乿
乽傊偊乧乧偦偆側傫偩乿
乽偆傫乿
丂彮偟徠傟偔偝偦偆偵偟側偑傜傕丄僒僀僋儘僾僗柡偼屩傜偟偘偵偆側偢偔丅
丂斵彈偑堎悽奅偺僇儔僋儕巇妡偗劅劅儊僈僷儁僢僩傪惍旛偡傞偙偲偑偱偒偨偺偼丄庬懓摿惈偱庴偗宲偄偱偒偨抌栬乮嬥懏壛岺乯媄擻偵壛偊偰丄偦傫側壠掚娐嫬偱堢偭偰偒偨偐傜偐乧乧媟棫偵嵗偭偰婡懱偺嵍旾傪廋棟偡傞偦偺巔傪尒偮傔丄峛夘偼彫偝偔徫傒傪晜偐傋偨丅
丂栙乆偲嶌嬈傪懕偗傞峛夘偲儂僲僇丅庤帩偪柍嵐懣偵側偭偨僒僉偼丄儂僲僇偵偦偭偲嬤婑傝丄偪傚偄偪傚偄偲庤彽偒偟偨丅
乽壗丠乿
丂儂僲僇偼庤傪巭傔偰丄媟棫偺忋偐傜恎傪忔傝弌偡丅
乽傗偭傁帡偰傞傛側丄傾僀僣乧乧乿
乽乧乧両乿
丂帹尦偵彫惡偱殤偐傟丄僒僀僋儘僾僗柡偺摦偒偑屌傑偭偨丅
乽偩劅劅扤丄偵丠乿
乽扤偭偰乧乧儀僀儕偝傫偵偩傛丅恊晝偝傫偺掜巕偱丄儂僲僇偺弶楒偺憡庤劅劅乿
乽偪丄偪傚偭偲懸偭偰偭両丂偼偼偼弶楒偭偰丄乧乧偪丄堘偆偐傜偭両丂堘偆偐傜偭両乿
丂撪怱傪尒摟偐偝傟偨傛偆偵巜揈偝傟丄偁傢偰偰惡傪忋偘傞丅
丂摢晹僙儞僒乕偺挷惍傪懕偗偰偄偨峛夘偑丄乽偳偆偟偨偺丠乿偲岦偒捈偭偰偒偨丅
乽偪丄偪偭偪傖偄崰偺榖偩偟乧乧偦傟偵丄傋丄儀僀儕偝傫偵偼丄傟乧乧儗僀僔儍丄偝傫偑乧乧偄偨丄偟劅劅乿
丂偝偭偒埲忋偵婄傪愒傜傔丄偆偮傓偔儂僲僇丅
丂偦傟偼斵彈偑傑偩梒偐偭偨崰丄晝恊偺僼傽僋僩儕乕偱摥偒偩偟偨尦婻巑尒廗偄偺彮擭偲丄
乽僒僉偝傫丄儗僀僔儍偝傫偭偰丠乿
乽儀僀儕偝傫偺楒恖乧乧儂僲僇偺恊晝偝傫偺岺朳偱丄媊巿偺儌僯僞乕傗偭偰傞僆乕僩儅僩儞偺偍巓偝傫偩偤乿
乽偍丄僆乕僩儅僩儞丠乿
丂偙偪傜偺悽奅偱偼丄庡偵侾俀乣侾俋悽婭偵偐偗偰儓乕儘僢僷摍偱嶌傜傟偨帺摦恖宍傗丄僨僕僞儖夞楬偺僾儘僌儔儉愝寁偱巊傢傟傞寁嶼儌僨儖傪巜偡扨岅側偺偩偑丄
丂劅劅偊乕偭偲妋偐丄杺暔柡斉僈僀僲僀僪乮彈惈宆傾儞僪儘僀僪乯偩偭偨偭偗乧乧
丂岦偙偆偺悽奅偱偼僑乕儗儉傗噣庺偄偺恖宍噥傑偱杺暔柡壔偟偰恖娫偺抝惈偲楒垽偡傞偲偄偆偺偩偐傜丄傾儞僪儘僀僪偲恖娫偺僇僢僾儖側傫偰捒偟偔傕側傫偲傕側偄偺偐傕偟傟側偄丅側偍乽僆乕僩儅僩儞乿偲暦偄偰丄朸侽侽偵弌偰偒偨敔宆偺帺摦懳恖峌寕儘儃僢僩偑偪傜偭偲摢傪棭傔偨偺偼撪弿偩丅
丂峛夘偑撪怱偱傂偲傝僣僢僐儈偟偰偄傞偲丄栙偭偰壓傪岦偄偰偄偨儂僲僇偑丄傐偮傝偲偮傇傗偄偨丅
乽帡偰側偄傛乧乧乿
乽乧乧偊丠乿
丂峛夘偲僒僉偑尒偮傔傞拞丄斵彈偼庤偵偟偨岺嬶傪帩偪捈偟丄婄傪愒偔偟偨傑傑嵘傒偮偗傞傛偆側栚偮偒偱儊僈僷儁僢僩偺廋棟傪嵞奐偟偨丅乽帡偰側偄乧乧丄帡偰側偄乧乧乧乧帡偰側偄偐傜劅劅乿
乽乽乧乧乧乧乿乿
丂帺暘偵尵偄暦偐偣傞傛偆偵偦偆孞傝曉偟側偑傜丄堦怱晄棎偵庤傪摦偐偡丅
丂棴傔懅傪揻偄偨僒僉偑傆偲尒忋偘傞偲丄婡懱偺尐偵屪偭偨峛夘偑壗偐尵偄偨偘側婄偲娽嵎偟傪儂僲僇偵岦偗偰偄偨乧乧
乽儂僲僇偪傖傫丄偦偙丄庢傝晅偗偑媡劅劅乿
乽乧乧偁乿
亙仠亜
丂峏幯巗拞墰岞墍惵嬻峀応丄抧嬫梊慖夛嶰夞愴丅
丂偙傟偵彑偰偽儀僗僩係劅劅弨寛彑偵恑傔傞偲偁偭偰丄奺僠乕儉偲傕枩慡偺僐儞僨傿僔儑儞偱婡懱傪帩偪崬傒丄墳墖偵傕偙傟傑偱埲忋偵恖偑廤傑偭偰偄傞丅
丂柧椢娰妛墍偐傜偼偄偮傕偺柺乆偵壛偊偰丄惍旛傪庤揱偭偨僆乕僈柡偺僒僉偲傾儔僋僱柡偺儎儓僀偺巔傕偁偭偨丅僼僃儞僗偺奜懁偐傜棫偪尒偱娤愴偡傞偺偱丄壓敿恎偑嫄戝僌儌偱傕戝忎晇乧乧傕偭偲傕偁偐傜偝傑偵恖奜側尒偨栚偵丄墦姫偒偵偟偰寵埆姶傪業傢偵偟偰偄傞幰傕彮側偔側偄丅
丂偦傫側拞丄峛夘偲堦弿偵弌斣傪懸偭偰偄偨儂僲僇偼丄僫僊偵僷僪僢僋偺棤傊偲楢傟偰偙傜傟偨丅
乽乧乧僫僊偪傖傫丄媫偵偳偆偟偨偺丠乿
丂傕偆偡偖帋崌側傫偩偗偳乧乧偲屗榝偆儂僲僇偺尵梩偵丄僫僊偼偮偐傫偱偄偨斵彈偺庤傪曻偡偲丄備偭偔傝怳傝曉偭偨丅
乽乧乧側偁儂僲僇丄僐乕僗働偲壗偐偁偭偨丠乿
乽両乿
丂僺僋儞丄偲尐偑挼偹忋偑傞丅乽傋丄暿偵壗傕乧乧側偄丄傛乿
乽乧乧乧乧乿
丂偁偐傜偝傑偵栚傪塲偑偣堩傜偡恊桭偵丄僫僊偼攚拞偺怗庤傪偔偹傜偣棴傔懅傪揻偄偨丅
丂帺暘傕偦偆側偺偩偑丄側傑偠扨娽偑戝偒偄暘丄梋寁偵偦傟偑傛偔傢偐傞乧乧
乽偙側偄偩偐傜傆偨傝偲傕丄側乣傫偐僊僋僔儍僋偟偰傞偭偰偄偆偐丄堄幆偟側偄傛偆偵偟傛偆偲偟偰丄偐偊偭偰堄幆偟夁偓偰傞偭偰偄偆偐劅劅乿
乽偦丄偦傫側偙偲乧乧側偄丄偗偳乧乧乿
丂婄傪愒傜傔尵偄揵傓儂僲僇丅偦傫側斵彈偵丄僫僊偼婄偺恀傫拞偵偁傞扨娽傪僊儑儘儕偲摦偐偡丅
乽乧乧乧乧乿
丂儂僲僇偼偦偺帇慄偐傜摝偘傞傛偆偵偆偮傓偄偨丅
丂峛夘偑帺暘偺弶楒偩偭偨恖偵帡偰偄傞乧乧偲丄悽榖從偒僆乕僈柡偺僒僉偵巜揈偝傟偰偐傜偢偭偲丄斵彈偺怱偺掙偵偖偠偖偠偟偨婥帩偪偑揵偺傛偆偵傢偩偐傑偭偰偄傞丅
丂斵劅劅峛夘傪丄偐偺恖偺噣戙傢傝噥偲偟偰尒偰偄傞傫偠傖側偄偐偲偄偆丄帺屓寵埆偵帡偨婥帩偪偑丅
丂楒垽偵僱僈僥傿償婥枴側偺傕偁偭偰丄堦搙偦偆巚偭偰偟傑偆偲側偐側偐偦偙偐傜敳偗弌偣側偄丅偩偗偳峛夘偺偦偽傪棧傟偨偔側偄乧乧儊僈僷儁僢僩偺廋棟傗惍旛丄帋崌拞偺僶僢僋傾僢僾傪棟桼乮僟僔乯偵丄帺暘偱帺暘偵尵偄栿偟偰偄傞偺傕寵偩偲巚偆劅劅
丂偦傫側恊桭偺婥帩偪偵婥偯偄偰偄傞偺偐丄偼側偐傜偍尒捠偟側偺偐丄僫僊偼戝偒偔懅傪媧偆偲丄
乽儂僲僇両乿
丂嫮偄岥挷偱屇偽傟丄儂僲僇偼斀幩揑偵婄傪忋偘偨丅
丂師偺弖娫僫僊偺愒偔岝傞扨娽偲栚偑崌偭偰丄恎懱偑摦偐側偔側傞丅
乽側丄僫僊丄偪傖傫乧乧壗丄傪劅劅乿
丂幾娽偵尒偮傔傜傟丄儂僲僇偺栚偺徟揰偑掕傑傜側偔側偭偰偄偔丅
乽僎僀僓乕偺僫僊偑柦偢傞両丂乧乧儂僲僇丄偪傚偭偲慺捈偵側傟偭乿
乽偁劅劅乿
丂倁僒僀儞偟偨塃庤傪墶偵搢偟偰栚偺抂偵摉偰丄偳偙偧偺傾僯儊傒偨偄側億乕僘傪偒傔偰埫帵傪堦敪丅偦偟偰崨偗偨忬懺偱屌傑偭偨儂僲僇偺攚屻偵夞偭偰丄偦偺椉尐偵億儞偲庤傪抲偔丅
乽傎傜儂僲僇丄僐乕僗働偑懸偭偰傞偧乿
乽偊丠丂偁丄偆劅劅偆傫乧乧乿
丂壗傕峫偊偢偵傏傫傗傝偟偰偄偰丄媫偵偼偭偲変偵曉偭偨傛偆側姶妎傪偍傏偊丄僫僊偵攚拞傪墴偝傟偨儂僲僇偼摢傪怳偭偰偦偆墳偊傞偲丄尵傢傟偨傑傑僷僪僢僋偵岦偐偭偰纟傪曉偟偨丅
乽乧乧偁傟丠乿
丂側傫偩偐傛偔傢偐傜側偄偗偳丄偄偮偺娫偵偐偪傚偭偲偩偗婥帩偪偑寉偔側偭偨傛偆側婥偑偡傞乧乧斵彈偼懌傪巭傔偰怳傝岦偒丄偵傑偭偲旝徫傓恊桭偺婄傪尒偨丅
乽偁傝偑偲丄僫僊偪傖傫乿
乽偑傫偽傟傛丄儂僲僇乿
丂偦偺屻傠巔傪尒憲傝丄僎僀僓乕柡偼敮偺拞偐傜怢傃偨怗庤傪婡寵傛偝偘偵備傜備傜偲摦偐偡丅
丂劅劅傾僞僔傕僐乕僗働偼儀僀儕偝傫偵帡偰傞偲巚偆偧丅婡夿偄偠傝偑岲偒側偲偙偲偐丄摱婄側偲偙偲偐乧乧
乽儂僲僇偪傖傫丄偰屇傇偲偙偲偐側偭侓乿
丂偒偟偟偭丄偲僀僞僘儔偭傐偄徫傒傪晜偐傋傞僫僊丅
丂偦偺婥偵側傟偽儂僲僇偵乽崱偡偖僐乕僗働偵僐僋傟乿偲丄幾娽偺椡偱柦椷偡傞偙偲傕偱偒傞偺偩偑丄偦偙偼壋彈側杺暔柡丅垽偺崘敀偼憖傜傟偰偱偼側偔帺暘偺堄巚偱劅劅偲巚偭偰偟傑偆偺偼丄斵彈傕傑偨偦偆偄偆偺偵摬傟偰偄傞偐傜側偺偐傕偟傟側偄乧乧巜揈偝傟偨傜愨懳斲掕偡傞偩傠偆偗偳丅
亙仠亜
乽戞巐帋崌丄柧椢娰妛墍亀僠乕儉丒儌僲傾僀僈乕儖僘亁懳丄棫壴旽戝晅懏崅峑亀僠乕儉丒僀儞僼傿僯僢僩儕僶乕僒乕亁傪奐巒偟傑偡劅劅乿
丂僫僊偨偪柧椢娰妛墍偺柺乆偑尒庣傞拞丄塃榬晹偲嵍媟晹傪惵偔揾傝暘偗偨奃敀怓偺恖宆廳婡偑丄傾僫僂儞僗偲偲傕偵懸婡慄傊偲曕傪恑傔傞丅僇儔乕儕儞僌偩偗偱側偔丄搊榐婡懱柤傕乹俿倃亅係係夵乺偐傜乹僽儔僂儂儖儞乺傊偲夵傔傜傟丄偦偺柤偺捠傝丄妟偵摉偨傞晹暘偵僽儗乕僪僞僀僾偺忺傝僣僲偑怴偨偵庢傝晅偗傜傟偨丅塃泺晹偺僇僂儕儞僌偵偼俵俤俬俼倄俷俲倀俲俙俶偲幬傔偵報帤偝傟偰偄傞丅
丂偦傫側峛夘偨偪偺婡懱偵憡懳偡傞偺偼丄弮敀偺僇僂儕儞僌偱慡恎傪寗側偔暍傢傟丄偦偙偐偟偙偵愒偄儔僀儞偺揾憰偑巤偝傟偨丄偄傢備傞僨儌儞僗僩儗乕僞乕僇儔乕偺儊僈僷儁僢僩丅僟儊乕僕儅乕僇乕偺怓偼僀僄儘乕丅偍偦傜偔偙傟傕屻晅偗偝傟偨偺偱偁傠偆丄僑乕儖僪偵揾傜傟偨妟偺倁帤僣僲偑栚傪堷偔丅
丂側傫偱傕戝庤廳婡儊乕僇乕偑奐敪偟偨丄師婜庡椡儌僨儖偺帋嶌婡劅劅僾儘僩僞僀僾側偺偩偲偐丅
乽偦傟偵偟偰傕偁偺恖傜丄偳側偄尒偰傕崅峑惗偵偼尒偊偟傑傊傫乧乧乿
乽偄傗偳偆尒偰傕偍偭偝傫偱偟傚傾儗乿
丂庤傪杍偵摉偰偰庱傪孹偘傞儎儓僀偺揤慠儃働婥枴側敪尵偵丄暥梩偼懄嵗偵僣僢僐傒曉偟偨丅
丂憡庤僠乕儉偺婡懱偺椬偵棫偮僾儗僀儎乕偼斵彈偨偪偲摨擭戙偺抝巕偩偑丄屻傠偱峊偊偰偄傞僙僐儞僪擇恖偼斾歡偩偲偐榁偗婄偩偲偐偱偼側偔丄惓恀惓柫偺傾儔僒乕抝惈偩偭偨丅
丂暥梩偼庤偵偟偨僗儅儂偺俥俿僨傿僗僾儗僀偵丄梊慖夛偺嶲壛僠乕儉儕僗僩傪昞帵偝偣傞丅
乽僠乕儉丒俬俶俥儕僶乕僒乕丄僾儗僀儎乕恄尨僕儞乮偠傫偽傜丒偠傫乯丄搊榐婡懱柤乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺丅乧乧偝偭偒偺傾僫僂儞僗偱妛峑戙昞傒偨偄偵徯夘偝傟偰偨偗偳丄幚幙偼屄恖嶲壛側偺偹乿
乽庤揱偳偆偰偔傟傞偍桭偩偪丄妛峑偵偄偨偼傟傊傫偺偱偭偟傖傠偐乧乧丠乿
丂偦傟傪墶偐傜擿偒崬傒丄壗婥偵僸僪僀偙偲傪尵偆儎儓僀丅偳偆偱傕偄偄偑丄僆僲儅僩儁傒偨偄側柤慜偩側偲巚偆丅
丂儌乕僞乕僗億乕僣偲偟偰偼傑偩傑偩楌巎偺愺偄儘儃俿俼倄偩偐丄儊乕僇乕偑幚愌偺偁傞僾儗僀儎乕傗僠乕儉偵婡懱傗僷乕僣傪採嫙偟偨傝偡傞偙偲傕偁傞丅儊僇僯僢僋偑攈尛偝傟偰偄偰傕偍偐偟偔偼側偄丅
乽偗偳偁偺僠乕儉偭偰偝丄妋偐堦搙傕愴傢偢偵彑偪忋偑偭偰偒偨傫偩傛側乿
乽儅僕偐丠丂側傫偱傑偨偦傫側偙偲偵側偭偰傫偩丠丂僫僊乿
丂偮偄偝偭偒傑偱乽偁偺敀偄偺偐偭偗乕乿偲偐尵偭偰偄偨僒僉偩偭偨偑丄堦揮乽偊乣偭乿偲偄偭偨姶偠偱廰柺傪晜偐傋偰怳傝曉傞丅
丂対傪岎偊偢彑棙傪摼傞劅劅彑幰傪柤忔傞側偳丄愴摤庬偱偁傞僆乕僈偺斵彈偵偼棟夝偟偑偨偄偙偲偱偁偭偨丅
乽偊偭偲乧乧僇僫僞丄僷僗乿
乽側傫偱偙偭偪偵怳傫偹傫丅乧乧傑偁丄堦夞愴偼弨旛偑娫偵崌傢傊傫偐偭偨憡庤僠乕儉偑婞尃偟偰丄擇夞愴偼帋崌奐巒捈屻偵婡懱偑媫偵摦偐傫傛偆偵側偭偨憡庤偑幐奿偵側偭偰劅劅偱丄嶰夞愴傑偱棃偨偭偪傘偆傢偗傗乿
丂弿愴偱偼偙偆偄偭偨儅僔儞僩儔僽儖偵傛傞幐奿偑偨傑偵偁偭偨傝偡傞偺偩偑丄擇夞楢懕晄愴彑偲偄偆偺偼偝偡偑偵捒偟偄丅側偍丄帋崌奐巒捈屻偵婡懱偑摦偐側偐偭偨応崌偵尷傝丄嶰暘娫偺惂尷帪娫撪偵嵞巒摦偱偒傟偽僟儊乕僕儅乕僇乕侾億僀儞僩暘偺噣尭揰噥傪庴偗偰帋崌偵暅婣偱偒傞偺偩偑丄擇夞愴偱偐偺僠乕儉偲摉偨偭偨憡庤偼偦傟偑偱偒側偐偭偨傢偗偩丅
乽側傫偩丄梫偡傞偵塣偩偗偺儎僣偭偰傢偗偐乧乧側傜儂僲僇偨偪偺妝彑偩側侓乿
丂偦偆尵偭偰嫻偺慜偱対偲暯庤傪扏偒崌傢偣丄僯儎儕偲晄揋側徫傒傪晜偐傋傞僒僉丅
乽偣傗偗偳媡偵尵偆偨傜丄婡懱偵偄偭傌傫傕僟儊乕僕庴偗偰傊傫偭偪傘偆偙偲傗偐傜側丅桘抐偼嬛暔傗偱乿
丂偐偨傗儊乕僇乕嬣惢丄偙偪傜偼巊偊傞拞屆僷乕僣傪偐偒廤傔偰儗僗僩傾偟偨婡懱丅儂僲僇偺挌擩側惍旛偱丄慜擇愴偺僟儊乕僕偼壜擻側尷傝儕儁傾偝傟偰偄傞偲偼偄偊丄晄埨偑慡偔側偄偲偄偆傢偗偱偼側偄丅
丂傑偁丄偦偙傜偁偨傝偼峛夘傕儂僲僇傕廳乆彸抦偟偰偄傞偲巚偆偑丅
乽偦傟偵偟偰傕丄偦偺僕儞僶儔僕儞偲偐偄偆憡庤偺嫄恖婡尛偄乧乧偳偆傕婥偵側傞乿
乽捒偟偄傢偹丅儖儈僫偑偦傫側偙偲尵偆側傫偰乿
乽偍丠丂偝偰偼偁傫側丄偍傏偭偪傖傑偭傐偄偺偑僞僀僾側偺偐丠丂偍慜乿
乽擭偐傜擭拞敪忣偟偰偄傞婱條傜杺暔柡偲堦弿偵偡傞側偭乿
丂僫僊偵拑壔偝傟丄娫敮擖傟偢偵搟柭傝曉偡儖儈僫丅偦偟偰傑偨丄憡庤僠乕儉偺僾儗僀儎乕傊偲帇慄傪栠偡丅
丂帹偵僀儞僇儉傪晅偗僾儘億傪庤偵偟偨丄傁偭偲尒偼攚偺崅偄惔寜姶偺偁傞僀働儊儞丅墶偵棫偮弮敀偺儊僈僷儁僢僩偲憡傑偭偰丄傑傞偱偙偺応偺庡栶偺傛偆偵傕尒偊傞乧乧偑丄
丂劅劅僄價僴儔偲僒僀僋儘僾僗傪尒傞偁偺栚偮偒丄傑傞偱僾儔僀僪偩偗偑旍戝壔偟偨斀杺攈偺恄姱暫偺傛偆偩乧乧
丂岥拞偱偦偆偮傇傗偒丄彈巕崅惗償傽儖僉儕乕偼恎傪嫮挘傜偣偨丅
丂帋崌奐巒偺僐乕儖偑嬁偒丄僔僌僫儖偑愒偐傜惵偵愗傝懼傢傞丅
乽尒偊偨偧僢両丂栺懇偝傟偨彑棙傊偺僂傿僯儞僌儘乕僪両両乿
丂僠乕儉丒俬俶俥儕僶乕僒乕偺僾儗僀儎乕恄尨僕儞偼偦偆惡傪忋偘側偑傜丄垽婡乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺傪僟僢僔儏偝偣偨丅
丂堦夞愴丄擇夞愴偲傕晄愴彑偱丄偦傠偦傠偪傖傫偲愴偭偰彑偨偹偽奿岲偑偮偐側偄側偲巚偭偰偄偨偲偙傠偵丄懳愴憡庤偲偟偰弌偰偒偨偺偼拞屆偺僣僊僴僊婡懱乧乧斵偑撪怱偱僈僢僣億乕僘傪庢偭偨偺偼尵偆傑偱傕側偄丅
丂偦偆丄偙偪傜偑晧偗傞梫慺側偳堦愗側偄丅偙偺戝夛偵弌応偡傞偨傔偵丄恊偺僐僱偲嬥傪巊偭偰丄儊乕僇乕偐傜僾儘僩僞僀僾偺婡懱劅劅嵟怴媄弍傪偮偓崬傫偱嶌傜傟偨儚儞僆僼婡傪庢傝婑偣偨偺偩偐傜丅
丂僕儞偼偦偺婄偵彑棙傪妋怣偟偨徫傒傪晜偐傋丄庤庱傪擯偭偰俥俿僨傿僗僾儗僀忋偺傾僀僐儞傪慖戰丅弮敀偺婡懱偼慜偵偲傃崬傓傛偆偵塃榬傪孞傝弌偡乧乧偑丄憡庤偺婡懱偼敿恎傪偢傜偟偰偦傟傪偐傢偟丄僇僂儞僞乕偱嵍偺堦寕傪曻偭偰偒偨丅
乽偔乧乧両乿
丂婡懱偺岦偒傪嫮堷偵曄偊偰偦偺峌寕傪旔偗傛偆偲偟偨偑丄偑傜嬻偒偺塃尐偵僋儕僥傿僇儖僸僢僩傪傕傜偄丄偄偒側傝僟儊乕僕儅乕僇乕偺怓偑僀僄儘乕偐傜僆儗儞僕傊偲曄傢傞丅
丂僗儔僀僨傿儞僌婥枴偵媟傪塣偽偣丄摜傫挘傜偣傞傛偆偵婡懱傪棫偰捈偡偲丄
乽乧乧傗傞側僢両丂偝偡偑偼弨乆寛彑傑偱彑偪忋偑偭偰偒偨偩偗偺偙偲偼偁傞僢両乿
丂僾儘億偐傜怢傃偨働乕僽儖傪傂偲怳傝偟丄斵偼幣嫃偑偐偭偨岥挷偱懳愴憡庤偵岅傝偐偗偨丅
丂傓傠傫撪怱偱偼偦傫側偙偲栄傎偳傕巚偭偰偼偄側偄丅崱偺偼扨側傞傑偖傟丅傛偗偨偲偒偵怳傝夞偟偨庤偑丄偨傑偨傑忋庤偄嬶崌偵摉偨偭偨偩偗乧乧偁傫側宆棊偪偺儊僈僷儁僢僩偑丄偙偺乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺偺婡摦椡偵偮偄偰偙傟傞偼偢偑側偄偺偩劅劅
乽偩偑僶僩儖偼巒傑偭偨偽偐傝僢両丂彑晧偼偙傟偐傜乧乧乧乧暦偗傛両乿
丂僣僊僴僊婡懱偺僾儗僀儎乕劅劅峛夘偼僕儞偺乽岅傝乿傪僈儞柍帇偟偰僾儘億傪憖嶌丅乹僽儔僂儂儖儞乺偼攚拞偺働乕僽儖傪東偟偰慜偵摜傒崬傫偩丅偁傢偰偨傛偆偵孞傝弌偝傟偨戝怳傝側僷儞僠傪奜傊抏偒丄偑傜嬻偒偵側偭偨嫻尦偵塃偺対傪孞傝弌偡丅
乽乧乧両丂偝偣傞偐僢両乿
丂僾儘億偐傜擖椡偝傟偨摦嶌傪娫敮擖傟偢偵僉儍儞僙儖偝傟丄偄偒側傝偺惂摦偵斶柭偠傒偨壒傪忋偘傞旼偲懌庱偺娭愡晹乧乧忋敿恎傪擯偭偰僟儊乕僕儅乕僇乕傊偺捈寕傪恏偆偠偰旔偗丄乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺偼嬄偗斀傝塲偖傛偆側懱惃偵側傝側偑傜傕娫崌偄傪庢傝丄椉榬傪戝偒偔怳偭偰峔偊捈偡丅
乽偙偺婡摦椡偵偮偄偰偙傟傞偺偼僢丄摨偠僾儘僩僞僀僾劅劅暦偗偭偰偽両乿
乽乧乧乧乧乿
丂愴偭偰偄傞嵟拞偵傾僯儊偭傐偔僙儕僼傪寛傔偨偄傜偟偄偑丄偦傫側偙偲偵晅偒崌偆婥側傫偐偝傜偝傜側偄丅
丂峛夘偼偝傜偵帺婡傪墴偟崬傒丄堦杮僤僲偺儊僈僷儁僢僩偼憡庤偺嵍尐栚偑偗偰捛寕傪曻偭偨丅敿恎傪欜歭偵堷偄偨偨傔儅乕僇乕偺怓偙偦曄傢傜側偐偭偨偑丄弮敀偺儊僈僷儁僢僩偼曅懌棫偪偵側傝偐偗丄僶儔儞僗傪曵偟偰屻傠偵傛傠傔偔丅
丂僺僢劅劅両乽乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺僗僥乕僕傾僂僩丅僽儗僀僋両乿
丂偄偮偺娫偵偐僗僥乕僕偺抂傑偱捛偄媗傔傜傟偰偄偨丅柍棟栴棟廳怱傪堏偟偨塃懌偑応奜偵偼傒弌偟丄寈崘壒偲摨帪偵摜傒墇偊偨儔僀儞偑愒偔岝傞丅
丂擇懱偺儊僈僷儁僢僩偼偦偺摦偒傪巭傔丄僾儗僀儎乕偲偲傕偵嵞傃懸婡慄傊偲栠偭偨丅
乽儁僫儖僥傿偼捝偄偑丄巇愗傝捈偣偨偺偼傓偟傠岲搒崌丅偄偔偧両丂杮摉偺愴偄偼偙傟偐傜偩偭両乿
乽乧乧乧乧乿
乽乧乧側偁僇僫僞丄傾僀僣側傫偱偄偪偄偪壗偐尵偄側偑傜丄帺暘偺儘儃僢僩偵億乕僘庢傜偣偰傫偩丠乿
丂媟晹傪戝偒偔奐偒丄巜傪僺儞偲怢偽偟偨椉榬傪戝偒偔夞偟偰崢傪擯傞劅劅
丂儌乕僞乕壒傪柭傜偟偰戝偘偝側峔偊傪偲傞乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺傪嬥栐偺奜偐傜層嶶廘偘偵尒傗傝丄僫僊偼椬偵栤偄偐偗傞丅
乽僸儘僀僢僋儉乕僽偱亀帺暘偑庡栶偩亁偭偰傾僺偭偰傞傫傗側劅劅乿
乽偆傢偦傟晧偗偨傜傔偭偪傖僀僞偄傗偮偠傖傫乧乧乿
乽傑偁偣傗偗偳乧乧枹偩偵偁傫側偙偲偡傫偺偍傞傫偐乿
丂僟儊乕僕僇僂儞僩侾乕侽偱帋崌嵞奐丅僔僌僫儖偑曄傢傞偲摨帪偵丄惵偄婡懱偲敀偄婡懱偼恀偭惓柺偐傜夛揋偡傞丅
丂対傪孞傝弌偡偙偲悢崌丅屳偄偺峌寕傪椊偓崌偆偑乧乧
乽偽偭乧乧僶僇側僢両丠丂墴偝傟偰偄傞僢丠乿
丂愭傎偳偐傜偺柍棟側婡摦偱媟晹偺摜傫挘傝偑岠偐側偔側傝偩偟偨弮敀偺儊僈僷儁僢僩偑丄彊乆偵屻戅偟巒傔傞丅
乽傑偩偩乧乧傑偩偄偗傞僢丅僾儘僩僞僀僾偼埳払偠傖側偄僢両乿
丂側偍傕偳偙偐偱暦偄偨傛偆側僙儕僼傪揻偒側偑傜丄僕儞偼僾儘億偺廃埻偵晜偐傇俥俿僨傿僗僾儗僀偐傜僐儅儞僪傪慺憗偔擖椡丄僄儞僞乕僉乕偱偁傞僩儕僈乕傪抏偄偨丅
丂偡偱偵儅乕僇乕偺怓偑曄傢偭偰偄傞塃尐傪惓柺偵岦偗丄乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺偼幬傔慜傊堦曕摜傒弌偡乧乧
亀僐乕僗働偔傫偭両丂嵍偭両亁
乽乧乧両両乿
丂僀儞僇儉偐傜暦偙偊偰偒偨儂僲僇偺惡偵丄峛夘偼偡偐偝偢斀墳偟偨丅
丂僼僃僀儞僩傪偐偗偰媡懁傊偲墶偭挼傃偟偨弮敀偺婡懱偵崌傢偣偰乹僽儔僂儂儖儞乺傕嵍傊偲摜傒崬傒丄偦偺摦偒偵楢摦偝偣偨崢偺擯傝偐傜撱偖傛偆偵曻偭偨塃榬偱憡庤偺庱傪姞傞丅
丂壓榬晹偺僇僂儕儞僌偑妱傟偰丄惵偄攋曅偑廃埻偵旘傃嶶傞丅
丂墶堏摦偺儀僋僩儖偵儔儕傾僢僩偺堦寕傪崌傢偝傟偰丄愒偄椉懌偑抧柺偐傜棧傟傞劅劅
丂乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺偼丄偦偺傑傑壒傪棫偰偰墶搢偟偵側偭偨丅
乽乧乧偳偆偩偭両乿
丂僐儞僩儘乕儖働乕僽儖傪偟側傜偣丄峛夘偑嫨傫偩丅
丂弮敀偺婡懱偼僗僥乕僕偵扏偒偮偗傜傟偨傑傑丄僾儗僀儎乕偺憖嶌偵傕斀墳偣偢丄僺僋儕偲傕摦偐側偄丅
乽乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺帋崌懕峴晄擻丅劅劅戞巐帋崌Winner両丂僠乕儉丒儌僲傾僀僈乕儖僘両両乿
丂帋崌廔椆偺儂乕儞偲崑夣側俲俷彑偪偵暒偔娊惡偺拞丄乹僽儔僂儂儖儞乺偼徴寕偱摦偐側偔側偭偨塃榬偺戙傢傝偵丄嵍榬傪崅乆偲宖偘偨丅
丂惍旛偟偨僷乕僩僫乕傪怣棅偟丄婡懱傪尷奅傑偱巊偄愗偭偨僾儗僀儎乕偲丄僇僞儘僌僗儁僢僋偩偗偵棅偭偨幰偲偺嵎偑擛幚偵尰傟偨帋崌偩偭偨丅
乽乧乧僐乕僗働偔傫両乿乽儂僲僇偪傖傫両乿
丂嬱偗婑偭偰偒偨僒僀僋儘僾僗柡偲栚傪崌傢偣丄僴僀僞僢僠偟偰彑棙傪婌傃崌偆丅傆偨傝偑娤媞惾偺曽傪尒傞偲丄僼僃儞僗偺岦偙偆偐傜僫僊傗斵曽偨偪偑庤傪怳偭偰偄傞丅
丂偩偑丄儖儈僫偩偗偼堦恖丄尟偟偄昞忣偱僗僥乕僕傪尒偮傔偰偄偨丅偦偺帇慄偺愭偱丄墶搢偟偵側偭偨帺婡偺偦偽偵棫偮攕幰劅劅僕儞偑偆偮傓偄偨傑傑丄堦弖僯儎僢偲岥偺抂傪榗傔傞丅
丂偦偟偰斵偼丄偍傕傓傠偵婄傪慜偵岦偗傞偲丄
乽墭偄乧乧墭偄偧両丂偦偆傑偱偟偰彑偪偨偄偺偐偍慜僢両乿
丂傑傢傝偵暦偙偊傞傛偆儚僓偲戝惡傪忋偘丄峛夘偺婄傪巜嵎偟偨丅
亙仠亜
乽乧乧乧乧乿
乽乧乧乧乧乿
乽側丄側傫偩乧乧丠乿
丂儗僊儏儗乕僔儑儞傕堘斀偟偰偄側偄偟丄斀懃傕偟偰偄側偄丅儅乕僔儍儖偐傜偺寈崘傕栣偭偰側偄丅
丂鎎傞峛夘丄偞傢偮偔娤媞惾丅
丂傑傢傝偺帇慄偑帺暘偵廤傑偭偰偄傞偺傪妋擣偟丄僕儞偼偝傜偵惡傪挘傝忋偘偨丅
乽偦傕偦傕偦傫側僗僋儔僢僾偺婑偣廤傔偱偱偒偨儊僈僷儁僢僩偑丄崅惈擻僾儘僩僞僀僾婡偲屳妏偵愴偄彑棙偡傞側傫偰枩偵傂偲偮傕偁傝偊側偄両丂偮傑傝乧乧僢両乿
丂偦偟偰丄峛夘偺攚拞偵塀傟側偑傜嫰偊偨傛偆側帇慄偱偙偪傜傪偆偐偑偆僸僩僣栚偺恖奜彮彈傪嵘傔偮偗傞偲劅劅
乽偦偙偵偄傞壔偗暔彈偵杺朄傪巊傢偣偰僢丄僘儖傪偟偨偲偄偆偙偲偩僢両乿
乽側偭丠乿
丂埇偭偨塃庤傪嫻偵摉偰丄嵍庤傪墶偵戝偒偔奐偒丄噣僊儍儔儕乕偵岦偐偭偰噥壈柺傕側偔偦偆庡挘偟偨丅
乽帺暘偺婡懱傪杺朄偱嫮壔偟偨偐僢丄偁傞偄偼偙偭偪偺婡懱傪杺朄偱庛懱壔偝偣偨偐僢両丂偙偄偮傜偼堦夞愴偐傜偦偆傗偭偰晄惓傪偟懕偗丄彑偪忋偑偭偰偒偨傫偩僢両乿
乽傆偞偗傞側偭両丂扤偑偦傫側偙偲偡傞偐両乿
丂帠幚偱偁傞偐偺傛偆偵寛傔偮偗傞偦偺岥挷偵丄偄偮傕偼梋寁側潌傔帠傪寵偆峛夘傕偝偡偑偵惡傪峳偘偰搟柭傝曉偡丅
乽拞悽暥柧儗儀儖偺僼傽儞僞僕乕悽奅偐傜棃偨壔偗暔彈偵丄儊僈僷儁僢僩偺惍旛側偳偱偒傞傢偗偑側偄僢両丂偩偐傜杺朄偲偄偆僠乕僩偵棅偭偨僢両丂偪傚偭偲峫偊傟偽扤偱傕暘偐傞偙偲偩僢両乿
乽儂僲僇偪傖傫偨偪偺偙偲抦傝傕偟側偄偱丄彑庤側偙偲尵偆側偭両乿
丂傇偭偪傖偗丄尵偄偑偐傝埲奜偺壗暔偱傕側偄丅
丂僼傽儞僞僕乕悽奅偼拞悽儓乕儘僢僷晽劅劅側偳偲偄偆屌掕娤擮偟偐側偄僕儞偵丄杺暔柡傗斵彈偨偪偺杺朄偵偮偄偰偺棟夝側偳偁傝偼偟側偄丅偲偄偆偐丄杺朄杺朄偲尵偭偰傞妱偵丄杮婥偱偦傟偑巊傢傟偨偲峫偊偰偄傞偐偳偆偐傕媈傢偟偄丅
丂梫偼敾掕傪暍偡偨傔偵丄峛夘偨偪偑晄惓傪偼偨傜偄偨偲娤媞偨偪傗儅乕僔儍儖偵巚傢偣傟偽偄偄偺偩偐傜丅
乽偍偄僆儅僄偭丄尵偆偵偙偲寚偄偰側傫偰偙偲偸偐偟傗偑傞両乿
乽壗僀僠儍儌儞偮偗偰傫偹傫偭両丂偍慜偦傟儗僀僴儔乮儗僀僔儍儖僴儔僗儊儞僩亖恖庬揑曃尒偵婎偯偔寵偑傜偣乯傗偧偭両乿
乽偒偭偪傝晧偗偨偔偣偵傒偭偲傕偹偊偧偭両丂愴偄僫儊偰傫偺偐僥儊僄偭両乿
丂僼僃儞僗偺奜懁偐傜丄僫僊偨偪傕搟傝偺惡傪忋偘傞丅
丂偩偑丄懠偺娤媞偨偪偼椬摨巑偱婄傪尒崌傢偣偨傝丄僶僩儖僗僥乕僕偵崲榝偺帇慄傪搳偘偐偗偨傝丄偁偐傜偝傑偵晭曁偺昞忣傪晜偐傋偨傝劅劅
丂僈僢劅劅両乽乧乧両丂僐乕僗働偔傫偭両両乿
丂偄偒側傝儂僲僇偵岦偐偭偰搳偘偮偗傜傟偨愇偑丄斵彈傪偐偽偭偨峛夘偺偙傔偐傒偵捈寕偟偨丅
乽偩丄戝忎晇乧乧乿
乽乧乧乧乧乿
丂妟傪墴偝偊偰婄傪偟偐傔側偑傜傕丄斵偼怱攝偐偗傑偄偲徫傒傪晜偐傋傛偆偲偡傞丅
丂儂僲僇偼桬婥傪怳傝峣偭偰丄愇偑旘傫偱偒偨曽傪嵘傒偮偗偨丅
乽傑乧乧杺朄側傫偰丄巊偭偰丄側偄乧乧乧乧偪傖傫偲丄惍旛乧乧偟偨乧乧乿
丂偨偳偨偳偟偔丄偲傕偡傟偽岥偛傕傝偦偆偵側傝側偑傜傕丄娤媞惾偵岦偐偭偰斀榑偡傞丅
丂偩偑埆堄偼梕堈偵揱攄偟丄憹暆偟偰偄偔乧乧
丂岥偱偼側傫偲偱傕尵偊傞傛側偀劅劅
丂杺朄巊偭偰側偄偙偲徹柧偟偰傒偣傠傛劅劅
丂偦偺懠戝惃偵噣婄噥偼側偄丅愒怣崋丄傒傫側偱搉傟偽晐偔側偄丅
丂堸傒偝偟偺儁僢僩儃僩儖傗價儞丄嬻偒娛丄僑儈側偳偑丄傆偨傝偵師乆偲搳偘偮偗傜傟傞丅
丂峛夘偼傑傞偱僸僩偺廥偄柺傪尒偣傑偄偲偡傞偐偺傛偆偵丄儂僲僇偺摢傪書偒婑偣丄弬偵側偭偨丅
乽儂僲僇偭両乿乽峛夘偉偭両乿
丂僫僊偲斵曽偺嫨傃惡偑丄娤媞惾偐傜偺攍惡偵偐偒徚偝傟傞丅
丂墭偄側偝偡偑壔偗暔彈墭偄劅劅
丂恖娫條偺戝夛偵弌偰偔傫偠傖偹乕傛偭劅劅
丂偲偭偲偲尦偄偨悽奅偵婣傝傗偑傟偭劅劅
丂偐乕偊傟偭丄偐乕偊傟偭劅劅
丂偐乕偊傟偭丄偐乕偊傟偭劅劅
丂偐乕偊傟偭丄偐乕偊傟偭劅劅
丂偐乕偊傟偭丄偐乕偊傟偭劅劅
丂乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧
丂偩偑丄帺暘偨偪偑崱偙偺応偐傜摝偘偨傜丄憡庤偺尵偭偨偙偲傪擣傔偨偙偲偵側傞丅
丂偦傟偩偗偼愨懳偱偒側偄丅僒僀僋儘僾僗柡傪偐偒書偔榬偵丄峛夘偼椡傪崬傔偨丅
乽偔偭偦偋僥儊僄傜偦偙摦偔側偭両丂慡堳僽僢偲偽偟偰傗傞偭両両乿
乽偩傔傛僒僉偭両丂庤傪弌偟偨傜偙偭偪偑埆幰偵偝傟傞両乿
乽僒僉偼傫偙傜偊偰乧乧偙傜偊偰偍偔傟傗偡偭両乿
丂僼僃儞僗傪堷偒偪偓偭偰斀懳懁傊墸傝崬傕偆偲偡傞僆乕僈柡傪丄昁巰偵巭傔傞暥梩偲儎儓僀丅杺暔柡偑恖娫偵婋奞傪壛偊偨傜嵟屻丄棟桼側偳娭學側偟偵丄僕儍乕僫儕僗僩傪柤忔傞儗億壆傗抦幆恖偲徧偡傞惡偲婄偩偗偑僨僇偄楢拞偑婐乆偲偟偰斵彈偨偪偺攔愃偵摦偔偩傠偆丅
丂僕儞偼憶偓懕偗傞僊儍儔儕乕偵攚傪岦偗丄僯儎儕乧乧偲岥偺抂傪榗傔傞丅
丂偦偺帪丄偁偨傝偵敀偄塇崻偑晳偄嶶偭偨乧乧
乽乧乧両丠乿
丂師偺弖娫丄娤媞惾偵偄偨幰偨偪偼僴僢偲変偵曉傝丄搳偘偮偗傛偆偲偟偰偄偨傕偺傪庤偐傜庢傝棊偲偟偨丅
丂偦偟偰殥偟棫偰傞傛偆偵婣傟僐乕儖傪孞傝曉偟偰偄偨抝偨偪偼丄椻悈傪梺傃偣傜傟偨傛偆側姶妎偲偲傕偵丄帺暘偨偪偺曽偑廃埻偐傜敀偄栚偱尒傜傟偰偄傞偙偲偵婥偯偔丅
乽偁乧乧乿
乽偄丄偄傗偦偺乧乧偭乿乽偙丄偙傟偼劅劅乿
丂斵傜偼杍傪堷偒偮傜偣側偑傜丄岆杺壔偡傛偆偵敿徫偄傪晜偐傋傞乧乧偑丄帇慄偵懴偊偒傟側偔側偭偨堦恖偑墎傪愗偭偨傛偆偵惡傪忋偘丄慡堳偑偦傟偵屇墳偟偰岥乆偵憶偓弌偟偨丅
乽乧乧偪丄堘偭丄偍劅劅壌偼偍慜傜偵丄偮丄偮傜傟偨偩偗偩偐傜側偭両乿
乽側偭壗尵偭偰傗偑傞偭両丂偍慜偑嵟弶偵愇搳偘偮偗偨傫偩傠偑偭両乿
乽偍慜偙偦偭両丂媰偄偰摝偘弌偡傑偱偰偭偰乕揑偵傗傠偆偤偭偰僎儔僎儔徫偭偰偨傠偑偭両乿
乽傏丄儃僋偼偭丄傗丄巭傔偨曽偑偄偄偭偰偄偄偄尵偭偨傫偩丄側偭乿
乽塕偮偗偭両丂堦斣婐偟偦乕偵婣傟婣傟偭偰姭偄偰偨偔偣偵偭両乿
丂偦偟偰丄屳偄偵愑擟傪側偡傝偮偗崌偆丅偙傟傕傑偨丄尒偨偔乮尒偣偨偔乯側偄僸僩偺廥偝丅
丂偩偑峛夘偼榬偺拞偱儂僲僇偵恎偠傠偓偝傟丄偁傢偰偰恎懱傪棧偟偨丅
乽偛劅劅偛傔傫丄儂僲僇偪傖傫乿
乽偆偆傫丅乧乧僐乕僗働偔傫偙偦戝忎晇丠乿
丂儂僲僇偼庱傪怳傞偲丄峛夘偺愒偔庮傟偨妟傊偲庤傪怢偽偟偨丅
丂偦偺巜偑乧乧偄傗偦偺恎懱偑傑偩偐偡偐偵恔偊偰偄傞偙偲偵婥偯偒丄峛夘偼寛堄傪屌傔偰斵彈偺庤傪庢偭偨丅
乽乧乧僐乕僗働丄偔傫丠乿
乽寛彑傑偱峴偭偨傜偪傖傫偲尵偆偮傕傝偩偭偨偗偳乧乧崱尵偆偹乿
丂偦偆慜抲偒偟偰丄屗榝偆儂僲僇偺僸僩僣栚偵帇慄傪崌傢偣傞偲丄
乽杔偼孨偑岲偒偩丅乧乧儂僲僇偪傖傫丄杔偺楒恖偵側偭偰乿
乽偊乧乧丠乿
丂師偺弖娫丄儂僲僇偺廃埻偐傜壒偑徚偊偨丅
丂恊桭傗拠娫偨偪偺嬃偔惡傕丄懠偺娤媞偨偪偺偞傢傔偒傕丄嬱偗偮偗偨儅乕僔儍儖偵擄暼傪偮偗傞懳愴憡庤偺暔尵偄傕丄寈旛僗僞僢僼偵媗傔婑傜傟偰側偍傕尵偄摝傟傛偆偲偡傞抝偨偪偺曎夝傕丄暦偙偊偰偄傞偗偳暦偙偊側偄丅
乽杮婥乧乧側偺丠乿
乽傕偪傠傫乿
乽偱傕巹丄杺暔柡乧乧僒僀僋儘僾僗丄偩傛丅栚偑堦偮偩偟丄僣僲傕偁傞偟丄敡傕惵偄偟劅劅乿
乽偦傟偑儂僲僇偪傖傫側傫偩偐傜丄偦傟偱偄偄傫偩乿
乽乧乧乧乧乿
丂峛夘偼斵彈偺戝偒側摰傪恀偭捈偖尒偮傔偰丄椡嫮偔偆側偢偔丅
丂偦偺帇慄偵婥埑偝傟偰儂僲僇偑栚傪堩傜偡偲丄杊岇僼僃儞僗偺岦偙偆偵僫僊偨偪偺巔偑尒偊偨丅
丂儂僲僇丄慺捈偵側傟偭劅劅
丂恊桭偺惡偑丄傑傞偱攚拞傪墴偟偰偔傟傞偐偺傛偆偵丄摢偺拞偱偙偩傑偡傞丅
丂儂僲僇偼岦偒捈傝丄堦曕慜偵恑傒弌傞偲丄
乽巹傕乧乧巹傕僐乕僗働偔傫偺偙偲偑丄乧乧戝岲偒偭両乿
丂椉榬傪峀偘偰偲傃偮偔傛偆偵書偒偮偒丄偦偺庤傪峛夘偺庱尦偵夞偟偰恎懱傪偔偭偮偗偨丅
丂傓偵傘傫劅劅偲丄嫻偺朿傜傒偑墴偟晅偗傜傟傞丅
丂偦偟偰嵍榬傪撍偒忋偘偨傑傑棫偮惵偄恖宆廳婡傪僶僢僋偵丄傆偨傝偼怬傪廳偹偨劅劅
乽乧乧乧乧乿乽乧乧乧乧乿乽乧乧乧乧乿乽乧乧乧乧乧乧乧乧乿
乽偽偭丄壔偗暔彈偲僉僗偩偲僢両丠丂乧乧傒傒傒尒偨偐傾儗傪僢両丂恖慜偱偁傫側恀帡傪傪偡傞傛偆側搝傜偩僢両両丂偁偄偮傜偑杺朄偱僘儖偟偨偺偼柧敀劅劅乿
乽偄偄偐傜偝偭偝偲揚廂偟側偝偄丅師偺帋崌偑巒傔傜傟側偄乿乽乧乧偊丠乿
丂懥傪旘偽偟偰巟棧柵楐側僐僩傪傑偔偟棫偰傞僕儞偵丄儅乕僔儍儖偺抝惈偼椻偨偔尵偄曻偭偨丅
丂傓傠傫丄敾掕峈媍側偳堦愗偲傝崌傢側偄丅偼側偐傜偲傝崌偆偮傕傝傕側偄丅
乽偩乧乧偩偐傜偝偭偒偐傜偢偭偲尵偭偰傞偩傠偑僢両丂偁偺僣僊僴僊偑僾儘僩僞僀僾婡偺乹俧傾僋僙儔儗乕僞乺偵彑偮側偳丄枩偵傂偲偮傕偁傝偊側偄偲劅劅乿
乽偁丄偁偺丄偡偄傑偣傫乧乧乿
丂側偍傕儅乕僔儍儖偵尵偄曞傠偆偲偡傞斵偺屻傠偐傜丄崱傑偱偢偭偲栙偭偰尒偰偄偨丄偲偄偆偐僪儞堷偒偟偰偄偨傾儔僒乕抝惈劅劅僠乕儉丒俬俶俥儕僶乕僒乕偺僙僐儞僪偺傂偲傝偑丄偍偢偍偢偲岥傪嫴傫偱偒偨丅
乽偠乧乧幚偼偦偺婡懱丄帋嶌儌僨儖偺傑傑偩偲儗僊儏儗乕僔儑儞捠傜側偄偐傜丄嬱摦宯傪巗斕偺傕偺偲懼偊偰傞傫偱偡偗偳乿
乽側傫乧乧偩偲僢両丠乿
丂梫偡傞偵丄僈儚偩偗偩偭偨丅
乽閤偟偨傢偗偠傖側偄傫偱偡偗偳偹乣丅晛捠丄帋嶌婡偺栤戣揰傪夵椙偟偨巗斕儌僨儖偺曽偑丄憤崌惈擻偼岦忋偟偰傑偡偟乿
乽偆丄偆偆偆塕偩僢両丂傉丄僾儘僩僞僀僾偼検嶻宆傛傝傕丄嫮偄乧乧偼偢乧乧乧乧乿
丂傕偆堦恖偵偦偆尵傢傟丄崨偗偨婄偱僗僥乕僕偵傊偨傝崬傓僕儞丅僙僐儞僪傆偨傝偼婄傪尒崌傢偣丄偦偦偔偝偲揚廂弨旛傪巒傔傞乧乧弌岦埖偄偲偼偄偊丄偙傟埲忋晅偒廬偆媊棟偼側偄丅
丂偦傫側懳愴憡庤傪怟栚偵丄峛夘偼儂僲僇偲廳偹偰偄偨怬傪偦偭偲棧偟偨丅
乽偁丄偁偺乧乧儂僲僇偪傖劅劅傓偖偅両丠乿
乽傫乧乧偪傘偭丄偪傘傁劅劅偵傘傓偭丄傓偪傘乧乧傟傠偭丄傫偭丄乧乧傫偪傘丄乧乧乧乧乿
丂奆傑偱尵傢偝偢丄儂僲僇偼椉庤偱峛夘偺摢傪偮偐傓偲丄擇搙栚偺僉僗偱偦偺岥傪嵡偓丄墴偟擖傟偨愩偱岥撪傪骧鏦偡傞丅
乽傫丄傓偖偭丄乧乧傉偼偭両丂傎丄儂僲僇丄偪傖傫劅劅丠乿
乽偊傊傊偭丅傕偭偲乧乧傕偭偲尒偣偮偗傛偆丅僐乕僗働偔傫偲巹偺儔僽儔僽側偲丒偙丒傠侓乿
丂廜恖娐帇偺拞偱戝抇側偙偲傗偭偰偟傑偭偨斀摦側偺偐丄杺暔柡偲偟偰偺杮擻偑昞偵弌偰偒偨偺偐丄儂僲僇偼峛夘偺懥塼偑偮偄偨帺暘偺怬傪側偧傞傛偆偵鋜傔傞偲丄懅傪宲偓側偑傜帺暘偺柤慜傪屇傇垽偟偄噣僆僗噥偵岥妏傪偮傝忋偘偰旝徫傫偩丅
丂墣偭傐偔弫傫偩偦偺扨娽偵尒偮傔傜傟偰丄妎屽偟偰偄偨偲偼偄偊丄偁偁傕偆摝偘傜傟側偄側乧乧偲巚偄側偑傜傕徫傒傪曉偡峛夘丅崱夞偺審偱杺暔柡偑偙偺悽奅偺恖娫偵傑偩傑偩庴偗擖傟傜傟偰偄側偄偙偲傪捝姶偟偨偑丄偦傟偱傕屻夨傗晄埨偼慡偔側偄丅
乽偒偟偟偭丄傗偭偨偹儂僲僇偭侓乿
乽偍傔偱偲偆偳偡偊丄儂僲僇偼傫乿
乽慉傑偟偄偤偭乧乧偙偺偙偺偭両乿
丂僷僪僢僋傪捠偭偰嬱偗婑偭偰偒偨僫僊偨偪杺暔柡偺拠娫偵潌傒偔偪傖偵偝傟傞儂僲僇傪尒偰丄峛夘偼巚偆丅偙傫側傒傫側偑偄傞傫偩偐傜丄壗偑偁偭偰傕偒偭偲戝忎晇乧乧偲丅
丂偦偟偰恊桭偨偪偺僴僌偐傜夝曻偝傟偨僒僀僋儘僾僗柡偑丄傂偲偮偟偐側偄戝偒側摰偱恀偭捈偖尒偮傔偰偔傞丅
丂椬偵棃偨斵曽偵攚拞傪扏偐傟丄峛夘偼丄崱搙偼帺暘偐傜斵彈傪書偒偟傔偨丅
乽偁乕丄偄偮傑偱傕僀僠儍偮偄偰側偄偱丄孨偨偪傕偝偭偝偲揚廂偟偰偔傟側偄偐乧乧乿
乽乧乧傂偀偭両丠乿
丂墶偐傜奝暐偄偲偲傕偵暦偙偊偰偒偨儅乕僔儍儖偺惡偵丄儂僲僇偼婄傪恀偭愒偵偟偰丄偁傢偰偰峛夘偺攚拞偵塀傟傞丅
乽乽乧乧乧乧乿乿
乽戝惃偺帇慄偼崕暈偱偒偨傒偨偄傗偗偳丄恖尒抦傝偼傑偩捈傜傊傫偺傗側乧乧乿
丂崱偵側偭偰巚偄弌偟偨傛偆偵徠傟傞儂僲僇偲峛夘丅偦傫側傆偨傝偵斵曽偼偳偙偐慉傑偟偦偆側昞忣偱丄娽嬀偺墱偺栚傪嵶傔偨丅
丂to be continued...
劅 appendix 劅
乽戝忎晇側偺丠丂杺朄傪恖偵岦偗偰巊偭偪傖偄偗側偄傫偠傖乧乧乿
乽忬嫷傪尒掕傔傞偨傔旘傃忋偑偭偨嵺偵丄偨傑偨傑偄偮傕傛傝懡偔塇崻偑嶶偭偰偟傑偭偨偩偗偩丅偦傟偵巹偑巊偆偺偼杺朄偱偼側偔恄椡丅栤戣側偄乿
丂怱攝偡傞僋儔僗儊僀僩偵偦偆尵偄曉偡偲丄嬻偐傜晳偄崀傝偨儖儈僫偼攚拞偺梼傪柖嶶偝偣偨丅岝偺塇崻偵帺暘偺椡傪偺偣偰旘傃嶶傜偣丄帠懺傪捑惷壔偝偣偨偙偲偵婥偯偄偰偄傞偺偼斵彈劅劅暥梩偩偗偺傛偆偩丅
乽偱傕乧乧偁傝偑偲偆丄儖儈僫乿
乽姩堘偄偡傞側丅杺暔柡偺偁偄偮傜傪彆偗偨傢偗偠傖側偄乧乧傑傢傝偺恖娫偵婋奞偑媦偽側偄傛偆偵偡傞偵偼丄偁偁偡傞偺偑堦斣庤偭庢傝憗偐偭偨偩偗偩偐傜側乿
丂偦偆晅偗壛偊丄儖儈僫偼僶僩儖僗僥乕僕偵栚傪岦偗傞丅乽乧乧傓偟傠僄價僴儔偑僒僀僋儘僾僗偵懧偪偰偟傑偭偨偙偲偺曽偑丄巹偵偲偭偰偼桼乆偟偒偙偲偩乿
乽乧乧乧乧乿
丂廳乆偟偄岥挷偱榬傪慻傓償傽儖僉儕乕偵丄暥梩偼曫傟偨傛偆側棴傔懅傪揻偄偨丅
乽傑偝偐偲偼巚偆偗偳丄儂僲僇偲奀榁尨偵彫屍傒偨偄側恀帡偟側偄偱傛乿
乽偩偭乧乧扤偑偡傞偐偭丅偦傫側媥傒偺偨傃偵幚壠偵栠偭偰偒偰庤揱偄傕偟側偄偔偣偵弌偝傟偨椏棟偵働僠偮偗偨傝晹壆偺嬿偺儂僐儕偵寵枴尵偭偨傝帺暘偺巕偳傕偺柺搢墴偟晅偗偰梀傃偵峴偭偨傝慜偲摨偠嬸抯傗帺枬榖傪墑乆暦偐偣偨傝偡傞傛偆側偙偲偭両乿
乽乧乧側傫偱偦傫側偵嬶懱揑側偺傛乿
丂婄傪愒傜傔偦偭傐傪岦偔儖儈僫偩偭偨偑丄偦偺摰偼偪傜偪傜偲丄僗僥乕僕偱弨寛彑恑弌傪婌傇僫僊傗儂僲僇偨偪傪尒偰偄傞傛偆偩偭偨丅
乽儂儞僩丄慺捈偠傖側偄傫偩偐傜乧乧乿
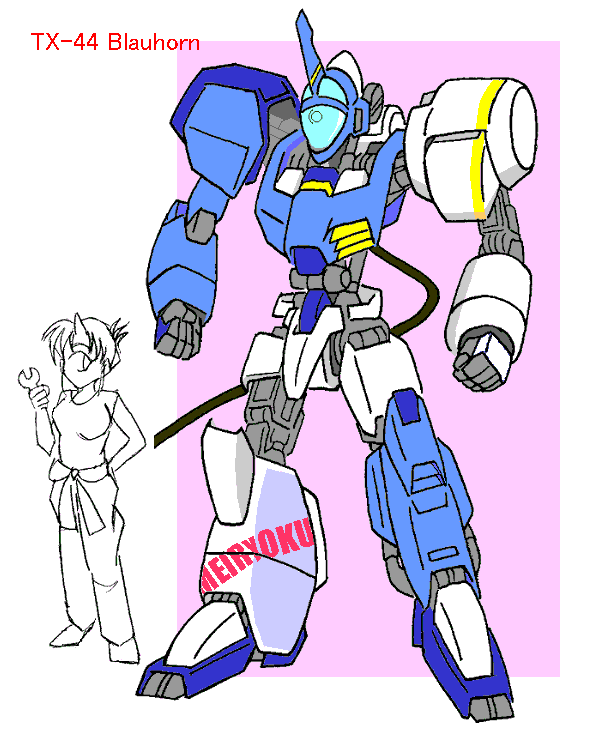
丂傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽丄傢傫偩偽偩偽偩偽偩偭丄僴僢両
丂傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽丄傢傫偩偽偩偽偩偽偩偭丄僴僢両
乽僐儅儞僢丄僪乕僢両両丂抧媴杊塹戉俶俿俼偱偁傞偭両乿
乽乽乽僐儅儞僢丄僪乕僢丄乧乧僥傿僢両両乿乿乿
乽側偭乧乧側傫側傫偩偍慜傜偭両丠乿
丂堄幆傪庢傝栠偟偨斵傜劅劅偁偺偲偒儂僲僇偵愇傪搳偘偮偗偨抝偨偪偼丄栚偺慜偵墶堦楍偱暲傫偱朸摿愴戉晽億乕僘傪僉儊傞楢拞偵丄嵗傝崬傫偩傑傑屻戅傝側偑傜搟柭傝曉偟偨丅
丂暻偵戝彫偝傑偞傑側儌僯僞乕偑愝抲偝傟偨丄憢偺側偄晹壆丅偦偙偵偄傞慡堳丄僈僞僀偺偄偄恎懱偵僌儗乕抧偵愒偲惵偺儔僀儞偑擖偭偨丄僂侟僩儔杊塹戉傒偨偄側傁偭偮傫傁偭偮傫偺儗僓乕僗乕僣傪拝偰丄帹摉偰偺偲偙傠偵揹忺偲傾儞僥僫偺偮偄偨僷僀儘僢僩梡僿儖儊僢僩傪彫榚偵書偊偰偄傞丅崢偵傇傜壓偘偰偄傞偺偼僾儘僢僾僈儞乧乧僆儌僠儍偩傠偆丄偨傇傫丅
乽僐儅儞僢丄僪乕僢両両 丂変乆偼孨偺傛偆側恖娫傪懸偭偰偄偨偭両丂搝傜偲愴偆巊柦偵栚妎傔偨愴巑傪偭両両乿
乽乽乽僐儅儞僢丄僪乕僢両両 乿乿乿
乽偩偐傜偄偭偨偄側傫側傫偩偭両丠乿
乽偰偄偆偐側傫偱偙傫側偲偙傠偵乧乧偘偭両乿
乽側乧乧側傫偱偙傫側偺拝偣傜傟偰傫偩側偭両丠乿
丂偼偭偲婥偯偔偲丄楢拞偲摨偠奿岲劅劅杊塹戉晽儗僓乕僗乕僣巔偵偝傟偰偄偨丅
丂偁傫側恀帡傪偟偨偣偄偱丄偳偆傗傜偙偄偮傜偵噣偍拠娫噥擣掕偝傟偰偟傑偭偨傛偆偩丅
丂杺暔柡傪乽恖椶偺揋乿乽暯榓傪嫼偐偡埆乿偲悂挳偟揋帇偡傞偙偲偱丄僸乕儘乕偵側偭偨婥偱偄傞偍傔偱偨偄楢拞偵丅
丂偟偐偟崱偝傜屻夨偟偰傕丄傕偆抶偄丅
丂傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽丄傢傫偩偽偩偽偩偽偩偭丄僴僢両
丂傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽傢傫偩偽丄傢傫偩偽偩偽偩偽偩偭丄僴僢両
乽偝偁偭両丂変傜抧媴杊塹戉俶俿俼戉堳偲偟偰僢丄偲傕偵抧媴怤棯傪偨偔傜傓埆偺杺暔偨偪偲愴偆偺偩偭両両乿
乽乽乽僐儅儞僢丄僪乕僢両両乿乿乿
乽僐儅儞僢両乿乽僐儅儞僢両乿乽僐儅儞僢両乿乽僐儅儞僢両乿
乽僐儅儞僢両乿乽僐儅儞僢両乿乽僐儅儞僢両乿乽僐儅儞僢両乿
乽乽乽僐儅儞僢丄僪乕僢丄乧乧僥傿僢両両乿乿乿
乽偆傢偁偁傛偭婑傞側婄嬤偯偗傞側旲懅悂偒偐偗傞側偁偁偁偭両乿乽傂偭丄恖偺榖傪劅劅乿
丂傾僢劅劅劅劅劅劅劅劅両両
丂堦廡娫屻劅劅
乽僐儅儞僢丄僪乕僢両両丂抧媴杊塹戉俶俿俼偱偁傝傑偡偭両丂擟柋悑峴拞側偺偱幾杺偟側偄偱偄偨偩偒偨偄偭両乿
乽偄偄偐傜偝偭偝偲柶嫋徹弌偟偰乿
丂偡偭偐傝噣愼傑偭偰噥偟傑偭偨斵傜偼愴摤婡偺傛偆側僂僀儞僌傗傜僲乕僘傗傜悅捈旜梼傗傜偱忺傝晅偗傜傟偨帺摦幵偵忔傝丄僒僀儗儞傪崅傜偐偵柭傜偟側偑傜揋偺怤棯嫆揰乮徫乯偱偁傞柧椢娰妛墍偺晘抧傊偲撍擖乧乧乧乧偡傞捈慜偵幵椉朄堘斀乮晄惓夵憿乯偱僷僩僇乕偵巭傔傜傟丄掞峈偟偨偨傔偦偺応偱慡堳戇曔偝傟偨劅劅
25/08/09 23:28峏怴 / 俵俷俶俢俷
栠傞
師傊