02「進撃の女子高生ゲイザー(後編)」
デート。親しい男女が楽しみながらその仲を深めるために、外に出かけること。
具体的には、食事やショッピングに行ったり、映画館や遊園地に行ったり、公園や景色のいい場所を散策したり──
「どうしてこうなった……?」
朝いちで、ちょっと気になる?男子である彼方から休日デートを申し込まれ、そのあと駆け寄ってきたホノカに「よかったね! おめでとう!」とニコニコ顔で握られた両手をぶんぶん上下に振り回され、文葉には「ほーら言った通りになったでしょ♪」とドヤ顔を決められ、他の女子たちにもなんやかんやと囃し立てられ(ルミナだけは何故かムスッとしていた)、半分惚けた状態で一日過ごして今に至る。
「…………」
放課後、今日は部活の日。
部室にある自分に割り当てられたロッカーの前で、ナギは肩を落として半眼になった。
「昼、何食ったかおぼえてないんだよなぁ……」
手持ちのマヨネーズの中味が減っていたので、一応なんか食べたみたいなのだが。
はああ……と溜め息をつきながらロッカーを開けてカバンを中に放り込み、制服を脱いで白筒袖の道着と黒紺色の行灯袴に着替え、足に白足袋を履く。
道着の上から胸当てを付け、右手に弓懸(ゆかげ)をはめて、ナギは壁に立てかけてある姿見を見た。
弓道部に入部して二か月。今さら袴姿の自分に違和感をおぼえたり、照れたりはしない。
だから鏡に映る自分の顔が赤いのは、別の理由があるからで……
<●>
部活動・同好会活動のさかんな明緑館学園。その理由に、施設が充実していることが挙げられるだろう。
本格的な弓道場もそのひとつ。なお、弓道部員は女子ばかりで男子部員は今のところひとりもいない。
ヒュン…… トス──ッ!
「ちっ、また中(あた)んない」
腕力強化用のゴム弓を卒業し、実際に和弓を引くようになって半月。ナギは単眼種特有の超視力と一点集中力で、初心者であるにもかかわらず、先輩たちと並んでそこそこ的を射抜ける実力を見せていたのだが……今日に限って矢が的に届かなかったり、明後日の方に飛んでいったりしている。
──う〜っ、余計なこと考えてるせいか、かすりもしない……っ。
顔をしかめ、次の矢を手にして脚を開くナギ。弓道の基本姿勢である「射法八節」は、他の新入部員ともども、部長から直々に教え込まれている。
足踏み、胴造り、矢をつがえて弓構え、打起しから引分け、引ききった姿勢で会(かい)──
ヒュン……
「あーまた外したっ。……ったく、みんなアイツが変なこと言ったせいだっ」
弓を持ったまま、ナギは腰に手を当てて鼻を鳴らした。黒髪から伸びた触手もいらだたしげに、うねうねとせわしなく動く。
…………………………………………
……………………
…………
「ほ、ほ、本気かオマエっ!? あ、アタシとでででデートとか……っ!?」
「あのなぁ……みなが見とる前で、嘘や冗談でんなことゆえると思うんか」
「そ、そーだっ! そもそもなんでこんなとこで誘うんだよオマエっ! 普通、誰もいない校舎裏とか空いた部室とか屋上とかに呼び出すとか、放課後の教室にふたりっきりの時とか、それから、それから──」
「まあ、コッチもそんだけ本気やっていうこっちゃ。それに、甲介もみんなの前でホノカちゃんにコクっとったし、それにあやかってみたんや」
「あやかって、って……。くっそーみんな見てるから断りづれぇ…………これがいわゆる孔明の罠か?」
「……そういう言い回しどこで覚えてくんねん」
…………………………………………
……………………
…………
今は的に集中して、意識しないでおこう──と思えば思うほど、頭の中は彼方の、そしてデートの約束のことで一杯になってしまう。
「『離れ』と『残心』がおろそかになってるぞ、ナギ」
「わかってるよ。ったく」
射法八節の残り二つを、横から指摘される。
決まりごとにうるさいのは種族特性だよな〜と、口の中で愚痴りながら、ナギは声の主の方に向き直った。
「聞こえてるぞ。口うるさくて悪かったな」
褐色の身体を道着に包み、腰まであるストレートの黒髪を頭の高い位置で結わえた三角けも耳っ娘は、A組のアヌビス娘、レイン。
袴のお尻に開けたスリットから髪と同じ色をした犬の尻尾がとび出し、手足の先もデフォルメされた犬のそれなので、足袋が履けずに素足である。もっとも、人間の衣服や履き物をそのまま身に付けることができる魔物娘の方が少数派なのだが。
「…………」
彼女はナギを一瞥すると、的に向き直り、手にした弓に矢をつがえた。
背筋を伸ばし、顎を引き過ぎず、お手本通りの構えで矢を放つ。
ヒュン…… トス──ッ!
肉球わんこハンドでどうやって弓を引いてるんだ? などと、ぼんやり思うナギ。
種族は違えど同じ魔物娘でさえそう思うのだから、この世界の医学者や生物学者たちが「魔物娘を真面目に分析しようとしたらハゲる」と口を揃えて言うのもむべなるかな。
閑話休題(それはさておき)。
立て続けに三射、それら全てを的に中(あて)て、レインはナギの顔に視線を戻した。
「気になる男子にデートの申し込みされてあれこれ悩んでいる、といったところか?」
「ななななんでそれ知ってるっ!?」
単眼を大きく見開いて驚くナギに、呆れたようにため息をつく。
「我らは魔物娘だぞ。他人の色恋沙汰には皆、ヒトの倍敏感だ」
「う……」
正論?をド直球でぶつけられて、ナギは言葉を詰まらせた。
つまり、今朝の──いや、昨日からの一件は魔物娘たち全員の知るところであり、それは同時にナギと彼方が、マカップルとして認識されているということである。
「あ、焦ってんのか? みんな」
「真っ先にサイクロプスがパートナーを得て、次いでゲイザーもとなると、自分たちも──と思ってしまうのも無理ないだろう」
「なんか遠回しに『単眼種にオトコができるのは超珍しい』って言われてるみたいでムカつくな……」
ナギはそう返すと、レインを半眼で睨んだ。
<●>
同じ頃、彼方は廊下でクラスの一部の男子たち──DT、彼女なし歴=年齢──に絡まれていた。
「なんて……なんて真似をしてくれたんだ永野〜っ!!」
「……!? な、なんやいきなりっ!?」
目の幅涙を流す彼らにいきなり詰め寄られ、思わずあとずさってしまう。
「お前なあ……な、ん、でっこのタイミングでナギの奴にコクるんだよぉっ?」
「は?」
「は、じゃねえだろ」
「ホノカちゃんと海老川のふたりだけでも腹一杯なのに、ナギとお前までマカップル化してみろ、ただでさえずっぱ甘ったるいB組の空気がさらにスゥイイイッツになっちまうだろがぁっ!」
魂の叫び。
「俺らDTこじらせ隊がそんな環境下で生命活動を維持できないのは、お前だって分かってるはずだろがぁっ!」
魂の主張。
「くっそーむかつく誰かリア獣ハンター呼んでこいっ!」
魂の……以下略。
「お前ら、ええ加減痛々しいイチャモンつけんなや……」
マカップル──もちろん魔物娘と人間男子のカップルのことなのだが、そこには〝バカップル〟の意味(揶揄)も多分に含まれている。
とはいえ公式第一号のホノカ&甲介があんな調子だから、「魔物娘と付き合ったらバカップル化する」と思われても仕方がない……ある意味間違いではなかったりするのだが。
頭に手をやってため息を吐く彼方の前に、一人の男子が進み出た。その容姿に似合わぬゴツゴツした拳を握りしめ、彼方の鼻先にそれを突きつける。
「見ろぉぉぉっ、あのふたりが人目もはばからずにイチャイチャイチャイチャイチャイチャイチャイチャするたびに壁を殴り続けて鍛え上げられた、このゴッドハンドをををををっ!! ……そうっ! 今の私は阿修羅をも凌駕するっ!」
「……そいつぁすごいな。どうだい? いっちょアタシとひと勝負してみないか?」
「えっ……?」
いきなりなんの脈絡も伏線もなく背後から肩をガシッと叩かれ……もとい鷲づかみされたゴッドハンド(笑)男子。
ギギギギッと効果音が聞こえてきそうな動きでゆっくり振り返ると、そこにいたのは──
「げえっ! リアル◯ュレックっ!!」
「誰がシュ◯ックだあっ!!」
燃えるように渦巻く赤い髪、学校指定の体操服から覗く薄緑色の肌。マッシブかつ均整の取れたプロポーション、彼方たち男子より頭ひとつ分高い身長。その額にバンダナを巻き、こめかみの上の方から一対の角が斜め上を向いて生えている。
「…………」
すくみ上がったDT男子たち全員に鋭い視線を注ぐ彼女は、十七人の魔物娘のひとり、C組のオーガ娘、サキ。ゴツい見た目とは裏腹に世話好きで気さくな奴だと、彼方は彼女と同郷であるナギから聞いていた。
「まっいいわ。ちょうど柔道部が休みで演武場が空いてるから、そこでゴッドハンドとやらを披露してもらおうか♪」
大きく発達した犬歯──というか牙を見せて、ニヤッと笑う。
ちなみに柔道部が休部しているのは、ホノカと甲介のマカップルに触発されたこの緑色の鬼娘が、パートナー探しのために体験入部し、腕試しと称して男子部員全員を問答無用かつ連続で投げ飛ばしたからだと言われている。
もちろん、彼女のお眼鏡に叶う者は一人もいなかった。
「ははは……冗だ──ぅえっ!?」
サキは彼方に詰め寄っていた男子の後ろ襟を無造作につかむと、返事も聞かずにその首筋を引っ張り、きびすを返した。強靭な筋肉に包まれた四肢と、豊かな胸と腰がうねる。
「ちょっ、ちょちょちょちょいっうおいっ!(きょろきょろ)うおおっ誰もいねえっ置いてかれたあああああっ!! ……ままま待てぇっ! さっきのはいわゆる言葉の綾であって必ずしもパンチ力が強化されたとか戦闘力が上がったとかそういう意味でなく逆境が人を強くするということを比喩的に表現したというかそのあのそのすすすすんません嘘吐いてましたハッタリかましてました調子こいてましただあああああやめてエロ同人誌みたく逆レされるうううった゛す゛け゛て゛お゛か゛あ゛さ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛〜んっ!!」
DT仲間にあっさり見捨てられ、抵抗空しくずるずる引きずられていくゴッドハンド(笑)男子。市場に売られるドナドナな仔牛めいたアトモスフィアが漂う。
そしてサキは廊下の端で振り返り、彼方に向かってウインクした。その口が「がんばれよ」と動く。
「……け、結局何しに来たんやあいつら」
そう言いつつも、彼方は片手を顔の前に立てた。感謝の意と、ついでに引っ張られていった仔牛の身を案じて。
なお、そのまま演武場に連れていかれたゴッドハンド(笑)男子は、投げの鬼スプリームと化したサキに一方的に九回も投げ飛ばされ、某金属生命体の中の人みたく全身打撲でグロッキー状態になったとか。
だが、これがきっかけでふたりの間に……
などということは全くなく、彼はDT歴を更新していくのであった。合唱もとい合掌。
<●>
明緑館学園女子寮、通称「撫子(なでしこ)寮」。ここ数年は寮生不在で閉鎖されていたが、今はこの世界にやって来た魔物娘たちの生活の場になっている。
三階建てで部屋数は二十。キッチン、バス、ランドリー、トイレは共用。なお、学園が昔女子校だった頃からのものなので、男子寮は存在しない。
「ううう……ああぁ……」
デート当日の朝、ナギは自室の中をうろうろと落ち着かなく歩き回っていた。
「う〜っ、もうすぐアイツが来やがるぅぅ……」
ナギたち魔物娘は人間の付き添いがいないと、学園の敷地外に出てはいけないと取り決められている。なので、今日は彼方が寮の玄関まで迎えに来ることになっているのだ。
「あー、もー、お、落ち着け、落ち着けアタシ。ちょっと外に出て遊びに行くだけだ。遊びに行くだけ──」
意識していないのに……否、顔が火照って胸がドキドキしているのは、思いっきり意識しているから。
「うー、がー、あー、うごごごご……」
それに気づいて頭を抱え、唸り声を上げても、約束した時間は刻々と近づいてくる。
昨日の夜、一緒に今日着ていく服を選んでくれた親友は、「用事があるから」と今朝から姿を見せてないし、ひとりだけだと心細さに拍車がかかる──
「レインは部長とショッピング行くって言ってたし……、サキの奴は休みの日は昼近くまで寝てるし……」
他の連中もそれぞれ予定があるだろう。「恥ずかしくて心細いから一緒に来てくれ」なんて頼めるわけがない。
コンコン──
「おはようございますナギさん。カナタさんが来られましたよ」
「ひゃいっ!」
部屋の外からノックとともに声をかけられ、ナギは弾かれたように背中を伸ばした。
ドアを開けると、そこには本格的なブリティッシュタイプのメイド服に身を包んだ一人の少女がいた。
ボブカットにしたライトブラウンの髪、ゴールデンレトリバーのそれに似た垂れ耳。エプロンの紐を結んだ後ろ腰のあたりからフサフサした尻尾が、手首には鳥の羽根が生えていて、ロングスカートの裾から覗く足先は鳥の脚を思わせる鱗に覆われている。
「お、おはよ……」
「はい、おはようございます」
その顔に柔和な笑みを浮かべる彼女は、十七人の魔物娘のひとり──E組のキキーモラ娘、イツキ。
母子相伝のメイドスキルを活かして撫子寮の舎監みたいな役割も務めており、清楚で物腰も柔らかく控えめ。一部では「嫁にしたい魔物娘不動のナンバーワン」とも評されている。
もっともこづかい稼ぎ程度のバイトしかやらない同級生の男子など、働き者の男性を好む彼女の眼中には全くなかったりするのだが。
「まあナギさん、とっても可愛い♪」
イツキは部屋から出てきたナギの姿を見て、両手をぽんと合わせた。
「うぎゃああああああっ! 言・う・なぁあああああ〜っ!!」
言われたナギは赤くなっていた顔を、更に真っ赤にして悲鳴を上げる。
しかしそのまま回れ右して部屋へ戻ろうとした彼女の肩に両手を置いて、メイドな魔物娘はその耳元でそっとささやいた。
「大丈夫、自信持ってください。今日のナギさんなら、きっとカナタさんをメロメロにできますよ♪」
「め、メロメロって……そ、そんな、しょんなぁぁ──」
恥ずかしさ、さらに二倍でドン。
単眼はぐるぐる回っているのに、呂律がちっとも回ってない。……上手いこと言った。
「それに──」
つぶやくようにそう言って、イツキは流れるような身のこなしでナギの前に立つと、その襟元に結ばれたリボンの曲がりを直した。
「ナギさんとホノカさんは私たちにとって、〝希望〟でもあるんですよ」
「……それってアタシらみたいな単眼種にオトコができたから、自分らも──って思えることか?」
「ええ、まあ……でも、それだけじゃないんですよ」
じっと見つめられて真顔になったナギに、イツキはゆっくりと首を振った。
彼女曰く、ナギやホノカが人間の男性と当たり前のようにお付き合いしているのを見せれば、魔物娘をいたずらに恐れたり、気味悪がったり、意味もなく敵視したりする方々の誤解を解くことができると。
「……で、アタシとホノカが〝希望〟ってわけ」
「はい♪」
にっこり笑みを浮かべてうなずくイツキ。
「大袈裟な……そもそも十七人しかいないアタシらに、何ビビってんだか」
少し頭が醒めたのか、腰に手を当ててフンと鼻を鳴らすナギだったが、その態度と表情には「悪い気はしない」と出ていた。
「そっか、うん、希望かぁ……」
さっきまで固まっていた背中の触手が、機嫌よさげにゆらゆら揺れ動く。
単純な娘であった。
<●>
「…………」
撫子寮の玄関で待っていた彼方は、イツキに連れられて降りてきたナギの姿に眼鏡の奥の目を丸くした。
「な、なんだよ…………に、似合わない──か?」
無言でじっと見つめられ、ナギは単眼を落ち着かなく左右に動かす。
彼女が着ているのは、襟や合わせ目、袖にフリルの付いた白のブラウスと、膝丈の裾がフレアになっているAラインの黒いシャンパースカート。その色味が長い黒髪と赤い単眼にぴったりマッチしていた。
だから──
「あ、いや、そうやなくて……えっと、なんちゅうか、その、ま──まあ、似合っとる、かな……」
「そ、そっか、に──似合ってるか……」
照れ隠しに鼻の頭を掻いて、あさっての方を向く彼方。ナギも顔を赤くしたまま、横を向いた。互いに目だけを動かして、相手の顔をちらちらとうかがう。
彼方の方はチェック地のカジュアルシャツにジーパン、その上から薄茶色のライダースジャケットを羽織っている。ゴスロリちっくなナギと並ぶとちぐはぐだが、お互い「持ってるもので目一杯お洒落してきました」的な初々しさがあって、なんか微笑ましい。
「……では、おふたりともいってらっしゃいませ」
そんなふたりをニコニコしながら見守っていたイツキに、耳元で「がんばって♪」とささやかれ、背中を押されて玄関を出る。
そして、寮の前に停めてあったサイドカーを見て、ナギの単眼がキラキラしだした。
「おーすげえ、鉄の馬だ……こ、これ、カナタのか?」
マジでライダーだった件。
「叔父さんのお下がりやけどな。バイク見るの初めてか? ……ほれっ」
投げ渡された半帽型ヘルメットを受け取る。ゴーグルはナギの単眼に合わせてスキー用のものに取り替えられていた。
「えっと、乗っていいのか? 乗っていいのかこれ?」
「ええで。そのために転がしてきたんやし」
サイドカーの側車をぺたぺた触りだしたナギに、彼方は苦笑しながら答えた。
「きししっ、馬車なんて乗るの久しぶりだ……」
「なんで馬車やねん」
車輪がついてて座席があって、(鉄の)馬に引かれているから馬車──という認識らしい。
「いいじゃんか。馬車でエスコートされるのは女の子の夢なんだから…………ちょっと、狭い、けど、なっ」
触手を髪の中に戻して、パッセンジャーシートに座るナギ。渡されたヘルメットをおっかなびっくり被る。
それを見て彼方もバイクにまたがり、グリップに引っかけていたジェットタイプのヘルメットを被ってバイザーを下ろした。
「ほな行こか、お姫さま」
「うむっ、よきに計らえ〜っ♪ ……ひゃあああっ!」
動き出したサイドカーに、ナギは嬉しそうに声を上げた。
さっきまでうだうだ悩んでいたのはなんだったんだと思われるほどの、切り替えの早さだった。
<●>
「……行っちゃった」
エキゾースト音を響かせて通用門を出ていくナギたちを寮の建物の影から見送り、ホノカは羨ましそうにつぶやいた。クリーム色の丸襟ブラウスの上から紺色のベストを羽織り、ボトムは裾にボアの付いたお気に入りのショートパンツ、薄紫色の髪はいつものようにバレッタでアップにして、脚はニーソとスニーカーという私服姿だ。
「まさか永野の奴、バイクの免許持ってたとは」
しかも初デートにサイドカーだなんて、なかなかやるわね……と、横にいた文葉が同じように小声で返した。こちらは桜色の膝上丈ワンピースに薄手のデニムジャケットを合わせ、髪は背中に流し、足元はホノカと同じくスニーカーを履いている。
「まあ目的地はわかってるし、彼方ならツーリングがてら遠回りするだろうから、電車で充分先回りできると思うよ」
ふたりの後ろでそう応えた甲介は、無地のロング丈長袖Tシャツとブラックジーンズというシンプルな格好。
……三人とも、ナギと彼方のデートを追っかける気満々であった。
いや、あと一人。
「あれ? ルミナさんは?」
「いつもの鎧着込んで来たから、フミハが『悪目立ちするから着替えてこい』って」
「あー」
サイクロプスやヴァルキリーが並んでいるだけで、十二分に目立つと思うのだが。
しかしホノカの言葉にその情景が容易に想像できて、なんとなく納得してしまう甲介だった。
「すまない。遅くなった」
噂をすればなんとやら。当のルミナが駆け寄ってきた。
クリーム色したブラウスに紺のリボンタイ、ベージュのロングスカート、足元は茶色のローファー。変装のつもりなのか髪の毛を一本のお下げにまとめ、赤いフレームの伊達メガネを顔にかけている。
まあそこまではいい。そこまでは。
「あんた、何持ってきたのよ……」
半眼になった文葉のその視線の先にあるのは、担がれたコントラバスケース。
ルミナはそれにちらりと目をやり、
「うむ、武器を隠して運ぶには楽器のケースを使うものだと、ある本に書いてあったのでな」
重々しくうなずいて、ドヤ顔を浮かべた。
「……なんの漫画読んだんだろ?」
「さあ……」
などと後ろでひそひそやってるマカップルをほっぽって、文葉が眉をつり上げる。
「ああもうっ、な、ん、で、いちいちそういうのを持ってくるのよっ!? このバトル脳はっ」
「失敬な! これはあのゲイザーが、万がいち人混みの中で暴れ出した時に備えて──」
「い い か ら 置 い て き な さ い っ!!」
「うう……っ」
眉間にシワを寄せて微笑む──当然目は全く笑ってない──クラスメイトに、さすがのルミナも気圧されてしまう。
さらに、
「差し出がましいとは思いますが……そういった大荷物を電車の中に持ち込むと、まわりの乗客から迷惑かられて蹴りを入れられると聞きましたよ」
少し離れたところから四人を見ていたメイド姿のイツキが、そっと近づいてきて口を挟んできた。
「だ、だがっ、魔物から無辜の人々を守るのが我が使命。鎧を封じた今、せめて武器がなくては──」
「その守るべき人間の方々との間に余計なトラブルを抱えるのは、戦天使としては不本意かつ不名誉なのではないかと思いますけど」
「うぐぅ……」
正論でぶった斬ってくる口上手のキキーモラに、ぽんこつヴァルキリーが勝てるわけなかった。
「ところでケースの中に何入れてきたのよ? ルミナ」
「剣道部で使ってる竹刀……」
「ひと昔前のスケバンかあんたは」
「……ナギちゃんに何か言ったの? イツキ」
「はい。ナギさんが自信を持てるように、虚実織り交ぜあれこれと♪」
<●>
郊外にある遊園地、更紗ファンタジアランドは休日もあって、大勢の人で賑わっていた。
「うおおおっ、すごい人混みだな〜。……お祭りかなんかあるのか?」
「あ〜まあ、確かに毎日お祭りしてるとこっちゅうのも、当たらずとも遠からずやけどな──」
駐車場にサイドカーをとめて、チケット売り場でフリーパスを購入。もの珍しさにまわりをキョロキョロするナギに、彼方は苦笑混じりに答えた。
もっとも異世界の魔物娘である彼女の反応は、さらに斜め上にいくのだが。
「毎日お祭り……う〜んさすが日本、未来に生きてるわ〜」
「いやいや、そうやなくて」
などと言い合いながら、ふたりは入場ゲートをくぐり、人の流れにのってカフェやショップが軒を連ねるアーケードの下をそぞろ歩く。
しかし、おのぼりさん丸出しな調子であたりを見回し、背中の触手をうねうねさせるナギに気づいた周囲が、徐々にざわつき始める。
え〜っ、あれ何? 魔物娘?
マジマジ!? うわーホンモノだ。初めて見た……
魔物娘接近遭遇なうw
触手ヒトツ眼、マジキモいんですけど──
「…………」
元いた世界──住んでいた親魔物領でさえも、幾度となくこの手の視線に晒されてきた。ゲイザーの自分を初めて見た人がどんなリアクションをするかは分かっていた……つもりだった。
だけど、
「ねえねえ隣にいるのって、ひょっとして〝アレ〟のカレシ?」
「うわ趣味悪ぅ〜っ。女子に相手されないから魔物娘にってか?」
「……っ!」
見ず知らずの女子グループに指差されて好き勝手言われ、我慢できなくなったナギは、思わず「黙れお前ら」と念を込めて邪眼を向けようとした。
「ナギ」
「ひゃおっ!?」
……が、横にいた彼方にいきなりお尻を軽くはたかれてとび上がる。
「い、いきなり何すんだカナタっ!?」
「ええから胸張って前向いて、当たり前って顔しとけ。なんも悪いことしてへんねんし」
「け……けど、あいつらカナタのこと──」
「知り合いでもなんでもない赤の他人をいきなり指差しでディスるような連中なんか、『ワタシラ人トシテノ常識ゴザイマセ〜ン』って自分で宣伝しとるようなもんやから、無視や無視」
ワザと聞こえるようにそう言うと、彼方は眉を吊り上げる女子たちをメガネの奥からちらりと横目で見た。
「何よあれっ? 感じワル〜っ」
「ヒトツ眼女と付き合うなんて頭おかしいんじゃない〜?」
「行こ行こ」
彼女たちは口々にそう言うと、これ見よがしにひそひそやりながら離れていく。
「お、おいカナタ……いいのかよ?」
「さっきもゆうたけど、ほっといたらええねん。かかわり全然ない奴にイチャモン付けられても、その時だけやしな。……それよか、さ〜どれから乗ろか?」
──ま、みんな甲介からの受け売りやねんけどな……
何事もなかったかのように流すと、彼方はポケットから出したスマートフォンを操作してFT(Floating Touch)ディスプレイを立ち上げ、園内マップを表示した。ナギは横からそれを覗き込む。
「おー、いっぱいあるな。アブダクション──だっけか?」
「アトラクション、な。……そういや、ナギのおった世界に遊園地とかなかったんか?」
「ん〜、こんな風に毎日やってる場所はなかったけど……」
苦笑を浮かべて問いかけてきた彼方に、ナギは人差し指を口元に当てて上を向いた。
「街のでかいお祭りで人力の回転木馬とか、水車の力で回る観覧車とか乗ったことあったなぁ。……あ、あとローラーコースターとかも」
「ふーん……ほな、一発目はこっちのコースター初体験、行ってみよか?」
「お、いいね。ドンと来いだ」
彼方のサイドカーにも興味津々だったし、もしかすると乗り物に乗るのが好きなのかもしれない。
しかしナギの知る〝ローラーコースター〟は、引っ張りあげたトロッコに乗って坂の上から線路をアップダウンしながら一直線に滑り落ちるという、単純かつ原始的なものだ。
当然、ここ更紗ファンタジアランドが誇る絶叫スパイラルコースター「スター・ドライブ・ライド」が、そんなラクダの背中(キャメルバック)だけという〝ヌルい〟代物であるわけもなく……
「え? ナニコレ? なんでこんなにがっちり身体固定するんだ? てゆーかこの乗り物、座席のまわりとか足元になんもないんだけど……え〜っとなんか仰向けで上に上がってるってちょっと高い高い高いっ!? ままま待て待て降りる降りる降りるまだ心の準備があああああっ! ……お? あ? え? ぎゃあああああああ〜っ落ちる落ちる落ちるぅううううっぐおおお触手ちぎれるちぎれるちぎれるぅうう〜っひぃいいいいいいい〜っ逆さになってる景色回ってる頭に血がのぼるぅうううう〜っぎゃああああヤダヤダヤダヤダとめてとめてとめてえええええっごごごごめんなさい魔王さま主神さま明日からタマネギ残さず食べますルミナのことへっぽこヴァルキリーだなんて言いませんだからお願いた゛す゛け゛て゛ぇええええええええ〜っ!!」
ごごごごごごごごごこぉおおお────────っ!!
「お、おおおお前らっ、ぜっ、全員──全員マゾかぁああああ……っ」
「んな大袈裟な……」
単眼ぐるぐる涙目、息も絶え絶え、半分腰が抜けた状態でふらふらと出口から出てきたナギにしがみつかれて睨まれて、彼方は肩をすくめて半笑いを浮かべるのであった。
<●>
「あーもうなんかマジムカつくあのメガネ関西弁っ」
「何あの態度っ? ちょーキモっ」
「キチってんのよあいつ。バケモノ女なんかと付き合ってるし」
先ほどナギと彼方にインネン付けた女子たちが、未だ憤懣やるかたなしといった調子で悪口を垂れ流しながら歩いていた。派手めのメイクに茶髪頭、着崩したギャルカジ……という、いかにもな三人組である。
「メイなんとか学園の中から出てこなくていいのに、あいつら」
「ああいうキチ男がいるから調子こいてんのよっ。……ホントウザい。人類の裏切りも──」
「ちょっストップ! マズイよそれ言ったらっ」
「そうね〜、そんなこと大声で言ってたら、魔物娘を怪獣怪人扱いしてヒーローごっこしてる連中のお仲間認定されちゃうわよ〜♪」
「「「……!」」」
知らず知らずのうちに、おしゃべりのテンションが上がっていたらしい。背後からかけられた声に、ギョッとして振り返る。
後ろにいたのは、彼女たちと同じ年頃の少女が二人。
ひとりは気の強そうなワンピース姿の少女、もうひとりはメガネをかけた金髪碧眼の少女──
「お前たち、園内でゲイザーとツガイの男を目撃したようだが、そいつらは今どこにいる? 答えろ」
「ちょっとルミナ……それ人にものを訊く態度じゃないわよ」
「む、そうか。……頼む、教えてくれ。ヤツを倒すことができるのはこの私だけだっ」
「「「…………」」」
──こっ、コイツやべええええっ…………ガチでマジだ……っ!
せーだいに誤解されたなんて露ほども思わず、握った拳を胸に当て真剣な表情で懇願する金髪少女。連れの方はその後ろで「あっちゃ〜」と額に手をやった。
二手に分かれてナギたちを探す、文葉とルミナのコンビだった。
「ああああっちあっち!」「あっちの方っ!」
戦天使の眼光に圧された三人は、あわてて今来た方を指差すと、かかわり合いになるのはゴメンとばかりに走り去る。
その背中を見送った文葉は溜め息を吐くと、スマートフォンに表示した園内マップを覗き込んだ。
「あっちだと、『ラビリンスX』あたりに行ってるかなあ……」
3D映像とプロジェクションマッピング、そして特殊メイクを施した生身の演者たちが売りの迷路型ホラーハウス──お化け屋敷である。
「よし、急いでそのエックスとやらへ行ってみよう」
「言っとくけど、中にいるモンスターはロボットか人間の役者さんだからね。間違っても殴ったり蹴とばしたり壊したりしないでよ」
さすがにそこまで非常識ではないとは思うが、一応クギを刺しておく。
「ふむ、倒してはいけないのか……いわゆる縛りプレイというやつだな」
「いや、そうじゃなくて」
……前言撤回。
<●>
一方、ホノカと甲介はというと──
「楽しかった。ね、コースケくん♪」
「ははは、そうだね……」
喜色満面のホノカにそう言われて、甲介は若干疲れたような笑みを浮かべた。
隠れた人気アトラクションである大型メリーゴーランド「カルーセル・オブ・ファンタジア」の、レトロな装飾とオルゴールに合わせてゆっくり上下しながら回る木馬の動きをいたく気に入ったホノカが、それに十回も乗り続けた挙げ句、係員をつかまえてその構造や仕組みについて根掘り葉掘り質問しだしたのに付き合っていたからである。
「ま、実際に尋ねてたの僕だけどね」
「うう……ごめん。でも、初対面の人に話しかけるの、苦手だから」
しかし応対してくれたメンテナンス担当の人が、甲介の後ろから顔を覗かせじっと見つめてくるサイクロプス──ホノカにビビりながらも詳しく教えてくれたので、彼女も充分満足できたようだ。
ちなみに「メリーゴーランド(メリーゴーラウンド)」と「カルーセル」、厳密にいうと木馬が上下に動かないか動くかで呼び分けるのだとか。
「でもいいのかなあ? 彼方とナギさん探さなくて」
「フミハたちには悪いけど、ナギちゃんが行きそうなアトラクションはだいたい予想つくし……」
甲介にそう答えると、ホノカは腕を絡めてその身体をくっつけてきた。「だから、もうちょっとだけコースケくんとふたりっきりでいたいな♪」
「ホノカちゃん……」
まんざらでもない表情を浮かべつつ、頭に空いた手をやり照れる甲介。
ヴヴヴヴヴ──ッ……
「あ、フミハからメール来た。えっと、『イチャついてないであいつら探してる?』 …………」
「……読まれてる、ね」
<●>
「みんな絶対おかしい! なんでわざわざ高い金払ってあんなコワイ目にあいたがるんだっ?」
園内にあるオープンカフェで、ランチタイム。
ひとつ眼の魔物娘をひそひそうかがう周囲の視線もなんのその。追いマヨネーズしてもらったホットドッグ型のサンドイッチをぱくつきながら、ナギは彼方に向かって熱く文句を垂れていた。
「……とかなんとかゆうてるけど、ジブンも3Dライドとかフリーフォールとか急流すべりとか、絶叫系ひと通り乗り倒してたやん」
「そ、それは、その……の、乗っとかないと、なんか負けたような気がして、さ」
「何と戦ってんねん、お前──」
コワガリなくせして絶叫マシン乗りたがる奴って、いるよね〜っ。
もしゃもしゃと口を動かし目と触手の先っちょを逸らすナギに、彼方は生暖かい視線を向けてツッコんだ。
そして紙コップに残ったコーヒーを飲み干すと、トレイを持って席を立つ。
「ほな、そろそろ次のとこ見に行こか? 並ばんでええように予約も取っといたし」
「ん、今度はなんに乗るんだ?」
指についたマヨネーズを舐めとりながら、ナギが尋ねてきた。
「乗りモンやないで。……ま、行ってみてのお楽しみ、や」
「お、おう……」
すっと差し出されたその手をつかんで、ナギはゆっくりと立ち上がった。
<●>
「ははは……やった、やったぞ…………魔物の巣食う迷宮を突破したぞっ! これもみな主神様の御加護の賜物っ!」
「……あ、あんたと一緒に、にっ、二度とおばけ屋敷に入らないからっ」
ホラーハウス「ラビリンスX」の出口に、興奮で顔を真っ赤にして勝ち誇るルミナと、げんなりした表情を浮かべて肩で息する文葉の姿があった。
そんな二人には「ラビリンスX 最速制覇認定証」が贈られていた。変に気合を入れたルミナが文葉を引っぱって大股で真っ暗な迷路に踏み込み、出てくるお化け役たちを「しょせんは紛い物! ヴァルキリーたる私を止めれるものなら止めてみろ!」と背中の翼を広げて威圧。ホラーハウスの雰囲気やらなんやかんやを一切合切無視して、出口まで通常十五分以上かかる迷路をわずか五分でゴールしたからである。
……要するに、力技だった。
<●>
座席の背もたれに身体を預けると、ぐっと後ろに倒れて仰向けになる。
首を巡らすと、周囲には巨大なドーム状の天井──360度スクリーンが広がっている。
「なんか椅子っていうより、ベッドみたいだな、これ……」
「そのまま寝落ちったらあかんで。せっかく来たんやさかい」
何度もリクライニングを確かめるナギに、隣の席に座る彼方が声をかけてきた。
「わ、わかってるって。ぷらねた……なんだっけ?」
「プラネタリウム、な。ドーム天井全体に星空を映すんやで」
「ふうん……」
素っ気ない返事で答えるナギ。
星空なんて、草っ原に寝っ転がってりゃいつだって見れるじゃん……と口の中でつぶやきながら、彼方が指差す方を見上げる。
全天周シアター「スター・ミュージアム」。プラネタリウムだけでなく3D映画なども投影されるのだが、ライド系のアトラクションを期待していたのか、彼女はいまいち触手──もとい食指が動かないようだ。
──けどまあこっちの世界は夜もムダに明るいから、星なんてちらほらしか見えないしなぁ……
ナギたちがいた世界では、飛行能力を持つ魔物娘によって、自分たちの住んでいる大地が途方もなく巨大な球体──世界で一番高い山が、ひと抱えもあるボールについた砂粒にたとえられるようなものであることが発見されてはいたが、さすがの彼女たちも気圏を越えて宇宙(その概念はあった)に飛び出すことはできず、天動説と地動説の決着も全くついていない。
ほどなくして操作員のアナウンスとともに、投影が始まった。低いところに更紗市の街並みを精緻に描いたイラストが、向かって右側に太陽の位置を表す丸い光が映し出される。
「では、時間を速めて先に夜を迎えましょう。今日の日の入りの時刻は──」
階段状の傾斜がついた客席の正面が「南」、左側が「東」で右側が「西」、頭の後ろが「北」。〝太陽〟が西へと沈み、それと入れ替わるように街中でも見られる明るい星──金星や木星が瞬きはじめた。
「おー、なんかそれっぽい」
「やろ?」
「……それでは今から街の灯を消して、皆さまを星の世界にいざないます。私が五つ数えるまで目を閉じていてください」
都会の夜空でも目立つ星々の説明が終わり、ここから本番である。
その気になれば暗闇を見通すこともできなくはないが、ナギもアナウンスに従ってその大きな目を閉じた。
「──さん、に、いち。……では、ゆっくり目を開けてください」
まぶたを上げると、目の前に星の海が広がった。
「や、よかったぁ……やっぱ投影時間フルに使こて、夜明けまでやってくれると値打ちあるわ〜。……ん? ナギ、どないした?」
「…………」
四十五分の投影が終わって明るさが戻り、伸びをしながら身を起こした彼方は、隣にいるナギの様子がおかしいことに気づいた。
リクライニングして寝転んだまま、右手の甲で目を隠し、何かを我慢しているかのように肩を震わせている……
喰いしばった歯の間から、かすかに嗚咽が漏れる。
「…………父さん、……か、あ、さん──」
「ナギ、お前……」
その閉じた目から、涙が一筋流れた。
「あ、あの、お客さま……次のお客さまが入ってこられるので、そろそろ──」
案内係の女性が、声をかけてきた。
彼方はナギの頭にそっと手を置き、空いた手を顔の前に立てて頼み込んだ。
「も、もうちょっとだけ……ギリギリまで待ってくれへん? かんにんやけど……」
<●>
夕焼けが、あたりを染め始めた。
遊園地デートの締めは観覧車がテッパン……というわけで、プラネタリウムを出たナギと彼方は、ファンタジアランドのシンボルでもある大観覧車に乗り込んだ。
ゴンドラの中で、向かい合って座る。
「まさか星空見て、ホームシックになるてなぁ……」
「うぅ〜っ忘れろっ! 今すぐ忘れろっ!」
脱力したようにつぶやく彼方に、ナギは目と顔を赤くしたまま叫んだ。彼女曰く、元の世界では十六歳で一人前。だから今さら親が恋しいなんて、単なる気の迷いみたいなものだ……と。
ちなみに第二世代以降の魔物娘が早期の独立を促されるのは、長い間実家に居座られると母娘で一番身近な男性──父親を〝共有〟する事態になりかねないからだとも言われている、らしい。
「……けどな、ナギ」
「あん?」
「生きてたらいつかは会える──そう思っとかんと、ホンマに会われへんようになるで」
「な、なんだよ急に……」
メガネをはずし、いきなり真顔になって見つめてくる彼方に、ナギは目を瞬かせた。
「魔物娘って人間の倍以上の寿命あるんやろ? せやったらその間に向こうへ帰る方法とか、それが無理でも連絡とる方法とか見つかるんちゃうか? そない思た方がナンボか気ぃ楽やで」
だが、これまでフィクションでしか魔法が存在しなかったこの世界で、はたしてそんなものが見つかるのだろうか?
それでも──
「……なんだよ〜、アタシらにさっさと元の世界に帰ってほしいってか?」
「い、いや、そないな意味でゆうたんやなくて、その──」
一転、しどろもどろになる彼方に、ナギはぷっと吹き出した。「きししっ、大丈夫だよ。この世界にはホノカや仲間たちもいるし、それにカナタ……オマエもいるしな」
「ナギ……」
希望は持ち続けよう。全てはそこから始まるのだから。
「……それにアタシ、この世界でやりたいことがあるんだ」
しばしの沈黙のあと、ナギが口を開いた。
「へ〜、なんや?」
「えっと……あ、バカにするなよ」
「せえへんせえへん」
「ホントにバカにすんなよ……」
彼方の顔を睨みつけて念をおし、ナギはおもむろに息を吸うと、
「宇宙飛行士」
「は?」
予想の遥か上空を斜め上に音速でカッ飛んでいく単語に、彼方の目が点になった。
「ほら〜っ、やっぱりバカにしたっ」
「し、してへんしてへんっ。……ちゅうか、なんでまた?」
「え? だって一度でいいから宇宙ロケットってのに乗ってみたいし……それに魔物娘初の宇宙飛行士って、なんかカッコよくないか?」
「なんやねんその志望動機……」
「希望は持ち続るモンだろ? だ、か、ら──」
きししっと笑ってそう言うと、ナギは席を立って彼方の隣に腰を下ろした。
「協力しろよな。イヤだって言っても、オマエはもうアタシのものなんだからなっ」
「お、おい……」
彼方の腕に自分の腕と触手を絡め、ニマッと笑みを浮かべる。
赤い単眼に見つめられ、一瞬身体を強張らせた彼方は、ふっと表情を緩めた。
「はー、やっぱおもろいわお前。……ええで、とことん付きおうたる」
「なんだよそれ……」
そう言いながら、二人は互いにゆっくりと顔を近づけていき……
「カナタ、アタシを好きになれっ」
「……もうなってるがな。それってゲイザーの〝お約束〟かなんかか?」
「ち、ちげーしっ!(赤面) てゆーかどこでそんなコト知ったんだオマエっ!?」
……などと言い合いながら、唇を合わせた。
はじめは軽く、次に強く、さらに深く──
「……ん、ふぁ……っ」
半開きになったナギの単眼が、怪しく光る。キスで無意識に魔物娘としての本能が目覚め、その淫気にあてられた彼方もまた、無意識に昂ぶっていく。
「ちょっ、か──カナタっ、強引……っ」
身体を引き寄せられて胸とスカートの中を弄られ、ナギはくぐもった声を上げた……
…………………………………………
「お客さ〜ん、降りてくださ〜い」
「「……!? うわぁああああああ〜っ!!」」
係員に棒読みっぽい口調で声をかけられて、我に返ったナギと彼方は悲鳴じみた声を上げ、はだけた衣服を押さえてあわててゴンドラからとび出した。
のちにその係員はこう語った。中でキスするカップルはよくいるけど、コトに及ぼうとするのを見たのは初めてだった……と。
そしてふたりは観覧車乗り場の前で、各々の親友とばったり出くわしてしまう。
「あ……な、ナギちゃん…………や、やっほー」
「……や、やあ彼方」
「ホノカにコースケ!? なんであんたらがここに?」
さらに反対側からも、聞きおぼえのある声が。
「ようやく見つけた……貴様、今までどこで何をしていた?」
「ちょっとルミナっ! 気付かれずにって言ったでしょっ!」
全員集合。偉そうに睨みつけてくるルミナ以外、皆バツの悪そうな顔をして目を逸らす。
「フミハたちまで!? これっていったい……」
「まさかお前ら、ずっとあとつけてきとったんかい……つーか止(と)めろや甲介っ」
「ゴメン、ちょっと心配になってさ──」
「私はお前が人間に危害を加えないか監視しに来ただけだ。けっしてデートを覗き見しに来たのではないっ」
「墓穴掘ってる自覚……ないわよね、ルミナ」
「「…………」」
ベタなことする友人たちに、互いに顔を見合わせると、ナギと彼方は同時に肩を落として溜め息を吐いた。
そして、クスッと笑い合うと、
「なんか食うて帰ろか、ナギ」
「そだな……」
寄り添って手を繋ぎ、入場ゲートの方へと歩き出す。
「ま、待てっ。今度は逃さんぞっ!」
「このあとどうしようか? ホノカちゃん」
「せっかくだからわたしたちも、観覧車乗っていこうよ。ね、コースケくん」
「おいこらそこのバカップル…………ってちょっとルミナっ! ひとりで先行かないっ! こら〜っ! そこでいきなり羽根広げるなぁっ!」
彼方が幼い頃両親と死別し、叔父夫妻の家に厄介になっていることをナギが知るのは、もう少し経ってからである。
なお、後日ファンタジアランドから明緑館学園に苦情が入り、ルミナはしばらく出禁になった。
to be continued...
─ appendix ─
メリーゴーランドにて。
ルミナ「ふふっ……作り物とはいえこうして馬にまたがると、戦天使としての血が騒ぐな。……さあ勇者たちよ! 導き手にして轡を並べともに戦う者──ヴァルキリーたる我に続けえええええっ!!」
ノリのいい子どもたち「「「おぉ〜っ!!」」」
その父親「うわぁあああああっやめろおおおおおっ! うちの子をヴァルハラへ連れていかないでくれえええええええ〜っ!!」
文葉「マニアだ……北欧神話マニアがいる……っ」
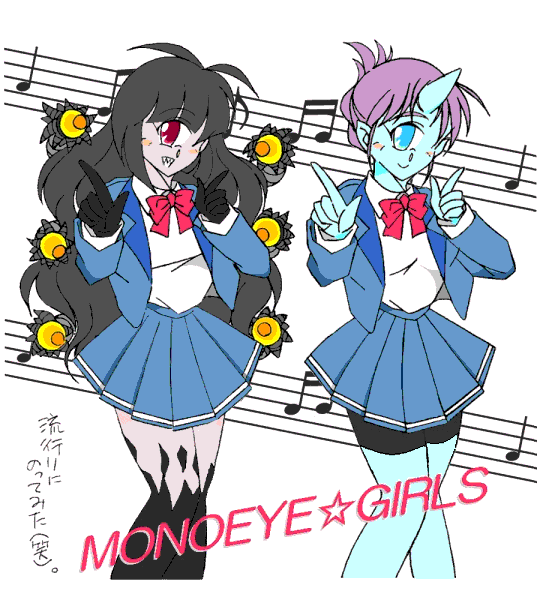
具体的には、食事やショッピングに行ったり、映画館や遊園地に行ったり、公園や景色のいい場所を散策したり──
「どうしてこうなった……?」
朝いちで、ちょっと気になる?男子である彼方から休日デートを申し込まれ、そのあと駆け寄ってきたホノカに「よかったね! おめでとう!」とニコニコ顔で握られた両手をぶんぶん上下に振り回され、文葉には「ほーら言った通りになったでしょ♪」とドヤ顔を決められ、他の女子たちにもなんやかんやと囃し立てられ(ルミナだけは何故かムスッとしていた)、半分惚けた状態で一日過ごして今に至る。
「…………」
放課後、今日は部活の日。
部室にある自分に割り当てられたロッカーの前で、ナギは肩を落として半眼になった。
「昼、何食ったかおぼえてないんだよなぁ……」
手持ちのマヨネーズの中味が減っていたので、一応なんか食べたみたいなのだが。
はああ……と溜め息をつきながらロッカーを開けてカバンを中に放り込み、制服を脱いで白筒袖の道着と黒紺色の行灯袴に着替え、足に白足袋を履く。
道着の上から胸当てを付け、右手に弓懸(ゆかげ)をはめて、ナギは壁に立てかけてある姿見を見た。
弓道部に入部して二か月。今さら袴姿の自分に違和感をおぼえたり、照れたりはしない。
だから鏡に映る自分の顔が赤いのは、別の理由があるからで……
<●>
部活動・同好会活動のさかんな明緑館学園。その理由に、施設が充実していることが挙げられるだろう。
本格的な弓道場もそのひとつ。なお、弓道部員は女子ばかりで男子部員は今のところひとりもいない。
ヒュン…… トス──ッ!
「ちっ、また中(あた)んない」
腕力強化用のゴム弓を卒業し、実際に和弓を引くようになって半月。ナギは単眼種特有の超視力と一点集中力で、初心者であるにもかかわらず、先輩たちと並んでそこそこ的を射抜ける実力を見せていたのだが……今日に限って矢が的に届かなかったり、明後日の方に飛んでいったりしている。
──う〜っ、余計なこと考えてるせいか、かすりもしない……っ。
顔をしかめ、次の矢を手にして脚を開くナギ。弓道の基本姿勢である「射法八節」は、他の新入部員ともども、部長から直々に教え込まれている。
足踏み、胴造り、矢をつがえて弓構え、打起しから引分け、引ききった姿勢で会(かい)──
ヒュン……
「あーまた外したっ。……ったく、みんなアイツが変なこと言ったせいだっ」
弓を持ったまま、ナギは腰に手を当てて鼻を鳴らした。黒髪から伸びた触手もいらだたしげに、うねうねとせわしなく動く。
…………………………………………
……………………
…………
「ほ、ほ、本気かオマエっ!? あ、アタシとでででデートとか……っ!?」
「あのなぁ……みなが見とる前で、嘘や冗談でんなことゆえると思うんか」
「そ、そーだっ! そもそもなんでこんなとこで誘うんだよオマエっ! 普通、誰もいない校舎裏とか空いた部室とか屋上とかに呼び出すとか、放課後の教室にふたりっきりの時とか、それから、それから──」
「まあ、コッチもそんだけ本気やっていうこっちゃ。それに、甲介もみんなの前でホノカちゃんにコクっとったし、それにあやかってみたんや」
「あやかって、って……。くっそーみんな見てるから断りづれぇ…………これがいわゆる孔明の罠か?」
「……そういう言い回しどこで覚えてくんねん」
…………………………………………
……………………
…………
今は的に集中して、意識しないでおこう──と思えば思うほど、頭の中は彼方の、そしてデートの約束のことで一杯になってしまう。
「『離れ』と『残心』がおろそかになってるぞ、ナギ」
「わかってるよ。ったく」
射法八節の残り二つを、横から指摘される。
決まりごとにうるさいのは種族特性だよな〜と、口の中で愚痴りながら、ナギは声の主の方に向き直った。
「聞こえてるぞ。口うるさくて悪かったな」
褐色の身体を道着に包み、腰まであるストレートの黒髪を頭の高い位置で結わえた三角けも耳っ娘は、A組のアヌビス娘、レイン。
袴のお尻に開けたスリットから髪と同じ色をした犬の尻尾がとび出し、手足の先もデフォルメされた犬のそれなので、足袋が履けずに素足である。もっとも、人間の衣服や履き物をそのまま身に付けることができる魔物娘の方が少数派なのだが。
「…………」
彼女はナギを一瞥すると、的に向き直り、手にした弓に矢をつがえた。
背筋を伸ばし、顎を引き過ぎず、お手本通りの構えで矢を放つ。
ヒュン…… トス──ッ!
肉球わんこハンドでどうやって弓を引いてるんだ? などと、ぼんやり思うナギ。
種族は違えど同じ魔物娘でさえそう思うのだから、この世界の医学者や生物学者たちが「魔物娘を真面目に分析しようとしたらハゲる」と口を揃えて言うのもむべなるかな。
閑話休題(それはさておき)。
立て続けに三射、それら全てを的に中(あて)て、レインはナギの顔に視線を戻した。
「気になる男子にデートの申し込みされてあれこれ悩んでいる、といったところか?」
「ななななんでそれ知ってるっ!?」
単眼を大きく見開いて驚くナギに、呆れたようにため息をつく。
「我らは魔物娘だぞ。他人の色恋沙汰には皆、ヒトの倍敏感だ」
「う……」
正論?をド直球でぶつけられて、ナギは言葉を詰まらせた。
つまり、今朝の──いや、昨日からの一件は魔物娘たち全員の知るところであり、それは同時にナギと彼方が、マカップルとして認識されているということである。
「あ、焦ってんのか? みんな」
「真っ先にサイクロプスがパートナーを得て、次いでゲイザーもとなると、自分たちも──と思ってしまうのも無理ないだろう」
「なんか遠回しに『単眼種にオトコができるのは超珍しい』って言われてるみたいでムカつくな……」
ナギはそう返すと、レインを半眼で睨んだ。
<●>
同じ頃、彼方は廊下でクラスの一部の男子たち──DT、彼女なし歴=年齢──に絡まれていた。
「なんて……なんて真似をしてくれたんだ永野〜っ!!」
「……!? な、なんやいきなりっ!?」
目の幅涙を流す彼らにいきなり詰め寄られ、思わずあとずさってしまう。
「お前なあ……な、ん、でっこのタイミングでナギの奴にコクるんだよぉっ?」
「は?」
「は、じゃねえだろ」
「ホノカちゃんと海老川のふたりだけでも腹一杯なのに、ナギとお前までマカップル化してみろ、ただでさえずっぱ甘ったるいB組の空気がさらにスゥイイイッツになっちまうだろがぁっ!」
魂の叫び。
「俺らDTこじらせ隊がそんな環境下で生命活動を維持できないのは、お前だって分かってるはずだろがぁっ!」
魂の主張。
「くっそーむかつく誰かリア獣ハンター呼んでこいっ!」
魂の……以下略。
「お前ら、ええ加減痛々しいイチャモンつけんなや……」
マカップル──もちろん魔物娘と人間男子のカップルのことなのだが、そこには〝バカップル〟の意味(揶揄)も多分に含まれている。
とはいえ公式第一号のホノカ&甲介があんな調子だから、「魔物娘と付き合ったらバカップル化する」と思われても仕方がない……ある意味間違いではなかったりするのだが。
頭に手をやってため息を吐く彼方の前に、一人の男子が進み出た。その容姿に似合わぬゴツゴツした拳を握りしめ、彼方の鼻先にそれを突きつける。
「見ろぉぉぉっ、あのふたりが人目もはばからずにイチャイチャイチャイチャイチャイチャイチャイチャするたびに壁を殴り続けて鍛え上げられた、このゴッドハンドをををををっ!! ……そうっ! 今の私は阿修羅をも凌駕するっ!」
「……そいつぁすごいな。どうだい? いっちょアタシとひと勝負してみないか?」
「えっ……?」
いきなりなんの脈絡も伏線もなく背後から肩をガシッと叩かれ……もとい鷲づかみされたゴッドハンド(笑)男子。
ギギギギッと効果音が聞こえてきそうな動きでゆっくり振り返ると、そこにいたのは──
「げえっ! リアル◯ュレックっ!!」
「誰がシュ◯ックだあっ!!」
燃えるように渦巻く赤い髪、学校指定の体操服から覗く薄緑色の肌。マッシブかつ均整の取れたプロポーション、彼方たち男子より頭ひとつ分高い身長。その額にバンダナを巻き、こめかみの上の方から一対の角が斜め上を向いて生えている。
「…………」
すくみ上がったDT男子たち全員に鋭い視線を注ぐ彼女は、十七人の魔物娘のひとり、C組のオーガ娘、サキ。ゴツい見た目とは裏腹に世話好きで気さくな奴だと、彼方は彼女と同郷であるナギから聞いていた。
「まっいいわ。ちょうど柔道部が休みで演武場が空いてるから、そこでゴッドハンドとやらを披露してもらおうか♪」
大きく発達した犬歯──というか牙を見せて、ニヤッと笑う。
ちなみに柔道部が休部しているのは、ホノカと甲介のマカップルに触発されたこの緑色の鬼娘が、パートナー探しのために体験入部し、腕試しと称して男子部員全員を問答無用かつ連続で投げ飛ばしたからだと言われている。
もちろん、彼女のお眼鏡に叶う者は一人もいなかった。
「ははは……冗だ──ぅえっ!?」
サキは彼方に詰め寄っていた男子の後ろ襟を無造作につかむと、返事も聞かずにその首筋を引っ張り、きびすを返した。強靭な筋肉に包まれた四肢と、豊かな胸と腰がうねる。
「ちょっ、ちょちょちょちょいっうおいっ!(きょろきょろ)うおおっ誰もいねえっ置いてかれたあああああっ!! ……ままま待てぇっ! さっきのはいわゆる言葉の綾であって必ずしもパンチ力が強化されたとか戦闘力が上がったとかそういう意味でなく逆境が人を強くするということを比喩的に表現したというかそのあのそのすすすすんません嘘吐いてましたハッタリかましてました調子こいてましただあああああやめてエロ同人誌みたく逆レされるうううった゛す゛け゛て゛お゛か゛あ゛さ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛〜んっ!!」
DT仲間にあっさり見捨てられ、抵抗空しくずるずる引きずられていくゴッドハンド(笑)男子。市場に売られるドナドナな仔牛めいたアトモスフィアが漂う。
そしてサキは廊下の端で振り返り、彼方に向かってウインクした。その口が「がんばれよ」と動く。
「……け、結局何しに来たんやあいつら」
そう言いつつも、彼方は片手を顔の前に立てた。感謝の意と、ついでに引っ張られていった仔牛の身を案じて。
なお、そのまま演武場に連れていかれたゴッドハンド(笑)男子は、投げの鬼スプリームと化したサキに一方的に九回も投げ飛ばされ、某金属生命体の中の人みたく全身打撲でグロッキー状態になったとか。
だが、これがきっかけでふたりの間に……
などということは全くなく、彼はDT歴を更新していくのであった。合唱もとい合掌。
<●>
明緑館学園女子寮、通称「撫子(なでしこ)寮」。ここ数年は寮生不在で閉鎖されていたが、今はこの世界にやって来た魔物娘たちの生活の場になっている。
三階建てで部屋数は二十。キッチン、バス、ランドリー、トイレは共用。なお、学園が昔女子校だった頃からのものなので、男子寮は存在しない。
「ううう……ああぁ……」
デート当日の朝、ナギは自室の中をうろうろと落ち着かなく歩き回っていた。
「う〜っ、もうすぐアイツが来やがるぅぅ……」
ナギたち魔物娘は人間の付き添いがいないと、学園の敷地外に出てはいけないと取り決められている。なので、今日は彼方が寮の玄関まで迎えに来ることになっているのだ。
「あー、もー、お、落ち着け、落ち着けアタシ。ちょっと外に出て遊びに行くだけだ。遊びに行くだけ──」
意識していないのに……否、顔が火照って胸がドキドキしているのは、思いっきり意識しているから。
「うー、がー、あー、うごごごご……」
それに気づいて頭を抱え、唸り声を上げても、約束した時間は刻々と近づいてくる。
昨日の夜、一緒に今日着ていく服を選んでくれた親友は、「用事があるから」と今朝から姿を見せてないし、ひとりだけだと心細さに拍車がかかる──
「レインは部長とショッピング行くって言ってたし……、サキの奴は休みの日は昼近くまで寝てるし……」
他の連中もそれぞれ予定があるだろう。「恥ずかしくて心細いから一緒に来てくれ」なんて頼めるわけがない。
コンコン──
「おはようございますナギさん。カナタさんが来られましたよ」
「ひゃいっ!」
部屋の外からノックとともに声をかけられ、ナギは弾かれたように背中を伸ばした。
ドアを開けると、そこには本格的なブリティッシュタイプのメイド服に身を包んだ一人の少女がいた。
ボブカットにしたライトブラウンの髪、ゴールデンレトリバーのそれに似た垂れ耳。エプロンの紐を結んだ後ろ腰のあたりからフサフサした尻尾が、手首には鳥の羽根が生えていて、ロングスカートの裾から覗く足先は鳥の脚を思わせる鱗に覆われている。
「お、おはよ……」
「はい、おはようございます」
その顔に柔和な笑みを浮かべる彼女は、十七人の魔物娘のひとり──E組のキキーモラ娘、イツキ。
母子相伝のメイドスキルを活かして撫子寮の舎監みたいな役割も務めており、清楚で物腰も柔らかく控えめ。一部では「嫁にしたい魔物娘不動のナンバーワン」とも評されている。
もっともこづかい稼ぎ程度のバイトしかやらない同級生の男子など、働き者の男性を好む彼女の眼中には全くなかったりするのだが。
「まあナギさん、とっても可愛い♪」
イツキは部屋から出てきたナギの姿を見て、両手をぽんと合わせた。
「うぎゃああああああっ! 言・う・なぁあああああ〜っ!!」
言われたナギは赤くなっていた顔を、更に真っ赤にして悲鳴を上げる。
しかしそのまま回れ右して部屋へ戻ろうとした彼女の肩に両手を置いて、メイドな魔物娘はその耳元でそっとささやいた。
「大丈夫、自信持ってください。今日のナギさんなら、きっとカナタさんをメロメロにできますよ♪」
「め、メロメロって……そ、そんな、しょんなぁぁ──」
恥ずかしさ、さらに二倍でドン。
単眼はぐるぐる回っているのに、呂律がちっとも回ってない。……上手いこと言った。
「それに──」
つぶやくようにそう言って、イツキは流れるような身のこなしでナギの前に立つと、その襟元に結ばれたリボンの曲がりを直した。
「ナギさんとホノカさんは私たちにとって、〝希望〟でもあるんですよ」
「……それってアタシらみたいな単眼種にオトコができたから、自分らも──って思えることか?」
「ええ、まあ……でも、それだけじゃないんですよ」
じっと見つめられて真顔になったナギに、イツキはゆっくりと首を振った。
彼女曰く、ナギやホノカが人間の男性と当たり前のようにお付き合いしているのを見せれば、魔物娘をいたずらに恐れたり、気味悪がったり、意味もなく敵視したりする方々の誤解を解くことができると。
「……で、アタシとホノカが〝希望〟ってわけ」
「はい♪」
にっこり笑みを浮かべてうなずくイツキ。
「大袈裟な……そもそも十七人しかいないアタシらに、何ビビってんだか」
少し頭が醒めたのか、腰に手を当ててフンと鼻を鳴らすナギだったが、その態度と表情には「悪い気はしない」と出ていた。
「そっか、うん、希望かぁ……」
さっきまで固まっていた背中の触手が、機嫌よさげにゆらゆら揺れ動く。
単純な娘であった。
<●>
「…………」
撫子寮の玄関で待っていた彼方は、イツキに連れられて降りてきたナギの姿に眼鏡の奥の目を丸くした。
「な、なんだよ…………に、似合わない──か?」
無言でじっと見つめられ、ナギは単眼を落ち着かなく左右に動かす。
彼女が着ているのは、襟や合わせ目、袖にフリルの付いた白のブラウスと、膝丈の裾がフレアになっているAラインの黒いシャンパースカート。その色味が長い黒髪と赤い単眼にぴったりマッチしていた。
だから──
「あ、いや、そうやなくて……えっと、なんちゅうか、その、ま──まあ、似合っとる、かな……」
「そ、そっか、に──似合ってるか……」
照れ隠しに鼻の頭を掻いて、あさっての方を向く彼方。ナギも顔を赤くしたまま、横を向いた。互いに目だけを動かして、相手の顔をちらちらとうかがう。
彼方の方はチェック地のカジュアルシャツにジーパン、その上から薄茶色のライダースジャケットを羽織っている。ゴスロリちっくなナギと並ぶとちぐはぐだが、お互い「持ってるもので目一杯お洒落してきました」的な初々しさがあって、なんか微笑ましい。
「……では、おふたりともいってらっしゃいませ」
そんなふたりをニコニコしながら見守っていたイツキに、耳元で「がんばって♪」とささやかれ、背中を押されて玄関を出る。
そして、寮の前に停めてあったサイドカーを見て、ナギの単眼がキラキラしだした。
「おーすげえ、鉄の馬だ……こ、これ、カナタのか?」
マジでライダーだった件。
「叔父さんのお下がりやけどな。バイク見るの初めてか? ……ほれっ」
投げ渡された半帽型ヘルメットを受け取る。ゴーグルはナギの単眼に合わせてスキー用のものに取り替えられていた。
「えっと、乗っていいのか? 乗っていいのかこれ?」
「ええで。そのために転がしてきたんやし」
サイドカーの側車をぺたぺた触りだしたナギに、彼方は苦笑しながら答えた。
「きししっ、馬車なんて乗るの久しぶりだ……」
「なんで馬車やねん」
車輪がついてて座席があって、(鉄の)馬に引かれているから馬車──という認識らしい。
「いいじゃんか。馬車でエスコートされるのは女の子の夢なんだから…………ちょっと、狭い、けど、なっ」
触手を髪の中に戻して、パッセンジャーシートに座るナギ。渡されたヘルメットをおっかなびっくり被る。
それを見て彼方もバイクにまたがり、グリップに引っかけていたジェットタイプのヘルメットを被ってバイザーを下ろした。
「ほな行こか、お姫さま」
「うむっ、よきに計らえ〜っ♪ ……ひゃあああっ!」
動き出したサイドカーに、ナギは嬉しそうに声を上げた。
さっきまでうだうだ悩んでいたのはなんだったんだと思われるほどの、切り替えの早さだった。
<●>
「……行っちゃった」
エキゾースト音を響かせて通用門を出ていくナギたちを寮の建物の影から見送り、ホノカは羨ましそうにつぶやいた。クリーム色の丸襟ブラウスの上から紺色のベストを羽織り、ボトムは裾にボアの付いたお気に入りのショートパンツ、薄紫色の髪はいつものようにバレッタでアップにして、脚はニーソとスニーカーという私服姿だ。
「まさか永野の奴、バイクの免許持ってたとは」
しかも初デートにサイドカーだなんて、なかなかやるわね……と、横にいた文葉が同じように小声で返した。こちらは桜色の膝上丈ワンピースに薄手のデニムジャケットを合わせ、髪は背中に流し、足元はホノカと同じくスニーカーを履いている。
「まあ目的地はわかってるし、彼方ならツーリングがてら遠回りするだろうから、電車で充分先回りできると思うよ」
ふたりの後ろでそう応えた甲介は、無地のロング丈長袖Tシャツとブラックジーンズというシンプルな格好。
……三人とも、ナギと彼方のデートを追っかける気満々であった。
いや、あと一人。
「あれ? ルミナさんは?」
「いつもの鎧着込んで来たから、フミハが『悪目立ちするから着替えてこい』って」
「あー」
サイクロプスやヴァルキリーが並んでいるだけで、十二分に目立つと思うのだが。
しかしホノカの言葉にその情景が容易に想像できて、なんとなく納得してしまう甲介だった。
「すまない。遅くなった」
噂をすればなんとやら。当のルミナが駆け寄ってきた。
クリーム色したブラウスに紺のリボンタイ、ベージュのロングスカート、足元は茶色のローファー。変装のつもりなのか髪の毛を一本のお下げにまとめ、赤いフレームの伊達メガネを顔にかけている。
まあそこまではいい。そこまでは。
「あんた、何持ってきたのよ……」
半眼になった文葉のその視線の先にあるのは、担がれたコントラバスケース。
ルミナはそれにちらりと目をやり、
「うむ、武器を隠して運ぶには楽器のケースを使うものだと、ある本に書いてあったのでな」
重々しくうなずいて、ドヤ顔を浮かべた。
「……なんの漫画読んだんだろ?」
「さあ……」
などと後ろでひそひそやってるマカップルをほっぽって、文葉が眉をつり上げる。
「ああもうっ、な、ん、で、いちいちそういうのを持ってくるのよっ!? このバトル脳はっ」
「失敬な! これはあのゲイザーが、万がいち人混みの中で暴れ出した時に備えて──」
「い い か ら 置 い て き な さ い っ!!」
「うう……っ」
眉間にシワを寄せて微笑む──当然目は全く笑ってない──クラスメイトに、さすがのルミナも気圧されてしまう。
さらに、
「差し出がましいとは思いますが……そういった大荷物を電車の中に持ち込むと、まわりの乗客から迷惑かられて蹴りを入れられると聞きましたよ」
少し離れたところから四人を見ていたメイド姿のイツキが、そっと近づいてきて口を挟んできた。
「だ、だがっ、魔物から無辜の人々を守るのが我が使命。鎧を封じた今、せめて武器がなくては──」
「その守るべき人間の方々との間に余計なトラブルを抱えるのは、戦天使としては不本意かつ不名誉なのではないかと思いますけど」
「うぐぅ……」
正論でぶった斬ってくる口上手のキキーモラに、ぽんこつヴァルキリーが勝てるわけなかった。
「ところでケースの中に何入れてきたのよ? ルミナ」
「剣道部で使ってる竹刀……」
「ひと昔前のスケバンかあんたは」
「……ナギちゃんに何か言ったの? イツキ」
「はい。ナギさんが自信を持てるように、虚実織り交ぜあれこれと♪」
<●>
郊外にある遊園地、更紗ファンタジアランドは休日もあって、大勢の人で賑わっていた。
「うおおおっ、すごい人混みだな〜。……お祭りかなんかあるのか?」
「あ〜まあ、確かに毎日お祭りしてるとこっちゅうのも、当たらずとも遠からずやけどな──」
駐車場にサイドカーをとめて、チケット売り場でフリーパスを購入。もの珍しさにまわりをキョロキョロするナギに、彼方は苦笑混じりに答えた。
もっとも異世界の魔物娘である彼女の反応は、さらに斜め上にいくのだが。
「毎日お祭り……う〜んさすが日本、未来に生きてるわ〜」
「いやいや、そうやなくて」
などと言い合いながら、ふたりは入場ゲートをくぐり、人の流れにのってカフェやショップが軒を連ねるアーケードの下をそぞろ歩く。
しかし、おのぼりさん丸出しな調子であたりを見回し、背中の触手をうねうねさせるナギに気づいた周囲が、徐々にざわつき始める。
え〜っ、あれ何? 魔物娘?
マジマジ!? うわーホンモノだ。初めて見た……
魔物娘接近遭遇なうw
触手ヒトツ眼、マジキモいんですけど──
「…………」
元いた世界──住んでいた親魔物領でさえも、幾度となくこの手の視線に晒されてきた。ゲイザーの自分を初めて見た人がどんなリアクションをするかは分かっていた……つもりだった。
だけど、
「ねえねえ隣にいるのって、ひょっとして〝アレ〟のカレシ?」
「うわ趣味悪ぅ〜っ。女子に相手されないから魔物娘にってか?」
「……っ!」
見ず知らずの女子グループに指差されて好き勝手言われ、我慢できなくなったナギは、思わず「黙れお前ら」と念を込めて邪眼を向けようとした。
「ナギ」
「ひゃおっ!?」
……が、横にいた彼方にいきなりお尻を軽くはたかれてとび上がる。
「い、いきなり何すんだカナタっ!?」
「ええから胸張って前向いて、当たり前って顔しとけ。なんも悪いことしてへんねんし」
「け……けど、あいつらカナタのこと──」
「知り合いでもなんでもない赤の他人をいきなり指差しでディスるような連中なんか、『ワタシラ人トシテノ常識ゴザイマセ〜ン』って自分で宣伝しとるようなもんやから、無視や無視」
ワザと聞こえるようにそう言うと、彼方は眉を吊り上げる女子たちをメガネの奥からちらりと横目で見た。
「何よあれっ? 感じワル〜っ」
「ヒトツ眼女と付き合うなんて頭おかしいんじゃない〜?」
「行こ行こ」
彼女たちは口々にそう言うと、これ見よがしにひそひそやりながら離れていく。
「お、おいカナタ……いいのかよ?」
「さっきもゆうたけど、ほっといたらええねん。かかわり全然ない奴にイチャモン付けられても、その時だけやしな。……それよか、さ〜どれから乗ろか?」
──ま、みんな甲介からの受け売りやねんけどな……
何事もなかったかのように流すと、彼方はポケットから出したスマートフォンを操作してFT(Floating Touch)ディスプレイを立ち上げ、園内マップを表示した。ナギは横からそれを覗き込む。
「おー、いっぱいあるな。アブダクション──だっけか?」
「アトラクション、な。……そういや、ナギのおった世界に遊園地とかなかったんか?」
「ん〜、こんな風に毎日やってる場所はなかったけど……」
苦笑を浮かべて問いかけてきた彼方に、ナギは人差し指を口元に当てて上を向いた。
「街のでかいお祭りで人力の回転木馬とか、水車の力で回る観覧車とか乗ったことあったなぁ。……あ、あとローラーコースターとかも」
「ふーん……ほな、一発目はこっちのコースター初体験、行ってみよか?」
「お、いいね。ドンと来いだ」
彼方のサイドカーにも興味津々だったし、もしかすると乗り物に乗るのが好きなのかもしれない。
しかしナギの知る〝ローラーコースター〟は、引っ張りあげたトロッコに乗って坂の上から線路をアップダウンしながら一直線に滑り落ちるという、単純かつ原始的なものだ。
当然、ここ更紗ファンタジアランドが誇る絶叫スパイラルコースター「スター・ドライブ・ライド」が、そんなラクダの背中(キャメルバック)だけという〝ヌルい〟代物であるわけもなく……
「え? ナニコレ? なんでこんなにがっちり身体固定するんだ? てゆーかこの乗り物、座席のまわりとか足元になんもないんだけど……え〜っとなんか仰向けで上に上がってるってちょっと高い高い高いっ!? ままま待て待て降りる降りる降りるまだ心の準備があああああっ! ……お? あ? え? ぎゃあああああああ〜っ落ちる落ちる落ちるぅううううっぐおおお触手ちぎれるちぎれるちぎれるぅうう〜っひぃいいいいいいい〜っ逆さになってる景色回ってる頭に血がのぼるぅうううう〜っぎゃああああヤダヤダヤダヤダとめてとめてとめてえええええっごごごごめんなさい魔王さま主神さま明日からタマネギ残さず食べますルミナのことへっぽこヴァルキリーだなんて言いませんだからお願いた゛す゛け゛て゛ぇええええええええ〜っ!!」
ごごごごごごごごごこぉおおお────────っ!!
「お、おおおお前らっ、ぜっ、全員──全員マゾかぁああああ……っ」
「んな大袈裟な……」
単眼ぐるぐる涙目、息も絶え絶え、半分腰が抜けた状態でふらふらと出口から出てきたナギにしがみつかれて睨まれて、彼方は肩をすくめて半笑いを浮かべるのであった。
<●>
「あーもうなんかマジムカつくあのメガネ関西弁っ」
「何あの態度っ? ちょーキモっ」
「キチってんのよあいつ。バケモノ女なんかと付き合ってるし」
先ほどナギと彼方にインネン付けた女子たちが、未だ憤懣やるかたなしといった調子で悪口を垂れ流しながら歩いていた。派手めのメイクに茶髪頭、着崩したギャルカジ……という、いかにもな三人組である。
「メイなんとか学園の中から出てこなくていいのに、あいつら」
「ああいうキチ男がいるから調子こいてんのよっ。……ホントウザい。人類の裏切りも──」
「ちょっストップ! マズイよそれ言ったらっ」
「そうね〜、そんなこと大声で言ってたら、魔物娘を怪獣怪人扱いしてヒーローごっこしてる連中のお仲間認定されちゃうわよ〜♪」
「「「……!」」」
知らず知らずのうちに、おしゃべりのテンションが上がっていたらしい。背後からかけられた声に、ギョッとして振り返る。
後ろにいたのは、彼女たちと同じ年頃の少女が二人。
ひとりは気の強そうなワンピース姿の少女、もうひとりはメガネをかけた金髪碧眼の少女──
「お前たち、園内でゲイザーとツガイの男を目撃したようだが、そいつらは今どこにいる? 答えろ」
「ちょっとルミナ……それ人にものを訊く態度じゃないわよ」
「む、そうか。……頼む、教えてくれ。ヤツを倒すことができるのはこの私だけだっ」
「「「…………」」」
──こっ、コイツやべええええっ…………ガチでマジだ……っ!
せーだいに誤解されたなんて露ほども思わず、握った拳を胸に当て真剣な表情で懇願する金髪少女。連れの方はその後ろで「あっちゃ〜」と額に手をやった。
二手に分かれてナギたちを探す、文葉とルミナのコンビだった。
「ああああっちあっち!」「あっちの方っ!」
戦天使の眼光に圧された三人は、あわてて今来た方を指差すと、かかわり合いになるのはゴメンとばかりに走り去る。
その背中を見送った文葉は溜め息を吐くと、スマートフォンに表示した園内マップを覗き込んだ。
「あっちだと、『ラビリンスX』あたりに行ってるかなあ……」
3D映像とプロジェクションマッピング、そして特殊メイクを施した生身の演者たちが売りの迷路型ホラーハウス──お化け屋敷である。
「よし、急いでそのエックスとやらへ行ってみよう」
「言っとくけど、中にいるモンスターはロボットか人間の役者さんだからね。間違っても殴ったり蹴とばしたり壊したりしないでよ」
さすがにそこまで非常識ではないとは思うが、一応クギを刺しておく。
「ふむ、倒してはいけないのか……いわゆる縛りプレイというやつだな」
「いや、そうじゃなくて」
……前言撤回。
<●>
一方、ホノカと甲介はというと──
「楽しかった。ね、コースケくん♪」
「ははは、そうだね……」
喜色満面のホノカにそう言われて、甲介は若干疲れたような笑みを浮かべた。
隠れた人気アトラクションである大型メリーゴーランド「カルーセル・オブ・ファンタジア」の、レトロな装飾とオルゴールに合わせてゆっくり上下しながら回る木馬の動きをいたく気に入ったホノカが、それに十回も乗り続けた挙げ句、係員をつかまえてその構造や仕組みについて根掘り葉掘り質問しだしたのに付き合っていたからである。
「ま、実際に尋ねてたの僕だけどね」
「うう……ごめん。でも、初対面の人に話しかけるの、苦手だから」
しかし応対してくれたメンテナンス担当の人が、甲介の後ろから顔を覗かせじっと見つめてくるサイクロプス──ホノカにビビりながらも詳しく教えてくれたので、彼女も充分満足できたようだ。
ちなみに「メリーゴーランド(メリーゴーラウンド)」と「カルーセル」、厳密にいうと木馬が上下に動かないか動くかで呼び分けるのだとか。
「でもいいのかなあ? 彼方とナギさん探さなくて」
「フミハたちには悪いけど、ナギちゃんが行きそうなアトラクションはだいたい予想つくし……」
甲介にそう答えると、ホノカは腕を絡めてその身体をくっつけてきた。「だから、もうちょっとだけコースケくんとふたりっきりでいたいな♪」
「ホノカちゃん……」
まんざらでもない表情を浮かべつつ、頭に空いた手をやり照れる甲介。
ヴヴヴヴヴ──ッ……
「あ、フミハからメール来た。えっと、『イチャついてないであいつら探してる?』 …………」
「……読まれてる、ね」
<●>
「みんな絶対おかしい! なんでわざわざ高い金払ってあんなコワイ目にあいたがるんだっ?」
園内にあるオープンカフェで、ランチタイム。
ひとつ眼の魔物娘をひそひそうかがう周囲の視線もなんのその。追いマヨネーズしてもらったホットドッグ型のサンドイッチをぱくつきながら、ナギは彼方に向かって熱く文句を垂れていた。
「……とかなんとかゆうてるけど、ジブンも3Dライドとかフリーフォールとか急流すべりとか、絶叫系ひと通り乗り倒してたやん」
「そ、それは、その……の、乗っとかないと、なんか負けたような気がして、さ」
「何と戦ってんねん、お前──」
コワガリなくせして絶叫マシン乗りたがる奴って、いるよね〜っ。
もしゃもしゃと口を動かし目と触手の先っちょを逸らすナギに、彼方は生暖かい視線を向けてツッコんだ。
そして紙コップに残ったコーヒーを飲み干すと、トレイを持って席を立つ。
「ほな、そろそろ次のとこ見に行こか? 並ばんでええように予約も取っといたし」
「ん、今度はなんに乗るんだ?」
指についたマヨネーズを舐めとりながら、ナギが尋ねてきた。
「乗りモンやないで。……ま、行ってみてのお楽しみ、や」
「お、おう……」
すっと差し出されたその手をつかんで、ナギはゆっくりと立ち上がった。
<●>
「ははは……やった、やったぞ…………魔物の巣食う迷宮を突破したぞっ! これもみな主神様の御加護の賜物っ!」
「……あ、あんたと一緒に、にっ、二度とおばけ屋敷に入らないからっ」
ホラーハウス「ラビリンスX」の出口に、興奮で顔を真っ赤にして勝ち誇るルミナと、げんなりした表情を浮かべて肩で息する文葉の姿があった。
そんな二人には「ラビリンスX 最速制覇認定証」が贈られていた。変に気合を入れたルミナが文葉を引っぱって大股で真っ暗な迷路に踏み込み、出てくるお化け役たちを「しょせんは紛い物! ヴァルキリーたる私を止めれるものなら止めてみろ!」と背中の翼を広げて威圧。ホラーハウスの雰囲気やらなんやかんやを一切合切無視して、出口まで通常十五分以上かかる迷路をわずか五分でゴールしたからである。
……要するに、力技だった。
<●>
座席の背もたれに身体を預けると、ぐっと後ろに倒れて仰向けになる。
首を巡らすと、周囲には巨大なドーム状の天井──360度スクリーンが広がっている。
「なんか椅子っていうより、ベッドみたいだな、これ……」
「そのまま寝落ちったらあかんで。せっかく来たんやさかい」
何度もリクライニングを確かめるナギに、隣の席に座る彼方が声をかけてきた。
「わ、わかってるって。ぷらねた……なんだっけ?」
「プラネタリウム、な。ドーム天井全体に星空を映すんやで」
「ふうん……」
素っ気ない返事で答えるナギ。
星空なんて、草っ原に寝っ転がってりゃいつだって見れるじゃん……と口の中でつぶやきながら、彼方が指差す方を見上げる。
全天周シアター「スター・ミュージアム」。プラネタリウムだけでなく3D映画なども投影されるのだが、ライド系のアトラクションを期待していたのか、彼女はいまいち触手──もとい食指が動かないようだ。
──けどまあこっちの世界は夜もムダに明るいから、星なんてちらほらしか見えないしなぁ……
ナギたちがいた世界では、飛行能力を持つ魔物娘によって、自分たちの住んでいる大地が途方もなく巨大な球体──世界で一番高い山が、ひと抱えもあるボールについた砂粒にたとえられるようなものであることが発見されてはいたが、さすがの彼女たちも気圏を越えて宇宙(その概念はあった)に飛び出すことはできず、天動説と地動説の決着も全くついていない。
ほどなくして操作員のアナウンスとともに、投影が始まった。低いところに更紗市の街並みを精緻に描いたイラストが、向かって右側に太陽の位置を表す丸い光が映し出される。
「では、時間を速めて先に夜を迎えましょう。今日の日の入りの時刻は──」
階段状の傾斜がついた客席の正面が「南」、左側が「東」で右側が「西」、頭の後ろが「北」。〝太陽〟が西へと沈み、それと入れ替わるように街中でも見られる明るい星──金星や木星が瞬きはじめた。
「おー、なんかそれっぽい」
「やろ?」
「……それでは今から街の灯を消して、皆さまを星の世界にいざないます。私が五つ数えるまで目を閉じていてください」
都会の夜空でも目立つ星々の説明が終わり、ここから本番である。
その気になれば暗闇を見通すこともできなくはないが、ナギもアナウンスに従ってその大きな目を閉じた。
「──さん、に、いち。……では、ゆっくり目を開けてください」
まぶたを上げると、目の前に星の海が広がった。
「や、よかったぁ……やっぱ投影時間フルに使こて、夜明けまでやってくれると値打ちあるわ〜。……ん? ナギ、どないした?」
「…………」
四十五分の投影が終わって明るさが戻り、伸びをしながら身を起こした彼方は、隣にいるナギの様子がおかしいことに気づいた。
リクライニングして寝転んだまま、右手の甲で目を隠し、何かを我慢しているかのように肩を震わせている……
喰いしばった歯の間から、かすかに嗚咽が漏れる。
「…………父さん、……か、あ、さん──」
「ナギ、お前……」
その閉じた目から、涙が一筋流れた。
「あ、あの、お客さま……次のお客さまが入ってこられるので、そろそろ──」
案内係の女性が、声をかけてきた。
彼方はナギの頭にそっと手を置き、空いた手を顔の前に立てて頼み込んだ。
「も、もうちょっとだけ……ギリギリまで待ってくれへん? かんにんやけど……」
<●>
夕焼けが、あたりを染め始めた。
遊園地デートの締めは観覧車がテッパン……というわけで、プラネタリウムを出たナギと彼方は、ファンタジアランドのシンボルでもある大観覧車に乗り込んだ。
ゴンドラの中で、向かい合って座る。
「まさか星空見て、ホームシックになるてなぁ……」
「うぅ〜っ忘れろっ! 今すぐ忘れろっ!」
脱力したようにつぶやく彼方に、ナギは目と顔を赤くしたまま叫んだ。彼女曰く、元の世界では十六歳で一人前。だから今さら親が恋しいなんて、単なる気の迷いみたいなものだ……と。
ちなみに第二世代以降の魔物娘が早期の独立を促されるのは、長い間実家に居座られると母娘で一番身近な男性──父親を〝共有〟する事態になりかねないからだとも言われている、らしい。
「……けどな、ナギ」
「あん?」
「生きてたらいつかは会える──そう思っとかんと、ホンマに会われへんようになるで」
「な、なんだよ急に……」
メガネをはずし、いきなり真顔になって見つめてくる彼方に、ナギは目を瞬かせた。
「魔物娘って人間の倍以上の寿命あるんやろ? せやったらその間に向こうへ帰る方法とか、それが無理でも連絡とる方法とか見つかるんちゃうか? そない思た方がナンボか気ぃ楽やで」
だが、これまでフィクションでしか魔法が存在しなかったこの世界で、はたしてそんなものが見つかるのだろうか?
それでも──
「……なんだよ〜、アタシらにさっさと元の世界に帰ってほしいってか?」
「い、いや、そないな意味でゆうたんやなくて、その──」
一転、しどろもどろになる彼方に、ナギはぷっと吹き出した。「きししっ、大丈夫だよ。この世界にはホノカや仲間たちもいるし、それにカナタ……オマエもいるしな」
「ナギ……」
希望は持ち続けよう。全てはそこから始まるのだから。
「……それにアタシ、この世界でやりたいことがあるんだ」
しばしの沈黙のあと、ナギが口を開いた。
「へ〜、なんや?」
「えっと……あ、バカにするなよ」
「せえへんせえへん」
「ホントにバカにすんなよ……」
彼方の顔を睨みつけて念をおし、ナギはおもむろに息を吸うと、
「宇宙飛行士」
「は?」
予想の遥か上空を斜め上に音速でカッ飛んでいく単語に、彼方の目が点になった。
「ほら〜っ、やっぱりバカにしたっ」
「し、してへんしてへんっ。……ちゅうか、なんでまた?」
「え? だって一度でいいから宇宙ロケットってのに乗ってみたいし……それに魔物娘初の宇宙飛行士って、なんかカッコよくないか?」
「なんやねんその志望動機……」
「希望は持ち続るモンだろ? だ、か、ら──」
きししっと笑ってそう言うと、ナギは席を立って彼方の隣に腰を下ろした。
「協力しろよな。イヤだって言っても、オマエはもうアタシのものなんだからなっ」
「お、おい……」
彼方の腕に自分の腕と触手を絡め、ニマッと笑みを浮かべる。
赤い単眼に見つめられ、一瞬身体を強張らせた彼方は、ふっと表情を緩めた。
「はー、やっぱおもろいわお前。……ええで、とことん付きおうたる」
「なんだよそれ……」
そう言いながら、二人は互いにゆっくりと顔を近づけていき……
「カナタ、アタシを好きになれっ」
「……もうなってるがな。それってゲイザーの〝お約束〟かなんかか?」
「ち、ちげーしっ!(赤面) てゆーかどこでそんなコト知ったんだオマエっ!?」
……などと言い合いながら、唇を合わせた。
はじめは軽く、次に強く、さらに深く──
「……ん、ふぁ……っ」
半開きになったナギの単眼が、怪しく光る。キスで無意識に魔物娘としての本能が目覚め、その淫気にあてられた彼方もまた、無意識に昂ぶっていく。
「ちょっ、か──カナタっ、強引……っ」
身体を引き寄せられて胸とスカートの中を弄られ、ナギはくぐもった声を上げた……
…………………………………………
「お客さ〜ん、降りてくださ〜い」
「「……!? うわぁああああああ〜っ!!」」
係員に棒読みっぽい口調で声をかけられて、我に返ったナギと彼方は悲鳴じみた声を上げ、はだけた衣服を押さえてあわててゴンドラからとび出した。
のちにその係員はこう語った。中でキスするカップルはよくいるけど、コトに及ぼうとするのを見たのは初めてだった……と。
そしてふたりは観覧車乗り場の前で、各々の親友とばったり出くわしてしまう。
「あ……な、ナギちゃん…………や、やっほー」
「……や、やあ彼方」
「ホノカにコースケ!? なんであんたらがここに?」
さらに反対側からも、聞きおぼえのある声が。
「ようやく見つけた……貴様、今までどこで何をしていた?」
「ちょっとルミナっ! 気付かれずにって言ったでしょっ!」
全員集合。偉そうに睨みつけてくるルミナ以外、皆バツの悪そうな顔をして目を逸らす。
「フミハたちまで!? これっていったい……」
「まさかお前ら、ずっとあとつけてきとったんかい……つーか止(と)めろや甲介っ」
「ゴメン、ちょっと心配になってさ──」
「私はお前が人間に危害を加えないか監視しに来ただけだ。けっしてデートを覗き見しに来たのではないっ」
「墓穴掘ってる自覚……ないわよね、ルミナ」
「「…………」」
ベタなことする友人たちに、互いに顔を見合わせると、ナギと彼方は同時に肩を落として溜め息を吐いた。
そして、クスッと笑い合うと、
「なんか食うて帰ろか、ナギ」
「そだな……」
寄り添って手を繋ぎ、入場ゲートの方へと歩き出す。
「ま、待てっ。今度は逃さんぞっ!」
「このあとどうしようか? ホノカちゃん」
「せっかくだからわたしたちも、観覧車乗っていこうよ。ね、コースケくん」
「おいこらそこのバカップル…………ってちょっとルミナっ! ひとりで先行かないっ! こら〜っ! そこでいきなり羽根広げるなぁっ!」
彼方が幼い頃両親と死別し、叔父夫妻の家に厄介になっていることをナギが知るのは、もう少し経ってからである。
なお、後日ファンタジアランドから明緑館学園に苦情が入り、ルミナはしばらく出禁になった。
to be continued...
─ appendix ─
メリーゴーランドにて。
ルミナ「ふふっ……作り物とはいえこうして馬にまたがると、戦天使としての血が騒ぐな。……さあ勇者たちよ! 導き手にして轡を並べともに戦う者──ヴァルキリーたる我に続けえええええっ!!」
ノリのいい子どもたち「「「おぉ〜っ!!」」」
その父親「うわぁあああああっやめろおおおおおっ! うちの子をヴァルハラへ連れていかないでくれえええええええ〜っ!!」
文葉「マニアだ……北欧神話マニアがいる……っ」
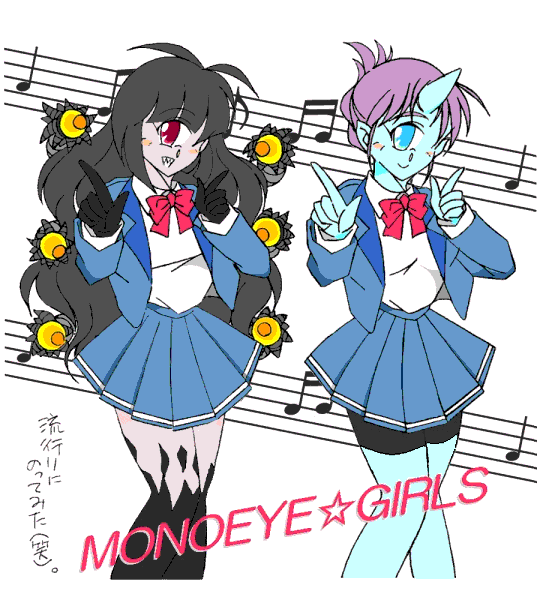
22/10/10 10:54更新 / MONDO
戻る
次へ