2話:バカがあいつであいつがバカで
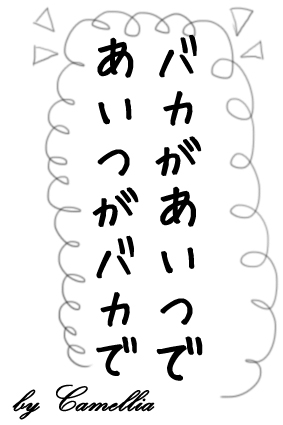
「平和じゃあ……」
ブランチ一歩手前の時間帯で、窓辺に面した仕事机に突っ伏した少女がつぶやく。顔を机の表面に向かって伏せているので、若干もごもごと鈍い発音になっているが何となくそう聞き取れる。
すっかり春の陽気になった温かい六月の時期になってくると、仕事もせずにぼんやり日向で動かずにいるだけでも十分なくらい時間の経過が早く感じる。本当に依頼や仕事が無ければそれだけで数日経過してしまうくらい。
「平和は良い。何もしたくなくなる。この恒久の膣……秩序に乾杯」
頭はなおも突っ伏したままで、左腕だけ頭よりも高く掲げてサムズアップをする。一体どこの誰に向かって感謝しているのは見当もつかない。
「ぐでんぐでんですねユナさん」
背後にある台所のほうから聞き知った秘書の声が耳に入る。
のどかな昼の陽気と同じような、それでいてゆっくりしたい気持ちと競合しない当たり障りの無い音声が脱力と癒しを加速させた。
ジャーと水道から水を流す音がするので洗い物なり何なりしているのだろう。できる秘書を持つと非常に誇らしいものだ、とユナは心の中で呟いた。
「たまにはハードボイルドもお休みしないと疲れちゃうのじゃー。だからいいのじゃー」
突っ伏した状態から顔だけ右に向けた。右目左目の順に腕から黒一面の視界から見慣れた事務所の風景に視点が移ると同時に、鼻腔をなんともかぐわしき甘美な香りがくすぐる。
思わずユナは鼻から大きく息を吸い込んでから、むくりと上体を起こした。
直後、有能な秘書が台所から声をかける。
「ユナさーん、ココアできましたよー」
「おぉ! さすがカメリア、気が利くのう!」
トレーで運ばれてくる甘味の誘惑に負け、だらだらとしていた先ほどとは打って変わってユナはバネのように飛び起きた。
カメリアの持って来た湯気も立っているアツアツのカップに手を伸ばそうとした。
その時。
「たのもー!」
「あばかーむ!」
それはもうびっくりするほどの勢いで、蹴破ったのかと勘違いするほどに大きな音を立てて二つの声が飛び込んできた。元気の良さと少女とおぼしき声であるため、訪ねて来た者の正体を想像することは容易であった。
ちなみに肝心の所長と秘書はどうなったのかといえば。
「うひゃあ!」
予想外の招かれざる客が来たことで面食らって盛大にトレーを傾けてしまい。
「ウボァー! 熱っ、甘っ! おいこらカメリアッ!!」
「ひゃああああユナさんすいません!!」
ユナが二人分の甘い熱湯と胸の辺りから思いっきり浴びることとなった。
手で体にかかったココアを熱そうに払いながら、かたやカメリアは慌てふためきながら手近な布でこぼした床を拭き取りはじめた。
「おー、なんだか騒がしいですぞお姉ちゃん」
「にぎやかなのは良いことです、妹」
相談所とは思えない喧騒を従業員達が演じているなか、訪れた二人の少女は非常に冷静かつナナメ上からの意見をお互いの顔を見ながら発した。
甘ったるい騒動が治まるまでの間、その場でニヤニヤしながら珍しいものを見るように傍観する展開は、その後2分少々続くことになる。
◆ ◆ ◆ ◆
「で、アレじゃ。わしがここの所長のユナカイトじゃ。こっちは秘書のカメリア。なんか悩みがあって来たんじゃと思うが、何でも言っていいぞ。あとドアは静かに開けろ」
先ほどのやたらめったらうるさい展開がウソのように、できるだけいつもの冷静さを取り繕ってユナは話した。
しかし、応接室のイスに座っているが、首にはふわふわした淡いピンク色のタオルがかけられ、小さな体からは石鹸の香りが漂っている。ココアを洗い落とすために軽くシャワーを浴びたという点のみがいつもと違っているくらいか。
小声で『わしの玉のようなお肌がヤケドしたらどうするんじゃアホ』とか、その横から『すいません……』という掛け合いが聞こえてくる。
「なんでも良いって言っておりますぞお姉ちゃん」
「なんでも良いなら思い切って言ってみませうか妹」
対面にいる二人は互いの顔を見合わせて、またユナのほうを見ると、なんとも掴みどころの無い言葉を飄々と言った。
ドアをぶち破って入ってきたのはゴブリンの姉妹だった。顔とか、赤髪を耳の脇でそろえたような髪型はまったくと言っていいほど同じだが、微妙に姉のほうが身長が高いので見分けるのは容易だ。
「じつはですね」
両手をヒザの上に置き、まず頭一個分背の低い妹が切り出した。
「お姉ちゃんがバカなんです」
「いえ妹がバカなんです」
即座に真顔で姉のほうも似たようなことを言う。意外だったのか、妹のほうはそれを聞いてむすっとした顔になり、姉に言い返した。
「なんと、お姉ちゃんも相談事があるから一緒に来たというのに、そんなことだったんですかバカ」
「何を言う。前々から妹はバカだとは思っていましたが、まさか自分だけがバカではないと思っていたのですかバカ」
バカがゲシュタルト崩壊しそうなほどバカバカ繰り返して、半分ケンカのように言い合っている姉妹。
しかし、それも本気でバカ呼ばわりしているというよりは、むしろ気の合う友達同士が馴れ合い的にバカバカ言っているそれに似ている。お互い中途半端に敬語で話しているから余計に面妖な光景に他ならない。
「わかった。お前ら二人ともバカなんじゃな」
用件も内容も非常に単純なものだな、と思いつつ姉妹漫才を眺めていたユナが間に口を挟んだ。とりあえず目の前の二人がどっちもバカなのは理解できた。
非常に失礼な言い草であるが、最初から一連のやり取りを見ていると自然にそういう意見がこぼれてしまう。
「あの、どうしてその……バカであることについて相談にいらしたのか、理由があればお願いしたいのですが」
用件とはいえ客に対して“バカ”をストレートに言うのはさすがにまずいと思ったのか、横に控えていたカメリアは言いにそうに言い放った。わりとそういうことについては客だろうが目上の者だろうが関係なくストレートに言うユナにとって、遠まわしにやんわり言うのはあまり気に食わなかったのか微妙に不服そうな顔をした。
当のバカを自負する赤髪のゴブリン姉妹は、自負するとおり特に気にする様子も無く、もう一度互いの顔を見合わせると何か思うところがあったのか、首を小さく縦に振った。
そして、先にまた妹が口を開く。
「この間、友達の男の子に盛大にバカにされました。お姉ちゃんが」
「いやいやあれは妹も入っていましたから。普通に妹もバカにされましたが」
両者一歩も持論を崩さずに、頬を膨らませつつまだ丁寧な口調でい言い合いを続けた。
話が進むどころか堂々巡りになってしまいユナは呆れて半笑いになったが、横からカメリアが仲裁するようにカメリアがまたそこにやんわりとした口調で言葉をねじ込む。
「その時の状況を詳しく教えてもらってもいいですか?」
頬を膨らませて正反対の方向を向いていた姉妹は、それを聞くと不服そうに互いの顔を見合わせて。
「いいよー」
「めいよー」
声だけはケンカ前と同じ調子に戻った。
――――――――――――――――――――
――――――――――――――
――――――――
――――
「なぁ、知ってるか? 星っていうのは空の天井に貼り付いているんだぜ」
いかにも美容に無頓着そうなボサボサ頭の少年が、空を仰いで指差しながら言った。
満天の星空とでも形容すれば良いだろうか。暗い帳のそこかしこに淡く、絶えなく光を発する星の光景。
遮る物など一切存在しない大パノラマの中心に立ち、すべての世界を統べたような自信のある顔で言った。
「なるほど、じゃあ星が光っているのはきっと天井で燃えているからなのですね」
少年のななめ後方で、同じく空を仰いでいた同じくらいの背丈のゴブリンの少女は、その自信に続けとばかりにそんなことを呟く。
すると、その隣にいた若干背の高いもう一人のゴブリンの少女が続けた。
「何を言っているのですが妹。天井で燃えたら延焼して空が落ちてきてしまうではないですか」
「空が落ちるとはとても詩的な表現ですが、そもそもそこで空の天井が燃えると考えるのが既に間違いなのですよお姉ちゃん。耐火性の魔法障壁が張ってあるか、モルタルだと考えるのが妥当な判断です」
「お前らホントにゴブリンかよ……」
気がついたら完全に話が着いていけない方向に流れていってしまった姉妹を見て、少年は呆気に取られた。まだ彼もそんなに多くの人生経験を積んでいないので、きっかけとなった自分の言葉以上に彼女らの言っている話に着いて行けない。
第一、大人になっても見た目どおりの単純というか幼い思考を持つのがゴブリンである。
互いに丁寧口調で不毛な禅問答を繰り広げる頭の良いキャラかと言われたら、全力でノーである。
実際それが目の前で起こっているのだからなんとも言えない。
「(そういえばこの二人って何歳なんだろう)」
見てくれは自分と同様の身長なり見た目をしていたので今まで特に気にしなかったのだが、ここに来てそのような根本的な疑問に立ち返った。まぁゴブリンなので年上かもしれないし年下かもしれないが。
「本物のゴブリンです。たしかに空が落ちてくるなんて発想するお姉ちゃんはアレかもしれませんが」
「む? それは妹が勝手に『星は燃えている』なんて言い出したからですよ。さも自分で見たかのように語って。そもそも星が燃えているって何ですか一体」
自分が間違っているのなら、それを理論立てたそっちのほうが間違っているのではないか、と姉のほうは不服そうな態度で妹に言い寄った。もちろんソレに乗りかかったのも彼女だが。
妹のほうは妹のほうで、軽く溜息をつくと見下したように首を横に振る。
「可能性の一つとしてボケてみただけです。便乗してツッコミ入れたおねえちゃんが単純なだけです
「またそうやって姉を小馬鹿にして。バカって言ったほうがバカなんですよ、このタコ助」
「何言っているのですか。単純とは言いましたがバカとは言ってないですよバカ」
罵り合いが発展するうちに、内容のレベルが頭良さげなものから次第に低俗な話題に変貌してきた。どんどんバカという単語が増えてきている。
でも、まだまだ落ち着いた物腰は崩さない双方。ここまで来ると賞賛ものである。
ある程度話が進んでくると、今度は辞書でも引かない限りわからないような非常に難しい単語で遠まわしな罵り合いが始まった。
数百年前の世界にでも来てしまったのかな、なんて思ってしまうくらい、さらに話に着いて行けなくなった。
「(やっぱりこの二人はゴブリンじゃないと思う)」
姿形と服装がゴブリンとまったく同じの別の生き物を流し目で眺めながら、少年は首をかしげた。
――――
――――――――
――――――――――――――
――――――――――――――――――――
「……と、いうことがあったんです」
「いやいやいやいや! 男の子関係ないじゃろ! 二人で勝手にバカにし合っただけではないか!?」
話が終わるや否や、ユナは速攻でツッコミを入れた。
そこに至るまでに相当な理由があるのかと思ったが、そんなことはなかった。
いたく真剣な様相で妹は当時の情景を詳細に語り、横では姉が『あの時はそんなこともあったなぁ』とばかりに目をつむり、懐かしむように眉をひそめてうんうんと大きく頷いていた。
非常にぶっ飛んだ、かつ単純な悩みであったのでユナは逆に頭を抱えた。色んな意味で。
これについて話題を振ったカメリア本人は、どう反応して良いものかわからず、ただただ苦笑いを浮かべていた。
「なので、どうすればいいでしょうか」
目を見開いて、姉がまっすぐユナに向かって言った。
漠然としすぎている質問を受けたユナは、あごに手を当てながら考える。すると、隣で苦笑いしていたカメリアがはっとした顔になってユナに耳打ちした。
「ユナさんユナさん、例えばこういうのはどうでしょうか……」
「ん?」
上半身を傾けて、もふもふしたヤギっぽい耳に小声で何かを吹き込んだ。
はじめはくすぐったかったのか聞きながら耳をぴこぴこ動かしていたが、話を聞くうちに内容に集中したのだろう。耳の動きは止まって、今度は首を上下に動かしていた。
そして、ニヤリと悪人みたいな笑みを浮かべた。
「ほー、ほうほう、その発想は無かった。面白そうじゃの! そんじゃあカメリア、準備はまかせたのじゃ!」
「わかりましたー♪」
左手で格好良く指を鳴らすと、カメリアは敬礼をして早走りで別の部屋へと走り去った。
何が起こるんです? といった具合にお互いきょとんとして顔を見合わせる姉妹に向けて、確信めいて言い放つ。
「なに、二人がバカではないという証明の手段を用意しよう。きっとそれが解決に繋がるはずじゃからな。ふふふ」
柄にもなく所長は不敵に、静かに笑う。まったくその後の予想ができない姉妹はやっぱり不思議な顔で首をかしげた。
その直後、カメリアが応接室に戻ってきた。いやに早い帰還だったが、有能と言うべきだろうか。
手には大きめのクリーム色をしたスケッチブックを抱えていた。
「さささっ、お二人ともこれをご覧になってください!」
くるんとクイズ解答者みたいに手元のそれを一回転。縦に回して上下が逆になった状態で、さっきまで後ろになっていた面が表側になる。
そこには『6×3=?』と書かれていた。なんてことはない。通常のかけ算の計算式である。
だが、これこそがカメリアの思いついた方法であった。
概要としては、まず簡単な問題を出題させて、正解させる。これにより計算もできるから自分達はバカではない、という自覚を持たせることで納得してもらうというもの。
わかりやすい言葉にすると『自己評価をする』という感じかもしれない。
「難しい問題なんて必要ない。これに順ずる適切な回答ができればバカではないぞ、なにせ掛け算じゃからな! 足し算や引き算と違って、学が無ければ解けない問題じゃ!」
力強く指を数字に向けるユナ。なぜか自分のアイディアでもないのに、自分の思いつきのように饒舌に説明する。
これに答えられればバカではない、なんて普通のヒトが聞けばバカにされているような内容だが、姉妹は納得したような顔で首と縦に振った。
「簡単すぎますねお姉ちゃん」
「おくびにも出ませんね妹」
ふふん、と鼻を鳴らして二人は自信満々に答える。これくらいの問題なら余裕と踏んだのだろう。双方の顔は余裕に満ちていた。
まず最初に回答を言おうとしたのは妹だった。
ジェスチャーで姉に向けて待ってくれと指示し、にんまりと笑いながら、スケッチブックを指差して。
「その答えは『6は3ではない』ですね!」
答えた。
そう、答えたことは答えた。同時にそうじゃないだろ的な雰囲気で空間が満たされた。
『えっ、えっ?』と意外すぎる反応に妹は急に挙動不審になった。
すると、隣に座っている姉が妹の肩をポンと叩く。妹が自分のほうを向くと、ゆっくりと首を横に振った。
「妹、それ違いますよ」
「なっ、だってだってここに『6 バツ 3』って!」
指差したまま腕をバタつかせて、これで間違いなわけがないじゃないかという感じになる。ついでに口調も見た目相応というか、冷静キャラが若干崩壊している。
姉のほうは腕を組んで胸を張り、スケッチブックを横目で眺めながらいつもと変らない冷静な態度で言葉を繋げた。
「6が3じゃないなら『=?』なんて付かないでしょう。計算問題です、どう見ても」
「くっ……この問題が解けないとは……」
「ではお姉ちゃんが真実に辿り着かせてあげましょう」
バカではないことを証明する問題を間違えてしょんぼりする妹の頭を撫でて励ましつつ、その分の汚名返上の意味を込めて力強く答えを示す。
「これは……『6攻め3受けリバ不可』ですよ!」
ドーンという効果音が見えそうなくらい力強く、こちらは指差しではなくグーの状態で紙面に向けて突き出した。
非常に堂々たる腕は確信を、緩みの無い視線は勝利を、まるでその手に握り締めたかの如く握っていた。
もちろん、答えの内容はともかくとして。
ここで妹が姉の回答に違和感を覚え、しっくりきていなさそうな妙な表情で姉に問いかけた。
「……あれ、計算問題では?」
「計算問題ですよ。すなわち空間的な考え方をすれば良いのです。数字的に見て3よりも大きな6は、数の強さから見れば倍という大きなものです。数字同士を重ね合わせて見てみると、6が3を完璧に吸収しているように見えなくもないです」
「い、言われてみれば6の下の丸い部分は、3の隙間にピッタリはまるように見えてきました……」
姉の理論は全然……というか完全に破綻している上に計算でもないが、この熱弁っぷりに感化された妹のほうはそんなことに気づくこともなく、まるでこれが正しい解答であるかのように納得しつつある節すらあった。
その後も姉は独自の理論を展開して、妹を完全に集中の渦に巻き込んでいった。
で、そうすると置いてけぼりを食らってしまう方がいるわけで。
「(おい、カメリア。これはどうすりゃいいのじゃ)」
「(ええと……どうしましょう?)」
「(しかも、どっちも言っている意味がまるでわからんぞ!!)」
アイコンタクトと、か細い声で所長と秘書がこそこそ話す。姉妹のトンデモ存在感が出すぎているせいでほとんど影に隠れていた。
口を挟まないように回答を見守っていたのは良かったものの、あまりにも派手に、しかも予想外の間違い方をしたので、もう完全に向こうのペースになっていた。
このまま放っておいても仕方ないがどうしたら良いのだろうか。
と考えていたユナは、咄嗟に話題を逸らさせる作戦を思いつき、ポンと手を叩く。正解かどうかはわからないが、とりあえずそれを試してみることにした。
「あー、うむ、ごほん!」
わざとらしく大きい咳払いをすると、姉妹が同じタイミングでユナのほうを振り向いた。
「実はさっきの問題の答えじゃがな、二人間違っているようで正解なのじゃ」
「どういうことですか?」
小柄な所長はすっくと立ち上がると。
「わしは『6×3に順ずる適切な回答』としか言っておらんし、ましてこの計算式の答えは一つなんて一言も言っておらんぞ?」
右手でスケッチブックの計算式の部分をもふもふと触れた。
「わしが求めたのは回答する能力と、そして柔軟な回答自体じゃ。バカだったらそもそも悩んだ末に『わかりません』になるところを、お前さんがたは見事に柔軟な答えを提示した。すなわち! 二人ともバカではないのじゃァッー!」
さも最初からこういうことを考えていたのだという風に、力をこめて今度は勢い良くスケッチブックを裏拳でぶん殴る。両手で持っていたカメリアは、その威力にちょっと後ろによろけた。
一応断りを入れておくと、この納得のできる妥協のセリフも完全即興。考えうる限り、思いついたまま口からリアルタイムで絶賛衛星生中継である。
ばかに説得力があったため、それを聞いていた自称バカも目をきらきら輝かせながら頷く。
「なるほど……とどのつまり私たちはバカではなかったと……!」
「いや、今言ったじゃろ」
「なんということでしょうか……」
今まで培ってきた常識すべてが百八十度逆転してしまったような絶望的な表情になる二人。
何がそこまで衝撃的だったのかいまいちわからないが、喜んだり驚いたり忙しそうだ。
ユナも二人の反応を見て、並べ立てた言葉で納得したのだと理解したが、やっぱり何を考えているかまではさっぱりわからない。
そうこうしていると、姉のほうが思い立ったように立ち上がった。表情は何か悟ったのか希望に満ち溢れている。姉は妹に向かって語りかける。
「善は急げですよ、妹。これをあの子に報告してバカではなかったと誇らしげに語りましょう!」
姉は握手を求めるように右手を差し出す。
応じて妹も立ち上がり、口から白い歯を見せながら左手で力強く握り返した。
「目を回してびっくりする姿が、まぶたの裏に浮かびます!」
互いに片方の腕で握手をし、空いているもう片方を握りこぶしにして拳同士をくっつけた。とても固い誓いを立てているようにも見えなくはない。
やんややんやと勝手に盛り上がる二人をユナは立ったまま見つめる。わしには目が点になる姿が鮮明に浮かぶぞ、と小さく発した。カメリアは事が済んだこと察知したのか、スケッチブックをたたみ始めていた。
「ありがとうございます! では私たちはこれでおいとま致します! では行きますよ妹!」
「準備万端だよお姉ちゃん。まぁ何も持ってきてはいないけど」
最後に拳をポンとぶつけ合い、和気藹々とした空気で姉妹は去っていった。あれほど嬉しがっていたのだから全速力でドアも閉めずに出てくのかと思ったが、意外にも普通に歩いて出て行った。
今回の客は、ここに来たときには悩みがあるような表情には見えなかった。
そして、今解決して帰ってゆく姿を見ても、たぶん第三者は相談所に相談を持ちかけ、解決して溌剌とした気持ちで戻る情景だとは思わないだろう。
悩みの重さは表面では推し量れない。ユナにとってはバカみたいなことでも、二人にとってみれば岩石のごとき巨大で重いものなのかもしれないから。
それが負担でなくなったとなれば、どんなに心が軽いのか。顔を見ればよくわかる。
そう思いながら、ユナは立ったまま少女たちが座っていたイスを眺めていた。すると、カメリアが元の形に戻したスケッチブックをテーブルに置き、背後からユナに語りかけた。
「いい笑顔でしたね。お日様みたい」
「わしには暴風雨にしか見えんかったわい」
皮肉交じりに言い捨てる。でもユナの表情は明らかに優しいものだった。達成感のある顔だった。
「でも……」
ふと、カメリアは人形のような白くきれいな指を頬に当て、視線を右上に移して何やら踏ん切りの悪い態度を示しながらユナに疑問を呈した。
「これって解決……解決したって言えますか、これ?」
「双方合意の上で納得じゃ。うん、問題ない。ない! な?」
「あ、はい」
「はい。今回もクールでハードボイルドに解決完了じゃっと。うんうん」
客とは対照的にいまいち納得のいかない様子のカメリアを強引に制し、ユナは再び応接用の黒いイスに腰掛ける。もはや何がハードボイルドなのか。
「というのは半分冗談として、わしはあの二人は頭が良いのだと思っておる」
ユナは両手を首のところで後ろ手に組み、同様に足も組んでくつろいだ体勢でそのまま天井を見つつ、そう言い放つ。あくまで半分じゃがな、と付け加えて。
カメリアが意図をつかめないまま黙って見守っていると、数秒後に所長はさらに淡々と話を続けた。
「天才っていうのはな、少なくとも周囲には理解されないものじゃ。普通の思考をしているとな、そういうのが奇行とかバカに見えたりする。でも、そういうバカみたいな奴らがカタブツにできない発想をすることによって、世の中は進むんじゃないかと思うのじゃ。技術しかり、魔法しかりな」
ふんっ、と一つ鼻で笑ってから天井の視線をドアのほうに向けた。
「まー、わしは神様じゃないしわからんしー。わし天才じゃないしー。ハードボイルドじゃしー」
「ふふふ、ユナさんらしいですね」
先ほどの自分の言葉を気恥ずかしく思ったのか、体をくねくねさせて言葉を濁す。傍から見ればその見た目もあいまって非常にかわいい光景である。
カメリアもそんな上司の姿を見て思わず顔から笑みがこぼれ落ちる。笑ってしまった秘書を見上げて、釣られた所長も笑ってしまう。
「あ、ちなみにユナさんはわかりますよねコレ?」
突然、ユナの前の机に置いてあったスケッチブックを持ち上げて、紙に書いた面ではなくスケッチブックのクリーム色をした表紙を見せた。
なんだそんなこと、と口に出さなくてもわかる超ドヤ顔でユナは首を縦に振る。次に両手を広げて首を横に振った。
完全に問題に対して舐めきった態度からも、よほどの自信があると見えた。
リーゼントを整えるようなジェスチャーで、もふもふ両手で栗色の前髪をかき上げる。そして胸の前で腕を組みつつ堂々を言い切った。
「ふっ、もちろんじゃとも。『9』じゃろ?」
「そう……えっ?」
「えっ」
正解ですという回答が来るとばかり思っていたユナは面食らって、ちょっと前のゴブリン妹みたいな素っ頓狂な顔になった。むしろ正解する答えが絶対来ると思っていたカメリアのほうが驚いていた。
どこが間違っているのかわからないユナは、10本しかない両手の指を一本ずつ地道に折りながら計算をはじめた。正答は指10本では足りないというのに。
所長の予想外のアホさにカメリアはどう対応して良いものか焦ったが、所長がさっき言ったことを思い出してこういう言葉をかけることにした。
「その……ユナさんもバカではないですね! はい!」
そう言うと、スケッチブックを抱えたままの秘書は台所のほうに向けていそいそと早走りで戻っていってしまった。
イスに座ったまま何が何やらわからず、展開に追いつけないユナはぽかんとした様子でただ見送った。
「ん、ん? なんか釈然とせんな……」
指を数える行為をやめ、さっきの言葉が気になって数回首をひねった。でも数秒後には、まぁいいかと前向きになって考えることをやめた。
ハードボイルドは過ぎたことにこだわり過ぎないのじゃ、と心の中で自分なりの答えを見つけて納得。散々しゃべってのどが渇いたので、今度は自分も立ち上がって台所へ向かった。
頭を使った分、本日のお昼ご飯は非常においしくなるんだろうとユナは子供心にわくわくしていたのであった。
11/10/23 22:33更新 / トロワ
戻る
次へ