亂戞嶰復丒愴揤巊偺噣媥擔噥亃
丂儂僔僩丄偄傗僗僥儔偑儐乕僠僃儞偵梺幒偱僀偐偝傟偰偐傜丄悢擔偑夁偓偨丅
丂傕偪傠傫偦偺偲偒偺偙偲偼丄傆偨傝偩偗偺旈枾乧乧偲偄偭偰傕晹壆偵偄偨偺偼彈偺巕偺僗僥儔偱偁偭偰丄抝巕惗搆偺儂僔僩偠傖側偄偐傜側傫偺栤戣傕劅劅
乽偝偭偒偐傜壗儃乕僢偲偟偰傞傫偱偡丠丂儂僔僩愭攜乿
乽偁丠丂偊丄偊偭偲乧乧偆偆傫丄側丄側傫偱傕側偄傢傛乿
乽傢傛丠乿
乽偭両丂偠傖丄偠傖側偔偰丄側偭丄側傫偱傕側偄丄側傫偱傕劅劅乿
乽偪丄偪傚偭偲儂僔僩愭攜偭丄偦偭偪彈巕僩僀儗偱偡傛丠乿
乽偁丠丂傑丄娫堘偊偨偭乮愒柺乯両丂乧乧乧乧乧乧乧乧偒傖偁偁偭両乿
乽偳丄偳偆偟偨傫偱偡媫偵丠乿
乽偁丄偄傗丄偦偺乧乧傢丄傢傞偄丄偍劅劅壌丄屄幒偱嵗偭偰偡傞側丅乧乧乧乧側丄側傫偱丠丂偄偮傕尒姷傟偰傞儌僲丄側偺偵劅劅 乿
乽乧乧丠乿
丂偩偗偳偦傟偼丄斵乧乧斵彈傪傎傫偺彮偟丄偱傕妋幚偵曄偊偰偄偨丅
丂丂仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛
丂崱擔偼幍擔偵堦搙偺岞媥擔丅儚乕儖僗僼傽儞僨儖妛堾傕慡偰偺妛晹偱媥島偟偰偍傝丄椌惗偨偪傕慜擔偺梉崗偐傜幚壠偵婣偭偨傝丄挬憗偔偐傜奜傊弌偐偗偨傝偟偰偄偰丄妛惗椌偺拞偼娬嶶偲偟偰偄傞丅
丂怘摪偱抶偄栚偺挬怘傪嵪傑偣偰晹壆偵栠傞偲丄儂僔僩偼堄枴傕側偔傑傢傝傪尒夞偟丄壗偛偲偐傪寛堄偟偨傛偆偵戝偒偔偆側偢偄偨丅
乽偊乧乧僄儞僕僃儕儞僋丄償傽儖僉儕乕乿
丂晹壆偵偁傞巔尒偺慜偱噣庺暥噥傪彞偊傞丅嬀偵塮偭偨偦偺恎懱偼岝偵曪傑傟丄愒偄僪儗僗傾乕儅乕傪揨偭偨愴揤巊偺彮彈傊偲曄傢偭偨丅
乽乧乧傫偭乿
丂尐傗崢傪擯偭偰帺恎偺巔傪妋擣偟丄儂僔僩乧乧斲丄僗僥儔偼夵傔偰巔尒偵岦偒捈偭偨丅
丂屛悈偺傛偆偵憮偔悷傫偩摰偑丄嬀偺拞偐傜偙偭偪傪尒曉偟偰偔傞丅
丂偝偭偒傑偱偲偼傑傞偱堘偆丄偩偗偳偙傟偑崱偺帺暘丅
丂劅劅偱傕丄偝偡偑偵偙偺奿岲偺傑傑偠傖栚棫偭偪傖偆傛偹丅
丂嫻拞偱偦偆偮傇傗偔偲丄攚拞偺梼傪徚偟丄嫻偵庤傪摉偰戝偒偔懅傪偟偰乧乧
乽儕儊僀僋乿
丂師偺弖娫丄恎偵傑偲偭偨僪儗僗傾乕儅乕偑岝偺棻巕偲壔偟偰旘傃嶶傝丄壓拝巔偵側傞丅岝偼嵞傃僗僥儔傪曪傒崬傓偲丄煾怓乮偔傝偄傠乯偺儚儞僺乕僗傊偲曄傢偭偨丅
丂嬢傗懗岥偵僼儕儖偑偁偟傜傢傟偰丄忋昳側拞偵傕壜垽傜偟偝傪姶偠偝偣傞僨僓僀儞丅嵍偺庤庱偵偼僽儗僗儗僢僩丄懌尦偼偍煭棊側僗僩儔僢僾僷儞僾僗劅劅幚傪尵偆偲偙偺僐乕僨傿僱乕僩丄儐乕僠僃儞偑乽屻妛偺偨傔偵乿偲墴偟晅偗乧乧傕偲偄戄偟偰偔傟偨僼傽僢僔儑儞帍偵嵹偭偰偄偨傕偺偺娵僐僺偩偭偨傝偡傞丅
丂偩偗偳劅劅
乽偡偰偒乧乧乿
丂偦傫側尵梩偑帺慠偵岥傪偮偄偰弌偨丅嬍傪揮偑偡傛偆側椓傗偐側惡丅
丂偆偒偆偒偟偨婥暘偵側偭偰丄崢傪寉偔怳傝丄巔尒偺慜偱偔傞偭偲僞乕儞丅
丂傆傢傝偲東偭偨僗僇乕僩偺悶傪揈傓偲丄僗僥儔偼嬀偵塮傞帺暘偵彫庱傪孹偘偰旝徫傫偩丅
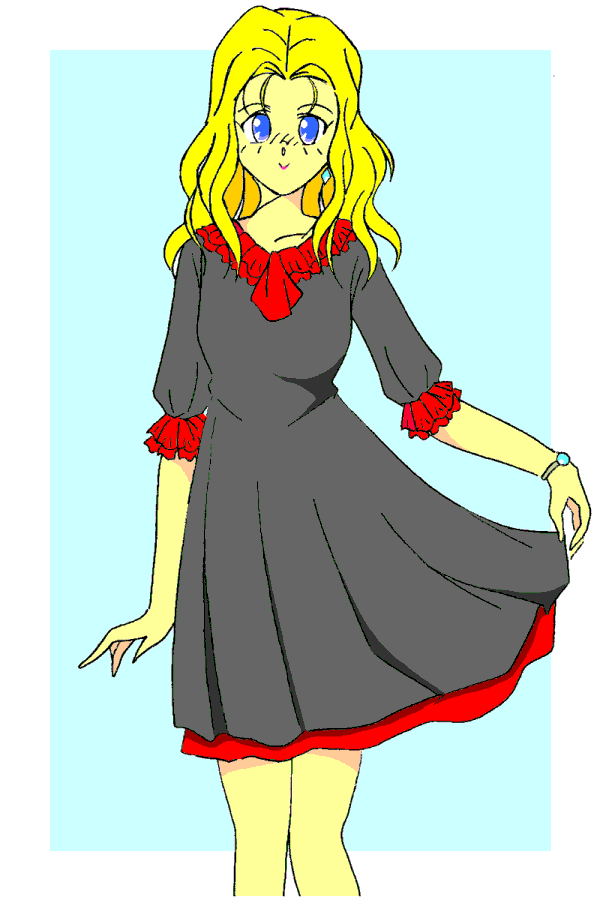
丂挿偔怢傃偨朓枿怓偺敮丄彫偝偔側偭偨庤偲嵶偄巜丄娵傒傪懷傃偨恎懱偮偒丅
丂妠傪堷偒丄攚嬝傪怢偽偟偰尐傪壓偘丄媟傪懙偊偰崢傪帩偪忋偘巔惃傪惍偊傞丅
丂傢偨偟丄彈偺巕側傫偩劅劅
丂偦偆帺妎偡傞偲丄僴乕僼僩僢僾偵曪傑傟偨嫻偺朿傜傒傗丄僼儔僢僩偵側偭偨屢娫偲偦偙傪暍偆僔儑乕僣偺姶怗偑丄偄偮傕偲曄傢傜側偄丄帺慠側傕偺偵巚偊偰偒偨丅
乽乧乧偆傫丄偄偄姶偠乿
丂嬀偺拞偺帺暘偵岦偐偭偰傕偆堦搙偵偭偙傝徫偄偐偗傞偲丄僗僥儔偼敀郪愭惗偐傜偍壓偑傝偱栣偭偨僷乕儖僺儞僋偺億乕僠傪庤偵丄晹壆偺僪傾傪墴偟奐偗偰奜傊弌偨丅
丂丂仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛
丂梫偡傞偵丄乽奐偒捈傝乿偱偁傞丅
丂崱偺偲偙傠扤偵傕僶儗偰偄側偄偟丄偄偮偱傕尦偵栠傟傞偟丄偳偺傒偪曄恎偟偨傜摢偺拞傑偱彈惈壔偟偰偟傑偆傫偩偟乧乧偩偭偨傜偄偭偦彈偺巕傪妝偟傫偠傖偍偆劅劅偲丄儂僔僩傕偲偄僗僥儔偼傂偲傝媥擔偺奨傊偲孞傝弌偟偨丅
丂妛堾慜偐傜杺摫僩儔儉偵忔偭偰丄屲偮栚偺掆棷強偱崀傝傞丅偦偙偼彜嬈抧嬫偺僔儑僢僺儞僌僗僩儕乕僩丅
丂偄偔偮傕偺揦偑尙傪楢偹丄戝惃偺攦偄暔媞偱偵偓傢偆愒楖姠偱曑憰偝傟偨捠傝傪丄斵彈偼億乕僠傪帩偮椉偺庤傪攚拞偵夞偟丄僗僇乕僩偺悶傪側傃偐偣寉傗偐偵曕偔丅
乽乧乧侓乿
丂姶偠曽偑彈惈偺偦傟偵曄傢偭偰偄傞偣偄偐丄偄偮傕偺奨暲傒偑堘偭偰尒偊傞丅
丂偡傟堘偆摨偠擭崰偺彮彈偨偪偺僼傽僢僔儑儞丄揦偵暲傫偱偄傞壔徬昳偵丄傾僋僙僒儕乕傗偍偟傖傟側彫暔乧乧抝偩偭偨偲偒偼婥偵傕棷傔側偐偭偨傕偺偵栚偑偄偭偰偟傑偆丅
丂偳傫偭劅劅乽偒傖偭両乿
丂傛偦尒偟側偑傜曕偄偰偄偨傜丄慜偐傜憱偭偰偒偨彫偝側彈偺巕偲傇偮偐偭偨丅僗僥儔偼屻傠偵傛傠傔偄偨偦偺巕傪丄偁傢偰偰書偒偲傔傞丅
乽偛傔傫偹丅戝忎晇丠乿
乽偆傫偭丅偁傝偑偲偆偍巓偪傖傫乿
丂曣恊傜偟偒彈惈偑嬱偗婑偭偰偒偰丄壗搙傕摢傪壓偘偰偒偨丅僗僥儔偼偼偵偐傫偩徫傒傪晜偐傋丄寉偔夛庍傪曉偟偰偦偺応傪棧傟偨丅
乽傆傆偭乧乧偍巓偪傖傫丄偐劅劅乿
丂岥尦傪傎偙傠偽偣丄傐偮傝偲偮傇傗偔丅
丂偦偧傠曕偒偵栠偭偨僗僥儔偩偭偨偑丄傆偲怳傝岦偄偰懌傪巭傔偨丅
乽偄偄側丄偙傟乧乧乿
丂僽僥傿僢僋偺揦愭偵忺傜傟偨丄悈怓偺僒儅乕僪儗僗丅偟偽偟偦傟傪尒偮傔偰偄偨僗僥儔偼丄墶偵偁偭偨僪傾傪奐偗偰揦偺拞傊擖偭偨丅
乽傢偁偭侓乿
丂惔慯側姶偠偺傾儞僒儞僽儖丄僇僕儏傾儖側僕儍働僢僩丄偪傚偭偲戝抇側儈僯僪儗僗乧乧偁偪偙偪偵忺傜傟偨怓偲傝偳傝偺堖暈偵丄傢偔傢偔偟偨婥帩偪傪梷偊傜傟偢丄揦拞傪尒偰夞傞丅
乽偙傟傕乧乧丄偙傟傕乧乧偁丄偙偭偪傕偄偄劅劅乿
丂僴儞僈乕偵妡偗傜傟偰偄偨僽儔僂僗傗僗僇乕僩傪庤偵庢傝丄嬀偺慜偱恎懱偵崌傢偣傞僗僥儔丅偦偙傊揦堳偺傂偲傝劅劅摢偺僣僲傪尒傞偵丄偍偦傜偔僒僉儏僶僗劅劅偑僯僐僯僐偟側偑傜曕傒婑偭偰偒偨丅
丂悅傟栚偱桪偟偘側婄棫偪丄挿偄崟敮傪屻摢晹偱僔僯儓儞偵偟偰丄敀偄僽儔僂僗偲抁傔偺僞僀僩僗僇乕僩傪恎偵偮偗偰偄傞丅嫻偺朿傜傒偼偪傚偭偲怲傑偟傗偐偩偭偨丅
乽偄傜偭偟傖偄傑偣乣丅偳偆偄偭偨傕偺傪偍扵偟偱偡偐丠乿
乽乧乧両丠丂偊丄偊偭偲丄偁丄偄偊丄偦偺劅劅乿
乽偁傜丄怽偟栿偁傝傑偣傫嬃偐偣偰偟傑偭偰丅偍媞偝傑偑偢偄傇傫柪傢傟偰偄傜偭偟傖傞傛偆側偺偱丄偍庤揱偄偟傛偆偐偲乿
乽偁丄偦偺丄偍劅劅偍峔偄側偔乿
丂庤偵偟偨彜昳傪丄偁偨傆偨偲扞偵栠偡丅偦偺婥偵側傟偽乽儕儊僀僋乿傪巊偭偰偳傫側奿岲傕帺桼帺嵼側偺偩偑丄偄傠傫側暈傪庢偭懼偊堷偭懼偊偡傞偺偑妝偟偔偰丄偮偄僥儞僔儑儞偑忋偑偭偰偟傑偭偰偄偨丄傛偆偩丅
丂偩偗偳偦偺揦堳偼丄徫傒傪晜偐傋偨傑傑丄偝傜偵娫傪媗傔偰偒偨丅
乽傕偟偐偟偰丄斵巵偝傫偲偺僨乕僩梡偐偟傜丠乿
乽偪丄偪劅劅堘偄傑偡偭両乿
丂帹尦偱偦偆殤偐傟丄僗僥儔偼偁傢偰偰尵偄曉偟偨丅
乽偠傖偁曅巚偄偺恖偺婥傪堷偒偨偄丄偲偐丠乿
乽偱丄偱偡偐傜丄偦傫側傫偠傖側偔偰乧乧乿
丂擼棤偵晜偐傃忋偑偭偨億僯僥彮擭劅劅僜乕儎偺徫婄丅偁傢偰偰偦傟傪徚偟嫀傠偆偲偡傞偑丄巚偊偽巚偆傎偳堄幆偟偰偟傑偄丄偦偺僀儊乕僕偑妋偐側傕偺偵側偭偰偄偔丅
乽乧乧乧乧乿
丂婄傪愒傜傔偨傑傑丄僗僥儔偼抪偢偐偟偘偵傕偠傕偠偲偆偮傓偄偰偟傑偆丅偦傫側斵彈偵僒僉儏僶僗偺揦堳偼栚怟傪壓偘丄乽偁傜偁傜乿偲岥傕偲傪傎偙傠偽偣偨丅
乽偆乣傫丄崱拝偰傞偺傕偄偄偗偳丄傕偭偲柧傞偄怓尛偄偺傕偺傕帡崌偆偐偟傜偹乧乧乿
乽偊丄偁丄偪劅劅偪傚偭偲偋丠乿
丂帋拝幒傊偲楢傟崬傑傟丄拝偰偄偨儚儞僺乕僗傪扙偑偝傟傞丅
丂奃怓偺僴乕僼僩僢僾偲僔儑乕僣偲偄偆壓拝巔偵偝傟丄抪偢偐偟偝偵嫻偺慜偱榬傪僋儘僗偝偣傞僗僥儔丅僒僉儏僶僗偺揦堳偼妟偵巜傪摉偰偰丄棴傔懅傪偮偄偨丅
乽偢偄傇傫抧枴側壓拝偹丅擭崰偺彈偺巕側傫偩偐傜丄傕偭偲壜垽偄偺傪拝偗偰僆僔儍儗偟側偒傖侓乿
乽偼丄偼偄乧乧乿
丂嫻偺僒僀僘傪應偭偰傕傜偆丅擕庱偵増偭偰儊僕儍乕傪姫偒晅偗傜傟偰丄僗僥儔偼巚傢偢惡傪忋偘偰偟傑偭偨丅
乽傗劅劅傗偁偀傫偭丄偔偡偖偭偨偁乣偄偭乿
乽偙傜偭丄摦偐側偄偺丅惓妋偵應傟側偄偠傖側偄乿
乽偁丄偁偺偭丄傎劅劅杮摉偵偙傟丄僒僀僘應偭偰傞偺丠乿
乽幐楃偹丅偨偟偐偵偁偨偟偼僒僉儏僶僗偩偗偳丄偍揦偺偍媞偝傫憡庤偵僄僢僠側偙偲偼偟側偄傢傛乿
乽乧乧乧乧乿
丂嵎偟弌偝傟偨僽儔僕儍乕偲僔儑乕僣傪恎偵偮偗傞丅攚拞偺儂僢僋傪棷傔傜傟偢偵傕偨傕偨偡傞僗僥儔傪尒偐偹偰丄揦堳偑庤傪怢偽偟偰偒偨丅
乽傎傜丄慜偐偑傒偵側偭偰偍偭傁偄傪偪傖傫偲僇僢僾偵擖傟傞偭丅攚拞傪棷傔偰丄榚偺偍擏傪婑偣忋偘偰乧乧尐偺僗僩儔僢僾傪挷惍偟偰偭偲丅偳偆丠丂偳偙偐嬯偟偄偲偙傠偼側偄偐偟傜丠乿
丂尐傪傐傫偲扏偐傟傞丅僗僥儔偼夵傔偰帋拝幒偺巔尒偵岦偒捈偭偨丅
乽偁乧乧乿
丂嬀偵塮偭偰偄偨偺偼丄敄偄僺儞僋怓偺僼儕儖偑偁偟傜傢傟偨敀偄僽儔僕儍乕偲僔儑乕僣傪恎偵偮偗偰丄杍傪愒偔愼傔偨帺暘偺巔劅劅
乽偙傟偑丄傢偨偟乧乧丠乿
丂柍堄幆偺偆偪偵丄偮傇傗偒偑偙傏傟偨丅
丂僼儖僇僢僾偵曪傑傟偰丄鉟楉側宍偵惍偊傜傟偨屓偑嫻偺憃媴偵尒擖偭偰偟傑偆丅
乽乧乧乧乧乿
丂彈偺巕偺壓拝傪偒偪傫偲拝偗偰偄傞偙偲偑婥抪偢偐偟偔丄偱傕壗屘偐婐偟偔屩傜偟偄丅
乽偆傫丄偲偭偰傕傛偔帡崌偭偰傞傢傛丅傛偐偭偨傜懠偺傕帋拝偟偰傒傞丠乿
乽偊丄偊偊乧乧乿
丂揦堳偺栤偄偐偗偵丄偼偵偐傓傛偆側昞忣傪晜偐傋偰墳偊傞丅
丂拝忺傞妝偟偝偵栚妎傔丄傑偨堦抜噣彈偺巕噥偺奒抜傪搊偭偰偟傑偭偨僗僥儔偱偁偭偨丅
丂丂仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛
丂僋儕僗僥傿傾儗僀僋偺屛斎偵偁傞僒儔僒僀儔丒僔僥傿偼丄偦偺屛悈傪婎偵偟偨愼怓丒朼愌嬈偑婎姴嶻嬈偱偁傞丅娤岝抧偲偟偰傕偦偙偦偙桳柤偱偁傝丄傑偨嬤擭偱偼杺椡偱摦偔婡夿劅劅杺摫婡夿惢嶌偺僼傽僋僩儕乕偑偄偔偮傕奐愝偝傟偨偨傔丄巗偵弌擖傝偡傞恖偺悢偼偄偪偩傫偲懡偔側偭偰偄傞偲偐丅
乽偘偭丄偁偺帪偺償傽儖僉儕乕両丠乿乽側傫偱偙傫側偲偙偵偄傞偺傛偭丠乿
乽偁丄偁側偨偨偪劅劅乿
丂僽僥傿僢僋傪弌偰怳傝岦偄偨弖娫丄僗僥儔偼尒抦偭偨擇恖乧乧偄傗嶰恖偲敨崌傢偣偨丅
丂敀偄儚儞僺乕僗偺忋偐傜敄巼怓偺儃儗儘傪塇怐偭偨儐僯僐乕儞柡偺僼傿乕僱偲丄僺儞僋偺傾僂僞乕僉儍儈僜乕儖偵崟偄僗僉僯乕僷儞僣傪崌傢偣偨憰偄偺僟乕僋僄儖僼柡儀僱僢僞丄偦偟偰劅劅
乽傑偨惈挦傝傕側偔偦偺巕偵尵偄婑偭偰傞偺偭両丠乿
乽乽乧乧乧乧乿乿
乽偩丄戝忎晇偩傛揤巊偺偍巓偪傖傫偭乿
丂僼傿乕僱偺攚拞乮攏懱乯偵屪偭偰偄偨抝偺巕劅劅儖儖僩偑丄偄偒傝棫偮僗僥儔偵偁傢偰偰惡傪偐偗傞丅乽乧乧僼傿乕僱偍巓偪傖傫傕儀僱僢僞偍巓偪傖傫傕丄働儞僇傗傔偰側偐傛偔側偭偰偔傟偨偐傜偭両乿
乽乧乧乧乧乿
丂偳偆傗傜偙偺擇恖丄梒偄斵傪乽嫟桳乿偡傞偙偲偵偟偨傜偟偄丅
乽偁乣偦偺丄傑丄傑偁丄側傫偩乧乧偊丄俵偵愼傔傞偺偼傑偩傑偩偁偲偱傕偄偄偐側偭偰丅乧乧偄丄崱偼偙偺巕偺桪偟偄偍巓偪傖傫偱偄傛偆偐偲劅劅乿
丂層棎側帇慄傪岦偗偰偔傞僗僥儔偵偦偆尵偆偲丄儀僱僢僞偼愲偭偨帹偺愭傑偱恀偭愒偵偟偰栚傪偦傜偟偨丅
丂嫮婥嫮堷壛媠婥幙側僟乕僋僄儖僼偲偼巚偊側偄丄偦偺懺搙丅堦弖曫婥偵偲傜傟偨僗僥儔偩偭偨偑丄椬偵悷傑偟婄偱棫偮儐僯僐乕儞柡偵惡傪偐偗傞丅
乽僼傿乕僱偼偄偄偺丠乿
乽偟丄巇曽側偄偠傖側偄丅偍屳偄忳傟側偄傫偩偟乧乧乿
乽偱傕丄儐僯僐乕儞偭偰妋偐劅劅乿
丂乽弮寜偺杺暔柡乿偲傕屇偽傟傞儐僯僐乕儞偼丄懠偺杺暔柡偲岎傢偭偨抝惈偺惛傪庴偗傞偲丄偦偺僣僲偵偁傞帯桙偺椡傪幐偭偨傝丄垷庬偱偁傞僶僀僐乕儞傊揮壔偟偨傝偡傞偲尵傢傟偰偄傞丅
丂偩偑丄僼傿乕僱偼儀僱僢僞偲偼斀懳偵丄僗僥儔偺栚傪恀偭捈偖尒曉偟偨丅
乽傢偐偭偰傞丅偗偳丄偦偺偲偒偑棃傞偺偼愭偺榖偵側傝偦偆偩偟乧乧偦傟偵丄偨偲偊偳傫側巔偵側偭偰傕丄傢偨偟偼傢偨偟偩偐傜乿
乽乧乧乧乧乿
丂偒偭傁傝偲尵偄愗偭偨斵彈偺尵梩偑丄僗僥儔偺怱傪偞傢偮偐偣傞丅
丂偙傟偐傜傒傫側偱恖宍寑傪尒偵峴偔傫偩乣丄偲偼偟傖偖儖儖僩偵桪偟偘側徫婄傪晜偐傋傞僼傿乕僱偲儀僱僢僞丅嶨摜偺拞偵暣傟偰偄偔斵傜偺屻傠巔傪丄愴揤巊偺彮彈偼柍尵偱丄偦偟偰彮偟慉傑偟偘偵尒憲偭偨丅
丂偟偽偟偦偺応偵棫偪恠偔偟丄傗偑偰恖攇偵棳偝傟傞傛偆偵纟傪曉偡丅
乽偳傫側巔偵側偭偰傕丄傢偨偟偼傢偨偟乧乧偐乿
丂傐偮傝偲偮傇傗偒丄僗僥儔偼僔儑乕僂僀儞僪僂偵塮傞帺暘偵栚傪傗偭偨丅
丂煾怓偺儚儞僺乕僗傪拝偨丄憮偄摰偲朓枿怓偺敮偺彮彈偑尒曉偟偰偔傞丅
丂嬻偄偨庤偱丄偦偭偲嫻尦傪墴偝偊傞丅暈偺壓偵拝偗偰偄傞偺偼丄僽僥傿僢僋偺揦堳偵姪傔傜傟偰攦偭偨僽儔僕儍乕偲僔儑乕僣偺僙僢僩丅
丂劅劅傕偟傕丄傕偟傕偙偺傑傑乧乧
乽僗僥儔偝傫乿
丂偙偺傑傑丄噣僗僥儔噥偺傑傑偱偄偨傜乧乧
乽僗僥儔偝傫乿
丂傢偨偟傕丄僼傿乕僱傗儀僱僢僞傒偨偄偵乧乧
乽僗僥儔偝傫偭乿乽乧乧偊偭丠乿
丂偦偺惡偑帺暘偺憐憸偠傖側偔幚嵺偵暦偙偊偰偒偨偙偲偵婥偯偒丄僗僥儔偼偁傢偰偰傑傢傝傪尒夞偟偨丅
乽傗偭傁傝僗僥儔偝傫偩乿
乽偦偭乧乧僜乕儎偭丄偔傫丠乿
丂巹暈巔劅劅儕僱儞偺敀僔儍僣偵嵁怓偺僆乕僶乕僆乕儖偲偄偆奿岲偺億僯僥彮擭偑丄捠傝傪墶愗傝嬱偗婑偭偰偔傞丅
乽傛偐偭偨乧乧偄偮傕偲堘偆奿岲偩偭偨偐傜丄恖堘偄偐偲巚偄傑偟偨乿
乽偁丄偊乧乧偊偭偲丄偦偺劅劅乿
乽偁乧乧乿
丂傑偝偐偙傫側偲偙傠偱弌夛偆偲偼丄巚偭偰傕偄側偐偭偨乧乧傑偁丄偦傟偼岦偙偆傕摨偠側偺偩傠偆偗偳丅
丂僗僥儔偼婄傪愒傜傔丄僪僉僪僉偡傞嫻偵傑偨庤傪摉偰偰屗榝偆丅偮傜傟偰僜乕儎傕婄傪愒偔偟偰丄
乽偛丄偛傔傫側偝偄丅偁乣丄偊偭偲丄偦劅劅偦偺暈傕丄偵丄帡崌偭偰傑偡乧乧偲偭偰傕乿
乽偁丄偆丄偆傫丄偁傝偑偲偆乧乧乿
乽乧乧乧乧乿
乽乧乧乧乧乿
丂屳偄偵婄傪恀偭愒偵偟偰尒偮傔崌偆丅偦傫側擇恖傪摴峴偔恖偨偪偑丄偔偡偔偡徫偄側偑傜惗抔偐偄帇慄傪岦偗偰捠傝夁偓偰偄偔丅
乽乧乧偄丄峴偒傑偟傚偆僜乕儎偔傫偭両乿
乽偊丠丂峴偔偭偰偳偙傊乧乧偆傢偀偭両丠乿
丂捑栙偲抪偢偐偟偝偵懴偊傜傟側偔側偭偨僗僥儔偼丄僜乕儎偺庤傪嫮堷偵偮偐傓偲丄偦偺応偐傜摝偘弌偡傛偆偵嬱偗弌偟偨丅
丂丂仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛
乽傛偆偙偦僪儔僑僯傾椏棟揦儔僽儔僀僪丒僒儔僒僀儔嶰崋揦傊両丂偍擇恖條偱偡偐丠丂偙偪傜偺僥乕僽儖傊偳偆偧乣侓乿
丂嬤偔偵偁偭偨儗僗僩儔儞偵擖傝丄僥乕僽儖惾偵岦偐偄崌偭偰嵗傞丅
丂拲暥傪庢傝偵偒偨僉僉乕儌儔偺僂僃僀僩儗僗偵丄僷儉儉劅劅戃忬偺僷儞惗抧偵嬶傪媗傔偨僪儔僑僯傾偺僼傽僗僩僼乕僪劅劅偺僙僢僩儊僯儏乕傪拲暥偟丄僗僥儔偲僜乕儎偼忋栚尛偄偱偍屳偄偺婄傪偆偐偑偭偨丅
乽偁乧乧偁偺偭乿
乽偼丄偼偄偭乿
乽偊丄偊偭偲丄偦偺丄僗僥儔偝傫偼丄偒丄崱擔偼壗傪丠丂乧乧偁丄傕偟偐偟偰傑偨扤偐偑劅劅乿
乽偦偆偠傖側偔偰丄崱擔偼偦偺丄偟劅劅僔儑僢僺儞僌丄偐側丠丂僜乕儎偔傫偙偦丄崱偐傜偳偙偐峴偔偮傕傝丄偩偭偨偺丠乿
丂椬偵抲偄偰偁傞僽僥傿僢僋偺巻戃偵偪傜偭偲栚傪傗偭偰丄栤偄曉偡僗僥儔丅
乽杔偼乧乧偙傟偱壗偐嶣偭偰傒傛偆偐側丄偭偰乿
丂偦偆尵偭偰丄僜乕儎偼庱偐傜壓偘偰偄偨彫偝側崟偄敔傪僥乕僽儖偵偺偣偨丅
丂惓柺偵娵偔摟偒捠偭偨晹昳劅劅儗儞僘偑廲偵擇偮暲傫偱偄傞丅
乽幨恀婡丠乿
乽偼偄丅晝偝傫偺丄偍壓偑傝側傫偱偡偗偳乧乧乿
丂擇娽儗僼偺敔僇儊儔偵庤傪揧偊偰丄偼偵偐傓傛偆偵摎偊傞僜乕儎丅
丂偦偙偵拲暥偟偨椏棟偑塣偽傟偰偒偨丅僗僷僀僔乕側崄傝偑旲傪偔偡偖傝丄榖偑搑愗傟傞丅
乽偛拲暥偼埲忋偱傛傠偟偄偱偟傚偆偐丠丂偦傟偱偼偛備偭偔傝偳偆偧乣侓乿
乽偄丄偄偨偩偒傑偡偭乿乽乧乧偄偨偩偒傑偡乿
丂偪傚偆偳拫帪丅擇恖偼僙僢僩儊僯儏乕偵庤傪怢偽偟偨丅
丂僗乕僾偺擖偭偨儅僌僇僢僾傪椉庤偱帩偭偰傆乕傆乕偡傞僗僥儔偵丄僜乕儎偼僷儉儉傪庤偵僋僗僢偲徫傒傪晜偐傋傞丅
乽側乧乧壗丠乿
乽偄丄偄偊丄僗僥儔偝傫傕儂僔僩愭攜傒偨偔擫愩側傫偩偭偰乧乧偁丄偊偭偲儂僔僩愭攜偭偰偄偆偺偼杔傛傝慜偵妛堾偵擖偭偨劅劅乿
乽偦丄偦傟傛傝僜乕儎偔傫偺偙偲丄偒丄暦偐偣偰梸偟偄丄偐傕丅斀杺暔椞偐傜摝偘偰偒偨偭偰乧乧偁偭両乿
丂帺暘乮儂僔僩乯偺偙偲偐傜榖戣傪堩傜偦偆偲偟偰丄傑偨梋寁側偙偲傪尵偭偰偟傑偭偨丅偁傢偰偰岥偵庤傪傗傞僗僥儔丅
丂偟偐偟僜乕儎偼摿偵婥偵偟偨慺怳傝傕側偔丄榖偟巒傔偨丅傎偭傌偨偵僜乕僗偑晅偄偰偄傞偺偼偛垽沢偩丅
乽偊偭偲丄杔偺壠偼僜儔儕傾嫵抍椞偱桝擖嶨壿偺揦傪傗偭偰偨傫偱偡丅偱傕丄惞搒偐傜棃偨嫵抍孯偑奨偵嫃嵗傞傛偆偵側偭偰偐傜丄娭強傗専栤偑傗偨傜偲尩廳偵側偭偰偟傑偭偰乧乧乿
丂恖傗暔偺峴偒棃偑嬌抂偵惂尷偝傟偨偨傔丄椞奜偐傜攧傝暔偑慡偔擖偭偰偙側偔側傝丄偦偟偰偄傛偄傛揦傪忯傑側偗傟偽側傜側偔側偭偨偁傞擔偺栭拞丄偄偒側傝晝恊偵扏偒婲偙偝傟乽摝偘傞偧乿偲尵傢傟偰劅劅
乽乧乧偦傟偱丄壠懓偱揱庤傪棅偭偰僒儔僒僀儔偵朣柦丄偲偄偆偐栭摝偘偟偰偒偨傫偱偡乿
乽乧乧乧乧乿
丂奨摴偑惍旛偝傟丄揝摴偑晘愝偝傟傞傛偆偵側偭偨崱偺帪戙丄斀杺暔椞偵廧傓恖娫偑奆乆丄杺暔柡傪栂怣揑偵揋帇偟偰偄傞傢偗偱偼側偄丅
丂僸僩側傜偞傞幰偨偪偲昁梫埲忋偵娭傢傜側偄乧乧偲偄偆偺偑嵟嬤偺斀杺暔椞丒斀杺暔崙壠偺僗僞儞僗偱偁傞丅偲偼偄偊丄枹偩偵乽杺暔偼恖娫傪嬺傜偆嫲傞傋偒懚嵼乿偩偲寲揱偡傞屆廘偄庡恄嫵抍捈妽椞傕傑偩傑偩巆偭偰偄傞丅
丂乧乧傕偟偐偟偨傜僜乕儎偺椉恊偼丄懅巕偑桬幰偺帒幙帩偪偩偲偄偆偙偲傪抦偭偰偄偨偺偐傕偟傟側偄丅嫵抍孯偑暆傪棙偐偡僜儔儕傾偱傕偟偦偺偙偲偑柧傞傒偵側偭偨傜丄斵偼栤摎柍梡偱挜暫偝傟丄乽嫵抍偺寱乿乽庡恄偺椡偺戙峴幰乿側偳偲偄偭偨尐彂偒偲堷偒姺偊偵帺桼傪扗傢傟偰偟傑偆劅劅
丂偩偐傜偙偺婡夛偵恊杺暔椞傊偺朣柦傪幚峴偟偨乧乧側傫偰旘桇偟夁偓偐側丠丂偲丄岥偺拞偺僷儉儉傪堸傒崬傒巚偆僗僥儔丅
乽偛丄偛傔傫側偝偄丅寵側偙偲恥偄偪傖偭偰乿
乽婥偵偟側偄偱僗僥儔偝傫丅晝偝傫偨偪傕偙偺奨偱傑偨偍揦傪奐偔偙偲偑偱偒偨偟丄杔傕妛堾偵捠偊傞偟丄幚偺偲偙傠偙偭偪偵棃偰傛偐偭偨偭偰巚偭偰傞傫偱偡乿
乽僜乕儎偔傫乧乧乿
丂杺暔柡偝傫偨偪偵廝傢傟傞偺偩偗偼丄崲傝傕傫偱偡偗偳偹乧乧偲丄偔偪傃傞偺僜乕僗傪偸偖偭偰嬯徫偡傞偦偺婄傪丄僗僥儔偼峥偟偘偵尒偮傔偨丅
丂偦傟偵婥偯偄偰偄傞偺偐偄側偄偺偐丄僜乕儎偼斵彈偵岦偒捈傝丄墦椂偑偪偵栤偄偐偗偨丅
乽偲丄偲偙傠偱僗僥儔偝傫乧乧偊偭偲丄偙丄偙偺偁偲丄壗偐梊掕偼劅劅乿
乽偁丄偆傫丄摿偵側偄偗偳乧乧乿
乽偠傖偁丄傕偟丄傛丄傛偐偭偨傜乧乧偊偭偲丄偦偺乧乧乧乧偡偭丄僗僥儔偝傫偺丄偟傖丄幨恀傪嶣傜偣偰偔傟傑偣傫丄偐乧乧丠乿
乽偼丠乿
丂丂仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛
丂彜揦奨傪屛懁傊偲敳偗丄悈楬傪墶偵彮偟峴偔偲彫崅偄媢偵側偭偰偄偰丄偦偙偵僒儔僒僀儔巗柉岞墍偑偁傞丅
丂椢偑惍旛偝傟丄僽儔儞僐傗偡傋傝戜丄僕儍儞僌儖僕儉側偳偺梀嬶偑抲偐傟偨峀応傗丄僕僷儞僌晽掚墍丄栰奜僗僥乕僕側偳偑愝偗傜傟偰偄偰丄奨偵廧傓恖乆偺宔偄偺応偲偟偰恊偟傑傟偰偄傞丅
丂僗僥儔偲僜乕儎偼嶣塭応強傪扵偟偰丄屛偑堦朷偱偒傞岞墍偺梀曕摴傪扝偭偰偄偔丅
丂傑傢傝偵偼巕偳傕偨偪傗壠懓楢傟丄壗慻偐偺僇僢僾儖偑丄巚偄巚偄偵宨怓傪妝偟傫偩傝丄嶶嶔偟偨傝偟偰偄傞丅
乽傎傜偭丄偛庡恖偝傑憗偔憗偔偭両乿
乽偪乧乧偪傚偭偲懸偭偰傛儅儕傿両乿
丂僞儞僋僩僢僾抁僷儞巔偺僐儃儖僩彮彈偑丄摨偠擭崰偺彮擭傪堷偭挘偭偰妝偟偦偆偵嬱偗偰偄偔丅
乽傕偆変枬偱偒偹偊偭両丂儐僂僩丄偦偙偺椦偺拞偱儎儖偧偭両乿
乽傂偭丄恖偑尒偰傞偭偰偙傫側拫娫偭偐傜乧乧偆傢偁偁偁偁偁偭儕僫偝偀傫偭両乿
丂俿僔儍僣偵僟儊乕僕僕乕儞僘偲偄偆儔僼側奿岲傪偟偨挿恎偺僆乕僈柡偑丄岾敄偦偆側嵶恎偺抝惈偺嬢庱傪偮偐傫偱戝屢偱嶨栘椦偺拞傊偲擖偭偰偄偔丅
丂偁傞堄枴暯榓側丄恊杺暔椞偺媥擔偺晽宨丅
乽乧乧偱丄晝偝傫偑尵偭偨傫偱偡丅亀妋偐偵昳晄懌偩偗偳丄憅屔偵壗擭傕曻偭偰偍偄偨傕偺傪専昳傕偣偢偵擺傔傞偭偰偳偆偄偆偮傕傝偩亁偭偰劅劅乿
乽偦丄偦傫側偙偲偁偭偨傫偩乧乧乿
丂偲傝偲傔偺側偄榖偵憡捚傪偆偪側偑傜丄僗僥儔偼椬傪曕偔僜乕儎傪墶栚偱偪傜偭偲偆偐偑偭偨丅
丂劅劅偊偭偲偙傟偭偰丄僨乕僩乧乧偩傛偹丠
乽乧乧乧乧乿
丂劅劅偳傫側晽偵尒傜傟偰傞偺偐側丠丂巓掜偵偟偐尒偊側偐偭偨傝偟偰乧乧
丂摢傂偲偮暘攚偺掅偄億僯僥彮擭偵丄偔偡傝偲旝徫傓丅
丂僜乕儎偼棫偪巭傑傞偲丄椉庤偺巜偱榞傪偮偔傝丄傑傢傝傪偖傞偭偲尒夞偟偨丅
乽偙偺曈偱偄偄偐側乧乧僗僥儔偝傫丄偪傚偭偲偦偙偵棫偭偰傕傜偊傑偡偐丠丂庤偡傝偵寉偔傕偨傟偐偐傞姶偠偱乿
乽偁丄偆傫丄傢偐偭偨劅劅乿
丂僗僥儔偼屛懁偵愝偗傜傟偨庤偡傝偵崢傪梐偗傞偲丄攚嬝傪怢偽偟偰僜乕儎偺曽傊岦偒捈偭偨丅
乽偙傫側姶偠丄偐側丠乿
乽偼偄丅乧乧偁丄偦傫側偵嬞挘偟側偄偱乿
丂壓傪岦偄偰僇儊儔偺僼傽僀儞僟乕傪擿偒側偑傜丄僜乕儎偑摎偊傞丅
丂懁柺偺僟僀儎儖偱僺儞僩傪崌傢偣丄奧偺撪懁偵偁傞旝挷惍梡偺儖乕儁傪愜傝忯傓丅
乽偠傖偁丄嶣傝傑偡偹乿
乽偁丄偆丄偆傫乿
丂嬞挘偟側偄偱偲尵傢傟偨偺偵丄巚傢偢恎峔偊偰偟傑偆丅柍棟傕側偄乧乧儂僔僩偲偟偰側傜偲傕偐偔丄噣僗僥儔噥偲偟偰幨恀偵嶣傜傟傞偺偼丄偙傟偑弶傔偰側偺偩偐傜丅
丂僇僔儍儕劅劅
丂偐偡偐側壒偲偲傕偵僔儍僢僞乕偑愗傜傟偨丅僗僥儔偼傎偭偲懅傪揻偒丄尐偺椡傪敳偄偰昞忣傪榓傜偘傞丅
丂僜乕儎偼僼傽僀儞僟乕偵栚傪傗偭偨傑傑丄嶣塭梡儗儞僘偵晅偄偰偄傞僐僢僉儞僌乮僔儍僢僞乕僠儍乕僕乯儗僶乕傪巜偱慺憗偔壓偘傞偲丄
丂僇僔儍儕劅劅
乽乧乧偊丠乿
丂擇夞栚偼姰慡偵晄堄懪偪偩偭偨丅乽偪丄偪傚偭偲僜乕儎偔傫偭両丠乿
乽偁偼偼丄偛傔傫側偝偄丅偱傕丄偒偭偲崱偺曽偑帺慠側姶偠偱嶣傟偰傞偲巚偄傑偡傛乿
乽傕偆偭乿
丂埆傃傟傕偣偢摢偵庤傪傗傞億僯僥彮擭偺婄傪丄僗僥儔偼杍傪愒傜傔偵傜傒偮偗傞丅
丂偪側傒偵僼傽僀儞僟乕梡偲嶣塭梡偵儗儞僘偑暿乆偵側偭偰偄傞擇娽僇儊儔偼丄僺儞僩崌傢偣偑擄偟偄傜偟偔丄弶怱幰偼乽摨偠峔恾偱擇枃嶣傝乿偑悇彠偝傟偰偄傞偺偩偲偐丅
乽応強傪曄偊偰丄傕偆彮偟嶣塭偟偰傕偄偄偱偡偐丠乿
乽偊丄偊偊丅偱傕崱搙偼偪傖傫偲嶣傞慜偵惡偐偗偰劅劅偭偰丄偦偆偩偭侓乿
丂偲丄偦偙偱嬃偐偝傟偨偍曉偟傪巚偄偮偒丄斵彈偼埆媃偭傐偄徫傒傪晜偐傋偨丅
乽偡丄僗僥儔偝傫丠乿
乽尒偰偰丄僜乕儎偔傫乿
丂僗僥僢僾傪摜傓傛偆偵偁偲偢偝傞偲丄嵍庤庱偺僽儗僗儗僢僩傪怗偭偰丄偦偺応偱偔傞偭偲僞乕儞丅
丂師偺弖娫僗僥儔偺拝偰偄偨煾怓偺儚儞僺乕僗偑岝偵曪傑傟丄懅傪偺傓僜乕儎偺栚偺慜偱宍偲怓傪曄偊偰偄偔劅劅
乽乧乧偳偆丠丂帡崌偆丠乿
丂傑傢傝偑偳傛傔偔拞丄拝偰偄偨暈傪僽僥傿僢僋偵偁偭偨偁偺悈怓偺僒儅乕僪儗僗偵乽儕儊僀僋乿偟偨僗僥儔偼丄僗僇乕僩偺悶傪傆傢傝偲傂傞偑偊偟偰怳傝岦偒丄偐傜偐偆傛偆側徫傒傪晜偐傋偨丅
乽偁丄偼丄偼偄乧乧丄偲丄偲偭偰傕乧乧乿
丂婄傪恀偭愒偵偟偰摎偊傞僜乕儎丅側偍丄岝偺拞偱堦弖尒偊偨斵彈偺壓拝巔偼丄偟偭偐傝偔偭偒傝栚偵從偒晅偄偰偄偨傝偟偰丅
乽傆傫偭丄堖憰僠僃儞僕偔傜偄傢偨偔偟偵傕偱偒傑偡傢乿
乽偱傕僙儕僇偝傫偼丄崱偺儊僀僪暈巔偑堦斣帡崌偭偰傑偡傛乿乽乧乧偊丠乮傐偭乯乿
丂挘傝崌偍偆偲偡傞僔儑僑僗柡傪丄椬偵偄偨尋媶幰晽偺惵擭偑偨偟側傔傞丅
丂傕偭偲傕摉偺僗僥儔帺恎偼乽僜乕儎偔傫偵偍曉偟偺僪僢僉儕戝惉岟両乿偲偱傕巚偭偰偄傞偺偐丄墶偱偦傫側偙偲尵傢傟偰偄傞側傫偰乮偁偲攦偭偨偽偐傝偺僽儔僕儍乕偲僔儑乕僣傪尒傜傟偨偙偲偵傕乯慡偔婥偯偄偰偄側偄傛偆偩丅
乽傆傆偭丄偠傖偁師偼偙偺暈偱嶣偭偰偔傟傞丠丂僜乕儎偔傫侓乿
乽偊丄偁丄偦劅劅偦偺丄偊偭偲丄偼丄偼偄偭乧乧乿
丂嵎偟弌偝傟偨偦偺庤傪丄僜乕儎偼偍偢偍偢偲埇傝曉偡丅
丂偩偑丄
乽乧乧偁傜丠丂壗偐偟傜丠乿
丂偦偺尐墇偟偵丄奨偺寈绱戉巑偨偪偑偨偩側傜偸條巕偱栰奜僗僥乕僕偺曽傊偲憱偭偰偄偔偺偑尒偊偰丄僗僥儔偼夦鎎側昞忣傪晜偐傋傞丅
丂僜乕儎傕斵彈偺帇慄傪捛偭偰屻傠傪怳傝岦偒丄旣崻傪婑偣偨丅
乽壗偐偁偭偨丄傒偨偄偱偡偹乿
乽峴偭偰傒傑偟傚偆丄僜乕儎偔傫乿
乽偊丠丂偪丄偪傚偭偲僗僥儔偝乧乧偆傢偁偁偁偁偁偁偁偭両丠乿
丂僗僥儔偼僜乕儎偺庤傪偓傘偭偲埇傝偟傔丄偦偺傑傑屻傪捛偭偰憱傝弌偟偨丅
丂to be continued...
劅 appendix 劅
丂僗僥儔偑弌偨偁偲偺僽僥傿僢僋偵偰劅劅
乽偆乣傫乧乧乿
乽偁傟丠丂偳偆偐偟偨傫偱偡偐愭攜丠乿
乽偁丄偄傗丄偝偭偒憡庤偟偨嬥敮偺巕側傫偩偗偳乧乧側乣傫偐偁偨偟偵暤埻婥偑帡偰傞偭偰偄偆偐丄摨偠擋偄偑偡傞偭偰偄偆偐劅劅乿
乽婥偺偣偄偱偡偹乮偒偭傁傝乯乿
乽懄摎偭両丠乿
乽偩偭偰愭攜傒偨偔丄彈暔偺堖暈偑岲偒偡偓偰傾儖僾壔偟偪傖偭偨側傫偰恖娫丄偦偆偦偆偄傞傢偗側偄偱偟傚偑乿
乽偪傚偭丄側傫偱偦偺偙偲抦偭偰傞偺傛偁側偨偭両丠乿
丂傕偪傠傫偦偺偲偒偺偙偲偼丄傆偨傝偩偗偺旈枾乧乧偲偄偭偰傕晹壆偵偄偨偺偼彈偺巕偺僗僥儔偱偁偭偰丄抝巕惗搆偺儂僔僩偠傖側偄偐傜側傫偺栤戣傕劅劅
乽偝偭偒偐傜壗儃乕僢偲偟偰傞傫偱偡丠丂儂僔僩愭攜乿
乽偁丠丂偊丄偊偭偲乧乧偆偆傫丄側丄側傫偱傕側偄傢傛乿
乽傢傛丠乿
乽偭両丂偠傖丄偠傖側偔偰丄側偭丄側傫偱傕側偄丄側傫偱傕劅劅乿
乽偪丄偪傚偭偲儂僔僩愭攜偭丄偦偭偪彈巕僩僀儗偱偡傛丠乿
乽偁丠丂傑丄娫堘偊偨偭乮愒柺乯両丂乧乧乧乧乧乧乧乧偒傖偁偁偭両乿
乽偳丄偳偆偟偨傫偱偡媫偵丠乿
乽偁丄偄傗丄偦偺乧乧傢丄傢傞偄丄偍劅劅壌丄屄幒偱嵗偭偰偡傞側丅乧乧乧乧側丄側傫偱丠丂偄偮傕尒姷傟偰傞儌僲丄側偺偵劅劅 乿
乽乧乧丠乿
丂偩偗偳偦傟偼丄斵乧乧斵彈傪傎傫偺彮偟丄偱傕妋幚偵曄偊偰偄偨丅
丂丂仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛
丂崱擔偼幍擔偵堦搙偺岞媥擔丅儚乕儖僗僼傽儞僨儖妛堾傕慡偰偺妛晹偱媥島偟偰偍傝丄椌惗偨偪傕慜擔偺梉崗偐傜幚壠偵婣偭偨傝丄挬憗偔偐傜奜傊弌偐偗偨傝偟偰偄偰丄妛惗椌偺拞偼娬嶶偲偟偰偄傞丅
丂怘摪偱抶偄栚偺挬怘傪嵪傑偣偰晹壆偵栠傞偲丄儂僔僩偼堄枴傕側偔傑傢傝傪尒夞偟丄壗偛偲偐傪寛堄偟偨傛偆偵戝偒偔偆側偢偄偨丅
乽偊乧乧僄儞僕僃儕儞僋丄償傽儖僉儕乕乿
丂晹壆偵偁傞巔尒偺慜偱噣庺暥噥傪彞偊傞丅嬀偵塮偭偨偦偺恎懱偼岝偵曪傑傟丄愒偄僪儗僗傾乕儅乕傪揨偭偨愴揤巊偺彮彈傊偲曄傢偭偨丅
乽乧乧傫偭乿
丂尐傗崢傪擯偭偰帺恎偺巔傪妋擣偟丄儂僔僩乧乧斲丄僗僥儔偼夵傔偰巔尒偵岦偒捈偭偨丅
丂屛悈偺傛偆偵憮偔悷傫偩摰偑丄嬀偺拞偐傜偙偭偪傪尒曉偟偰偔傞丅
丂偝偭偒傑偱偲偼傑傞偱堘偆丄偩偗偳偙傟偑崱偺帺暘丅
丂劅劅偱傕丄偝偡偑偵偙偺奿岲偺傑傑偠傖栚棫偭偪傖偆傛偹丅
丂嫻拞偱偦偆偮傇傗偔偲丄攚拞偺梼傪徚偟丄嫻偵庤傪摉偰戝偒偔懅傪偟偰乧乧
乽儕儊僀僋乿
丂師偺弖娫丄恎偵傑偲偭偨僪儗僗傾乕儅乕偑岝偺棻巕偲壔偟偰旘傃嶶傝丄壓拝巔偵側傞丅岝偼嵞傃僗僥儔傪曪傒崬傓偲丄煾怓乮偔傝偄傠乯偺儚儞僺乕僗傊偲曄傢偭偨丅
丂嬢傗懗岥偵僼儕儖偑偁偟傜傢傟偰丄忋昳側拞偵傕壜垽傜偟偝傪姶偠偝偣傞僨僓僀儞丅嵍偺庤庱偵偼僽儗僗儗僢僩丄懌尦偼偍煭棊側僗僩儔僢僾僷儞僾僗劅劅幚傪尵偆偲偙偺僐乕僨傿僱乕僩丄儐乕僠僃儞偑乽屻妛偺偨傔偵乿偲墴偟晅偗乧乧傕偲偄戄偟偰偔傟偨僼傽僢僔儑儞帍偵嵹偭偰偄偨傕偺偺娵僐僺偩偭偨傝偡傞丅
丂偩偗偳劅劅
乽偡偰偒乧乧乿
丂偦傫側尵梩偑帺慠偵岥傪偮偄偰弌偨丅嬍傪揮偑偡傛偆側椓傗偐側惡丅
丂偆偒偆偒偟偨婥暘偵側偭偰丄崢傪寉偔怳傝丄巔尒偺慜偱偔傞偭偲僞乕儞丅
丂傆傢傝偲東偭偨僗僇乕僩偺悶傪揈傓偲丄僗僥儔偼嬀偵塮傞帺暘偵彫庱傪孹偘偰旝徫傫偩丅
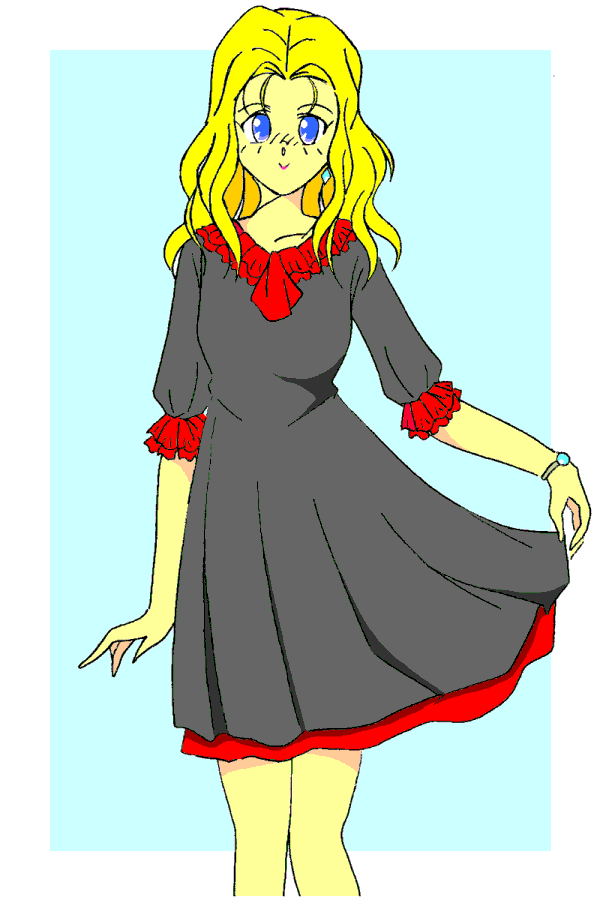
丂挿偔怢傃偨朓枿怓偺敮丄彫偝偔側偭偨庤偲嵶偄巜丄娵傒傪懷傃偨恎懱偮偒丅
丂妠傪堷偒丄攚嬝傪怢偽偟偰尐傪壓偘丄媟傪懙偊偰崢傪帩偪忋偘巔惃傪惍偊傞丅
丂傢偨偟丄彈偺巕側傫偩劅劅
丂偦偆帺妎偡傞偲丄僴乕僼僩僢僾偵曪傑傟偨嫻偺朿傜傒傗丄僼儔僢僩偵側偭偨屢娫偲偦偙傪暍偆僔儑乕僣偺姶怗偑丄偄偮傕偲曄傢傜側偄丄帺慠側傕偺偵巚偊偰偒偨丅
乽乧乧偆傫丄偄偄姶偠乿
丂嬀偺拞偺帺暘偵岦偐偭偰傕偆堦搙偵偭偙傝徫偄偐偗傞偲丄僗僥儔偼敀郪愭惗偐傜偍壓偑傝偱栣偭偨僷乕儖僺儞僋偺億乕僠傪庤偵丄晹壆偺僪傾傪墴偟奐偗偰奜傊弌偨丅
丂丂仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛
丂梫偡傞偵丄乽奐偒捈傝乿偱偁傞丅
丂崱偺偲偙傠扤偵傕僶儗偰偄側偄偟丄偄偮偱傕尦偵栠傟傞偟丄偳偺傒偪曄恎偟偨傜摢偺拞傑偱彈惈壔偟偰偟傑偆傫偩偟乧乧偩偭偨傜偄偭偦彈偺巕傪妝偟傫偠傖偍偆劅劅偲丄儂僔僩傕偲偄僗僥儔偼傂偲傝媥擔偺奨傊偲孞傝弌偟偨丅
丂妛堾慜偐傜杺摫僩儔儉偵忔偭偰丄屲偮栚偺掆棷強偱崀傝傞丅偦偙偼彜嬈抧嬫偺僔儑僢僺儞僌僗僩儕乕僩丅
丂偄偔偮傕偺揦偑尙傪楢偹丄戝惃偺攦偄暔媞偱偵偓傢偆愒楖姠偱曑憰偝傟偨捠傝傪丄斵彈偼億乕僠傪帩偮椉偺庤傪攚拞偵夞偟丄僗僇乕僩偺悶傪側傃偐偣寉傗偐偵曕偔丅
乽乧乧侓乿
丂姶偠曽偑彈惈偺偦傟偵曄傢偭偰偄傞偣偄偐丄偄偮傕偺奨暲傒偑堘偭偰尒偊傞丅
丂偡傟堘偆摨偠擭崰偺彮彈偨偪偺僼傽僢僔儑儞丄揦偵暲傫偱偄傞壔徬昳偵丄傾僋僙僒儕乕傗偍偟傖傟側彫暔乧乧抝偩偭偨偲偒偼婥偵傕棷傔側偐偭偨傕偺偵栚偑偄偭偰偟傑偆丅
丂偳傫偭劅劅乽偒傖偭両乿
丂傛偦尒偟側偑傜曕偄偰偄偨傜丄慜偐傜憱偭偰偒偨彫偝側彈偺巕偲傇偮偐偭偨丅僗僥儔偼屻傠偵傛傠傔偄偨偦偺巕傪丄偁傢偰偰書偒偲傔傞丅
乽偛傔傫偹丅戝忎晇丠乿
乽偆傫偭丅偁傝偑偲偆偍巓偪傖傫乿
丂曣恊傜偟偒彈惈偑嬱偗婑偭偰偒偰丄壗搙傕摢傪壓偘偰偒偨丅僗僥儔偼偼偵偐傫偩徫傒傪晜偐傋丄寉偔夛庍傪曉偟偰偦偺応傪棧傟偨丅
乽傆傆偭乧乧偍巓偪傖傫丄偐劅劅乿
丂岥尦傪傎偙傠偽偣丄傐偮傝偲偮傇傗偔丅
丂偦偧傠曕偒偵栠偭偨僗僥儔偩偭偨偑丄傆偲怳傝岦偄偰懌傪巭傔偨丅
乽偄偄側丄偙傟乧乧乿
丂僽僥傿僢僋偺揦愭偵忺傜傟偨丄悈怓偺僒儅乕僪儗僗丅偟偽偟偦傟傪尒偮傔偰偄偨僗僥儔偼丄墶偵偁偭偨僪傾傪奐偗偰揦偺拞傊擖偭偨丅
乽傢偁偭侓乿
丂惔慯側姶偠偺傾儞僒儞僽儖丄僇僕儏傾儖側僕儍働僢僩丄偪傚偭偲戝抇側儈僯僪儗僗乧乧偁偪偙偪偵忺傜傟偨怓偲傝偳傝偺堖暈偵丄傢偔傢偔偟偨婥帩偪傪梷偊傜傟偢丄揦拞傪尒偰夞傞丅
乽偙傟傕乧乧丄偙傟傕乧乧偁丄偙偭偪傕偄偄劅劅乿
丂僴儞僈乕偵妡偗傜傟偰偄偨僽儔僂僗傗僗僇乕僩傪庤偵庢傝丄嬀偺慜偱恎懱偵崌傢偣傞僗僥儔丅偦偙傊揦堳偺傂偲傝劅劅摢偺僣僲傪尒傞偵丄偍偦傜偔僒僉儏僶僗劅劅偑僯僐僯僐偟側偑傜曕傒婑偭偰偒偨丅
丂悅傟栚偱桪偟偘側婄棫偪丄挿偄崟敮傪屻摢晹偱僔僯儓儞偵偟偰丄敀偄僽儔僂僗偲抁傔偺僞僀僩僗僇乕僩傪恎偵偮偗偰偄傞丅嫻偺朿傜傒偼偪傚偭偲怲傑偟傗偐偩偭偨丅
乽偄傜偭偟傖偄傑偣乣丅偳偆偄偭偨傕偺傪偍扵偟偱偡偐丠乿
乽乧乧両丠丂偊丄偊偭偲丄偁丄偄偊丄偦偺劅劅乿
乽偁傜丄怽偟栿偁傝傑偣傫嬃偐偣偰偟傑偭偰丅偍媞偝傑偑偢偄傇傫柪傢傟偰偄傜偭偟傖傞傛偆側偺偱丄偍庤揱偄偟傛偆偐偲乿
乽偁丄偦偺丄偍劅劅偍峔偄側偔乿
丂庤偵偟偨彜昳傪丄偁偨傆偨偲扞偵栠偡丅偦偺婥偵側傟偽乽儕儊僀僋乿傪巊偭偰偳傫側奿岲傕帺桼帺嵼側偺偩偑丄偄傠傫側暈傪庢偭懼偊堷偭懼偊偡傞偺偑妝偟偔偰丄偮偄僥儞僔儑儞偑忋偑偭偰偟傑偭偰偄偨丄傛偆偩丅
丂偩偗偳偦偺揦堳偼丄徫傒傪晜偐傋偨傑傑丄偝傜偵娫傪媗傔偰偒偨丅
乽傕偟偐偟偰丄斵巵偝傫偲偺僨乕僩梡偐偟傜丠乿
乽偪丄偪劅劅堘偄傑偡偭両乿
丂帹尦偱偦偆殤偐傟丄僗僥儔偼偁傢偰偰尵偄曉偟偨丅
乽偠傖偁曅巚偄偺恖偺婥傪堷偒偨偄丄偲偐丠乿
乽偱丄偱偡偐傜丄偦傫側傫偠傖側偔偰乧乧乿
丂擼棤偵晜偐傃忋偑偭偨億僯僥彮擭劅劅僜乕儎偺徫婄丅偁傢偰偰偦傟傪徚偟嫀傠偆偲偡傞偑丄巚偊偽巚偆傎偳堄幆偟偰偟傑偄丄偦偺僀儊乕僕偑妋偐側傕偺偵側偭偰偄偔丅
乽乧乧乧乧乿
丂婄傪愒傜傔偨傑傑丄僗僥儔偼抪偢偐偟偘偵傕偠傕偠偲偆偮傓偄偰偟傑偆丅偦傫側斵彈偵僒僉儏僶僗偺揦堳偼栚怟傪壓偘丄乽偁傜偁傜乿偲岥傕偲傪傎偙傠偽偣偨丅
乽偆乣傫丄崱拝偰傞偺傕偄偄偗偳丄傕偭偲柧傞偄怓尛偄偺傕偺傕帡崌偆偐偟傜偹乧乧乿
乽偊丄偁丄偪劅劅偪傚偭偲偋丠乿
丂帋拝幒傊偲楢傟崬傑傟丄拝偰偄偨儚儞僺乕僗傪扙偑偝傟傞丅
丂奃怓偺僴乕僼僩僢僾偲僔儑乕僣偲偄偆壓拝巔偵偝傟丄抪偢偐偟偝偵嫻偺慜偱榬傪僋儘僗偝偣傞僗僥儔丅僒僉儏僶僗偺揦堳偼妟偵巜傪摉偰偰丄棴傔懅傪偮偄偨丅
乽偢偄傇傫抧枴側壓拝偹丅擭崰偺彈偺巕側傫偩偐傜丄傕偭偲壜垽偄偺傪拝偗偰僆僔儍儗偟側偒傖侓乿
乽偼丄偼偄乧乧乿
丂嫻偺僒僀僘傪應偭偰傕傜偆丅擕庱偵増偭偰儊僕儍乕傪姫偒晅偗傜傟偰丄僗僥儔偼巚傢偢惡傪忋偘偰偟傑偭偨丅
乽傗劅劅傗偁偀傫偭丄偔偡偖偭偨偁乣偄偭乿
乽偙傜偭丄摦偐側偄偺丅惓妋偵應傟側偄偠傖側偄乿
乽偁丄偁偺偭丄傎劅劅杮摉偵偙傟丄僒僀僘應偭偰傞偺丠乿
乽幐楃偹丅偨偟偐偵偁偨偟偼僒僉儏僶僗偩偗偳丄偍揦偺偍媞偝傫憡庤偵僄僢僠側偙偲偼偟側偄傢傛乿
乽乧乧乧乧乿
丂嵎偟弌偝傟偨僽儔僕儍乕偲僔儑乕僣傪恎偵偮偗傞丅攚拞偺儂僢僋傪棷傔傜傟偢偵傕偨傕偨偡傞僗僥儔傪尒偐偹偰丄揦堳偑庤傪怢偽偟偰偒偨丅
乽傎傜丄慜偐偑傒偵側偭偰偍偭傁偄傪偪傖傫偲僇僢僾偵擖傟傞偭丅攚拞傪棷傔偰丄榚偺偍擏傪婑偣忋偘偰乧乧尐偺僗僩儔僢僾傪挷惍偟偰偭偲丅偳偆丠丂偳偙偐嬯偟偄偲偙傠偼側偄偐偟傜丠乿
丂尐傪傐傫偲扏偐傟傞丅僗僥儔偼夵傔偰帋拝幒偺巔尒偵岦偒捈偭偨丅
乽偁乧乧乿
丂嬀偵塮偭偰偄偨偺偼丄敄偄僺儞僋怓偺僼儕儖偑偁偟傜傢傟偨敀偄僽儔僕儍乕偲僔儑乕僣傪恎偵偮偗偰丄杍傪愒偔愼傔偨帺暘偺巔劅劅
乽偙傟偑丄傢偨偟乧乧丠乿
丂柍堄幆偺偆偪偵丄偮傇傗偒偑偙傏傟偨丅
丂僼儖僇僢僾偵曪傑傟偰丄鉟楉側宍偵惍偊傜傟偨屓偑嫻偺憃媴偵尒擖偭偰偟傑偆丅
乽乧乧乧乧乿
丂彈偺巕偺壓拝傪偒偪傫偲拝偗偰偄傞偙偲偑婥抪偢偐偟偔丄偱傕壗屘偐婐偟偔屩傜偟偄丅
乽偆傫丄偲偭偰傕傛偔帡崌偭偰傞傢傛丅傛偐偭偨傜懠偺傕帋拝偟偰傒傞丠乿
乽偊丄偊偊乧乧乿
丂揦堳偺栤偄偐偗偵丄偼偵偐傓傛偆側昞忣傪晜偐傋偰墳偊傞丅
丂拝忺傞妝偟偝偵栚妎傔丄傑偨堦抜噣彈偺巕噥偺奒抜傪搊偭偰偟傑偭偨僗僥儔偱偁偭偨丅
丂丂仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛
丂僋儕僗僥傿傾儗僀僋偺屛斎偵偁傞僒儔僒僀儔丒僔僥傿偼丄偦偺屛悈傪婎偵偟偨愼怓丒朼愌嬈偑婎姴嶻嬈偱偁傞丅娤岝抧偲偟偰傕偦偙偦偙桳柤偱偁傝丄傑偨嬤擭偱偼杺椡偱摦偔婡夿劅劅杺摫婡夿惢嶌偺僼傽僋僩儕乕偑偄偔偮傕奐愝偝傟偨偨傔丄巗偵弌擖傝偡傞恖偺悢偼偄偪偩傫偲懡偔側偭偰偄傞偲偐丅
乽偘偭丄偁偺帪偺償傽儖僉儕乕両丠乿乽側傫偱偙傫側偲偙偵偄傞偺傛偭丠乿
乽偁丄偁側偨偨偪劅劅乿
丂僽僥傿僢僋傪弌偰怳傝岦偄偨弖娫丄僗僥儔偼尒抦偭偨擇恖乧乧偄傗嶰恖偲敨崌傢偣偨丅
丂敀偄儚儞僺乕僗偺忋偐傜敄巼怓偺儃儗儘傪塇怐偭偨儐僯僐乕儞柡偺僼傿乕僱偲丄僺儞僋偺傾僂僞乕僉儍儈僜乕儖偵崟偄僗僉僯乕僷儞僣傪崌傢偣偨憰偄偺僟乕僋僄儖僼柡儀僱僢僞丄偦偟偰劅劅
乽傑偨惈挦傝傕側偔偦偺巕偵尵偄婑偭偰傞偺偭両丠乿
乽乽乧乧乧乧乿乿
乽偩丄戝忎晇偩傛揤巊偺偍巓偪傖傫偭乿
丂僼傿乕僱偺攚拞乮攏懱乯偵屪偭偰偄偨抝偺巕劅劅儖儖僩偑丄偄偒傝棫偮僗僥儔偵偁傢偰偰惡傪偐偗傞丅乽乧乧僼傿乕僱偍巓偪傖傫傕儀僱僢僞偍巓偪傖傫傕丄働儞僇傗傔偰側偐傛偔側偭偰偔傟偨偐傜偭両乿
乽乧乧乧乧乿
丂偳偆傗傜偙偺擇恖丄梒偄斵傪乽嫟桳乿偡傞偙偲偵偟偨傜偟偄丅
乽偁乣偦偺丄傑丄傑偁丄側傫偩乧乧偊丄俵偵愼傔傞偺偼傑偩傑偩偁偲偱傕偄偄偐側偭偰丅乧乧偄丄崱偼偙偺巕偺桪偟偄偍巓偪傖傫偱偄傛偆偐偲劅劅乿
丂層棎側帇慄傪岦偗偰偔傞僗僥儔偵偦偆尵偆偲丄儀僱僢僞偼愲偭偨帹偺愭傑偱恀偭愒偵偟偰栚傪偦傜偟偨丅
丂嫮婥嫮堷壛媠婥幙側僟乕僋僄儖僼偲偼巚偊側偄丄偦偺懺搙丅堦弖曫婥偵偲傜傟偨僗僥儔偩偭偨偑丄椬偵悷傑偟婄偱棫偮儐僯僐乕儞柡偵惡傪偐偗傞丅
乽僼傿乕僱偼偄偄偺丠乿
乽偟丄巇曽側偄偠傖側偄丅偍屳偄忳傟側偄傫偩偟乧乧乿
乽偱傕丄儐僯僐乕儞偭偰妋偐劅劅乿
丂乽弮寜偺杺暔柡乿偲傕屇偽傟傞儐僯僐乕儞偼丄懠偺杺暔柡偲岎傢偭偨抝惈偺惛傪庴偗傞偲丄偦偺僣僲偵偁傞帯桙偺椡傪幐偭偨傝丄垷庬偱偁傞僶僀僐乕儞傊揮壔偟偨傝偡傞偲尵傢傟偰偄傞丅
丂偩偑丄僼傿乕僱偼儀僱僢僞偲偼斀懳偵丄僗僥儔偺栚傪恀偭捈偖尒曉偟偨丅
乽傢偐偭偰傞丅偗偳丄偦偺偲偒偑棃傞偺偼愭偺榖偵側傝偦偆偩偟乧乧偦傟偵丄偨偲偊偳傫側巔偵側偭偰傕丄傢偨偟偼傢偨偟偩偐傜乿
乽乧乧乧乧乿
丂偒偭傁傝偲尵偄愗偭偨斵彈偺尵梩偑丄僗僥儔偺怱傪偞傢偮偐偣傞丅
丂偙傟偐傜傒傫側偱恖宍寑傪尒偵峴偔傫偩乣丄偲偼偟傖偖儖儖僩偵桪偟偘側徫婄傪晜偐傋傞僼傿乕僱偲儀僱僢僞丅嶨摜偺拞偵暣傟偰偄偔斵傜偺屻傠巔傪丄愴揤巊偺彮彈偼柍尵偱丄偦偟偰彮偟慉傑偟偘偵尒憲偭偨丅
丂偟偽偟偦偺応偵棫偪恠偔偟丄傗偑偰恖攇偵棳偝傟傞傛偆偵纟傪曉偡丅
乽偳傫側巔偵側偭偰傕丄傢偨偟偼傢偨偟乧乧偐乿
丂傐偮傝偲偮傇傗偒丄僗僥儔偼僔儑乕僂僀儞僪僂偵塮傞帺暘偵栚傪傗偭偨丅
丂煾怓偺儚儞僺乕僗傪拝偨丄憮偄摰偲朓枿怓偺敮偺彮彈偑尒曉偟偰偔傞丅
丂嬻偄偨庤偱丄偦偭偲嫻尦傪墴偝偊傞丅暈偺壓偵拝偗偰偄傞偺偼丄僽僥傿僢僋偺揦堳偵姪傔傜傟偰攦偭偨僽儔僕儍乕偲僔儑乕僣偺僙僢僩丅
丂劅劅傕偟傕丄傕偟傕偙偺傑傑乧乧
乽僗僥儔偝傫乿
丂偙偺傑傑丄噣僗僥儔噥偺傑傑偱偄偨傜乧乧
乽僗僥儔偝傫乿
丂傢偨偟傕丄僼傿乕僱傗儀僱僢僞傒偨偄偵乧乧
乽僗僥儔偝傫偭乿乽乧乧偊偭丠乿
丂偦偺惡偑帺暘偺憐憸偠傖側偔幚嵺偵暦偙偊偰偒偨偙偲偵婥偯偒丄僗僥儔偼偁傢偰偰傑傢傝傪尒夞偟偨丅
乽傗偭傁傝僗僥儔偝傫偩乿
乽偦偭乧乧僜乕儎偭丄偔傫丠乿
丂巹暈巔劅劅儕僱儞偺敀僔儍僣偵嵁怓偺僆乕僶乕僆乕儖偲偄偆奿岲偺億僯僥彮擭偑丄捠傝傪墶愗傝嬱偗婑偭偰偔傞丅
乽傛偐偭偨乧乧偄偮傕偲堘偆奿岲偩偭偨偐傜丄恖堘偄偐偲巚偄傑偟偨乿
乽偁丄偊乧乧偊偭偲丄偦偺劅劅乿
乽偁乧乧乿
丂傑偝偐偙傫側偲偙傠偱弌夛偆偲偼丄巚偭偰傕偄側偐偭偨乧乧傑偁丄偦傟偼岦偙偆傕摨偠側偺偩傠偆偗偳丅
丂僗僥儔偼婄傪愒傜傔丄僪僉僪僉偡傞嫻偵傑偨庤傪摉偰偰屗榝偆丅偮傜傟偰僜乕儎傕婄傪愒偔偟偰丄
乽偛丄偛傔傫側偝偄丅偁乣丄偊偭偲丄偦劅劅偦偺暈傕丄偵丄帡崌偭偰傑偡乧乧偲偭偰傕乿
乽偁丄偆丄偆傫丄偁傝偑偲偆乧乧乿
乽乧乧乧乧乿
乽乧乧乧乧乿
丂屳偄偵婄傪恀偭愒偵偟偰尒偮傔崌偆丅偦傫側擇恖傪摴峴偔恖偨偪偑丄偔偡偔偡徫偄側偑傜惗抔偐偄帇慄傪岦偗偰捠傝夁偓偰偄偔丅
乽乧乧偄丄峴偒傑偟傚偆僜乕儎偔傫偭両乿
乽偊丠丂峴偔偭偰偳偙傊乧乧偆傢偀偭両丠乿
丂捑栙偲抪偢偐偟偝偵懴偊傜傟側偔側偭偨僗僥儔偼丄僜乕儎偺庤傪嫮堷偵偮偐傓偲丄偦偺応偐傜摝偘弌偡傛偆偵嬱偗弌偟偨丅
丂丂仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛
乽傛偆偙偦僪儔僑僯傾椏棟揦儔僽儔僀僪丒僒儔僒僀儔嶰崋揦傊両丂偍擇恖條偱偡偐丠丂偙偪傜偺僥乕僽儖傊偳偆偧乣侓乿
丂嬤偔偵偁偭偨儗僗僩儔儞偵擖傝丄僥乕僽儖惾偵岦偐偄崌偭偰嵗傞丅
丂拲暥傪庢傝偵偒偨僉僉乕儌儔偺僂僃僀僩儗僗偵丄僷儉儉劅劅戃忬偺僷儞惗抧偵嬶傪媗傔偨僪儔僑僯傾偺僼傽僗僩僼乕僪劅劅偺僙僢僩儊僯儏乕傪拲暥偟丄僗僥儔偲僜乕儎偼忋栚尛偄偱偍屳偄偺婄傪偆偐偑偭偨丅
乽偁乧乧偁偺偭乿
乽偼丄偼偄偭乿
乽偊丄偊偭偲丄偦偺丄僗僥儔偝傫偼丄偒丄崱擔偼壗傪丠丂乧乧偁丄傕偟偐偟偰傑偨扤偐偑劅劅乿
乽偦偆偠傖側偔偰丄崱擔偼偦偺丄偟劅劅僔儑僢僺儞僌丄偐側丠丂僜乕儎偔傫偙偦丄崱偐傜偳偙偐峴偔偮傕傝丄偩偭偨偺丠乿
丂椬偵抲偄偰偁傞僽僥傿僢僋偺巻戃偵偪傜偭偲栚傪傗偭偰丄栤偄曉偡僗僥儔丅
乽杔偼乧乧偙傟偱壗偐嶣偭偰傒傛偆偐側丄偭偰乿
丂偦偆尵偭偰丄僜乕儎偼庱偐傜壓偘偰偄偨彫偝側崟偄敔傪僥乕僽儖偵偺偣偨丅
丂惓柺偵娵偔摟偒捠偭偨晹昳劅劅儗儞僘偑廲偵擇偮暲傫偱偄傞丅
乽幨恀婡丠乿
乽偼偄丅晝偝傫偺丄偍壓偑傝側傫偱偡偗偳乧乧乿
丂擇娽儗僼偺敔僇儊儔偵庤傪揧偊偰丄偼偵偐傓傛偆偵摎偊傞僜乕儎丅
丂偦偙偵拲暥偟偨椏棟偑塣偽傟偰偒偨丅僗僷僀僔乕側崄傝偑旲傪偔偡偖傝丄榖偑搑愗傟傞丅
乽偛拲暥偼埲忋偱傛傠偟偄偱偟傚偆偐丠丂偦傟偱偼偛備偭偔傝偳偆偧乣侓乿
乽偄丄偄偨偩偒傑偡偭乿乽乧乧偄偨偩偒傑偡乿
丂偪傚偆偳拫帪丅擇恖偼僙僢僩儊僯儏乕偵庤傪怢偽偟偨丅
丂僗乕僾偺擖偭偨儅僌僇僢僾傪椉庤偱帩偭偰傆乕傆乕偡傞僗僥儔偵丄僜乕儎偼僷儉儉傪庤偵僋僗僢偲徫傒傪晜偐傋傞丅
乽側乧乧壗丠乿
乽偄丄偄偊丄僗僥儔偝傫傕儂僔僩愭攜傒偨偔擫愩側傫偩偭偰乧乧偁丄偊偭偲儂僔僩愭攜偭偰偄偆偺偼杔傛傝慜偵妛堾偵擖偭偨劅劅乿
乽偦丄偦傟傛傝僜乕儎偔傫偺偙偲丄偒丄暦偐偣偰梸偟偄丄偐傕丅斀杺暔椞偐傜摝偘偰偒偨偭偰乧乧偁偭両乿
丂帺暘乮儂僔僩乯偺偙偲偐傜榖戣傪堩傜偦偆偲偟偰丄傑偨梋寁側偙偲傪尵偭偰偟傑偭偨丅偁傢偰偰岥偵庤傪傗傞僗僥儔丅
丂偟偐偟僜乕儎偼摿偵婥偵偟偨慺怳傝傕側偔丄榖偟巒傔偨丅傎偭傌偨偵僜乕僗偑晅偄偰偄傞偺偼偛垽沢偩丅
乽偊偭偲丄杔偺壠偼僜儔儕傾嫵抍椞偱桝擖嶨壿偺揦傪傗偭偰偨傫偱偡丅偱傕丄惞搒偐傜棃偨嫵抍孯偑奨偵嫃嵗傞傛偆偵側偭偰偐傜丄娭強傗専栤偑傗偨傜偲尩廳偵側偭偰偟傑偭偰乧乧乿
丂恖傗暔偺峴偒棃偑嬌抂偵惂尷偝傟偨偨傔丄椞奜偐傜攧傝暔偑慡偔擖偭偰偙側偔側傝丄偦偟偰偄傛偄傛揦傪忯傑側偗傟偽側傜側偔側偭偨偁傞擔偺栭拞丄偄偒側傝晝恊偵扏偒婲偙偝傟乽摝偘傞偧乿偲尵傢傟偰劅劅
乽乧乧偦傟偱丄壠懓偱揱庤傪棅偭偰僒儔僒僀儔偵朣柦丄偲偄偆偐栭摝偘偟偰偒偨傫偱偡乿
乽乧乧乧乧乿
丂奨摴偑惍旛偝傟丄揝摴偑晘愝偝傟傞傛偆偵側偭偨崱偺帪戙丄斀杺暔椞偵廧傓恖娫偑奆乆丄杺暔柡傪栂怣揑偵揋帇偟偰偄傞傢偗偱偼側偄丅
丂僸僩側傜偞傞幰偨偪偲昁梫埲忋偵娭傢傜側偄乧乧偲偄偆偺偑嵟嬤偺斀杺暔椞丒斀杺暔崙壠偺僗僞儞僗偱偁傞丅偲偼偄偊丄枹偩偵乽杺暔偼恖娫傪嬺傜偆嫲傞傋偒懚嵼乿偩偲寲揱偡傞屆廘偄庡恄嫵抍捈妽椞傕傑偩傑偩巆偭偰偄傞丅
丂乧乧傕偟偐偟偨傜僜乕儎偺椉恊偼丄懅巕偑桬幰偺帒幙帩偪偩偲偄偆偙偲傪抦偭偰偄偨偺偐傕偟傟側偄丅嫵抍孯偑暆傪棙偐偡僜儔儕傾偱傕偟偦偺偙偲偑柧傞傒偵側偭偨傜丄斵偼栤摎柍梡偱挜暫偝傟丄乽嫵抍偺寱乿乽庡恄偺椡偺戙峴幰乿側偳偲偄偭偨尐彂偒偲堷偒姺偊偵帺桼傪扗傢傟偰偟傑偆劅劅
丂偩偐傜偙偺婡夛偵恊杺暔椞傊偺朣柦傪幚峴偟偨乧乧側傫偰旘桇偟夁偓偐側丠丂偲丄岥偺拞偺僷儉儉傪堸傒崬傒巚偆僗僥儔丅
乽偛丄偛傔傫側偝偄丅寵側偙偲恥偄偪傖偭偰乿
乽婥偵偟側偄偱僗僥儔偝傫丅晝偝傫偨偪傕偙偺奨偱傑偨偍揦傪奐偔偙偲偑偱偒偨偟丄杔傕妛堾偵捠偊傞偟丄幚偺偲偙傠偙偭偪偵棃偰傛偐偭偨偭偰巚偭偰傞傫偱偡乿
乽僜乕儎偔傫乧乧乿
丂杺暔柡偝傫偨偪偵廝傢傟傞偺偩偗偼丄崲傝傕傫偱偡偗偳偹乧乧偲丄偔偪傃傞偺僜乕僗傪偸偖偭偰嬯徫偡傞偦偺婄傪丄僗僥儔偼峥偟偘偵尒偮傔偨丅
丂偦傟偵婥偯偄偰偄傞偺偐偄側偄偺偐丄僜乕儎偼斵彈偵岦偒捈傝丄墦椂偑偪偵栤偄偐偗偨丅
乽偲丄偲偙傠偱僗僥儔偝傫乧乧偊偭偲丄偙丄偙偺偁偲丄壗偐梊掕偼劅劅乿
乽偁丄偆傫丄摿偵側偄偗偳乧乧乿
乽偠傖偁丄傕偟丄傛丄傛偐偭偨傜乧乧偊偭偲丄偦偺乧乧乧乧偡偭丄僗僥儔偝傫偺丄偟傖丄幨恀傪嶣傜偣偰偔傟傑偣傫丄偐乧乧丠乿
乽偼丠乿
丂丂仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛 仚 仛
丂彜揦奨傪屛懁傊偲敳偗丄悈楬傪墶偵彮偟峴偔偲彫崅偄媢偵側偭偰偄偰丄偦偙偵僒儔僒僀儔巗柉岞墍偑偁傞丅
丂椢偑惍旛偝傟丄僽儔儞僐傗偡傋傝戜丄僕儍儞僌儖僕儉側偳偺梀嬶偑抲偐傟偨峀応傗丄僕僷儞僌晽掚墍丄栰奜僗僥乕僕側偳偑愝偗傜傟偰偄偰丄奨偵廧傓恖乆偺宔偄偺応偲偟偰恊偟傑傟偰偄傞丅
丂僗僥儔偲僜乕儎偼嶣塭応強傪扵偟偰丄屛偑堦朷偱偒傞岞墍偺梀曕摴傪扝偭偰偄偔丅
丂傑傢傝偵偼巕偳傕偨偪傗壠懓楢傟丄壗慻偐偺僇僢僾儖偑丄巚偄巚偄偵宨怓傪妝偟傫偩傝丄嶶嶔偟偨傝偟偰偄傞丅
乽傎傜偭丄偛庡恖偝傑憗偔憗偔偭両乿
乽偪乧乧偪傚偭偲懸偭偰傛儅儕傿両乿
丂僞儞僋僩僢僾抁僷儞巔偺僐儃儖僩彮彈偑丄摨偠擭崰偺彮擭傪堷偭挘偭偰妝偟偦偆偵嬱偗偰偄偔丅
乽傕偆変枬偱偒偹偊偭両丂儐僂僩丄偦偙偺椦偺拞偱儎儖偧偭両乿
乽傂偭丄恖偑尒偰傞偭偰偙傫側拫娫偭偐傜乧乧偆傢偁偁偁偁偁偭儕僫偝偀傫偭両乿
丂俿僔儍僣偵僟儊乕僕僕乕儞僘偲偄偆儔僼側奿岲傪偟偨挿恎偺僆乕僈柡偑丄岾敄偦偆側嵶恎偺抝惈偺嬢庱傪偮偐傫偱戝屢偱嶨栘椦偺拞傊偲擖偭偰偄偔丅
丂偁傞堄枴暯榓側丄恊杺暔椞偺媥擔偺晽宨丅
乽乧乧偱丄晝偝傫偑尵偭偨傫偱偡丅亀妋偐偵昳晄懌偩偗偳丄憅屔偵壗擭傕曻偭偰偍偄偨傕偺傪専昳傕偣偢偵擺傔傞偭偰偳偆偄偆偮傕傝偩亁偭偰劅劅乿
乽偦丄偦傫側偙偲偁偭偨傫偩乧乧乿
丂偲傝偲傔偺側偄榖偵憡捚傪偆偪側偑傜丄僗僥儔偼椬傪曕偔僜乕儎傪墶栚偱偪傜偭偲偆偐偑偭偨丅
丂劅劅偊偭偲偙傟偭偰丄僨乕僩乧乧偩傛偹丠
乽乧乧乧乧乿
丂劅劅偳傫側晽偵尒傜傟偰傞偺偐側丠丂巓掜偵偟偐尒偊側偐偭偨傝偟偰乧乧
丂摢傂偲偮暘攚偺掅偄億僯僥彮擭偵丄偔偡傝偲旝徫傓丅
丂僜乕儎偼棫偪巭傑傞偲丄椉庤偺巜偱榞傪偮偔傝丄傑傢傝傪偖傞偭偲尒夞偟偨丅
乽偙偺曈偱偄偄偐側乧乧僗僥儔偝傫丄偪傚偭偲偦偙偵棫偭偰傕傜偊傑偡偐丠丂庤偡傝偵寉偔傕偨傟偐偐傞姶偠偱乿
乽偁丄偆傫丄傢偐偭偨劅劅乿
丂僗僥儔偼屛懁偵愝偗傜傟偨庤偡傝偵崢傪梐偗傞偲丄攚嬝傪怢偽偟偰僜乕儎偺曽傊岦偒捈偭偨丅
乽偙傫側姶偠丄偐側丠乿
乽偼偄丅乧乧偁丄偦傫側偵嬞挘偟側偄偱乿
丂壓傪岦偄偰僇儊儔偺僼傽僀儞僟乕傪擿偒側偑傜丄僜乕儎偑摎偊傞丅
丂懁柺偺僟僀儎儖偱僺儞僩傪崌傢偣丄奧偺撪懁偵偁傞旝挷惍梡偺儖乕儁傪愜傝忯傓丅
乽偠傖偁丄嶣傝傑偡偹乿
乽偁丄偆丄偆傫乿
丂嬞挘偟側偄偱偲尵傢傟偨偺偵丄巚傢偢恎峔偊偰偟傑偆丅柍棟傕側偄乧乧儂僔僩偲偟偰側傜偲傕偐偔丄噣僗僥儔噥偲偟偰幨恀偵嶣傜傟傞偺偼丄偙傟偑弶傔偰側偺偩偐傜丅
丂僇僔儍儕劅劅
丂偐偡偐側壒偲偲傕偵僔儍僢僞乕偑愗傜傟偨丅僗僥儔偼傎偭偲懅傪揻偒丄尐偺椡傪敳偄偰昞忣傪榓傜偘傞丅
丂僜乕儎偼僼傽僀儞僟乕偵栚傪傗偭偨傑傑丄嶣塭梡儗儞僘偵晅偄偰偄傞僐僢僉儞僌乮僔儍僢僞乕僠儍乕僕乯儗僶乕傪巜偱慺憗偔壓偘傞偲丄
丂僇僔儍儕劅劅
乽乧乧偊丠乿
丂擇夞栚偼姰慡偵晄堄懪偪偩偭偨丅乽偪丄偪傚偭偲僜乕儎偔傫偭両丠乿
乽偁偼偼丄偛傔傫側偝偄丅偱傕丄偒偭偲崱偺曽偑帺慠側姶偠偱嶣傟偰傞偲巚偄傑偡傛乿
乽傕偆偭乿
丂埆傃傟傕偣偢摢偵庤傪傗傞億僯僥彮擭偺婄傪丄僗僥儔偼杍傪愒傜傔偵傜傒偮偗傞丅
丂偪側傒偵僼傽僀儞僟乕梡偲嶣塭梡偵儗儞僘偑暿乆偵側偭偰偄傞擇娽僇儊儔偼丄僺儞僩崌傢偣偑擄偟偄傜偟偔丄弶怱幰偼乽摨偠峔恾偱擇枃嶣傝乿偑悇彠偝傟偰偄傞偺偩偲偐丅
乽応強傪曄偊偰丄傕偆彮偟嶣塭偟偰傕偄偄偱偡偐丠乿
乽偊丄偊偊丅偱傕崱搙偼偪傖傫偲嶣傞慜偵惡偐偗偰劅劅偭偰丄偦偆偩偭侓乿
丂偲丄偦偙偱嬃偐偝傟偨偍曉偟傪巚偄偮偒丄斵彈偼埆媃偭傐偄徫傒傪晜偐傋偨丅
乽偡丄僗僥儔偝傫丠乿
乽尒偰偰丄僜乕儎偔傫乿
丂僗僥僢僾傪摜傓傛偆偵偁偲偢偝傞偲丄嵍庤庱偺僽儗僗儗僢僩傪怗偭偰丄偦偺応偱偔傞偭偲僞乕儞丅
丂師偺弖娫僗僥儔偺拝偰偄偨煾怓偺儚儞僺乕僗偑岝偵曪傑傟丄懅傪偺傓僜乕儎偺栚偺慜偱宍偲怓傪曄偊偰偄偔劅劅
乽乧乧偳偆丠丂帡崌偆丠乿
丂傑傢傝偑偳傛傔偔拞丄拝偰偄偨暈傪僽僥傿僢僋偵偁偭偨偁偺悈怓偺僒儅乕僪儗僗偵乽儕儊僀僋乿偟偨僗僥儔偼丄僗僇乕僩偺悶傪傆傢傝偲傂傞偑偊偟偰怳傝岦偒丄偐傜偐偆傛偆側徫傒傪晜偐傋偨丅
乽偁丄偼丄偼偄乧乧丄偲丄偲偭偰傕乧乧乿
丂婄傪恀偭愒偵偟偰摎偊傞僜乕儎丅側偍丄岝偺拞偱堦弖尒偊偨斵彈偺壓拝巔偼丄偟偭偐傝偔偭偒傝栚偵從偒晅偄偰偄偨傝偟偰丅
乽傆傫偭丄堖憰僠僃儞僕偔傜偄傢偨偔偟偵傕偱偒傑偡傢乿
乽偱傕僙儕僇偝傫偼丄崱偺儊僀僪暈巔偑堦斣帡崌偭偰傑偡傛乿乽乧乧偊丠乮傐偭乯乿
丂挘傝崌偍偆偲偡傞僔儑僑僗柡傪丄椬偵偄偨尋媶幰晽偺惵擭偑偨偟側傔傞丅
丂傕偭偲傕摉偺僗僥儔帺恎偼乽僜乕儎偔傫偵偍曉偟偺僪僢僉儕戝惉岟両乿偲偱傕巚偭偰偄傞偺偐丄墶偱偦傫側偙偲尵傢傟偰偄傞側傫偰乮偁偲攦偭偨偽偐傝偺僽儔僕儍乕偲僔儑乕僣傪尒傜傟偨偙偲偵傕乯慡偔婥偯偄偰偄側偄傛偆偩丅
乽傆傆偭丄偠傖偁師偼偙偺暈偱嶣偭偰偔傟傞丠丂僜乕儎偔傫侓乿
乽偊丄偁丄偦劅劅偦偺丄偊偭偲丄偼丄偼偄偭乧乧乿
丂嵎偟弌偝傟偨偦偺庤傪丄僜乕儎偼偍偢偍偢偲埇傝曉偡丅
丂偩偑丄
乽乧乧偁傜丠丂壗偐偟傜丠乿
丂偦偺尐墇偟偵丄奨偺寈绱戉巑偨偪偑偨偩側傜偸條巕偱栰奜僗僥乕僕偺曽傊偲憱偭偰偄偔偺偑尒偊偰丄僗僥儔偼夦鎎側昞忣傪晜偐傋傞丅
丂僜乕儎傕斵彈偺帇慄傪捛偭偰屻傠傪怳傝岦偒丄旣崻傪婑偣偨丅
乽壗偐偁偭偨丄傒偨偄偱偡偹乿
乽峴偭偰傒傑偟傚偆丄僜乕儎偔傫乿
乽偊丠丂偪丄偪傚偭偲僗僥儔偝乧乧偆傢偁偁偁偁偁偁偁偭両丠乿
丂僗僥儔偼僜乕儎偺庤傪偓傘偭偲埇傝偟傔丄偦偺傑傑屻傪捛偭偰憱傝弌偟偨丅
丂to be continued...
劅 appendix 劅
丂僗僥儔偑弌偨偁偲偺僽僥傿僢僋偵偰劅劅
乽偆乣傫乧乧乿
乽偁傟丠丂偳偆偐偟偨傫偱偡偐愭攜丠乿
乽偁丄偄傗丄偝偭偒憡庤偟偨嬥敮偺巕側傫偩偗偳乧乧側乣傫偐偁偨偟偵暤埻婥偑帡偰傞偭偰偄偆偐丄摨偠擋偄偑偡傞偭偰偄偆偐劅劅乿
乽婥偺偣偄偱偡偹乮偒偭傁傝乯乿
乽懄摎偭両丠乿
乽偩偭偰愭攜傒偨偔丄彈暔偺堖暈偑岲偒偡偓偰傾儖僾壔偟偪傖偭偨側傫偰恖娫丄偦偆偦偆偄傞傢偗側偄偱偟傚偑乿
乽偪傚偭丄側傫偱偦偺偙偲抦偭偰傞偺傛偁側偨偭両丠乿
20/08/13 20:14峏怴 / 俵俷俶俢俷
栠傞
師傊